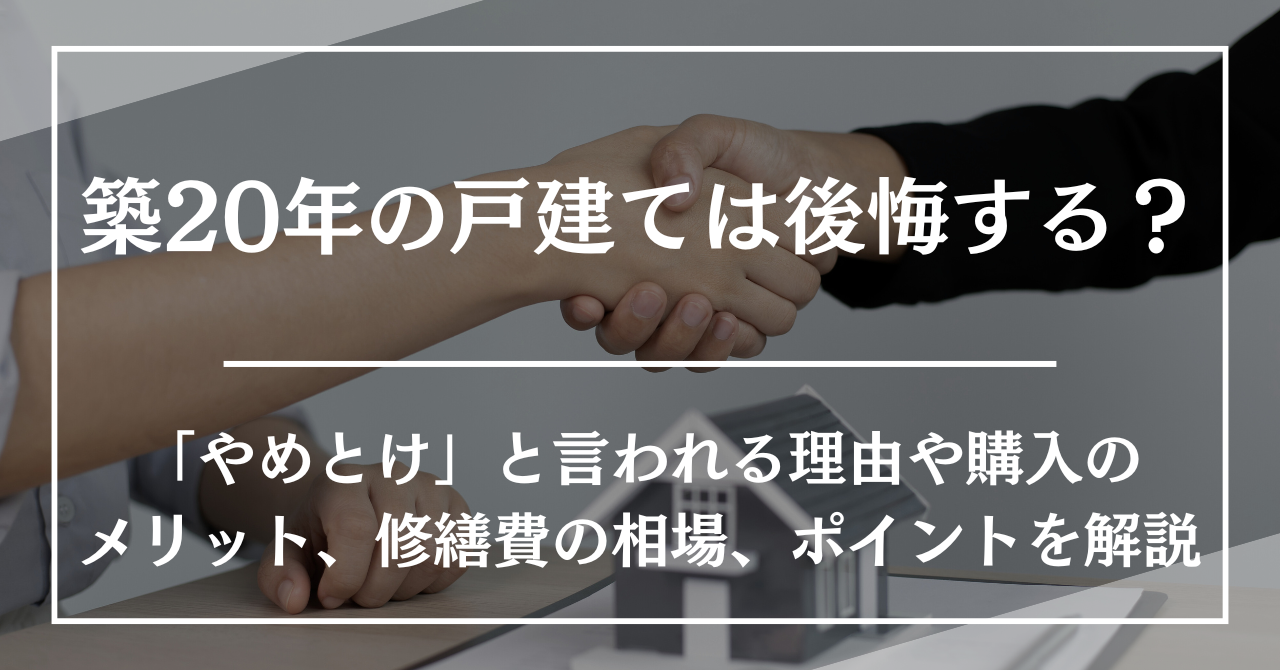※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「築20年の戸建てってすぐ壊れない?」
「住宅ローンが通らないって本当?」
「修繕費が高くつくのでは?」
そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
築20年の戸建ては「リスクがあるからやめとけ!」と言われがちですが、条件次第では賢い買い物になることもあります。
そこで本記事では、築20年の戸建てが敬遠される理由と購入のメリットについて解説します。
また、修繕費の目安や中古住宅を購入するときに確認すべきポイントも紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
築20年の戸建てはあと何年住める?

建物の寿命は、築年数だけで決まるものではありません。築20年の戸建ては、適切な手入れさえすれば、50年以上にわたって長く住み続けられます。
家が使えなくなる主な原因は、建物本体の老朽化ではなく、設備や外装の消耗であるためです。
たとえば、外壁や屋根は10〜15年ごとに塗り替えや補修が必要ですし、お風呂やキッチンなどの水回り設備も20年ほどで交換時期を迎えます。
定期的な点検や、シロアリ対策、基本的なメンテナンスさえ怠らなければ、家は長持ちします。
築20年の戸建てを購入したり、住み続けたりするときは、これまでの修繕の記録を確認し、今後の修理計画を立てておくことが大切です。
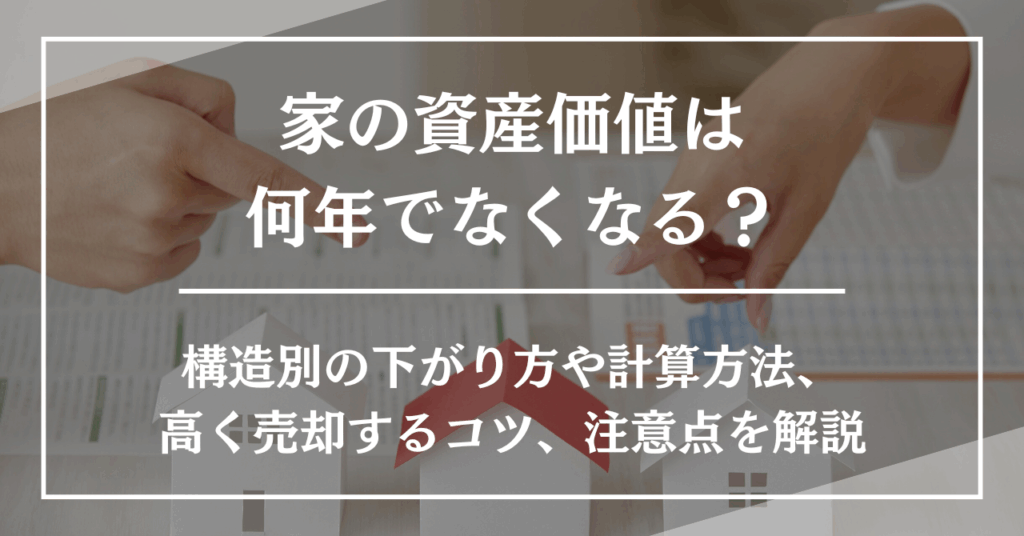
築20年の戸建ては「やめとけ」と言われる理由

築20年の戸建てが「やめとけ」と言われる背景には、修繕費や耐震性能の不安など複数のリスクが挙げられます。
ここからは、中古住宅を購入する主な4つの懸念点について詳しく解説します。
1.建物の劣化により修繕費がかさむ可能性がある
一般的な住宅設備の寿命は15~20年程度です。
そのため、築20年を過ぎると外壁や屋根、水回りといった主要部分の劣化が一気に進み、修繕費が数百万円規模になることも珍しくありません。
劣化の進行度は立地条件やメンテナンス履歴によって大きく変わります。
たとえば、海沿いや豪雪地帯では塩害や凍害で劣化が早まりますし、定期的に手入れされていない物件では想定外の補修が必要になるケースもあります。
中古住宅では、とくに床下や屋根裏など見えない部分の劣化を把握することが困難であるため、購入後に予期せぬ出費が発生することがあります。
2.耐震性能が現行基準に満たないことがある
築20年前後の戸建ては2000年の建築基準法改正前後に建てられた物件が多く、現行の耐震基準を満たしていない可能性があります。
2000年基準では基礎の仕様や壁の配置バランスが厳格化され、それ以前の建物では耐震性に課題があるケースも見られます。
たとえば、旧基準の建物では基礎の鉄筋量が不足していたり、耐力壁の配置が偏っていたりすることがあります。
大地震時の倒壊リスクを減らすには、耐震診断を受けて必要に応じて補強工事を行う必要があります。
補強工事の費用は建物の状態により異なりますが、一般的に100万円から200万円程度が目安です。
3.住宅ローンの審査に影響することがある
築20年の戸建ては残りの法定耐用年数が短いため、住宅ローンの借入期間が制限されることがあります。
木造住宅の法定耐用年数は22年とされており、築20年では建物残存価値はほぼゼロと判断されるためです。
借入期間が短くなると月々の返済額が増え、家計を圧迫する原因になります。
また、金融機関によっては築25年以上の物件は融資対象外としているところもあり、希望額を借りられない場合があります。
一方で、適合証明書を取得すれば融資の通過率も上がるため、購入前に複数の金融機関に相談し、資金計画を立てることが大切です。
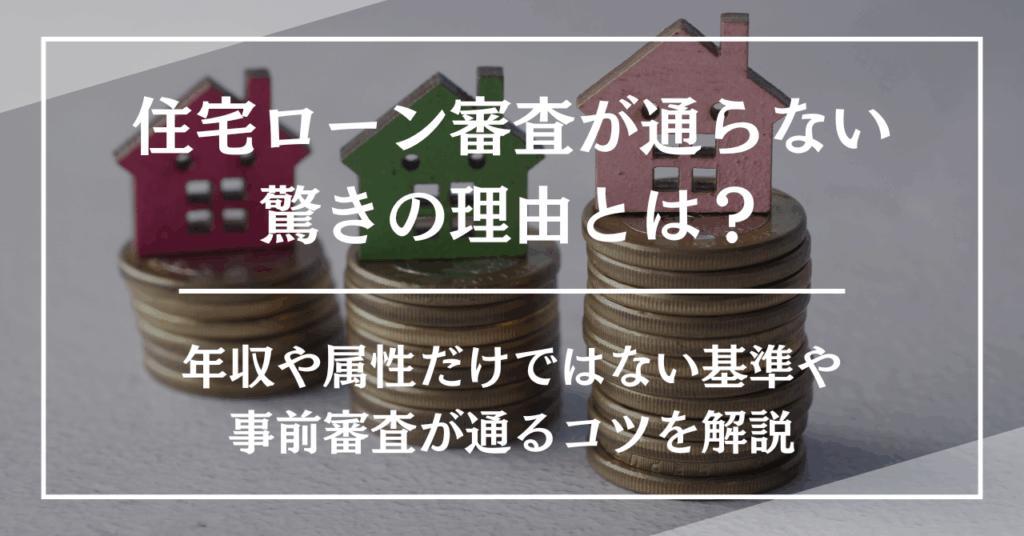
4.ひと昔前のデザインや設備が多い
築20年の戸建ては2000年代前半の建築であり、間取りや内装が現代のライフスタイルに合わないことが少なくありません。
たとえば、リビングが狭い、収納が不足している、和室中心の間取りといった特徴が見られます。
設備面でも古い給湯器やキッチン、浴室が残っていることが多く、省エネ性能や使い勝手で現代の基準に劣ります。
これらはリフォームによって改善できる問題ですが、その分の自己負担額が大きくなる点でデメリットと言えます。
さらに、「まずは最新の住宅トレンドや各メーカーの特徴を知りたい」という段階であれば、一度の入力で複数のハウスメーカーへまとめて資料請求できるサービスも便利です。
気になる会社のプランや設備仕様を自宅で比較できるため、リフォーム・建て替え・新築など、これからの住まい探しをより具体的に検討しやすくなります。
▼簡単な本人確認を経て資料が届くシステムなので、早めに情報収集を始めたい方にとって、効率よく検討を進められる選択肢のひとつです。
![]()
築20年の戸建てを購入するメリット

築20年の戸建ては価格の安さや立地の良さ、リノベーションの自由度など、新築にはないメリットが豊富です。
ここからは、中古住宅を購入する具体的な6つのメリットを詳しく解説します。
1.新築の2~5割程度安い
築20年の戸建ては同じ立地の新築物件と比較して、2割から5割程度安く購入できる場合があります。
税法上の評価で築20年を超えると建物の資産価値がほぼゼロと見なされ、不動産査定価格も大幅に下がるためです。
たとえば、新築で4,000万円の物件を、築20年なら2,000万円台で購入できる可能性もあります。価格が安い分、資金に余裕ができ、リフォームや必要な修繕に費用を回せます。
また、建物の評価額が低いことで毎年の固定資産税も安くなるため、初期費用とランニングコストの両面で家計に優しい、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢といえます。
2.資産価値が下がりにくい
築20年を過ぎた戸建ては、それ以降の価格下落が緩やかになる傾向があります。
不動産の価格は築年数とともに下がりますが、築20年前後で下落カーブが底を打ち、その後は土地の価値が中心となって価格が安定するためです。
土地の価値は立地条件で決まるため、エリアの人気が維持されれば資産価値も保たれます。
築20年の中古住宅は将来売却するときにも、購入価格から大きく値崩れするリスクが少なく、資産として持ちやすいことが特徴です。
築20年の物件を候補にしつつ、「新築ならどれくらい違うのか」や「他メーカーのプランも比較したい」と感じた場合には、一度の入力で複数のハウスメーカーへ資料請求できるサービスを活用すると検討がぐっと進めやすくなります。
最新の設備仕様や間取り、価格帯を自宅でまとめて確認できるため、築古物件の購入・リフォームとの比較もしやすく、予算配分のイメージを具体化するのに役立ちます。
▼まずは情報を揃えて判断したいという方にとって、効率よくモデルプランを集められる便利な方法です。
![]()
3.実物を見たうえで決められる
新築物件では完成前に契約することが多く、図面やモデルルームだけで判断しなければなりません。
一方で、築20年の戸建てなら、実際の建物を内覧し、日当たりや風通し、周辺環境まで確認したうえで購入を決められます。
現況を見ることで修繕が必要な箇所や劣化の程度を把握でき、購入後の修繕計画を具体的に立てやすくなります。
また、写真や図面ではわからない生活動線や収納の使い勝手、騒音なども体感できるため、入居後のギャップが少なくなります。
さらに、隣人の様子や近隣施設の利便性など、実際に住んでみないとわからない情報も事前に確認でき、新築にはない大きなアドバンテージです。
4.住宅ローン控除を受けられる
築20年の戸建ても、一定条件をクリアすれば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が適用され、税制面で大きなメリットが得られます。
中古住宅の場合、1982年1月1日以降に建築された住宅または耐震基準適合証明・既存住宅性能評価書などで証明された住宅が対象となります。
控除額は「年末ローン残高 × 0.7%」が基本で、一般住宅は借入上限2,000万円、認定住宅・省エネ性能適合住宅などは上限3,000万円となります(年間上限額:一般住宅14万円、認定住宅等21万円)。
控除期間は原則10年ですが、一定要件を満たすと13年に伸びる場合もあります。
さらに、耐震基準適合証明書を取得すれば、登録免許税や不動産取得税の軽減措置も併せて利用でき、購入時のコストを抑えることにつながります。
参照:No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
5.希望地域や好立地で見つかりやすい
都市部や駅近といった人気エリアでは新築物件の数が限られていますが、中古物件なら選択肢が豊富にあります。
とくに築20年前後の戸建ては流通量が多く、複数の選択肢から比較検討できるため、立地条件を妥協せずに済みます。
たとえば、子どもの通学可能エリアに絞って物件を探している方や、職場からのアクセスを最重要視している方は、中古物件も視野に入れて物件探しをすることをおすすめします。
予算内で立地の良い家を選べる可能性が高まります。
6.リフォームで自分好みにアレンジできる
築20年の戸建ては既存の間取りや設備が古い反面、リフォームやリノベーションで自分好みに作り変えられる自由度があります。
自分たちの好みや家族構成に合わせて一から設計できるため、デザイン性を重視した中古リノベーションの需要は年々増加しています。
たとえば、壁を取り払って開放的なLDKにしたり、収納を増やしたり、最新設備を導入したりと、ライフスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。
フルリノベーションを行っても新築を購入する場合に比べて、総額が抑えられるケースも多く、費用を抑えながら理想の住まいを実現できます。
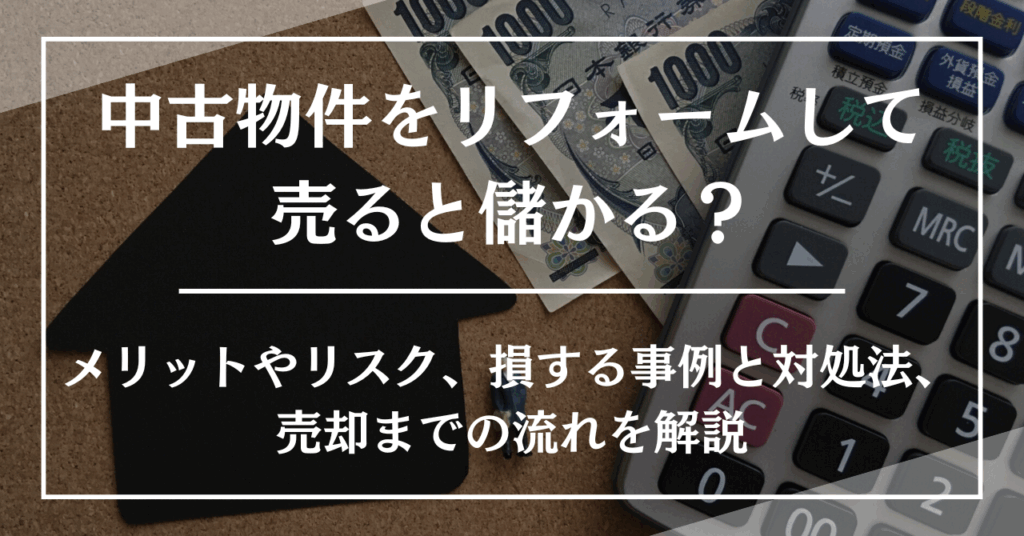
築20年の戸建てにかかる修繕費の目安

築20年の戸建ては外装、水回り、給湯器などで修繕が必要になるタイミングです。
以下の表で主な修繕箇所と費用目安をまとめました。
| 施工箇所 | 費用目安 | 交換・補修目安(寿命・周期) |
|---|---|---|
| 屋根・外壁(塗装・張替え含む) | 80万~150万円(30坪戸建ての場合) | 10~15年ごとに再塗装、20〜30年で張替え・重ね張りも検討 |
| 水回り(キッチン・浴室・トイレ等) | 100万~150万円程度(全面交換を含む) | 設備の寿命は15~20年、配管や給排水はそれより早めに劣化確認 |
| 給湯器・配管類 | 20万~40万円程度 | 給湯器本体は10~15年程度、配管・接続部分は早めに劣化確認 |
| 内装(クロス・床材等張替え) | 50万~80万円程度(30坪規模) | クロスは10~15年、床材は15〜20年程度が目安 |
| 白アリ防除・構造確認 | 10万~30万円程度(点検・予防含む) | 防蟻処理は5~10年ごとに再処理、構造体は定期点検が重要 |
修繕費は物件の状態や使用されている材料によって変動しますが、一般的には購入価格に加えて200万円から300万円程度を見込んでおくのが現実的です。
購入前にホームインスペクションを実施し、必要な修繕箇所を洗い出しておくことで、予算オーバーを防げます。
また、築20年の物件購入を前提に、「どこまでリフォームすべきか」「費用感が分からない」と感じた場合には、複数のリフォーム会社から見積もりを比較できる無料サービスを利用すると判断がしやすくなります。
建物の状態や施工内容によって費用が大きく変わるため、プロのアドバイザーを通して複数社を紹介してもらえる仕組みは、適正価格や信頼できる会社を見つけるうえで非常に役立ちます。
▼リビングの拡張や水回りの刷新など、具体的な希望に合わせたプランをまとめて把握でき、無理のない予算で理想の住まいを実現する心強いサポートとなるでしょう。
![]()
築20年の戸建てを購入するときに確認すべきポイント

築20年の戸建てを購入するときは、建物の安全性と正確な現状確認が不可欠です。
ここからは、中古住宅を購入する前に必ずチェックすべき5つのポイントを解説します。
1.ホームインスペクション実施の有無
ホームインスペクションとは、建物の劣化状況や不具合の有無を専門家が診断する建物診断のことです。
診断では基礎のひび割れ、外壁の劣化、屋根の状態、床下の湿気やシロアリ被害、給排水設備の不具合などを細かくチェックします。
第三者の目で確認できるため、購入後のトラブルを未然に防げることがメリットです。費用は5万円から10万円程度で実施できます。
売主がすでに実施している場合は報告書を確認し、未実施なら購入条件としてインスペクションを依頼することがおすすめです。
2.修繕・メンテナンス履歴の有無
定期的な修繕やメンテナンスの記録が残っている物件は、建物の状態が良好である証拠であり信頼性が高いといえます。
たとえば、外壁塗装や屋根補修、給湯器交換、防蟻処理などを実施している場合は、実施年月日と内容を確認しましょう。
修繕履歴があれば次回のメンテナンス時期を予測しやすく、購入後の資金計画が立てやすくなります。
逆に修繕履歴がまったくない物件は、見えない部分で劣化が進んでいる可能性があります。
その場合は購入後すぐに大規模な修繕が必要になるリスクを見込んで、予算に余裕を持たせる必要があります。
3.水回り設備の劣化状況
水回り設備は築15年を超えると配管の腐食や給湯器の劣化が進み、交換が必要になります。
キッチンや浴室、洗面台、トイレの状態を入念にチェックし、交換費用をリフォーム予算に計上しておきましょう。
とくに注意すべきは配管の状態です。赤水が出る、水漏れの跡がある、排水の流れが悪い、異臭がするといった症状がある物件は、配管全体の交換が必要になる可能性が高いです。
あわせて、内覧時には実際に水を流してみて、給湯器の水圧や排水の状態を確認してみましょう。設備の型番から製造年を調べることもできます。
こうした水回りの劣化が気になる場合は、早い段階で複数のリフォーム会社に見積もりを取り、必要な工事内容と費用感を把握しておくと安心です。
▼設備交換や配管工事は会社ごとに価格差が大きく、工期や提案内容も異なるため、一括で比較できるサービスを活用すると、無駄のない予算組みがしやすくなります。
![]()
4.床下や屋根裏の瑕疵
床下や屋根裏は普段目に触れない部分ですが、シロアリ被害や雨漏りといった深刻な問題が隠れている可能性があります。
これらの瑕疵は修繕に高額な費用がかかるため、購入前に専門業者による点検を受けることがおすすめです。
たとえば、シロアリは木造住宅の大敵で、被害が進むと建物の強度が著しく低下します。
床下を懐中電灯で照らして木材の状態を確認し、柱や土台に食害の跡がないかチェックしましょう。
また、天井や梁に水染みやカビがあれば、過去に雨漏りがあった証拠です。売主に修繕歴があるかを確認し、再発のリスクを確認しておくことが大切です。
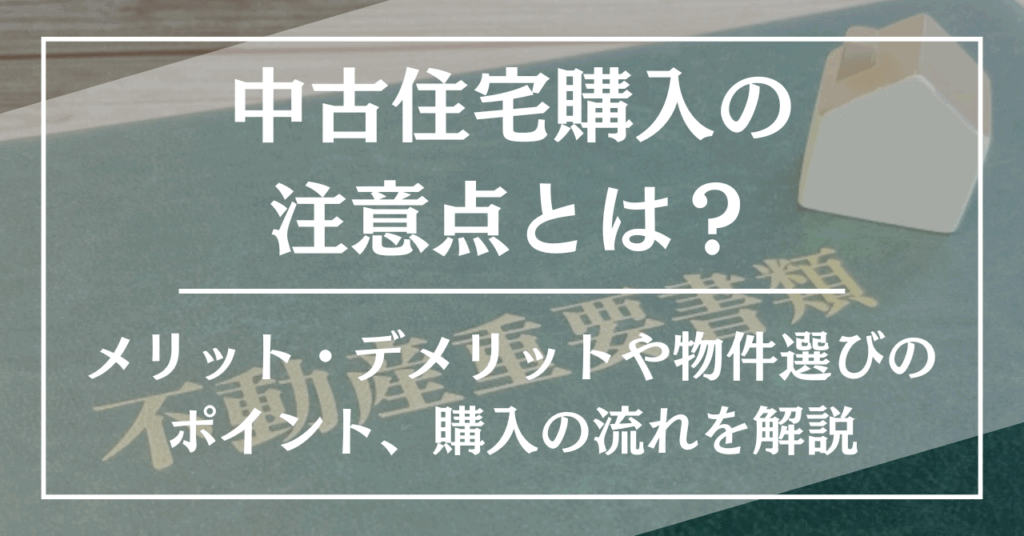
5.隣地との境界線
隣地との境界が不明確な物件は、将来的にトラブルの原因となったり、建て替え時に再建築ができなくなったりするリスクがあります。
境界杭や境界標が設置されているか、測量図が保管されているかを必ず確認しましょう。
万が一、境界が確定していない場合は、隣地所有者と立ち会いのもと境界確定測量を行うことが有効です。
測量には土地家屋調査士への依頼が必要で、費用は20万円から30万円程度かかります。
また、登記簿謄本や公図、測量図などの書類を法務局で取得し、敷地の正確な範囲を把握しておくことも重要です。境界問題は購入前に必ず解決しておきましょう。
築20年の戸建てを購入するときによくある質問

築20年の戸建て購入にあたっては、専門的な内容を事前に理解しておくことが重要です。
ここからは、よくある3つの質問に宅建士の視点から回答します。
1.契約不適合責任の期間とは何ですか?
契約不適合責任とは、売主が買主に引き渡した不動産に契約内容と異なる欠陥や不具合があった場合に、売主が負う責任のことです。
民法では買主が不適合を知ってから1年以内に売主に通知すれば、修補請求や損害賠償、代金減額、契約解除などを求められるとしています。
一方で、個人間の中古住宅売買では、引渡し後3か月程度に責任期間を短縮する特約を付けることが一般的です。
これは建物の欠陥がもともとのものなのか、経年劣化によるものなのかの判断が難しいためです。契約書には責任の範囲や期間が明記されているため、署名前に必ず確認しましょう。
とくに「売主は一切の責任を負わない」という免責特約がある場合は、購入後に不具合が見つかっても補償を受けられないため、慎重な判断が必要です。
2.再建築不可物件は購入できますか?
再建築不可物件とは、建築基準法第43条の接道要件を満たしていないため、現在の建物を取り壊すと新たに建物を建てることができない物件のことです。
原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地がこれに該当します。
再建築不可物件は、価格が周辺相場より大幅に安いため魅力的に見えますが、増改築にも制限があり、住宅ローンも組みにくいというデメリットがあります。
将来売却するときも買い手が限られるため、流動性が非常に低く資産価値も期待できません。
購入自体は可能ですが、現金一括購入が前提となり、大規模なリフォームもできないリスクを理解したうえで判断する必要があります。
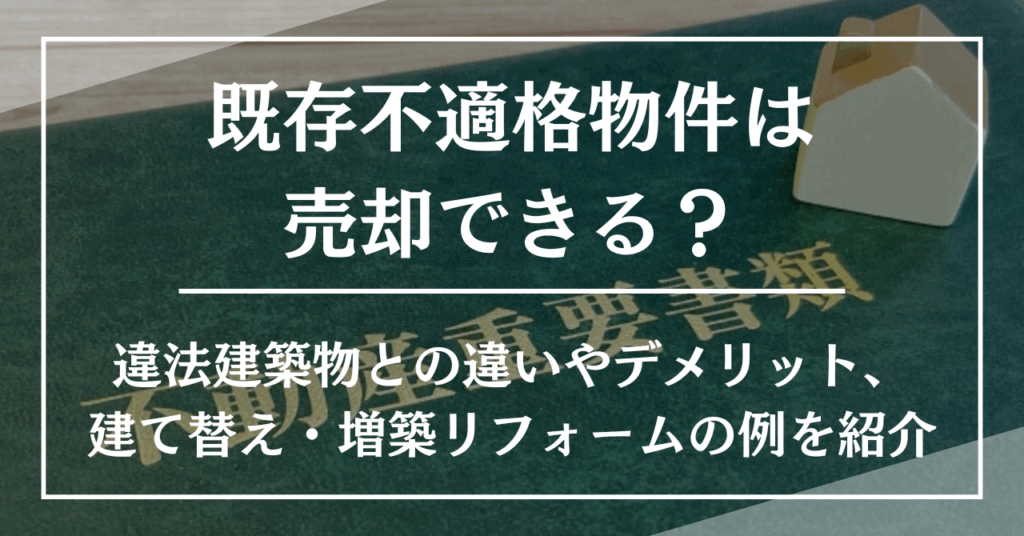
3.要セットバック物件とは何ですか?
要セットバック物件とは、前面道路の幅が4メートル未満の場合に、建築基準法により道路中心線から2メートル後退(セットバック)して建物を建てなければならない物件のことです。
セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建てることも塀を設置することもできません。そのため、実際に使える土地面積が登記簿上の面積より小さくなります。
たとえば、100平方メートルの土地でも、セットバック部分が10平方メートルあれば、実効面積は90平方メートルです。
要セットバック物件では、リフォームや建て替えのときに建築可能面積が減少し、希望する間取りが実現できない可能性があります。
このように、要セットバック物件は建築できる範囲が制限されるため、将来的に建て替えや間取り変更を検討している場合は、事前に複数の住宅メーカーのプランや提案を比較しておくことが重要です。
▼一度の入力で複数のハウスメーカーへ資料請求できるサービスを利用すれば、希望の広さや間取りが実現可能かどうか、最新の建築事例や設備仕様を自宅でじっくり確認できます。
![]()
築20年の中古住宅はメリットとリスクを理解して購入しよう!

築20年の戸建ては価格の安さと立地の良さで非常に魅力的な選択肢ですが、修繕費や耐震性などのリスクも考えられるため慎重な判断が必要です。
購入前にはホームインスペクションで建物の状態を把握し、修繕履歴や耐震性能を重点的に確認しましょう。
また、住宅ローン控除などの税制優遇も受けられるため、条件を満たしているか事前に確認することをおすすめします。
修繕費を含めた総合的な資金計画を立て、専門家のアドバイスを受けながら進めることで、満足度の高いマイホーム購入を実現してください。