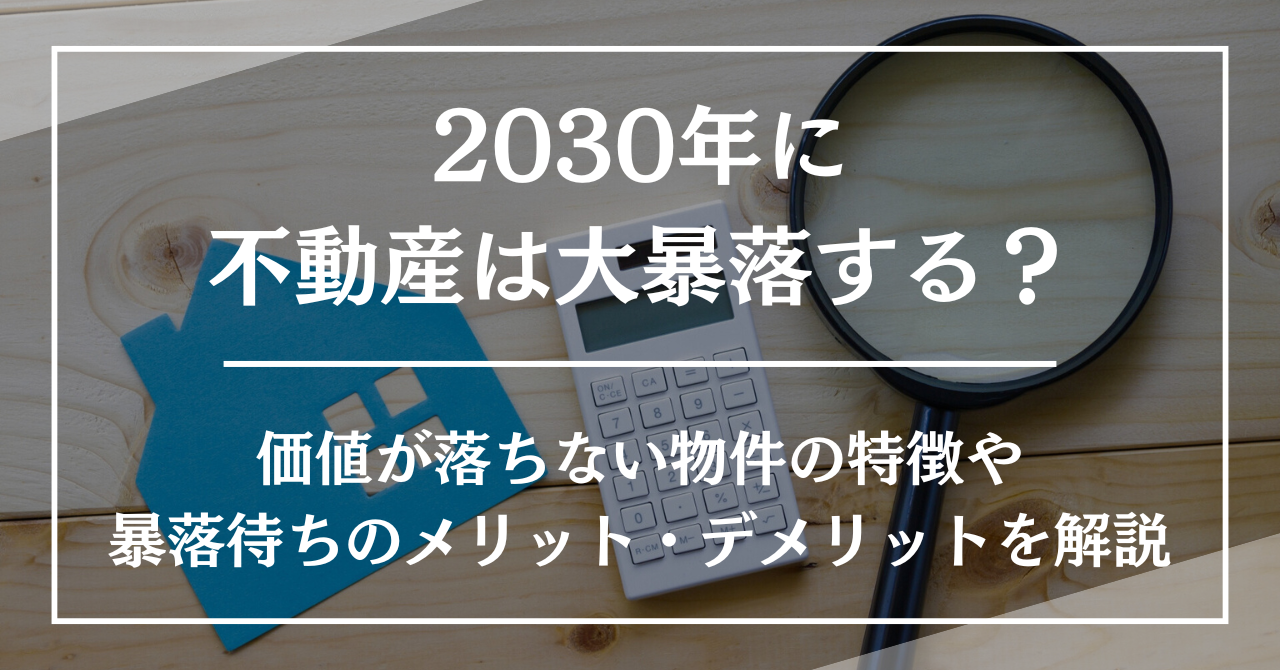※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「マイホームを買うなら今か、数年後がいいのか?」
「2030年に不動産が暴落するって本当なのか?」
「資産価値が落ちない物件はどう見極めるのか?」
実は2030年には「団塊世代の相続」と「人口減少」が重なり、不動産市場に大きな変化が訪れると予測されています。
将来の住まいや投資判断に迷う方も多いでしょう。
そこで本記事では、不動産が大暴落すると言われる「2030年問題」とは何かを解説します。
また、暴落待ちのメリットやデメリット、価値が落ちない物件の特徴についても紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
不動産が大暴落する「2030年問題」とは?
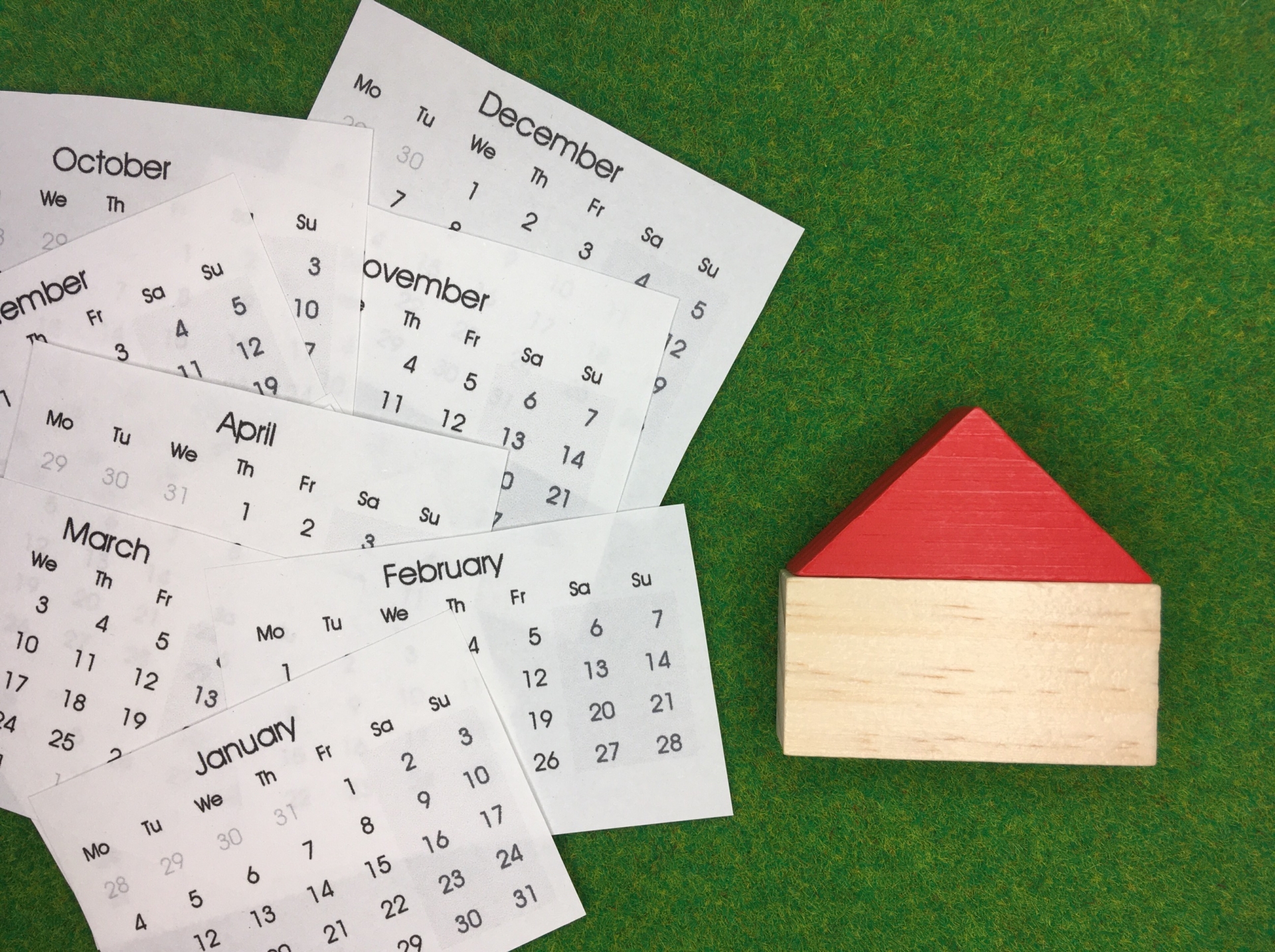
2030年、日本の不動産市場は立地と性能によって明確な価値の格差が生まれると予測されています。
これは「大暴落」というより、優良物件と劣化物件の「二極化」が進むことを意味します。
その主な理由は団塊世代の相続問題です。
団塊世代とは、1947年から1949年に生まれた後期高齢者世代のことを指し、2030年時点では全員が80歳以上です。
これにより相続した不動産を売却する動きが活発化し、市場に大量の物件が供給される可能性があります。
2023年10月1日時点でも全国の空き家数は900万戸に達し、空き家率は13.8%と過去最高を記録しています。
築年数の古い物件の老朽化も進んでおり、これらの要因が重なることで不動産価格への下落圧力が強まると考えられています。
参照:令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果|総務省

2030年問題で住宅価格が大暴落すると言われる理由

団塊の世代の人口が大幅に減少することで引き起こされる2030年問題ですが、不動産業界には以下の影響を及ぼします。
1.相続による空き家の増加
2.買主・借主の母数が減少
3.空き家の老朽化
結果として、「2030年に住宅価格が大暴落する!」と言われています。理由をそれぞれ解説します。
1.相続による空き家の増加
団塊世代の死亡者数増加により、相続によって取得した物件が市場に大量放出される可能性が高まっています。
「その他空き家」と呼ばれる既存住宅ストックの空き家は、1998年から2018年までの20年間で1.9倍に増加しました。
相続した物件の多くは維持管理が困難で、売却を選択する相続人が増える傾向にあります。
団塊世代の死亡率上昇に伴い、戸建用地の売却数が一気に増加する可能性が指摘されています。
これにより需要と供給のバランスが崩れ、価格下落の要因となることが予想されます。
2.買主・借主の母数が減少
少子化と人口減少により、不動産を購入する人の数そのものが大幅に減少します。
総人口が2030年に約1億1,900万人まで減少する中で、とくに住宅ローンを利用できる生産年齢人口の大幅減少が深刻な問題となります。
具体的には、2015年から2030年の間に、15歳から64歳までの働き世代である生産年齢人口は、約853万人も減少すると予測されています。
働いて収入を得る人が減れば、住宅購入の需要も自然と縮小します。
需要が減る一方で供給が増える状況は、経済の基本原理に従って価格下落圧力を生み出します。
これまで支えてきた買主が少なくなることで、不動産価格の値崩れリスクが高まることは避けられないのが現実です。
3.空き家の老朽化
空き家の多くは築年数が古く、維持管理コストや修繕リスクが価格低下の大きな要因となっています。
「その他空き家」約349万戸のうち、一戸建てが72.2%(約252万戸)、うち木造が68.8%(約240万戸)で、昭和55年以前に建築されたものが多数を占めています。
さらに築40年以上の分譲マンションストックは、2012年末の約29.3万戸から2022年末には約125.7万戸へと大幅に増加しました。
築年数の古い物件は耐震性や設備の老朽化により、購入者から敬遠される傾向が強く、価格競争力を失いやすいのが現状です。
古い物件や空き家の売却は、築年数や老朽化の影響で価格が下がりやすいため、複数の業者に査定を依頼して適正価格を確認することが大切です。
▼一括査定サービスを利用すれば、短時間で複数社の査定を比較でき、納得のいく売却計画を立てられます。
![]()
2030年まで暴落待ちするメリット
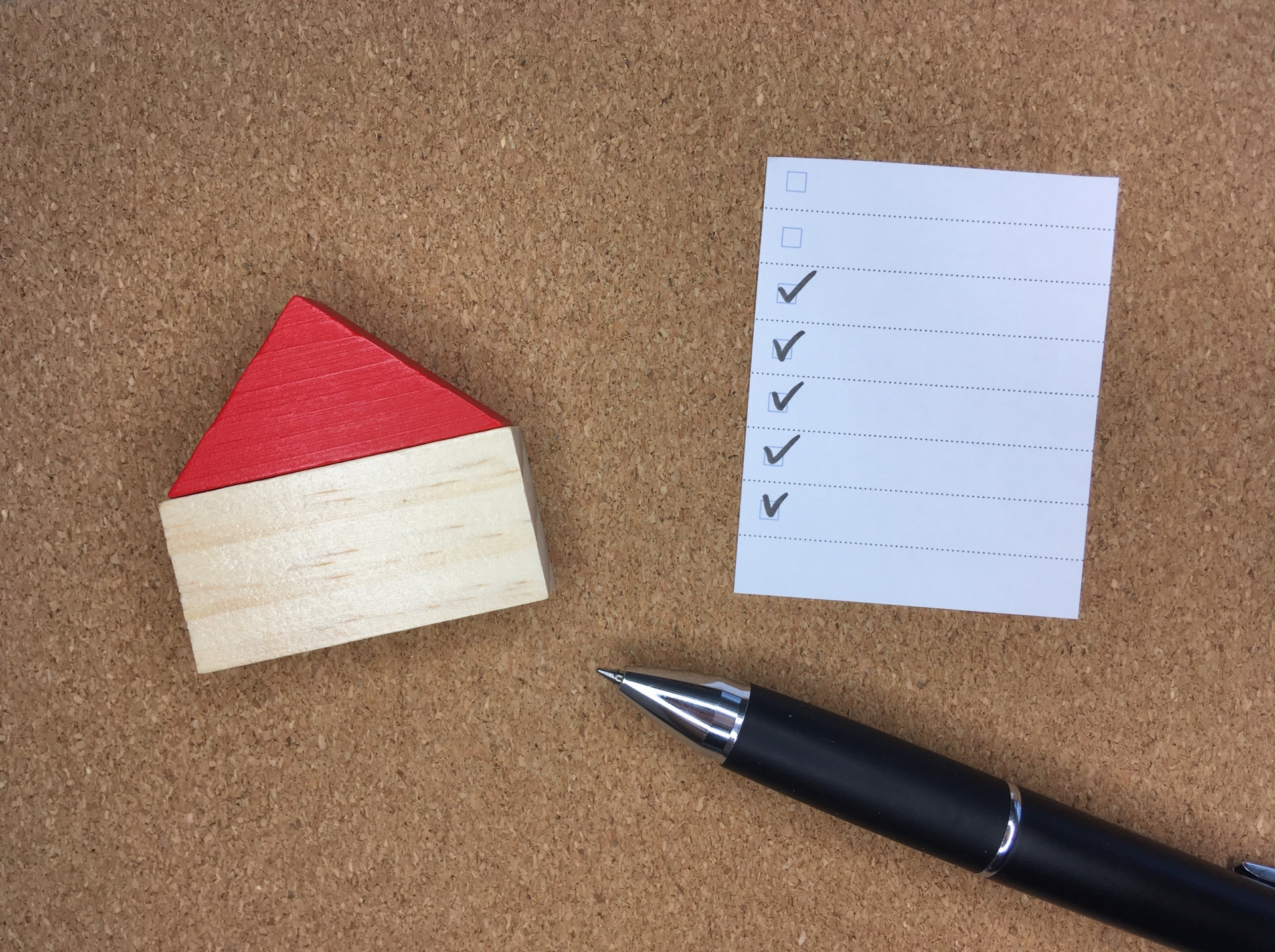
2030年に日本の不動産市場は需要と供給のバランスが崩れると予想されています。
そこで、「今は不動産の購入を控えて、将来買った方が安く手に入るのでは?」と考える方もいるでしょう。
いわゆる「暴落待ち」をすることによって得られるメリットは以下の通りです。
1.時代の流れを考えると合理的
2.不動産バブルの高値掴みを回避
3.二極化が顕在化してから購入可能
それぞれ解説します。
1.時代の流れを考えると合理的
人口減少と高齢化が進む中で不動産購入を待つことは、長期的な視点で見れば合理的な判断といえます。
空き家率の上昇と供給過剰が進展することで、これまで「手の届かない物件」が購入可能な価格帯に下がる可能性があります。
とくに立地条件の良い物件でも、需要と供給のバランス変化により、現在より割安で購入できる機会が増えると予想されます。
時代の大きな流れに逆らわず、市場の変化を待つことで、将来的に選択肢が広がることは、購入者にとって大きなメリットです。
逆に言うと、現在は売却市場が活発で、需要のあるタイミングでもあります。
▼複数の業者に査定を依頼して今の資産価値を把握することで、納得のいく売却判断につなげられます。
![]()
2.不動産バブルの高値掴みを回避
「暴落待ち」は、現在の不動産価格高騰期に購入することで生じる「高値掴み」のリスクを回避できます。
不動産経済研究所は、「2025年上半期の首都圏における戸当たり価格の中央値は6,898万円と、前期(2024年下半期)の6,458万円から440万円、6.8%上昇している」と発表しています。
価格が高騰している現状で急いで購入するよりも、将来の価格下落を見極めてから購入することで、資産価値の目減りを最小限に抑えることができます。
とくに投資目的で不動産を購入する場合、購入時期の見極めは収益性に直結する重要な要素です。
引用:首都圏マンション戸当たり価格と専有面積の中央値の推移2025年上半期|不動産経済研究所
3.二極化が顕在化してから購入可能
2030年頃までに価値が残る物件と価値が下落する物件の差が明確になることで、投資リスクを避けやすくなります。
実際に、地価や人気立地以外の地域では、すでに価格下落のリスクが指摘されている状況です。
市場の二極化が進むことで、将来性のある物件とそうでない物件の見分けがつきやすくなります。
この判断材料が豊富になることで、より確実性の高い不動産投資や住宅購入の決断ができるようになります。
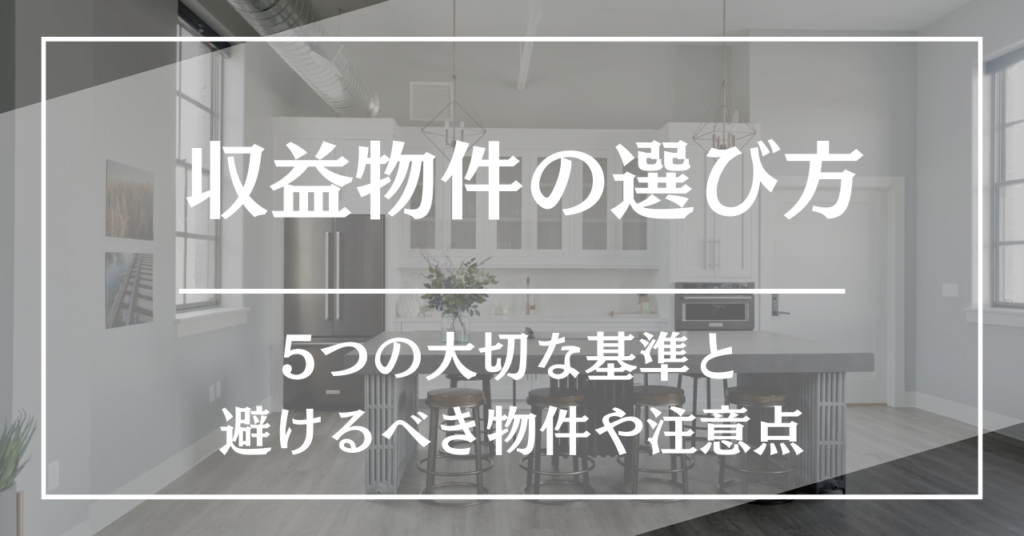
2030年まで暴落待ちするデメリット

一方で、2030年まで「暴落待ち」することで購入者にとってデメリットとなる状況も考えられます。
1.国土構造の変革
2.インターネットの普及
3.住宅ローン金利や経済状況の変化
それぞれ解説します。
1.国土構造の変革
人口減少に伴うインフラ維持コストの増大や地域の過疎化は、不動産購入後の資産価値に悪影響を与える可能性があります。
実際に地方では空き家率が高く、地域間格差が拡大している現状があります。
待っている間に地域そのものの魅力や機能が低下してしまえば、安く購入できても結果的に損失を被ってしまうでしょう。
また、リニア中央新幹線の開通に代表されるように、移動時間を短縮して人生の選択肢を広げるイノベーションの可能性があります。
実際に開通すると東京から大阪までが67分と、新幹線の半分の所要時間で十分になります。
週末だけ地方で過ごす2拠点生活が身近になると、住宅の需要と供給のバランスに新たな風が吹く可能性もあります。
そのため、現時点での資産価値を把握しつつ、国土構造の変化を慎重に見極める必要があります。
▼売却の理由がある方は、複数の業者に一括査定を依頼して今の相場感を確認するのがおすすめです。
![]()
2.インターネットの普及
コロナ渦以降、テレワークの普及などにより、居住地選択の価値観が大きく変化しています。
これまでの「駅近・都心アクセス重視」から、郊外や地方でも快適に働ける環境が整ったことで、立地に対する需要構造が変わりつつあります。
たとえば、若年層が都市から地方へ移住する動きも報じられており、従来の立地重視の傾向に変化が見られます。
これまでの常識で「価値が下がる」と思われていた郊外・地方物件でも、意外な需要が生まれる可能性があります。
暴落を待つことで、こうした新しい価値創造の機会を逸してしまうリスクも考慮する必要があります。
3.住宅ローン金利や経済状況の変化
暴落を待つことによる機会費用として、金利上昇や経済状況の変化があります。
現在の低金利環境が続く保証はなく、住宅ローン金利が上昇すれば借入コストが増加します。
仮に不動産価格が下落しても、金利上昇による支払い総額の増加により、実質的なメリットが相殺される可能性があります。
また、長期間の賃貸住宅費用も無視できないコストです。
経済状況の変化により収入が減少したり、購入のタイミングを逸したりするリスクも存在します。
「待つ」という選択にも相応のリスクとコストが伴うことを十分理解した上で判断することが重要です。
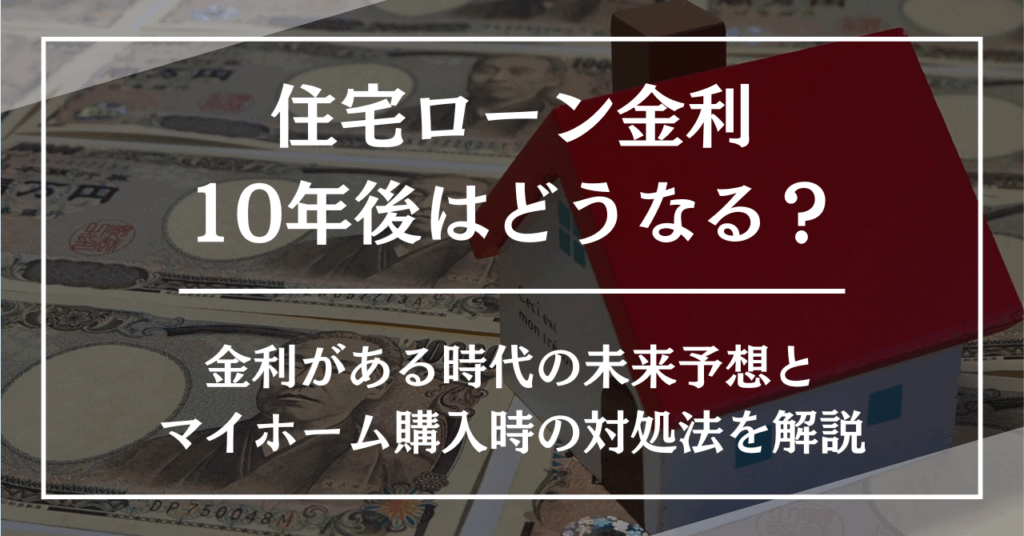
2030年に価値が落ちない物件の特徴

2030年問題によって、じりじりと住宅価格の下落が発生することが予想される中、今から暴落しない不動産を購入したい方は、以下の特徴を持つ不動産を購入することをおすすめします。
1.立地評価の基準が高い
2.建築物の性能が高い
3.市場の流通量が低い
それぞれ解説します。
1.立地評価の基準が高い
駅近・都心アクセス良好・商業施設や公共施設が充実している立地の物件は、人口減少下でも価値を維持しやすい特徴があります。
たとえば、東京23区の中心部や主要駅から徒歩5分圏内のマンションなどは、限られた土地に対する需要が安定しているため、供給過剰の影響を受けにくいと考えられます。
交通の利便性が高く、生活に必要な施設が集約された立地は、人口が減少しても一定の需要を維持できます。
とくに高齢化が進む中では、病院や商業施設へのアクセスの良さが重視される傾向にあるため、このような条件を満たす立地の物件は価値の下落リスクが低いといえるでしょう。
▼もしあなたの物件がこうした条件に該当する場合、資産価値を正しく把握するためにも、一括査定を依頼して売却の可能性を確認しておくのがおすすめです。
![]()
2.建築物の性能が高い
耐震性能・断熱性能・省エネ性能などの建築性能が高い物件は、購入者からの信頼が厚く価値が保たれやすい特徴があります。
昭和56年以降の新耐震基準に適合した物件や耐震改修を実施済みの住宅は、耐震診断での評価が高くなっています。
近年の自然災害の増加により、安全性への関心が高まっていることも、高性能物件の価値維持に寄与しています。
また、省エネ性能の高い物件は光熱費の削減効果もあり、生活コストの面でも魅力的です。
3.市場の流通量が低い
希少性のある地域や高級物件、ブランド住宅などは供給量が限られているため、価格下落の影響を受けにくい特徴があります。
都心部の高級マンションや、優れた眺望・緑地・景観などの環境資産を持つ物件は、代替性が低く独自の価値を有しています。
これらの物件は一般的な住宅市場の動向とは異なる動きを示すことが多く、景気悪化時でも相対的に価格が安定する傾向があります。
また、著名な建築家が設計した物件や歴史的価値のある建造物なども、希少性により価値を維持しやすいといえます。
市場に出回る数が少ないほど、需要と供給のバランスが価格維持に有利に働きます。
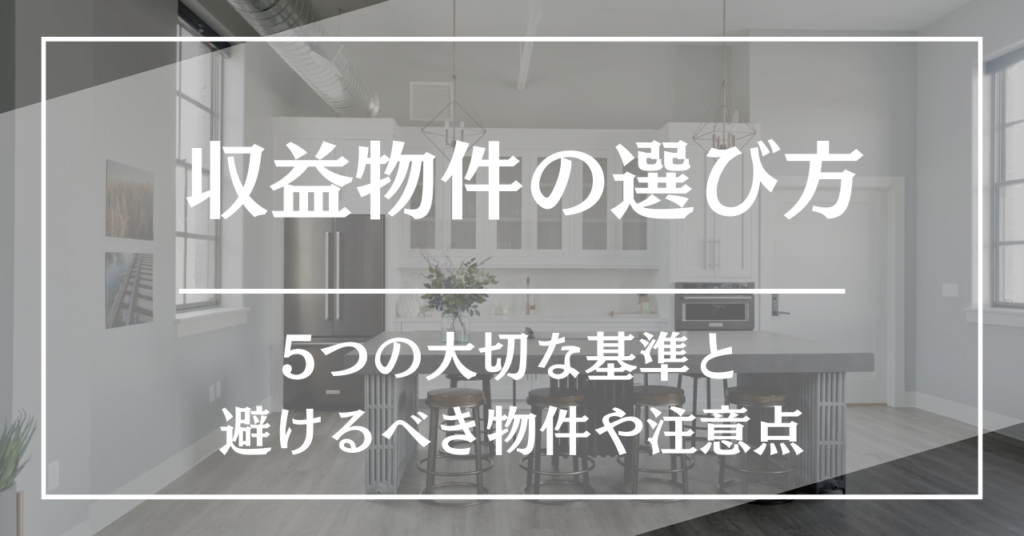
2030年問題に備えた不動産投資のポイント

不動産業界の将来を不安にさせる2030年問題ですが、しっかりと対策を取ることで成功するチャンスとなる可能性も高いです。
とくに不動産投資で物件を購入する方は、以下のポイントを押さえておきましょう。
1.テクノロジーを活用する
2.防災・減災対策に注力する
3.出口戦略を視野に入れて購入する
それぞれ解説します。
1.テクノロジーを活用する
データ分析やAI予測技術を活用することで、将来の地価動向や人口動態をより正確に見極めることが可能になります。
人口減少率の高い自治体のデータを分析し、リスクの高いエリアを事前に避けるツールなども開発されています。
国勢調査のデータや自治体の将来推計人口などを活用し、客観的な数値に基づいた投資判断を行うことが重要です。
感情的な判断ではなく、科学的なアプローチにより不動産投資のリスクを最小限に抑えることができます。
一括査定サイトに登録している宅建業者の中には、AIやデータ分析を活用してより精度の高い査定を行う業者も多数あります。
▼売却を検討している方は、こうした業者にまとめて査定依頼できる一括査定の利用がおすすめです。
![]()
2.防災・減災対策に注力する
耐震基準・耐火構造・ハザードマップを重視した物件選択により、自然災害リスクに強い不動産投資が可能になります。
耐震性が確保されている住宅の方が、購入判断において「安心感」を得やすく、市場での評価も高くなります。
近年の異常気象により自然災害が頻発している中、防災・減災対策の有無は物件価値に直結する要素となっています。
保険料の面でもメリットがあり、長期的な維持コストの削減にもつながります。
3.出口戦略を視野に入れて購入する
購入時点で出口戦略を明確にしておくことで、投資リスクを大幅に軽減できます。
具体的には、将来的な売却や賃貸を想定し、流動性の高い物件を選択することが重要です。
賃貸需要の見込める立地であれば、売却が困難な場合でも収益物件として活用する選択肢があります。
また、将来の家族構成の変化や転勤などのライフイベントにも柔軟に対応できる物件を選ぶことで、不動産投資の成功確率を高めることができるでしょう。
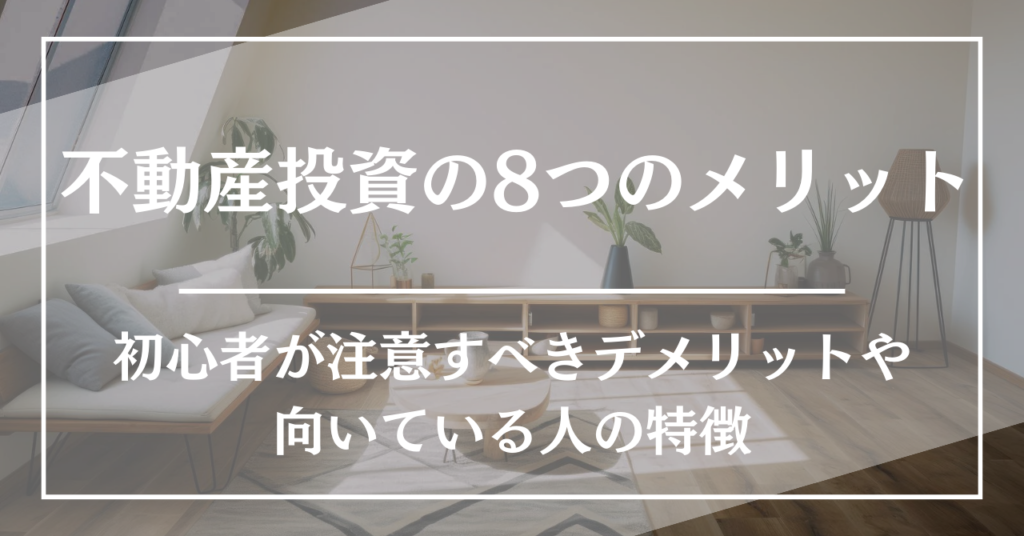
将来の資産価値を考慮して不動産を購入しよう!

2030年問題は「大暴落」ではなく「価値の二極化」をもたらすと考えられます。
高需要立地・高性能住宅は価格を維持する一方で、過疎地・築古物件は価格下落のリスクが高まります。
現在でも昭和56年新耐震基準以前の住宅が全国の住宅全体の3分の1以上を占めており、耐震改修率には地域差が大きいのが現状です。
単純に「待つ」だけではなく、立地・性能・耐震性を重視した適切な判断が必要と言えます。
市場の変化を正しく理解し、戦略的な不動産選択を行いましょう。