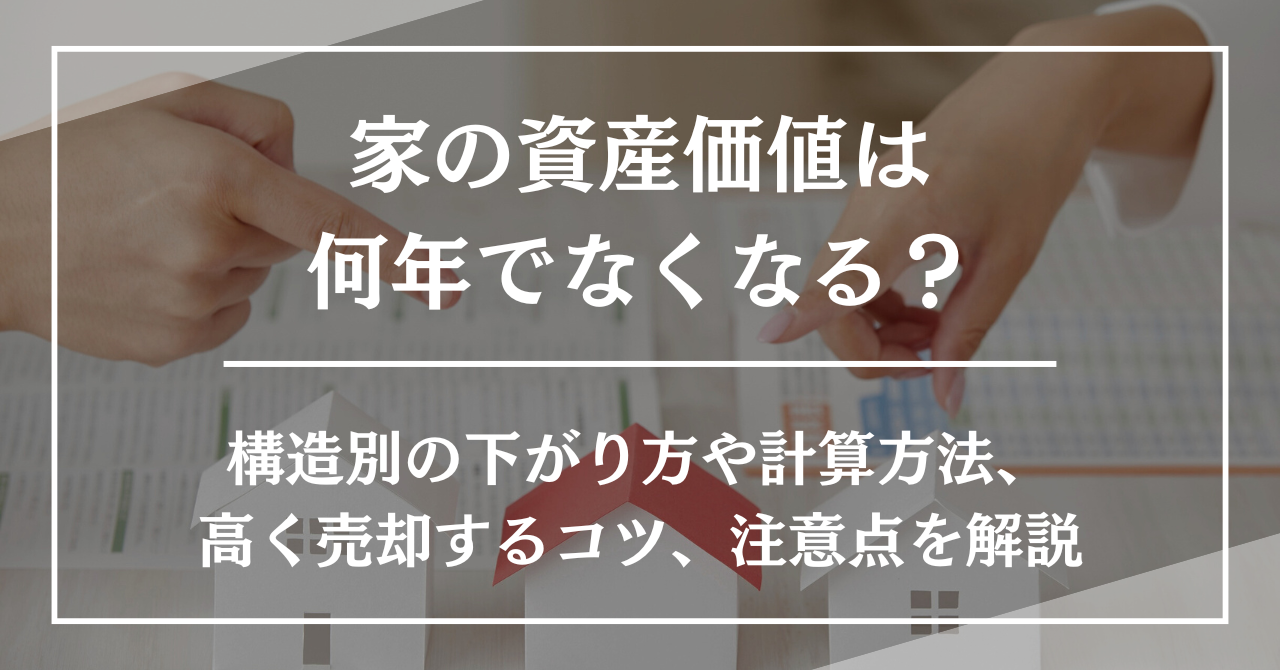※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「家って何年経つと価値がなくなるの?」
「築20年の戸建てはもう売れない?」
「リフォームすれば資産価値は上がる?」
そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。
家の資産価値は「構造」や「管理状態」、「住宅ローン金利」などで大きく変わることをご存じですか?
一概に築年数だけで判断するのは危険です。
そこで本記事では、「家の資産価値は何年でなくなるのか」を宅建士目線でわかりやすく解説します。
また、構造別の下がり方や計算方法、高く売却するコツ、注意点についても紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
家の資産価値は何年でなくなる?

戸建て住宅を所有している方にとって、建物の資産価値がどのように変化していくかは大きな関心事です。
一般的に木造戸建て住宅の建物価値は、築年数の経過とともに大きく低下し、約20年でほぼゼロになるといわれています。
ここでは築年数ごとの資産価値の変化について、具体的な数値とともに解説します。
1.築10年の戸建て住宅の資産価値は新築時の半値
築10年の木造戸建て住宅では、建物価値が新築時の約50%まで低下します。
税法上の減価償却の考え方や、実際の中古住宅市場における取引価格の分析結果に基づいても、とくに木造住宅は築15年までの下落率が大きいと言えます。
たとえば、新築時に3,000万円で購入した戸建て住宅のうち、建物部分が1,800万円だった場合、築10年後には建物評価額が約900万円にまで下がります。
一方で、土地の価値は経年劣化しないため、この時点での総資産価値は土地価格プラス900万円程度となります。
築10年では建物価値が半減するため、売却を検討するときは土地価格と合わせた総合的な評価が重要です。
こうした資産価値の変動を正しく把握するには、早い段階で複数の不動産会社に査定を依頼し、現在の市場価格を確認しておくことが役立ちます。
▼専門家による訪問査定であれば、実際の建物状態や周辺環境も踏まえた具体的な評価を受けられるため、売却プランを検討する際の判断材料として非常に有効です。
![]()
2.築20年の戸建て住宅の資産価値はほぼゼロ
築20年を超えた木造戸建て住宅の建物価値は、市場においてほぼゼロとして扱われます。
木造住宅の法定耐用年数は22年と定められており、帳簿上の建物の価値はこの期間でなくなるためです。
また、不動産業界の実務においても、築20年を超えた木造建物は資産価値がほとんど残存しないものとして査定されることが一般的です。
たとえば、築20年の戸建て住宅を売却する場合、建物評価額は購入時の1割以下となり、実質的には土地価格が売却価格の大部分を占めます。
一方で、適切なメンテナンスや管理を行っていれば、木造住宅でも法定耐用年数(22年)を超えて住み続けることは可能です。
買主側も建物の残存価値をほとんど考慮せず、土地の立地条件や広さを重視して購入判断を行うケースが多くなります。
3.築30年以上の戸建て住宅の資産価値は土地価格次第
築30年以上の戸建て住宅の資産価値は、完全に土地の評価額によって決まります。
実際に多くの不動産仲介会社では、築20年を超えた時点で建物価値をゼロとして扱うため、築30年ともなれば建物の資産価値はまったく考慮されません。
むしろ立地条件、土地の形状、周辺環境といった土地そのものの要素が価格を左右します。
築30年の戸建て住宅を売却する際は、建物を解体して更地として売却するか、古家付き土地として土地価格を基準に販売する方法が一般的です。
場合によっては買主が解体費用を負担するという条件付きで、売買価格の減額交渉があるケースも見受けられます。
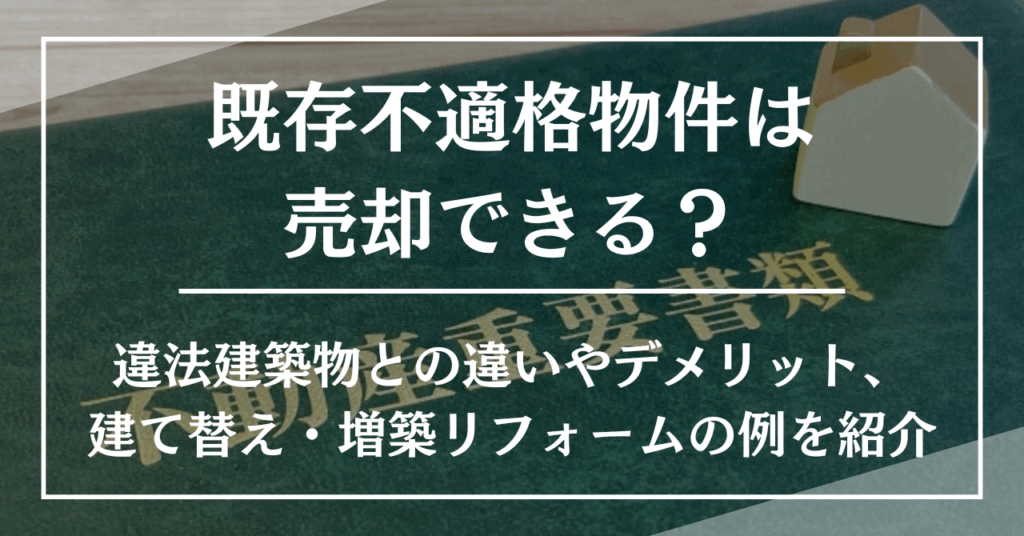
構造別で見た資産価値の下がり方
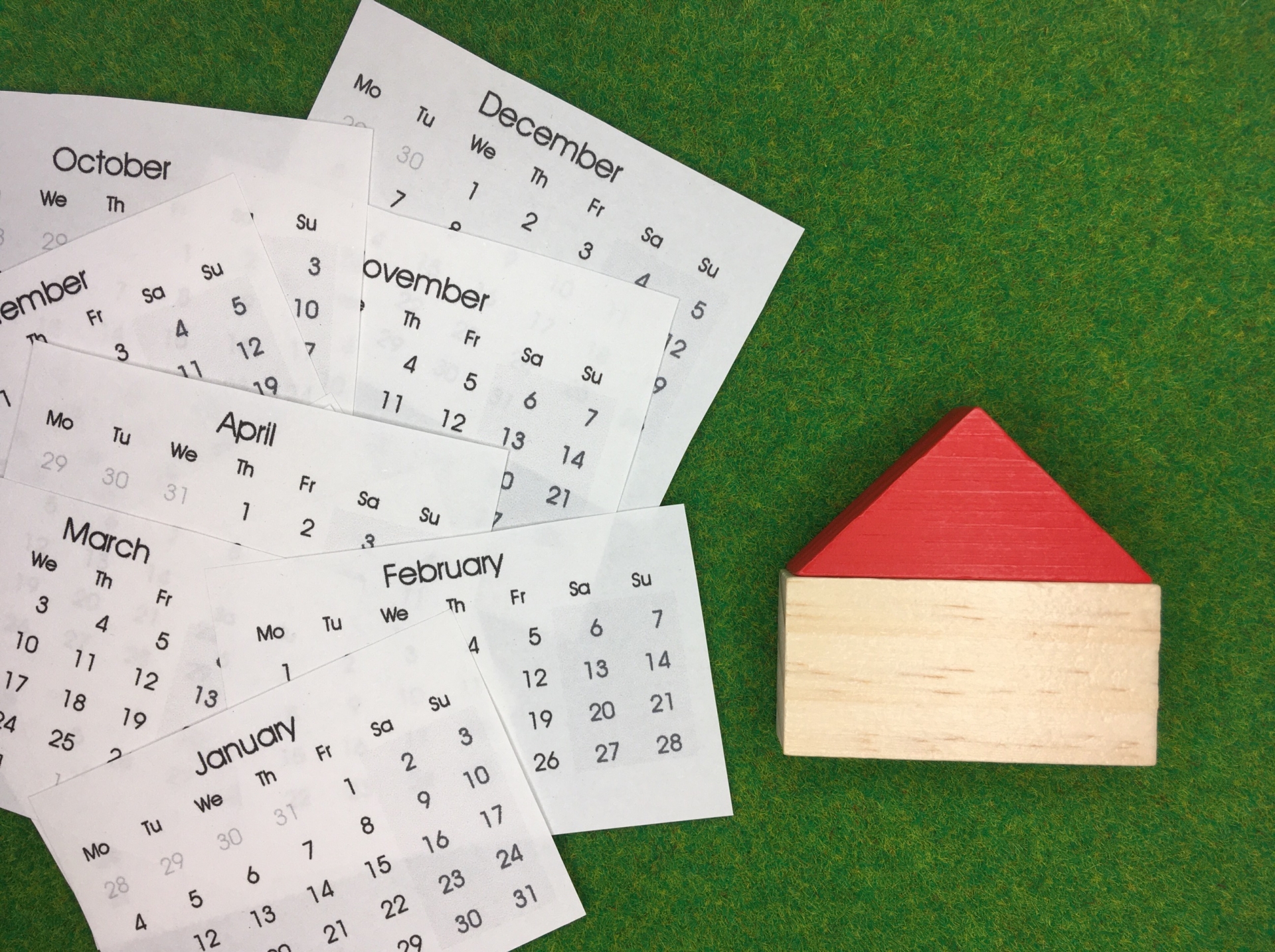
戸建て住宅の資産価値は、建物の構造によって下落スピードが大きく異なります。
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造では、それぞれ法定耐用年数や減価償却の計算方法が異なるためです。
ここでは税法上の耐用年数の考え方、減価償却の仕組み、そして構造別の違いについて詳しく解説します。
1.耐用年数とは?
そもそも耐用年数とは、税法上、建物の価値を償却するために定められた基準年数のことです。
国税庁が定める法定耐用年数は、建物の構造ごとに異なります。
| 構造 | 法定耐用年数(住宅用) |
|---|---|
| 木造・合成樹脂造 | 22年 |
| 鉄骨造(骨格材厚さ 3 mm 以下) | 19年 |
| 鉄骨造(骨格材厚さ 3 mm ~ 4 mm 以下) | 27年 |
| 鉄骨造(骨格材厚さ 4 mm 超) | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
ただし、これはあくまで税務上の計算基準であり、実際の建物の寿命や使用可能年数とは異なる点に注意が必要です。
たとえば、木造住宅の法定耐用年数は22年ですが、適切にメンテナンスされた木造住宅は30年、40年と問題なく使用できます。
耐用年数は実際の建物寿命ではなく、税務計算上の基準として理解しましょう。
2.減価償却とは?
減価償却とは、建物の取得価格を耐用年数で按分し、年々価値を減少させていく会計上の仕組みです。
たとえば、4,000万円(土地価格1,800万円+建物価格2,200万円)で新築の木造建物を購入した場合、年間100万円ずつ(建物価格2,200万円÷耐用年数22年)減価償却されます。
築10年時点では1,000万円が償却済みとなり、残存価値は1,200万円と計算されます。
不動産の実務査定では原価法と呼ばれる手法が用いられ、残存耐用年数をもとに建物の現在価値を評価します。
減価償却によって建物の価値がどの程度下がっているかを理解したうえで、実際に売却を検討する場合は、複数の不動産会社による訪問査定を利用すると安心です。
▼一度の入力で複数社に査定依頼できるサービスであれば、手間をかけずに比較検討でき、売却時期や資金計画の参考にもなるため、築年数のある物件を売却する方に特におすすめです。
![]()
3.木造と軽量・重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造の違い
建物の構造によって法定耐用年数が異なるため、資産価値の下落ペースも大きく変わります。
たとえば、同じ築20年の戸建てでも、木造であれば建物価値はほぼゼロですが、鉄筋コンクリート造(RC造)なら残存耐用年数が27年あるため、まだ相応の建物価値が認められます。
構造の違いは売却時の査定額に直結するため、購入時から意識しておくべき要素です。
家の資産価値を計算する方法

戸建て住宅の資産価値を正確に把握するには、複数の要素を総合的に判断する必要があります。
ここでは、資産価値を計算するときの主な参照値を解説します。
1.土地と中古住宅の周辺相場
家の資産価値を計算するうえで最も考慮すべき項目は、土地価格と地域の中古住宅相場です。
国土交通省の地価公示や不動産情報サイトの成約価格データを参考にすることで、土地の市場価格が確認できます。とくに土地は建物と異なり経年劣化しないため、資産価値の基盤となります。
また、同じエリアで同様の築年数の戸建て住宅がどの程度の価格で取引されているかを調べることで、建物部分の相場観も得られます。
たとえば近隣で築10年の戸建て住宅が2,500万円で成約している場合、その内訳を土地1,800万円、建物700万円と推定します。
自分の物件の土地面積や立地条件と比較することで、おおよその資産価値が算出できます。
2.建物の仕様や使用・管理の状態
建物の構造、リフォーム履歴、劣化の程度によって資産価値は大きく変動します。
たとえば、築20年の戸建て住宅でも、耐震補強工事を実施し、内装・外装を全面改修していれば、通常ならゼロとされる建物価値に数百万円の評価が加わることがあります。
とくに外壁塗装、屋根の補修、水回りのリフォームは、築年数以上の価値を維持するうえで重要なメンテナンスです。
逆に雨漏りやシロアリ被害などの劣化が進行していれば、査定額は大幅に下がります。
不動産会社の査定では、こうした付加価値が具体的な金額として反映されるため、メンテナンス履歴を記録しておくことが重要です。
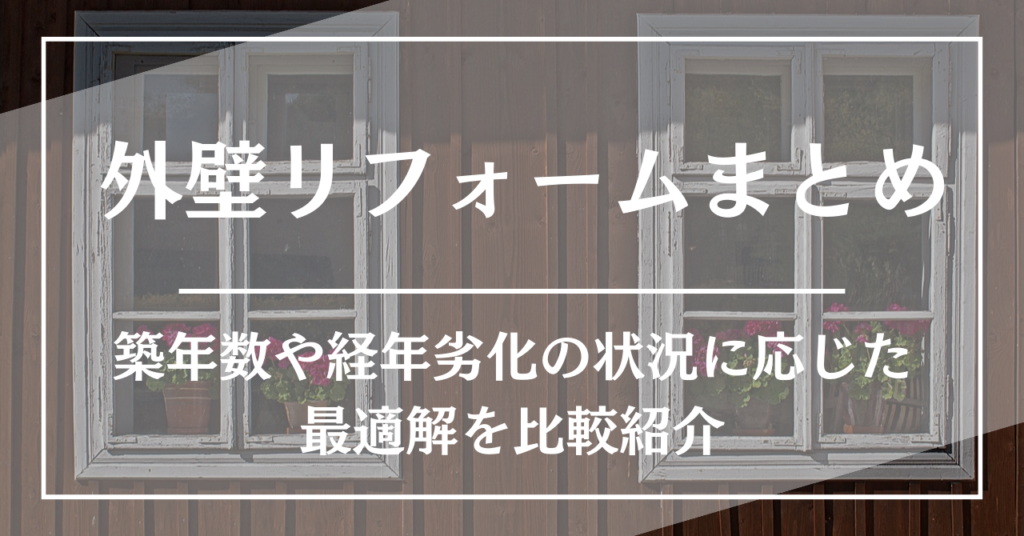
3.住宅ローン控除や金利水準の要因
住宅ローンの金利水準や税制優遇措置は、買主の購買意欲に直結するため、結果的に不動産の資産価値に影響します。
たとえば、住宅ローン控除を適用する場合、「新耐震基準に適合している住宅であること」が条件となります。つまり、1982年(昭和57年)以後に建築された中古住宅は適用されます。
一方で、旧耐震基準の住宅の場合、住宅ローン控除が受けられないため、売却価格に数十万円から百万円単位の違いが出ることがあります。
このように、住宅ローン控除などの税制優遇が適用されるかどうかは、成約価格に少なからず影響があります。
また、低金利下では買主の資金調達に必要なコストが下がるため、住宅取得のメリットが拡大し、成約価格も上がる傾向があります。
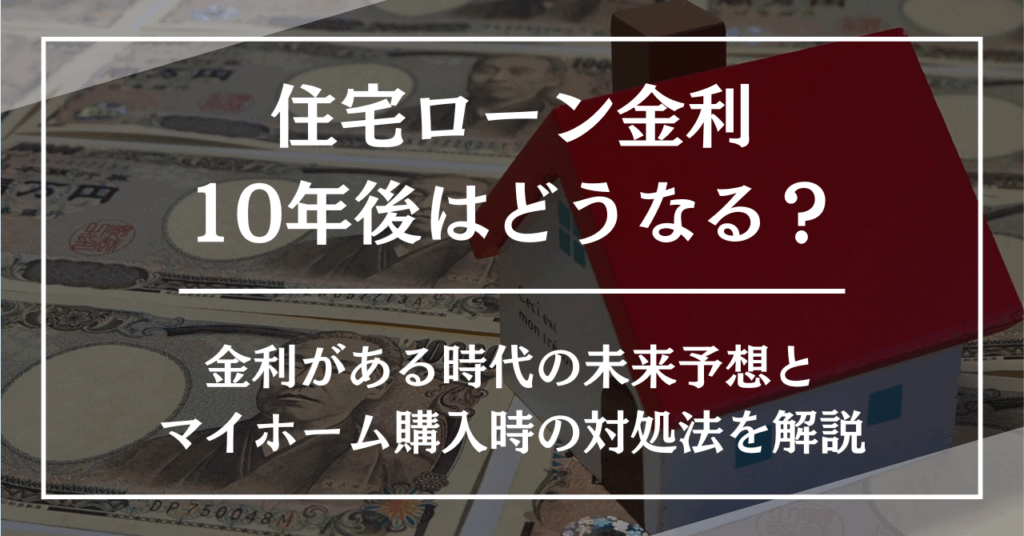
家の状態に応じた高く売却するコツ

築年数が経過した戸建て住宅を売却するときは、建物の状態や市場環境に応じた最適な売却方法を選ぶことが重要です。
ここでは、中古住宅の4つの主な売却方法について、それぞれの特徴とメリットを解説します。
1.古家付き土地として売る
築年数が古く建物価値がほぼゼロの木造戸建ては、建物を残したまま「古家付き土地」として売却するのが一般的です。
買主は建物を解体するか、リフォームして利用するか選択できるため、幅広い層にアピールできます。また、売主は解体費用を負担せずに済むメリットがあります。
たとえば、築40年の木造戸建てを売却する場合、更地にした場合の土地価格から解体費用(200〜300万円程度)を差し引いた価格で「古家付き土地」として販売します。
古家付き土地という形での売却は、単に「住居」としてだけでなく、不動産投資のターゲット層に対しても有効な戦略となります。
2.建物を解体して更地として売る
建物を解体し、更地にしてから売却することで、より高値での売却が期待できます。
買主の多くは古い建物の解体リスクや手間を嫌うため、最初から更地になっていることは安心材料になるためです。
とくに新築を建てたい買主にとっては、すぐに建築に取りかかれる更地は魅力的です。解体費用は先行投資となりますが、その分を上乗せした価格設定が可能です。
たとえば、古家付きなら2,000万円だった土地が、更地にすることで2,400万円で売却できれば、差額400万円から解体費300万円を引いても100万円のプラスになるケースがあります。
解体費用を上回る価格上昇が見込める場合は、更地にしてから売却する方が有利です。
3.建物をリフォームして資産価値を上げる
部分的なリフォームを施すことで、築年数の古い物件でも印象を改善し、査定額を上げることができます。
とくにキッチンや浴室などの水回りの設備を交換したり、外壁塗装、内装のクリーニングをしたりといった比較的低コストのリフォームでも、買主の第一印象は大きく変わります。
投資額を上回る価格上昇が見込める場合は、リフォームが有効な選択肢となります。
少しでも高値で売りたい方は、一度リフォーム業者に見積もりを依頼して、費用対効果を見極めたうえ判断することがおすすめです。
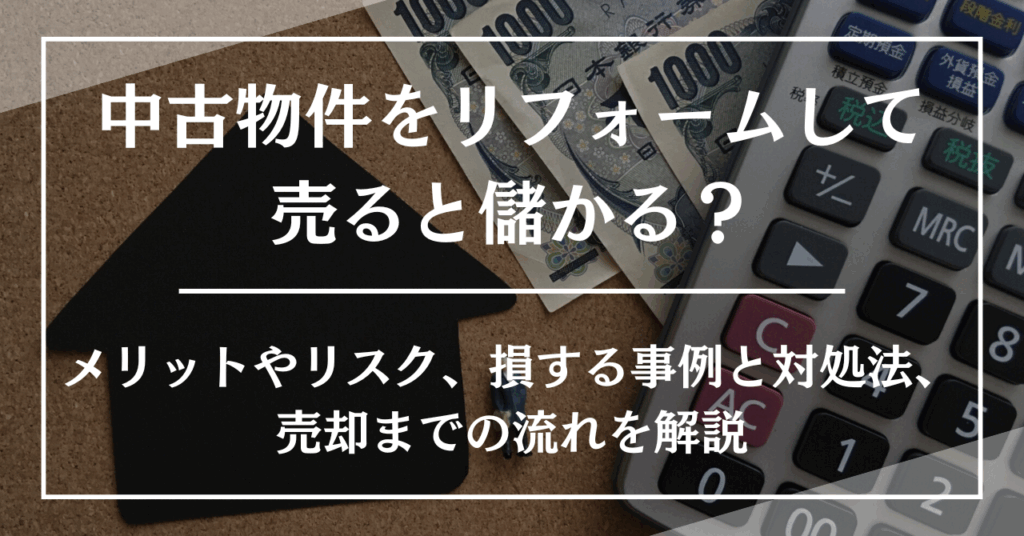
4.不動産会社に買取を依頼する
買取では不動産会社が直接買主となるため、仲介のように買い手を探す時間が不要です。
売却までの期間が大幅に短縮され、確実に現金化できるメリットがあります。
たとえば、中古の戸建て住宅を急いで現金化したい場合、仲介では3〜6か月かかるところを、買取なら1か月以内に売却完了できる場合があります。
ただし、買取価格は市場相場の70〜80%程度となることが一般的です。時間を優先するか価格を優先するかで、買取と仲介を使い分けることが重要です。
買取や仲介のどちらを選ぶにしても、まずは複数の不動産会社に査定を依頼して、正確な市場価格を把握しておくことが重要です。
▼一度の入力で複数社に訪問査定を依頼できるサービスを利用すれば、専門家が実際の建物や土地の状況を確認したうえで、買取価格や仲介想定価格の目安を提示してくれます。
![]()
資産価値が下がった家を売却するときの注意点

築年数が経過した戸建て住宅を売却するときには、通常の売買以上に注意すべきポイントがあります。ここからは、とくに重要な3つの注意点を解説します。
1.隣地との境界を確認する
境界が不明確なまま売却すると、後々のトラブルや価格交渉で不利になる可能性があります。
また、境界が確定していない場合、買主は隣地とのトラブルを懸念し、購入を躊躇することがあります。
測量費用は30〜50万円程度かかりますが、契約破談のリスクを考えれば必要な投資といえます。
売却前に土地家屋調査士に依頼して境界確定測量を行い、隣地所有者と境界確認書を取り交わしておきましょう。
2.契約不適合責任の内容を確認する
雨漏りやシロアリ被害、給排水管の不具合など、売却後に契約内容と異なる欠陥が発覚した場合、売主は修補や損害賠償の責任を負います。
とくに築20年以上経過している物件では、壁の向こう側にある躯体や設備に思わぬ欠陥が発覚するケースがあり、注意が必要です。
そのため、売買契約書に「現状有姿での引き渡しとし、給排水設備の不具合については売主は責任を負わない」といった免責条項を明記しておくこともリスク回避の観点からは有効です。
一方で、これらの免責条項は買主にとって不利な条件となるため、仲介業者が間に入ってもらい慎重な交渉が必要になることも頭に入れておきましょう。
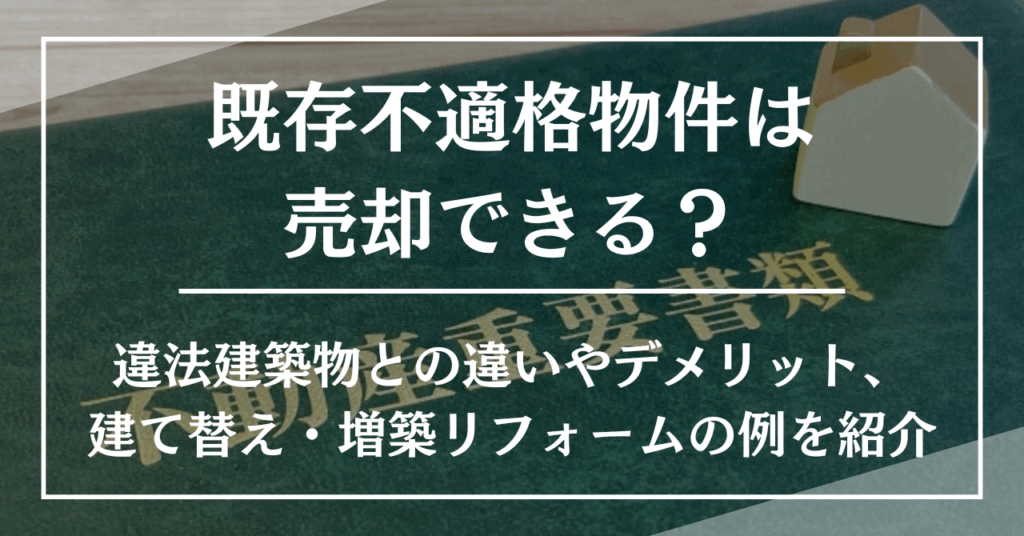
3.更地にする場合は1月2日以降にする
建物を解体して更地で売却する場合、解体のタイミングによって税金負担が変わることがあります。
固定資産税は住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減される一方で、更地の場合はこの特例が適用されないためです。
固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物の状態に基づいて課税されるため、たとえば12月中に解体を完了すると、翌年の固定資産税は特例なしの高額となります。
一方で、解体のタイミングを1月2日以降にすることで、固定資産税の負担を1年分軽減できます。
建物の解体スケジュールは固定資産税の課税評価のタイミングを考慮して計画しましょう。
建物の解体や更地化を検討する場合も、まずは複数の不動産会社に訪問査定を依頼して、土地と建物の現状価値を正確に把握しておくことが重要です。
▼一度の入力で複数社に査定依頼できるサービスを活用すれば、効率的に比較検討でき、固定資産税や売却スケジュールを踏まえた計画を立てやすくなります。
![]()
戸建て住宅の資産価値は約20年でなくなる!

木造戸建て住宅の建物価値は、おおむね20年でゼロとして扱われます。
不動産業界の実務査定においても、築20年を超えた木造建物は資産価値をほぼ認められず、売却価格は土地の評価額が中心となります。
一方で、戸建て住宅の資産価値は将来性や管理状態によっても変動します。
売却を検討するときは土地の立地条件や相場を重視し、必要に応じて更地にしたり、リフォームをしたりなどの戦略を検討することが重要です。