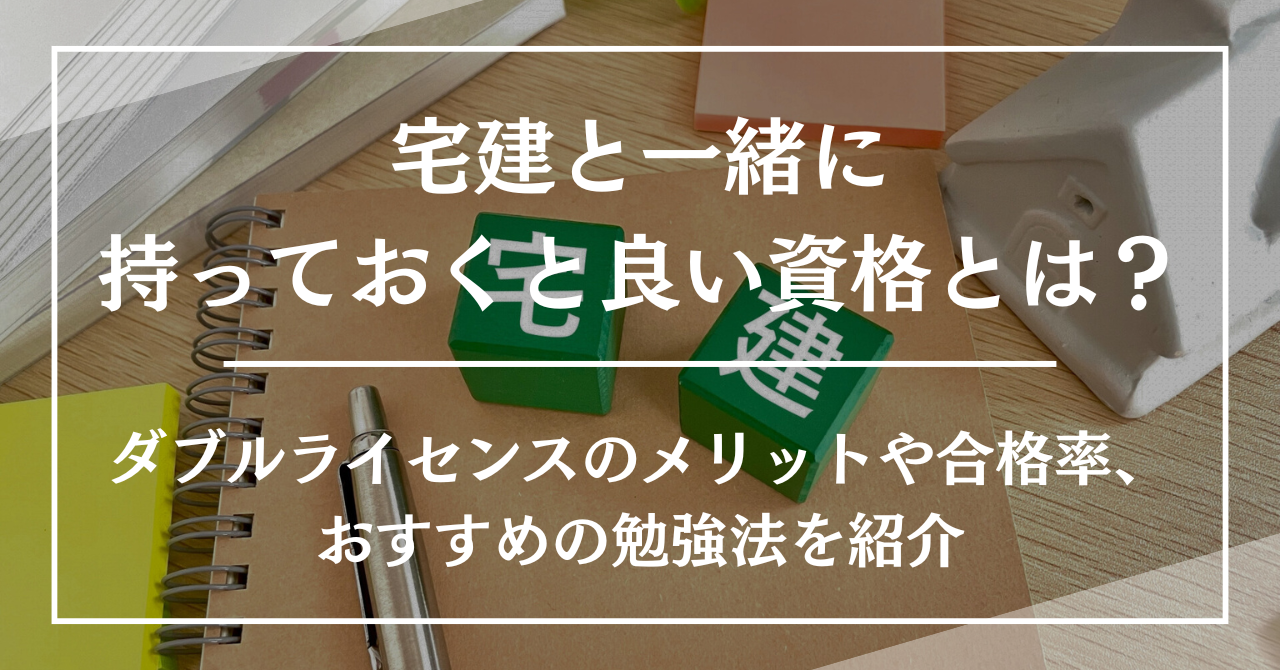※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「宅建を取ったけれど、次に何の資格を取ればいいの?」
「不動産業界で他の営業マンと差をつけるには?」
「ダブルライセンスで本当に収入は上がるの?」
宅建取得者の中には、より難しい資格を活かしてキャリアアップを目指したい方も多いでしょう。
宅建と相性の良い資格を組み合わせることで、営業力と信頼性を大幅に高められます。
そこで本記事では、宅建と一緒に持っておくと良い資格を宅建士目線で詳しく解説します。
また、ダブルライセンスのメリットやおすすめの勉強法についても紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
宅建と一緒に持っておくと良い資格とは?

宅建士資格は不動産取引のプロフェッショナルとして認められる重要な国家資格ですが、実務では宅建だけでは対応しきれない場面も少なくありません。
そこで注目したいのが、宅建と相性の良い資格との組み合わせです。
1.FP(ファイナンシャルプランナー)
2.賃貸不動産経営管理士
3.管理業務主任者
4.マンション管理士
5.土地家屋調査士
6.測量士補
7.不動産鑑定士
8.行政書士
9.司法書士
10.中小企業診断士
11.社労士(社会保険労務士)
ここからは、不動産業務と親和性が高く、キャリアアップにつながる11の資格、それぞれの特徴と活用法を解説していきます。
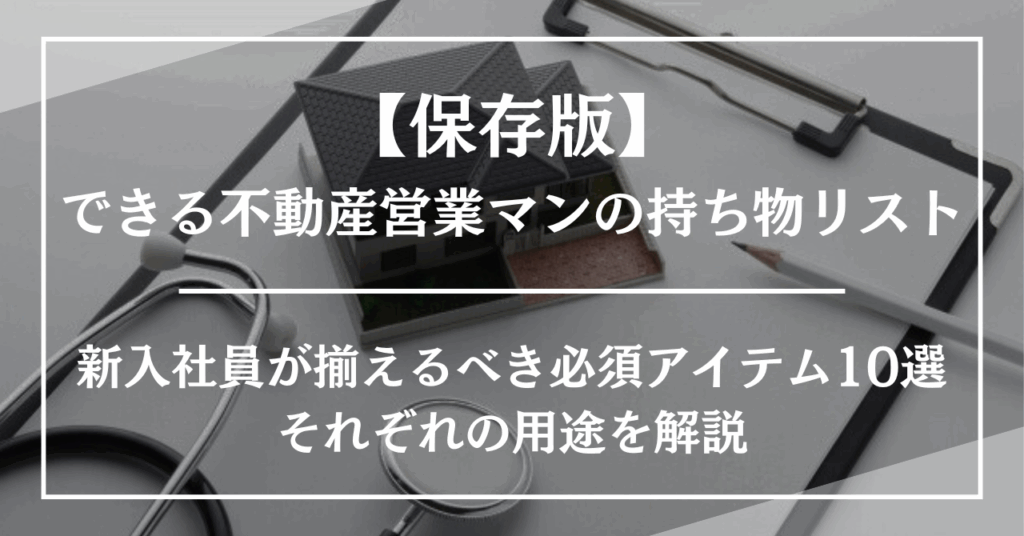
1.FP(ファイナンシャルプランナー)
FP(ファイナンシャルプランナー)は、顧客の夢や目標(ライフプラン)を実現するために、お金に関する幅広い知識から資金計画を立て、アドバイスやサポートを行う専門家です。
「FP技能士」と呼ばれる3級から1級までの国家資格と、「AFP」や「CFP」といった民間資格の2つに分かれます。FP試験は年3回実施され、学科試験と実技試験で構成されています。
それぞれの難易度と勉強時間の目安、受験資格は以下の表をご覧ください。
| 資格名称 | 勉強時間の目安 | 受験資格 |
|---|---|---|
| FP技能士3級 | 約80〜150時間 | 制限なし |
| FP技能士2級 | 約150〜300時間 | 3級合格または実務経験2年以上 |
| FP技能士1級 | 約400〜800時間 | 2級合格+実務経験1年以上 |
| AFP | 約150〜300時間 | 2級FP技能士合格+認定研修修了 |
| CFP | 約600〜1,000時間 | AFP認定者 |
不動産取引では物件の提案だけでなく、顧客の予算やライフプランに合わせた資金面のアドバイスが求められる場面が多くあります。
宅建士がFP2級を取得することで、住宅ローンの選び方や税制優遇措置の活用法まで踏み込んだ提案ができるようになり、住宅ローンアドバイザーとしての差別化が可能です。
FP技能士3級、2級であれば、宅建の「税・その他」分野と重複する部分も多いため、宅建合格後であればスムーズに学習を進められます。
2.賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務に関する専門知識を持つ国家資格です。
令和3年(2021年)に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)」が施行されたことにより、国家資格として位置づけられました。
試験は年1回11月に実施され、合格率は20%~30%程度で推移しています。
不動産賃貸・管理の会社で勤務する場合、物件の仲介だけでなく管理委託契約の締結や入居者トラブルへの対応など、賃貸経営全般をサポートできるため、宅建と並んで必要とされる資格です。
勉強時間は、100〜250時間が目安と言われていますが、不動産関連の知識がある方なら100時間程度で合格を目指せるでしょう。
3.管理業務主任者
管理業務主任者は、分譲マンションの管理会社に必置とされる国家資格で、管理組合に対する重要事項説明や管理事務報告を行うときに必要となります。
宅建士と同様に、マンション管理業者は30管理組合ごとに1名以上の管理業務主任者を設置することが義務付けられており、需要は安定しています。
試験は年1回12月に実施され、合格率は20〜25%程度です。
宅建士が管理業務主任者資格を取得することで、不動産の売買から購入後のマンション管理まで、一連の業務をすべてカバーできるようになり、多くの会社では資格手当が用意されています。
また、合格に必要な勉強時間は、一般的に100〜200時間程度が目安とされています。
出題範囲には民法や区分所有法など宅建と共通する分野が多く含まれるため、宅建合格者であれば短期間での取得も十分可能です。
参照:管理業務主任者試験|一般社団法人 マンション管理業協会
4.マンション管理士
マンション管理士は管理組合の運営や大規模修繕、トラブル解決など、マンション管理全般に関する高度な知識を持つ国家資格です。
管理業務主任者が管理会社側の資格であるのに対し、マンション管理士は管理組合側のコンサルタントとして位置づけられます。
試験は年1回11月に実施され、合格率は約8〜10%と難易度は高めです。
宅建士が本資格を取得することで、区分マンションの所有者や管理組合への専門的なアドバイスが可能となり、独立開業の道も開けます。
合格には、500時間程度の勉強時間が必要です。管理業務主任者との試験範囲の重複が多いため、両資格の同時取得を目指す受験者も少なくありません。
参照:マンション管理士試験|公益財団法人マンション管理センター
5.土地家屋調査士
土地家屋調査士は土地や建物の表示に関する登記申請や境界確定測量を行う国家資格で、不動産を正確に記録する専門家です。
宅建士が取引の法律面を担当するのに対し、調査士は測量や登記の実務を通じて取引の基礎となる情報を提供します。登録者数は約16,000人と少なく、希少価値の高い資格です。
試験は年1回10月に実施され、筆記試験と口述試験があります。
境界トラブルや分筆・合筆が必要な案件では、調査士の知識が不可欠となるため、宅建とのダブルライセンスは顧客との信頼関係を築くうえで強力な武器になります。
土地家屋調査士試験の合格に必要な勉強時間は、一般的に1000時間程度と言われています。
難関資格として位置づけられていますが、土地取引や開発案件に強みを持ちたい方、将来的に士業として独立を視野に入れている方におすすめの資格といえます。
6.測量士補
測量士補は土地の測量業務を行うために必要な国家資格で、測量法に基づいて測量計画の作成や実施を補助する役割を担います。
不動産取引では土地の面積や形状、境界の正確な把握が欠かせません。とくに開発案件や再開発プロジェクトでは測量知識が重視されます。
試験は年1回5月に実施され、合格率は約30〜40%程度です。また、必要な勉強時間は約200時間が目安です。測量に関する基礎知識があれば比較的取得しやすい資格といえます。
土地取引や開発業務に携わる機会が多い方、将来的に土地家屋調査士を目指す方にとっては、ステップアップのための資格として最適です。
7.不動産鑑定士
不動産鑑定士は不動産の経済価値を判定し、鑑定評価を行うことができる唯一の国家資格です。
公示地価の評価や裁判所の競売評価、企業の資産査定など、不動産価値の数値化が必要な場面で活躍します。学習範囲は広く、経済学や会計学の知識も求められます。
試験は短答式と論文式の2段階で実施され、合格率は短答式試験が例年33〜36%程度、論文式試験が約14〜17%程度、そして最終合格率は約5〜6%程度と難関です。
また、合格に必要な勉強時間は、2,000〜4,000時間が目安とされています。
しかし、合格後は独立開業も視野に入れられる高い専門性を持つため、不動産業界でのキャリアを大きく広げたい方には挑戦する価値のある資格といえます。
宅建士が鑑定士資格を取得することで、投資用不動産や収益物件の提案時に説得力のある価格根拠を示せるようになり、富裕層や法人顧客からの信頼獲得につながります。
8.行政書士
行政書士は官公署に提出する書類の作成や許認可申請の代理業務を行う国家資格で、契約書や内容証明など幅広い法律文書を取り扱います。
試験は年1回11月に実施され、合格率は約10〜15%程度です。また、必要な勉強時間の目安は500〜1,000時間です。
法律系資格の中では比較的取得しやすく、独立開業も視野に入れられるため、将来的に自分の事務所を持ちたい方におすすめの資格です。
不動産業務では売買契約書や賃貸借契約書の作成、宅建業免許の申請など、法務面での専門性が求められる場面が多くあります。
宅建士が行政書士資格を取得することで、宅建で学んだ民法や不動産関連法規の知識をさらに深められ、契約書類の作成から許認可業務まで一貫して対応できるようになります。
行政書士資格に興味を持った方や、効率的に合格を目指したい方には、オンラインで学べる「アガルートの行政書士講座」がおすすめです。
プロ講師による丁寧な講義と合格に直結するカリキュラムで、独学では難しい分野も効率的に学習できます。
![]()
9.司法書士
司法書士は不動産登記や商業登記、裁判所提出書類の作成を専門とする国家資格で、不動産取引における登記手続きのプロフェッショナルです。
売買や相続、抵当権設定など、不動産取引の最終段階では必ず登記が必要となり、司法書士の関与が不可欠となります。
試験は年1回7月に実施され、筆記試験と口述試験があります。合格率は5%以下で必要な勉強時間は約3,000時間と極めて難関ですが、合格後は高い専門性と社会的信用を得られます。
私は司法書士法人グループの不動産仲介会社に勤めていた経験がありますが、「○○先生のところの不動産屋です。」と名乗ると、顧客の安心感が大きく向上することを実感しました。
会社によっては資格手当を用意している場合も多いため、収入アップと権威性の向上のためにぜひ挑戦してみてください。
参照:司法書士試験|法務省
司法書士試験は合格率が非常に低く、独学では膨大な学習時間が必要です。
効率的に合格を目指すなら、オンライン講座を活用するのがおすすめです。
とくに、短期合格に特化した「アガルートの司法書士試験講座」では、合格に直結するカリキュラムとプロ講師の丁寧な指導で、効率的に学習を進められます。
![]()
10.中小企業診断士
中小企業診断士は企業の経営課題を分析し、改善策を提案する経営コンサルタントの国家資格です。
財務分析や事業計画の策定、マーケティング戦略の立案など、幅広い経営知識を持ち、中小企業の成長をサポートします。
不動産業務では法人顧客への資産活用提案や事業用不動産の選定、不動産を活用した事業承継対策など、経営視点が求められる場面が増えています。
宅建士が中小企業診断士を取得することで、単なる物件紹介を超えた経営戦略レベルの提案ができるようになり、経営者層からの信頼獲得につながります。
試験は1次試験と2次試験の2段階で実施され、合格率は4〜5%程度と難関です。また、合格には約1,000時間の勉強時間が目安になります。
法人営業に強みを持ちたい方や、将来的に経営コンサルタントとして活躍したい方におすすめの資格です。
参照:中小企業診断士試験|一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会
11.社労士(社会保険労務士)
社労士は労働・社会保険に関する法律の専門家として、企業の人事労務管理や各種保険手続きをサポートする国家資格です。
労働基準法や社会保険制度、就業規則の作成や給与計算など、企業経営に欠かせない労務分野を担当します。
不動産業界では、独立開業後に従業員管理や労務トラブルへの対応が経営課題となるケースも多く、社労士の知識は自社の経営強化にも直結します。
また、宅建士が社労士資格を取得することで、法人顧客に対して不動産活用と人事労務を組み合わせた総合的な提案ができるようになり、顧客との関係性を深められます。
試験は年1回8月に実施され、合格率は約6%前後と安定した難易度です。合格に必要な勉強時間は、平均して800~1,000時間が目安とされています。
不動産業の経営者を目指す方や、法人営業での差別化を図りたい方に適した資格といえます。
参照:社会保険労務士試験オフィシャルサイト|全国社会保険労務士会連合会 試験センター
社労士試験は専門知識が幅広く、独学だけでは効率的に合格するのが難しい資格です。
短期間で必要な知識を体系的に学びたい方には、オンライン講座の活用がおすすめです。
とくに、合格に直結するカリキュラムとプロ講師の指導が充実している「アガルートの社労士講座」なら、効率よく学習を進められます。
![]()
宅建とのダブルライセンスのメリット
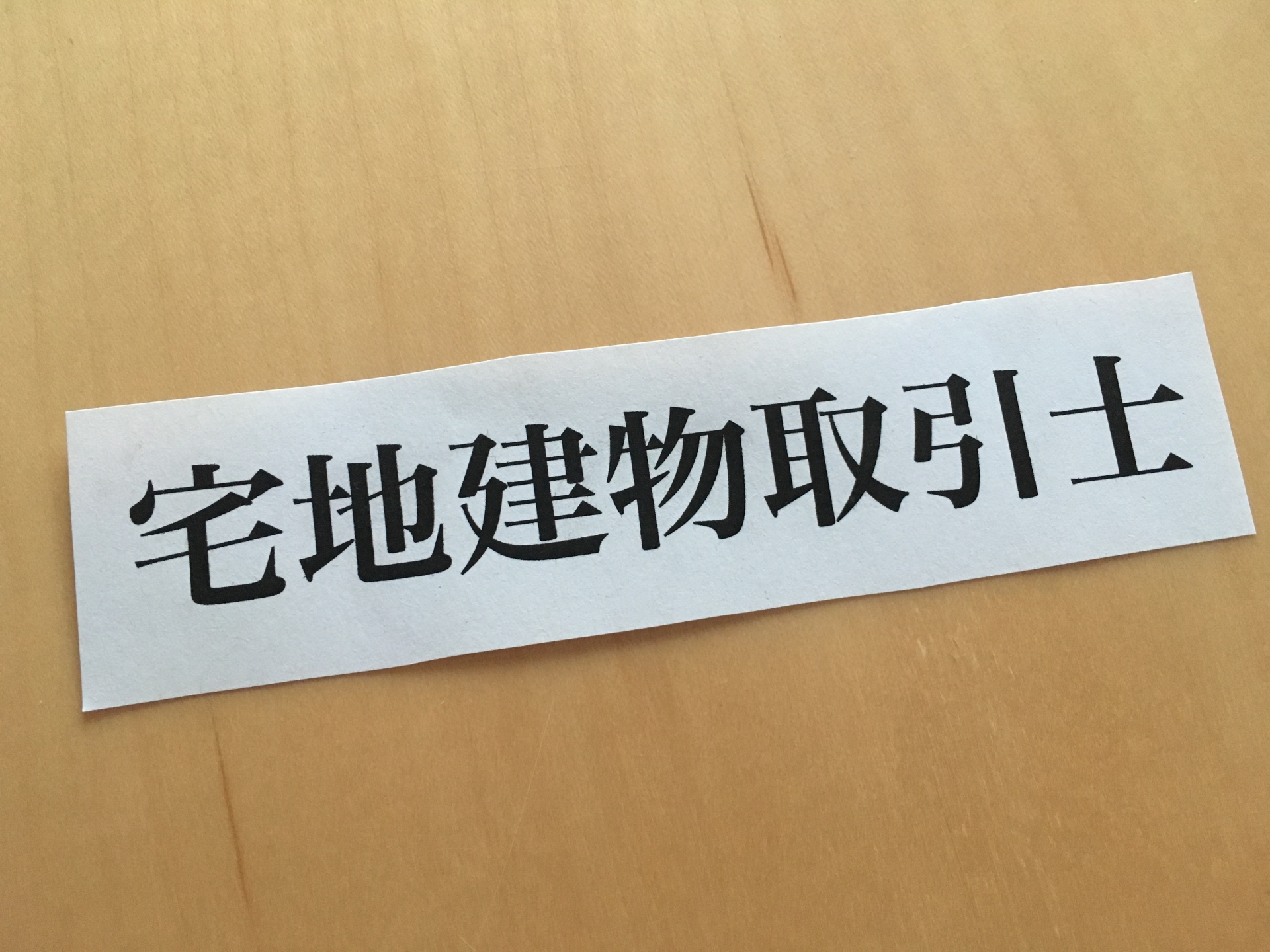
宅建士資格を取得した後、さらに別の資格を組み合わせることで得られるメリットは単なる知識の増加にとどまりません。
ここからは、宅建とのダブルライセンスによって、実務面やキャリア面でどのような効果が期待できるのかを具体的に解説します。
1.競争の激しい不動産業界で差別化が図れる
不動産業界は宅建士資格保有者が多数存在するため、資格を持っているだけでは差別化が難しい状況です。そこで重要になるのが、プラスアルファの専門性を示すことです。
複数の資格を保有することで、自分の強みや得意分野を明確にでき、顧客や社内での存在感を高められます。
とくにFP資格や不動産鑑定士との組み合わせは、資金面や価値評価という切り口で他の営業担当者と明確に差別化できます。
また、名刺やプロフィールに複数資格を記載することで、初対面の顧客にも専門性の高さを視覚的に伝えられます。
さらに資格保有者同士のネットワークにも参加しやすくなり、ビジネスチャンスの拡大にもつながります。
2.クライアントからの信頼度が向上する
顧客は不動産取引において、物件情報だけでなく資金計画や税金、登記手続きなど多岐にわたる不安や疑問を抱えています。
宅建士が他の専門資格も保有していれば、一人の担当者に対してまとめて相談できるため、顧客の手間が省け安心感が生まれます。
たとえば、宅建士とFPのダブルライセンスがあれば、物件提案と同時に住宅ローンの選び方や返済計画まで具体的にアドバイスでき、顧客満足度が大きく向上します。
信頼関係が構築されれば、リピート契約や知人への紹介といった好循環が生まれやすくなり、結果として成約率を高める効果もあります。
3.収入アップが期待できる
多くの不動産会社では資格手当制度を設けており、宅建士に加えてFPや管理業務主任者などの資格を取得すると、毎月数千円から数万円の手当が上乗せされます。
また、複数分野に対応できる営業担当者として顧客からの指名を受けやすくなり、成約件数の増加による歩合給アップも期待できます。結果として昇進や役職登用のチャンスも広がるでしょう。
さらに、FPや不動産鑑定士など独立開業が可能な資格であれば、将来的に自分の事務所を持ち、より高い収入を目指すことも現実的な選択肢となります。
資格取得への投資は時間と費用がかかりますが、長期的には確実にリターンが得られるため、キャリアアップの有効な手段といえます。
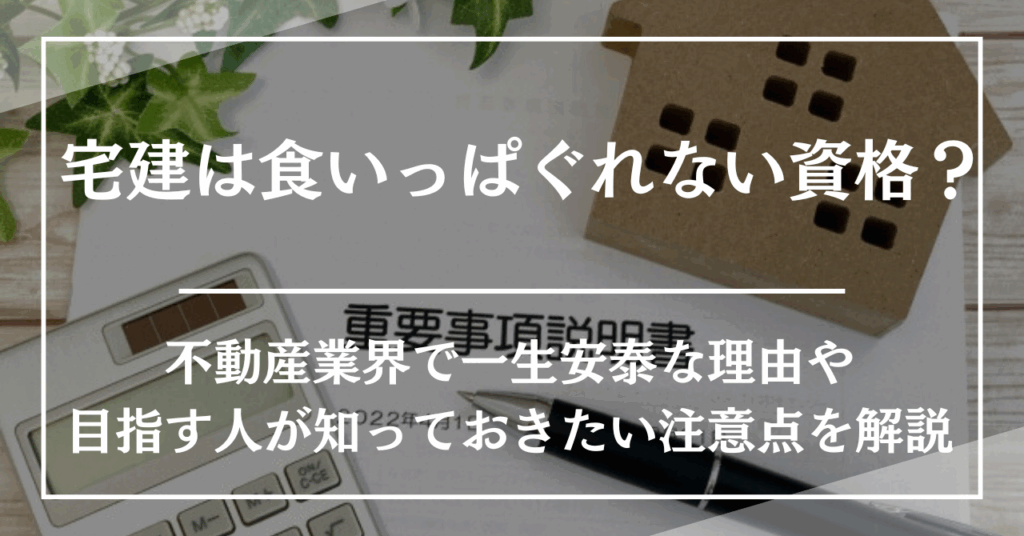
ダブルライセンスを取得するときのおすすめの勉強法
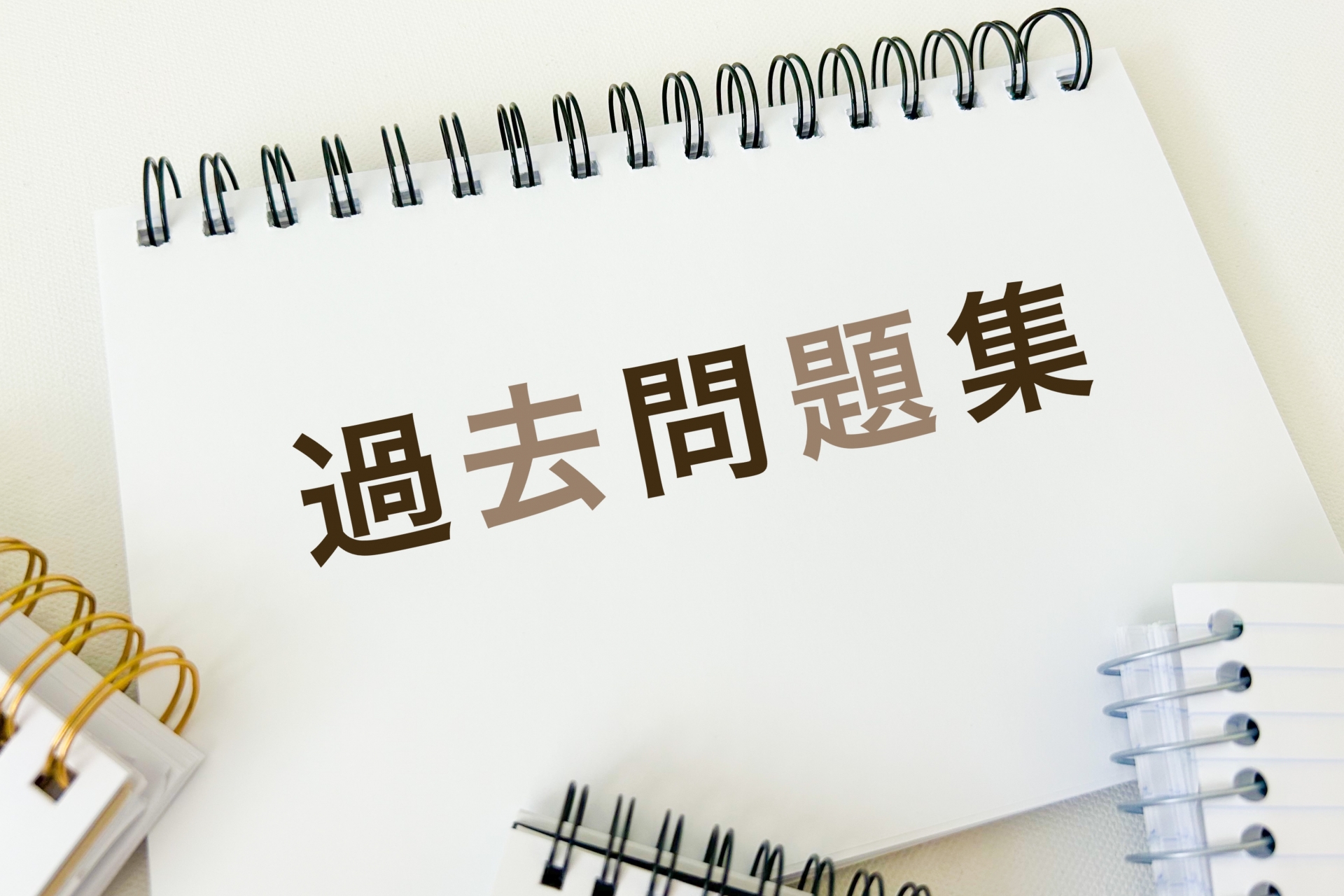
ダブルライセンスを目指すときに、闇雲に学習を始めるのではなく、しっかりとした学習計画を立てることが次の資格を取得するためには重要です。
ここでは、実務経験と並行しながら無理なくダブルライセンスを取得するための、実践的な勉強法を3つの視点から解説します。
1.資格取得の順番で学習を効率化する
ダブルライセンスの取得で最も重要なのは、学習内容に重複が多い資格から順番に挑戦することです。
たとえば、宅建合格後であれば、民法や不動産関連法規の基礎が身についているため、FP2級や管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士などが次のステップとして最適です。
これらの資格は宅建と共通する法律分野が多く、復習を兼ねながら新しい知識を積み上げられるため、学習時間を大幅に短縮できます。
逆に測量士補や中小企業診断士のように宅建とは異なる分野の資格は、ある程度の学習期間を確保してから挑戦する方が効率的です。
自分のキャリアプランに合わせて優先順位をつけ、段階的に資格を積み重ねていきましょう。
2.試験時期を考慮して併願も検討する
資格試験は実施時期が決まっているため、スケジュールを把握して効率的に受験計画を立てることが重要です。また、試験日が重ならない資格であれば、同じ年に複数受験する「併願」も有効です。
たとえば、宅建試験は例年10月中旬に実施され、FP2級は1月・5月・9月、管理業務主任者は12月、賃貸不動産経営管理士は11月に試験が行われます。
宅建合格直後であれば知識が新鮮なうちに11月や12月の不動産系試験に挑戦できるため、復習の負担を最小限に抑えられます。
ただし、無理なスケジュールは学習の質を下げる原因となるため、自分の生活リズムや仕事の繁忙期を考慮して現実的な計画を立てることが大切です。
3.オンライン学習教材を導入する
オンライン学習教材は通勤電車の中や休憩時間、寝る前のわずかな時間でも学習できるため、ダブルライセンス取得にはとても有効です。
スマートフォンやタブレットで講義動画を視聴し、一問一答形式の問題演習でアウトプットを繰り返すことで、効率的に知識を定着させられます。
また、オンライン教材には質問機能や模擬試験、学習進捗管理機能が搭載されているものが多く、独学でも挫折しにくい仕組みが整っています。
たとえば、スタディングやフォーサイト、アガルートなど、実績のあるオンライン教材を選ぶことで、費用対効果の高い学習が可能です。
教材選びでは合格実績や口コミ、サポート体制を確認し、自分の学習スタイルに合ったものを選びましょう。
とくに、効率的に宅建合格を目指したい方には、プロ講師による丁寧な指導と豊富なカリキュラムで学べる「アガルートの宅建講座」がおすすめです。
![]()
宅建を取ったらまずはFP3級・2級に挑戦してみよう!

FP3級は受験資格がなく受験日程も豊富なため、宅建士資格を取得したら次のステップとして最もおすすめの資格です。
また、すでにFP3級を保持している方は、税金や保険、住宅ローン、相続など宅建で学んだ知識と重複する分野が多い2級に挑戦してみましょう。
宅建士がFPの知識を持つことで、資金計画や住宅ローンの選び方、税制優遇措置の活用法などの相談にワンストップで対応でき、顧客満足度と成約率が飛躍的に向上します。
宅建合格の勢いを活かして、まずはFP取得に挑戦し、不動産業界で長く活躍できる実力を身につけていきましょう。