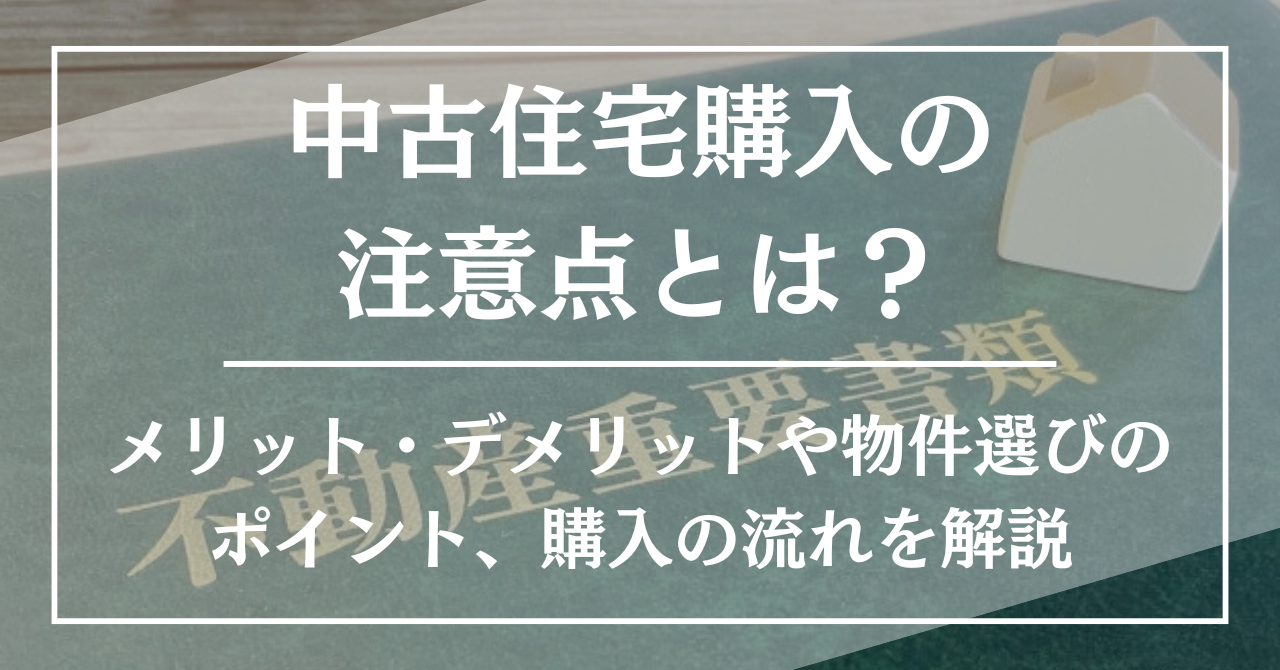※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「中古住宅を購入するメリットとは?」
「中古住宅の物件選びで大事なポイントは?」
「買ってはいけない中古物件の見極め方はある?」
東日本不動産流通機構の資料によると、首都圏の中古マンション成約数は2年連続で前年を上回り、約3.7万件、中古戸建て住宅の成約価格は3,948万円と4年連続で上昇しています。
日本の中古住宅市場は今後も拡大していくことが予想されています。
これから住宅購入を検討されている方の中には、コストパフォーマンスが高い中古住宅に興味を持っている方も多いでしょう。
そこで今回は、中古住宅の特徴やメリット・デメリットを解説します。
また、物件選びのポイントや購入までの流れ、注意点について紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
参照:首都圏不動産流通市場の動向(2024年)|公益財団法人東日本不動産流通機構
目次
中古住宅の意味と特徴とは?

中古住宅とは、過去に一度でも人が住んだことがある住宅のことを指します。
新築と比べると、価格が抑えられており、立地や物件の選択肢が豊富なのが特徴です。
法律上は「建築後1年以上経過」または「人が住んだ形跡がある」場合に中古住宅と分類されます。
たとえば築10年の戸建てや分譲マンションなどが該当します。
また、新築住宅は売主が不動産会社であるケースが多いのに対し、中古住宅は個人間売買が一般的で、税制や保証内容にも違いがあります。
このように、中古住宅はコストを抑えて希望の立地に住みたい方にとって、現実的で魅力的な選択肢です。
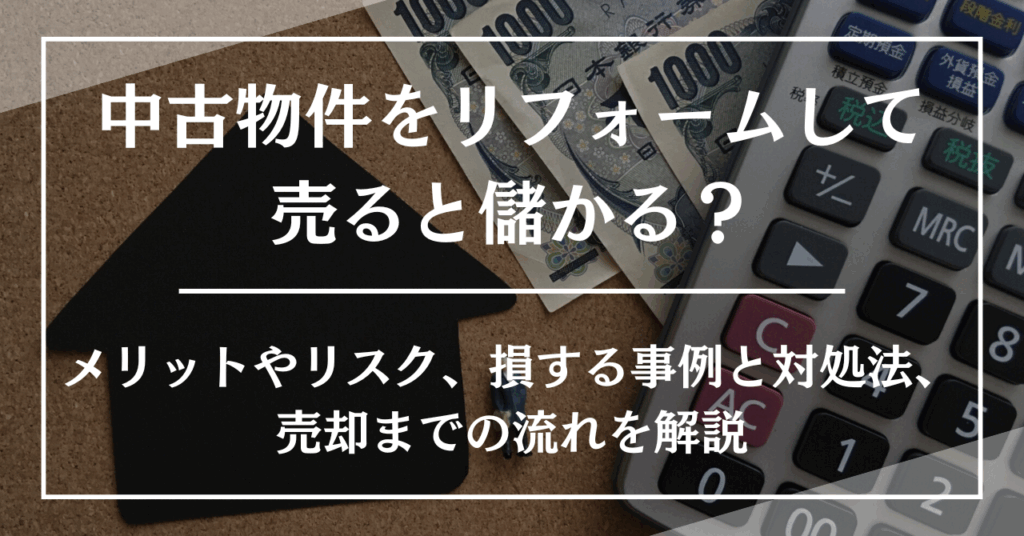
中古住宅を購入するメリット

中古住宅を購入するメリットは4つあります。
1.新築よりも購入価格が抑えられる
2.実物を見てから購入判断できる
3.リノベーション前提の自由度がある
4.固定資産税の評価額が安い
それぞれ解説します。
1.新築よりも購入価格が抑えられる
中古住宅最大の魅力は、やはり「価格の安さ」です。
立地や広さが同等であっても、新築に比べて数百万円以上安く購入できるケースも少なくありません。
新築物件には「新築プレミアム」がついているものの、入居したタイミングで約1~2割の価値がなくなるため、中古住宅は実質的な価格で購入可能です。
たとえば、同じエリアの築浅マンションであっても、新築と中古では10~20%ほど価格差が出ることがあります。
これにより、浮いた予算をリフォーム費用や家具・家電の購入に充てられる点も大きなメリットです。
購入価格を抑えて理想の住まいを実現したい方には、中古住宅が最適な選択肢となるでしょう。
2.実物を見てから購入判断できる
新築住宅は図面やモデルルームだけで判断しなければならないことが多いですが、中古住宅は実際の建物を見てから購入判断ができます。
時間帯を変えて複数回内覧することで、朝・昼・夕方の日当たりの変化や、平日・休日の騒音レベルの違いを体感できます。
隣家の窓配置による視線の問題、駐車場や道路からの距離感、においの有無など、図面では絶対にわからない生活環境を事前チェック可能です。
特に中古マンションでは、エントランスや廊下の清掃状況、掲示板の内容から住民の質を推測でき、管理組合の運営状況も確認できます。
実際に住む環境を五感で確認してから購入できるため、「こんなはずじゃなかった」という後悔を大幅に軽減できる点が最大のメリットです。
3.リノベーション前提の自由度がある
中古住宅は、「自分好みにカスタマイズしたい」という方にとって理想的な選択肢です。
新築では構造上変更できない間取りでも、中古なら壁を撤去して大きなLDKを作ったり、和室を洋室に変更したりと大胆な変更が可能です。
配管の位置変更によるキッチン・バスルームの移設、天井を抜いて吹き抜けを作るといった大規模改修も、建築基準法の範囲内で自由に行えます。
また、住宅ローンにリノベーション費用を組み込める一体型ローンや、工事完了まで金利のみ支払うつなぎ融資など、資金調達の選択肢も豊富です。
最近では、物件探しから設計・施工までワンストップで対応する専門業者も増えており、理想の住まいを現実的な予算で実現できる環境が整っています。
すでに希望の中古住宅を見つけている方は、リノベーション前提で理想の間取りや設備を実現するために、複数のリフォーム会社から見積もりを取って比較するのがおすすめです。
▼無料の一括見積もりサービスを活用すれば、全国の優良リフォーム会社から価格や工事内容をまとめて確認でき、予算内で希望の住まいをカスタマイズする計画をスムーズに進められます。
![]()
4.固定資産税の評価額が安い
中古住宅は、建物の経年によって固定資産税評価額が低くなっているため、新築と比べて税金負担が軽くなる傾向があります。
建物の評価額は木造住宅で築22年、鉄筋コンクリート造で築47年でほぼゼロまで下がり、土地の評価額も周辺相場の7割程度に設定されています。
例えば、新築時に年間15万円だった固定資産税が、築10年で約10万円、築20年で約7万円まで減額される計算です。
さらに、築年数が古い物件をリノベーションした場合でも、建物の評価額は既存部分のまま据え置かれるため、実質的な住環境は新築同等でも税負担は抑えられます。
35年の住宅ローンを考えると、新築との税額差は総額で数十万円から100万円以上になることもあり、長期的な家計負担軽減効果は非常に大きいといえます。
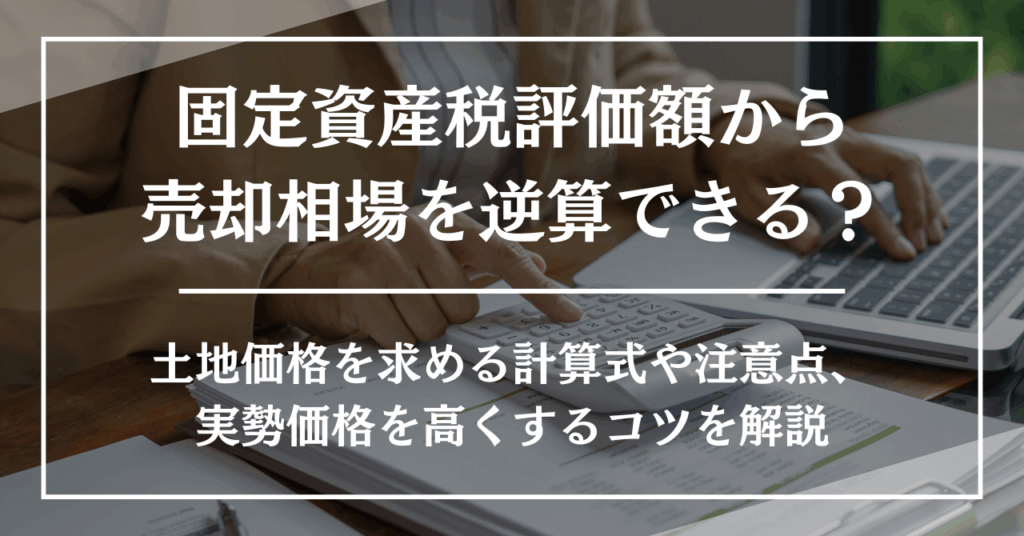
中古住宅を購入するデメリット
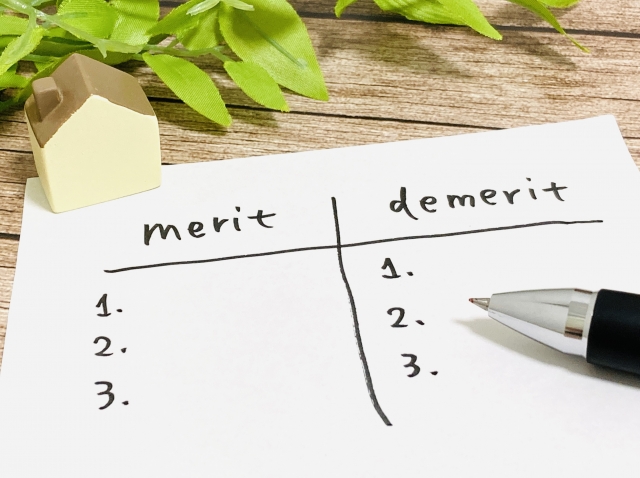
一方で、中古住宅を購入するデメリットは3つあります。
1.修繕費・メンテナンス費がかかる場合がある
2.住宅ローン減税の条件が限定される
3.耐震性・断熱性能基準が最新ではない
それぞれ解説します。
1.修繕費・メンテナンス費がかかる場合がある
中古住宅は、すでに建築から年数が経っているため、今後の修繕や維持に関わる費用が発生する可能性が高くなります。
築20年を超える戸建てでは、屋根材の劣化による雨漏りリスクや外壁クラックからの漏水、給湯器の寿命(約10年)による突然の故障など、緊急性の高い修繕が必要になるケースもあります。
特にシロアリ被害は床下から柱まで広範囲に及ぶことがあり、駆除・補修費用が200万円を超える場合もあります。
また、中古マンションでは、長期修繕計画書で将来の大規模修繕時期を確認しましょう。
修繕積立金の残高不足により一戸当たり50万円~100万円の一時金徴収が予定されていないか事前チェックが必須です。
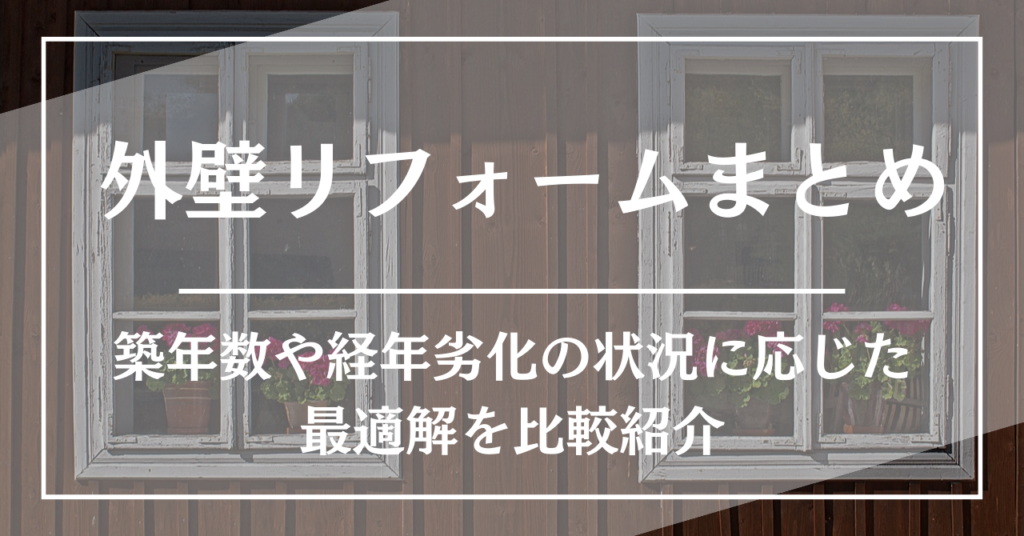
2.住宅ローン減税の条件が限定される
中古住宅は、新築と比べて住宅ローン減税の適用条件が厳しいことにも注意が必要です。
木造戸建ては築20年以内、鉄筋コンクリート造は築25年以内が原則で、これを超えると耐震基準適合証明書(費用約10万円)や既存住宅売買瑕疵保険(費用約5万円)の取得が必須となります。
証明書取得には2週間程度かかるため、売買契約前の準備が重要です。
また、個人間売買では消費税が非課税となるため、事業者売買と比べて控除上限額が減額されます。
床面積50㎡以上かつ借入金額の2分の1以上が居住用であることも条件で、二世帯住宅や店舗併用住宅では注意が必要です。
最大控除額は新築の年間35万円に対し、中古住宅では年間21万円となるケースもあり、10年間で140万円の差が生じる可能性があります。
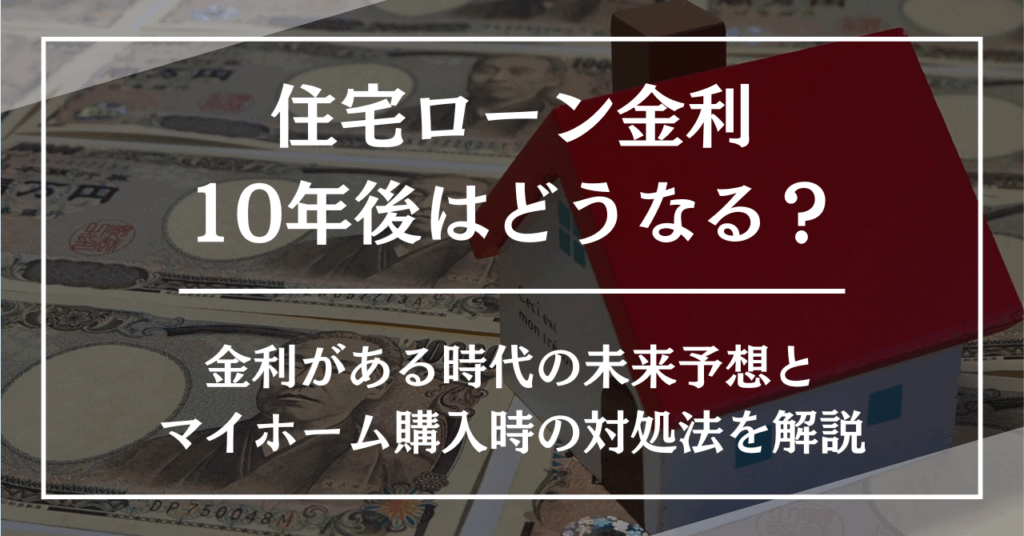
3.耐震性・断熱性能基準が最新ではない
築年数の古い中古住宅は、建築基準法が改正される前に建てられたものである可能性があり、耐震性や断熱性能に不安が残ることがあります。
1981年以前の旧耐震基準住宅は震度6強で倒壊リスクがあり、耐震補強には100万円~300万円が必要です。
断熱材も1980年代のグラスウールは現在の半分程度の性能で、アルミサッシの単板ガラスは熱損失が大きく、冷暖房費が新築の1.5倍になることもあります。
特に問題なのは、外壁内部の断熱材劣化や配管周りの気密不良で、赤外線カメラによる断熱診断でなければ発見できません。
耐震診断費用は約10万円、断熱改修は100万円~200万円が目安となり、購入時にこれらの改修費用を含めた総予算で検討することが重要です。
中古住宅の物件選びのポイント

中古住宅の物件を選ぶときは、3つのポイントを抑えましょう。
1.築年数や建物構造に問題がないか確認する
2.管理やメンテナンスの履歴を確認する
3.周辺環境や暮らしやすさを見極める
それぞれ解説します。
1.築年数や建物構造に問題がないか確認する
まずチェックすべきは、物件の「築年数」と「構造」です。
築年数が古い物件は、耐久性や断熱性が不足している可能性があり、今後の修繕費もかさむことがあります。
築年数の目安として、木造住宅は築15年で屋根・外壁の塗装が必要になり、築20年では水回り設備の交換時期を迎えます。
構造面では、木造は初期コストが安いものの15年ごとにメンテナンスが必要で、鉄筋コンクリート造は初期コストは高いが30年間は大規模修繕が不要です。
鉄骨造はその中間で、20年ごとの塗装メンテナンスが目安となります。
購入前に建物の履歴書である「建築確認済証」と「検査済証」の有無を確認し、構造に応じた将来の修繕計画を立てることが重要です。
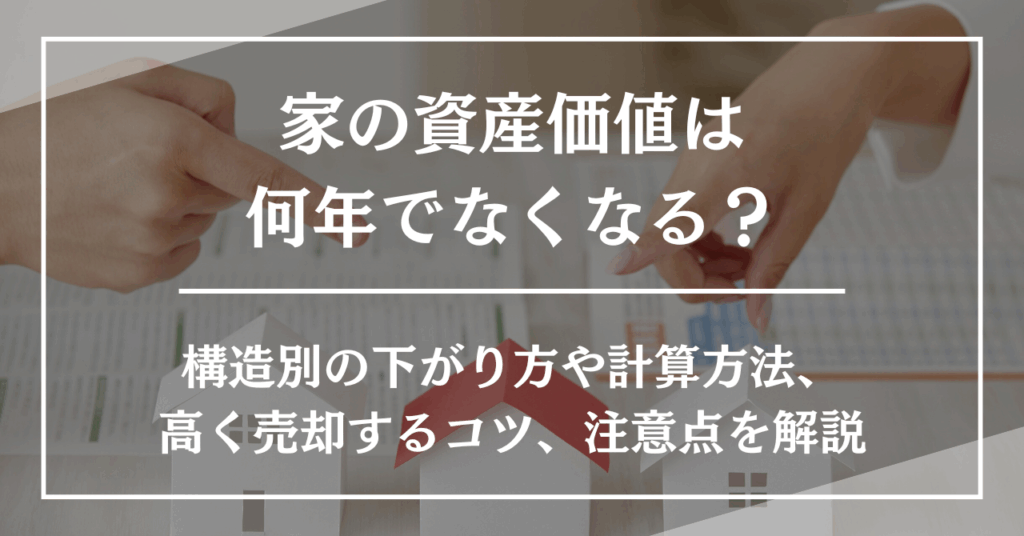
![]()
2.管理やメンテナンスの履歴を確認する
特に中古マンションの場合、建物の管理状態は資産価値にも大きく影響します。
共用部の清掃状況やゴミ置き場の整備状況などをチェックすることで、管理の質が見えてきます。
マンションでは、エレベーターの点検記録や消防設備の検査証明書、大規模修繕の実施履歴を確認し、管理費・修繕積立金の滞納状況も重要なチェックポイントです。
また、管理会社の変更履歴が頻繁な場合は、住民間のトラブルや管理組合の運営に問題がある可能性があります。
売主が保管している修繕履歴書やインスペクション報告書は、隠れた不具合を発見する重要な手がかりとなります。
すでに希望の中古住宅を見つけている方は、リノベーション前提で理想の間取りや設備を実現するために、複数のリフォーム会社から見積もりを取って比較するのがおすすめです。
▼無料の一括見積もりサービスを活用すれば、全国の優良リフォーム会社から価格や工事内容をまとめて確認でき、予算内で希望の住まいをカスタマイズする計画をスムーズに進められます。
3.周辺環境や暮らしやすさを見極める
住宅そのものだけでなく、立地や周辺環境も快適な暮らしに直結します。
通勤・通学に便利な交通アクセスや、スーパー・病院・公園などの生活インフラが整っているかを事前に確認しましょう。
具体的には、最寄り駅まで徒歩10分以内、主要駅まで乗り換え1回以内が理想的です。生活圏内に24時間営業のコンビニ、総合病院(車で15分以内)、小中学校(徒歩15分以内)があると利便性が高まります。
また、将来的な資産価値を考えると、人口減少エリアではなく、再開発計画のある地域を選ぶことも重要です。
現地調査では、平日の朝夕と休日の異なる時間帯に訪問し、通勤ラッシュ時の混雑状況や夜間の街灯の明るさを確認しましょう。
近隣住民の年齢層や洗濯物の干し方、ベランダの使い方から生活マナーの水準も推測できます。
ゴミ出しルールの掲示板や自治会の活動状況も、コミュニティの質を判断する重要な指標となります。
中古住宅を購入する流れ

中古住宅を購入する一般的な流れは、こちらの7ステップです。
1.情報収集と希望条件を整理する
2.物件を内見して比較検討する
3.買付申込書を提出する
4.住宅ローンの事前審査(仮審査)を受ける
5.売買契約を締結する
6.住宅ローンの本審査を申し込む
7.決済・引き渡し
それぞれ解説します。
1.情報収集と希望条件を整理する
まず不動産ポータルサイトで相場を把握し、エリアの平均成約価格を調べましょう。
条件は「絶対条件」と「希望条件」に分けて整理することが重要です。
|
絶対条件の例 |
予算上限、通勤時間60分以内、築年数25年以内 |
|
希望条件の例 |
駐車場付き、南向き、リフォーム済み |
物件探しでは、条件の8割を満たす物件があれば「良物件」と判断するのが現実的です。
完璧な物件を待っていると、市場から良い物件が消えてしまいます。
2.物件を内見して比較検討する
内見は可能な限り複数回、異なる時間帯に行いましょう。
おすすめは「平日夕方」と「土日昼間」の2回です。通勤ラッシュ時の騒音や休日の近隣住民の様子が確認できます。
また、内覧時には実際に蛇口をひねって、水圧や排水の様子を確認したり、部屋ごとに電波の強さを確認し、通信環境に問題がないかチェックしたりすることも有効です。
内覧は「建物」だけでなく「暮らしやすさ」全体を確認する重要な機会です。
気になる点があれば遠慮せず、不動産会社や宅建士に質問しましょう。
すでに希望の中古住宅を見つけている方は、リノベーション前提で理想の間取りや設備を実現するために、複数のリフォーム会社から見積もりを取って比較するのがおすすめです。
▼無料の一括見積もりサービスを活用すれば、全国の優良リフォーム会社から価格や工事内容をまとめて確認でき、予算内で希望の住まいをカスタマイズする計画をスムーズに進められます。
3.買付申込書を提出する
購入したい物件が見つかったら、「買付申込書(購入申込書)」を不動産会社に提出します。
これは購入の意思を正式に示すもので、人気物件ほど早い決断が求められます。価格交渉や条件交渉もこの段階で行います。
価格交渉のコツは「根拠のある値引き交渉」です。
たとえば、「エアコン設置費用として20万円減額希望」「水回り設備が古いため50万円の値引き希望」など、リフォーム費用や設備交換費用を根拠にした交渉が成功しやすいです。
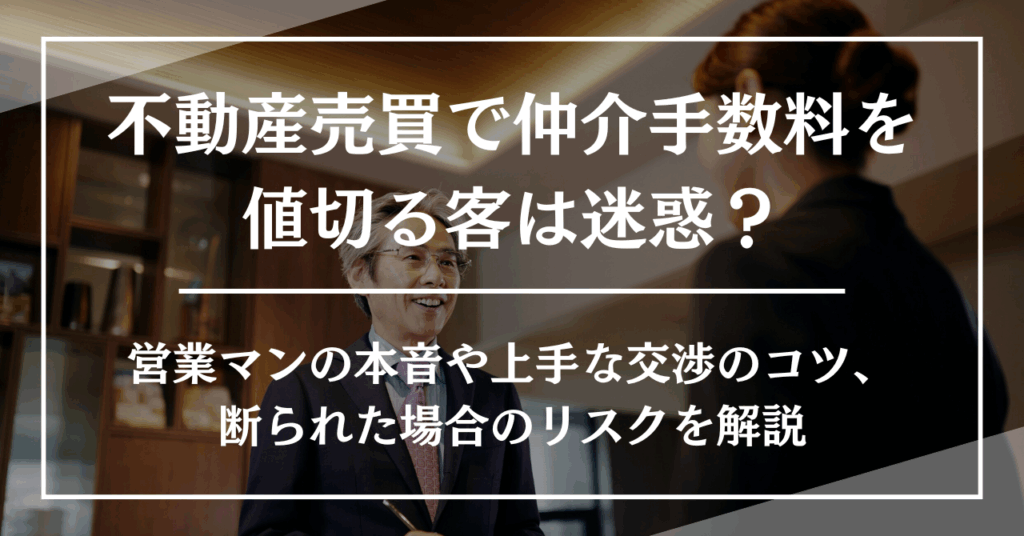
4.住宅ローンの事前審査(仮審査)を受ける
買付申込と並行して、金融機関に住宅ローンの仮審査を申し込みます。
ここで年収や勤続年数、他の借入状況から融資可能額の判断が行われます。
審査期間は通常3~7営業日ですが、自営業の場合は2週間程度かかることもあります。
物件購入は自己資金だけではまかなえないことが多いため、仮審査は早めに動くのがポイントです。
5.売買契約を締結する
住宅ローンの仮審査が通ったら、いよいよ売買契約です。
契約の際には宅建士から「重要事項説明書」の説明を受け、物件の権利関係や法的な制限事項などを確認します。
特に中古住宅は修繕履歴や管理状況、設備の保証範囲などをしっかり把握しましょう。
契約時には手付金(売買価格の5~10%程度)を支払います。
6.住宅ローンの本審査を申し込む
売買契約後は、正式に住宅ローンの本審査に進みます。
本審査では、物件の詳細情報や契約書類などが審査対象となりますので、書類の不備がないよう注意が必要です。
また、審査期間中は他社借入や転職を避けましょう。
審査通過後は金融機関と金銭消費貸借契約(ローン契約)を結びます。
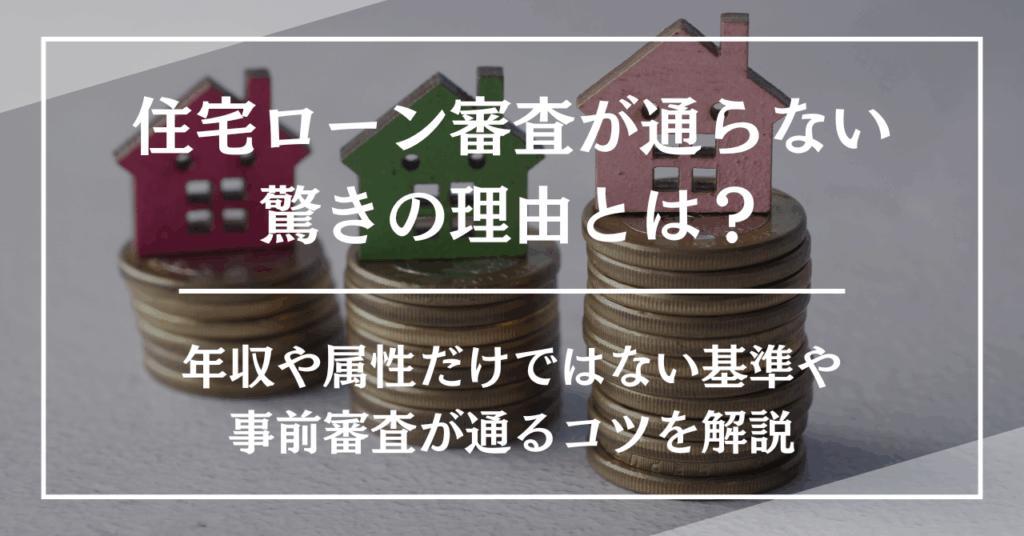
7.決済・引き渡し
最後に、ローン実行(融資)と同時に売買代金の残金を支払い、所有権移転登記を行います。
この日を「決済日」と呼び、不動産会社、金融機関、司法書士が立ち会います。
決済日は平日の午前中に設定されることが多く、通常2~3時間かかります。
鍵を受け取ったら引き渡しが完了し、晴れて新生活のスタートとなります。
中古住宅を購入するときの注意点

中古住宅を購入するときは、3つのことに注意しましょう。
1.利用できる補助金・減税措置は自分で調べる
2.住宅診断(ホームインスペクション)なしはトラブルの原因になり得る
3.リフォーム費用も含めた予算計画が高額になる可能性がある
それぞれ解説します。
1.利用できる補助金・減税措置は自分で調べる
中古住宅には、「住宅ローン減税」や「すまい給付金」、「長期優良住宅リフォーム補助金」など、条件を満たせば利用できる制度があります。
しかし、こうした制度は申請のタイミングや物件の条件によって適用の可否が分かれるため、不動産会社任せにせず、自分でも調べておくことが大切です。
特に築年数や耐震性能が要件に関わるケースが多いため、購入前に要件を確認しておきましょう。
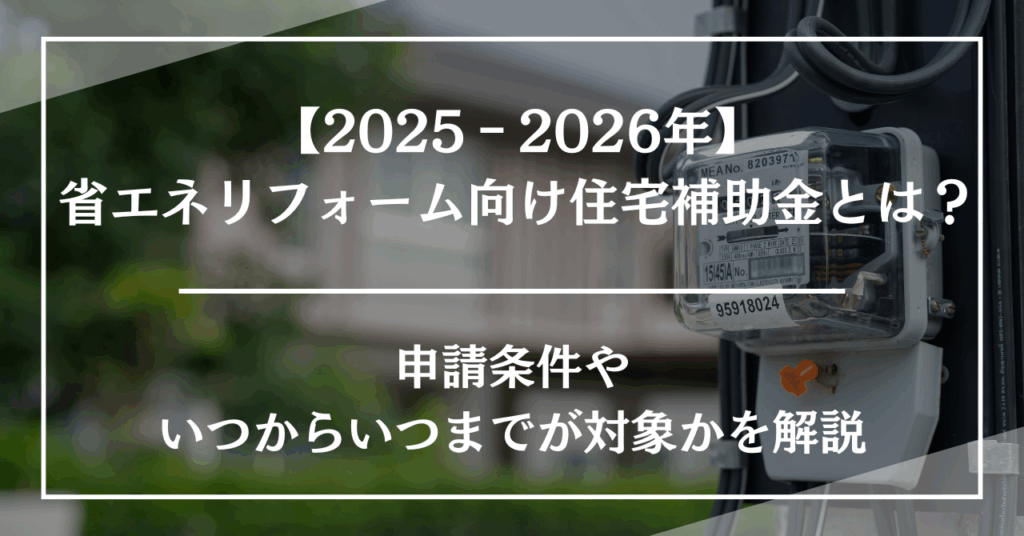
2.住宅診断(ホームインスペクション)なしはトラブルの原因になり得る
売買仲介の現場では、インスペクションを省いたことが原因で、引渡し後に雨漏りやシロアリ被害が発覚した事例があります。
ホームインスペクション(住宅診断)は、見た目ではわからない劣化や構造上の問題を専門家がチェックしてくれる重要なプロセスです。
費用は5~7万円程度ですが、安心して購入するための「保険」として、ぜひ導入を検討してください。
住宅購入では、ホームインスペクションで劣化や施工上の問題を確認することが重要ですが、それだけでは最適な物件選びは完結しません。
▼すでに希望の物件がある方でも、リフォームやリノベーションの必要性に応じて、複数の施工会社から見積もりを比較することが安心につながります。
![]()
3.リフォーム費用も含めた予算計画が高額になる可能性がある
中古住宅は新築に比べて価格が安く魅力的ですが、「購入後にかかる費用」の見積もりが甘いと、結果的に予算オーバーになるケースもあります。
たとえば水回りや外壁のリフォームは数十万円~100万円を超える場合も一般的です。
リフォームの規模によってはローンに組み込める商品もあるため、資金計画の段階からリフォーム費用を織り込むことが必要です。
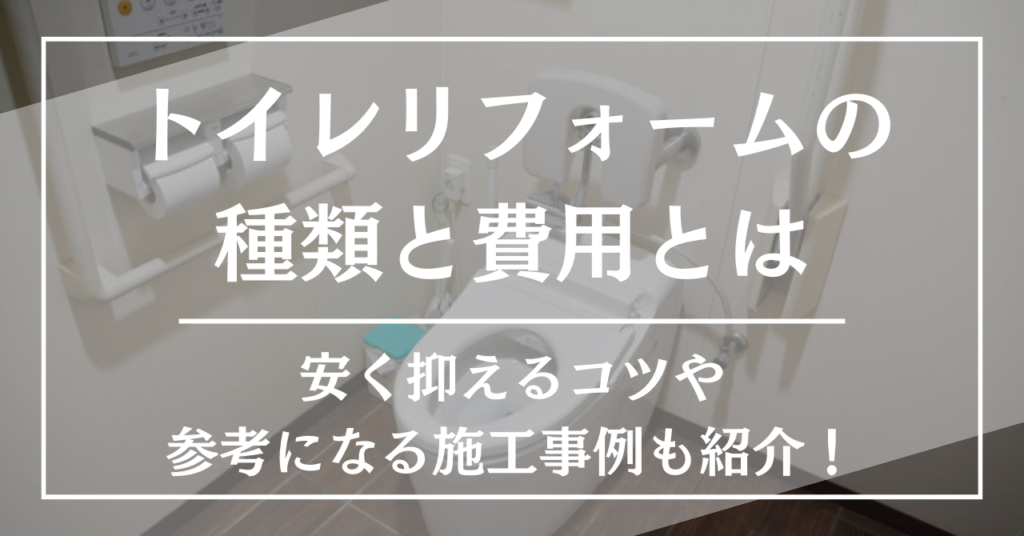
中古住宅を購入するときは見極めが大事!

中古住宅は、価格の安さや立地の選択肢が広い一方で、「見極め」が何より重要です。
新築と違い、築年数・メンテナンス状況・周辺環境・将来の資産価値など、チェックすべきポイントが多く、ひとつでも見落とすと、購入後に後悔することになりかねません。
購入後に満足される方の共通点は「事前にしっかり情報を精査し、納得して購入したこと」です。
住宅診断(インスペクション)やリフォーム費用の確認、契約書の理解など、少しの手間が安心な暮らしにつながります。
また、最近では住宅ローン減税や補助金など、中古住宅でも利用可能な支援制度が増えています。
制度を上手に活用しながら、物件の価値と将来性を見極めて選ぶことが、賢い中古住宅購入の第一歩と言えます。
信頼できる不動産会社や宅建士への相談も、成功への近道です。