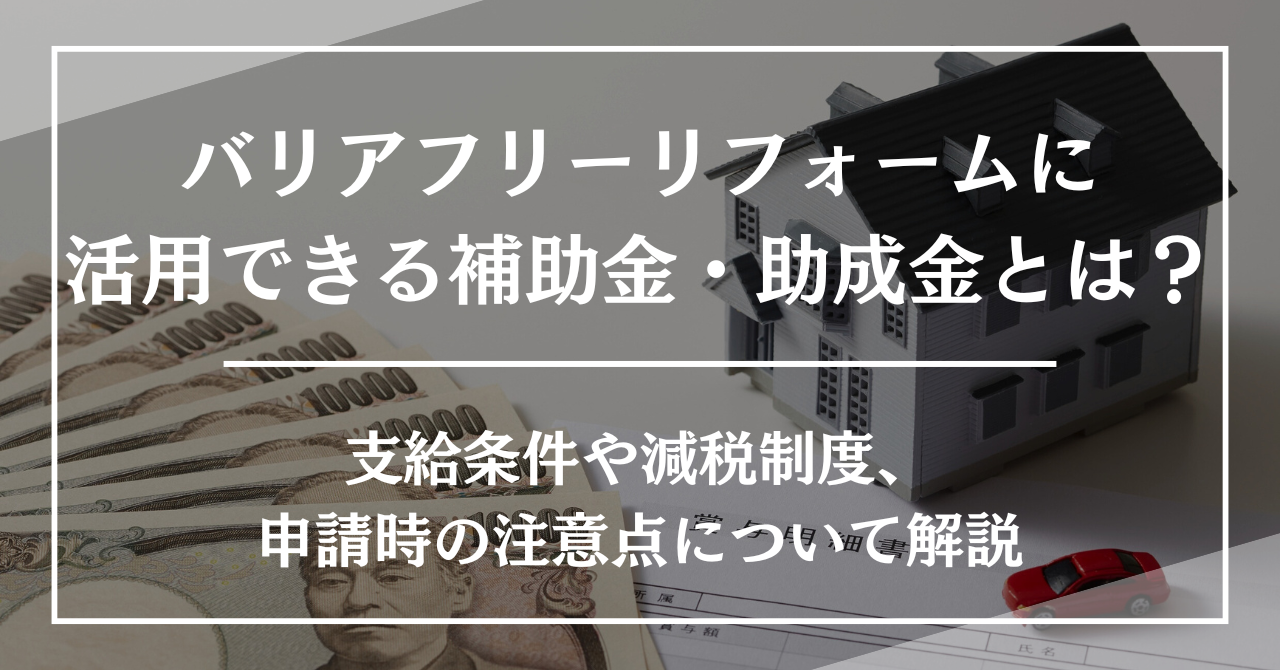※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「バリアフリーリフォームってどれくらい費用がかかるの?」
「申請のタイミングを間違えると損するって本当?」
「補助金や助成金は誰でも使えるの?」
実は、バリアフリーリフォームには国や自治体の補助制度を活用することで、自己負担を大幅に抑えられるケースがあります。
うまく使えば総額の3〜5割を軽減できることもあるのです。
一方で、制度が複雑で「何から始めればいいか分からない」という方も多いでしょう。
そこで本記事では、バリアフリーリフォームに活用できる補助金・助成金制度について解説します。
また、減税制度や申請時の注意点についても紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
バリアフリーリフォームの費用相場

バリアフリーリフォームの費用は、工事内容によって大きく異なりますが、一般的には50万円から150万円程度が相場となっています。
手すりの設置や段差の解消といった比較的軽微な工事であれば、数万円から対応可能です。
| 施工箇所 | 主なリフォーム内容 | 費用相場(税込) | 工期目安 | 主な補助制度例 |
|---|---|---|---|---|
| 玄関 | スロープ設置・手すり・引き戸交換 | 約2〜30万円 | 1〜3日 | 介護保険住宅改修・自治体助成 |
| 廊下・階段 | 手すり設置・段差解消・階段昇降機 | 約3〜100万円 | 1〜7日 | 介護保険住宅改修・長期優良住宅化 |
| トイレ | 洋式化・手すり・引き戸変更 | 約3〜75万円 | 1〜3日 | 介護保険住宅改修・自治体助成 |
| 浴室 | 段差解消・滑りにくい床・ユニットバス交換 | 約10〜150万円 | 3〜10日 | 長期優良住宅化・介護保険住宅改修 |
| 洗面所・脱衣所 | 高さ調整・滑り止め床・段差解消 | 約3〜15万円 | 1〜3日 | 自治体助成・介護保険住宅改修 |
| キッチン | 高さ調整式キッチン・間取り拡張 | 約30〜120万円 | 5〜10日 | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 |
| 寝室・リビング | 床段差解消・引き戸化・ベッドスペース確保 | 約5〜15万円 | 1〜3日 | 自治体助成・長期優良住宅化 |
ただし、浴室やトイレの全面改修、廊下の拡張工事などを含む場合は、100万円を超えるケースも珍しくありません。
国や一部の地方自治体では、バリアフリーリフォーム費用の負担を軽減するため、補助金・助成金制度を充実させており、実質的な自己負担を3割から9割程度減らすことが可能です。
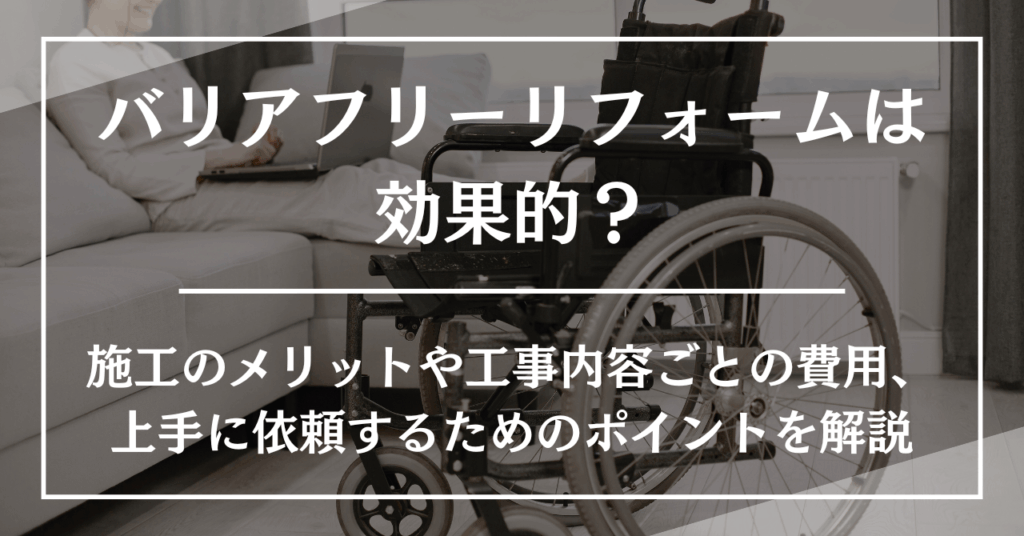
バリアフリーリフォームに活用できる補助金・助成金制度

バリアフリーリフォームを実施する際には、国や地方自治体が提供する複数の補助金・助成金制度を活用することで、大幅に費用負担を軽減できます。
主な制度として、介護保険による住宅改修支援、国土交通省の長期優良住宅化リフォーム推進事業、各自治体独自の助成金制度などがあり、条件を満たせば併用も可能です。
1.介護保険の住宅改修支援制度
介護保険の住宅改修支援制度は、要支援または要介護の認定を受けた方が対象となり、上限20万円まで住宅改修費用の補助が受けられる制度です。
対象となる工事は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への交換、これらに付帯する工事の計6項目に限定されています。
自己負担割合は所得に応じて1割から3割となるため、最大で18万円の補助を受けることが可能です。
申請にあたっては、工事着手前にケアマネージャーや施工業者と十分に相談し、必要書類を揃えることが必須となります。
住宅改修を検討する際、信頼できる施工業者を効率的に比較・選定できると安心です。
とくに、複数の業者から見積もりを一括で取れる「リショップナビ」を活用すれば、費用や工事内容を簡単に比較でき、最適な業者を選びやすくなります。
![]()
介護保険の住宅改修支援を受けるまでの流れ
補助金の支給までには、こちらのステップを踏んでいく必要があります。
1.要介護認定を取得し支援対象を確認
2.ケアマネジャーに相談し改修方針を決定
3.自宅の課題を整理し改修計画を作成
4.必要書類を揃えて事前申請を実施
5.承認後にバリアフリー工事を着工
6.工事完了後に実績書類を提出・精算
申請が通ってから着工に移るまでに最短で2~3週間、年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇をはさむと4~6週間に延びてしまうこともあります。
施工を実施する工務店側との連携も重要です。
介護保険の住宅改修支援を活用する場合の必要書類
介護保険の住宅改修支援制度の利用者が準備すべき書類はこちらです。
| 書類名 | 内容・用途 | 注意点・ポイント |
|---|---|---|
| ☆住宅改修費支給申請書 | 住宅改修を行う旨を保険者へ申請する基本書類 | 工事前に必ず提出。保険給付の対象確認に使用される |
| ☆住宅改修が必要な理由書 | 改修が必要な理由をケアマネジャー等が記入 | 要介護者の状態や生活動線を具体的に記載すること |
| ☆工事費見積書 | 改修予定の工事内容と費用を示す書類 | 工事項目ごとに金額明細を明確に記載する |
| ☆改修後の完成予定図・写真 | 改修後のイメージを示す資料 | 図面または写真で、どの箇所を改修するかを明確にする |
| 領収書 | 実際に住宅改修にかかった費用を証明する書類 | 支払日・金額・施工業者名を明記すること |
| 工事費内訳書 | 実際の工事費を項目ごとに示す明細書 | 提出内容が見積書と大きく異ならないか確認される |
| 改修前・改修後の写真 | 工事内容を確認するための証拠資料 | 各箇所(便所・浴室・廊下など)を撮影、撮影日を明記する |
| 住宅所有者の承諾書 | 利用者が住宅の所有者でない場合に必要 | 所有者が改修を承諾した旨を記載・署名すること |
「☆」マークの書類は、工事前に行う「事前申請(最初の申請)」で提出が必要な書類です。
一方で、その他の書類は、工事完了後の「支給申請(2回目の申請)」で提出します。
2.長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、国土交通省が実施する補助金制度で、最210万円の支援が受けられる大規模な制度です。
この制度では、省エネルギー性能の向上、耐震性の確保、劣化対策に加えて、バリアフリー改修を含む総合的なリフォームが条件となっています。
単独でバリアフリー工事のみを行う場合は対象外となるため注意が必要です。
たとえば、親の介護をきっかけにして三世帯住宅へのフルリフォームをしたり、災害対策のための躯体補強リフォームを実施したりなどが挙げられます。
申請手続きは専門性が高く、事業者登録を受けた工務店やリフォーム会社が代行するのが一般的です。
補助額が大きい分、審査基準も厳しく設定されているため、実績のある施工業者を選定することが重要です。
長期優良住宅化リフォームの申請や施工を検討する際は、実績あるリフォーム業者の比較が重要です。
複数の施工会社からまとめて見積もりを取れる「リショップナビ」を活用すれば、費用や工事内容を簡単に比較でき、条件に合った信頼できる業者を効率的に選べます。
![]()
長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助額と補助率
対象となるリフォーム工事費の「3分の1(1/3)」が補助されます。
補助上限額は、リフォーム後の住宅性能の水準や世帯条件によって異なります。
| 住宅性能区分 | 補助上限額(通常) | 特例上限額(※) | 条件の概要 |
|---|---|---|---|
| ① 一定の性能向上が認められる住宅 | 80万円/戸 | 130万円/戸 | 長期優良住宅の認定は受けないが、耐震・省エネなど性能向上を実施した場合 |
| ② 長期優良住宅(増改築)認定住宅 | 160万円/戸 | 210万円/戸 | 国の「長期優良住宅(増改築)」認定を取得した場合 |
特例上限額(※)は、三世代同居対応改修工事を実施する場合、若者・子育て世帯によるリフォームの場合または、既存住宅を購入して改修する場合のいずれかに該当する場合に適用されます。
参照:補助を受けるための要件|令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業
3.地方自治体の補助金制度
各市町村では独自のバリアフリーリフォーム補助金制度を設けており、上限10万円から50万円程度の助成金が用意されています。
対象者は自治体によって異なりますが、高齢者世帯だけでなく、障がい者や子育て世帯を対象としているケースもあります。
たとえば、愛知県名古屋市では「障害者住宅改造補助事業」を創設し、現に居住している(又は予定の)市内の家屋をバリアフリー改修工事した場合、補助基準額に応じて最大全額を補助してくれます。
同じ都道府県内でも市町村によって制度内容が大きく異なる場合があるため、お住まいの地域の制度を個別に調べる必要があります。
また、多くの自治体では、工事着手前の申請と完了後の領収書提出が支給条件となっているため、事前の確認が欠かせません。
バリアフリーリフォームに活用できる減税制度

バリアフリーリフォームを実施した場合、所得税や固定資産税の控除を受けることで、さらに経済的な負担を軽減することが可能です。
補助金や助成金と併用できる場合も多く、トータルでの節税効果は大きくなります。
ただし、減税制度を利用するためには、対象となる工事内容や住宅の条件を満たす必要があり、申告時には領収書や施工証明書などの書類提出が必須となります。
1.所得税の控除
バリアフリー改修促進税制を利用すると、工事費用の約10%相当の所得税額控除が受けられます。
対象者はマイホームについてバリアフリー改修工事を行った方です。
また、この制度を適用するためには、50歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けた方、障がい者、65歳以上の親族と同居している方のいずれかに該当する必要があります。
控除を受けるには確定申告が必要で、工事内容を証明する書類を添付して申請します。
バリアフリー改修促進税制を受けるまでの流れ
所得控除の適用までには、こちらのステップを踏んでいく必要があります。
1.マイホームにバリアフリー改修を実施
2.改修後6か月以内に居住開始
3.所得金額など適用要件を満たすか確認
4.確定申告で控除申請する
普段確定申告をしない会社員の方は、忘れないように注意が必要です。
バリアフリー改修促進税制を活用する場合の必要書類
適用要件(所得・居住要件・改修費用など)や添付書類については幅が広く、数も多いと言えます。
| 書類名 | 内容・用途 | 注意点・ポイント |
|---|---|---|
| 確定申告書 | 所得税控除を申請する基本書類 | 所轄税務署に提出 |
| 控除額計算明細書 | 控除額を算定する明細表 | 所定様式に記入 |
| 増改築等工事証明書 | 改修工事を証明する証明書 | 建築士等の証明が必要 |
| 登記事項証明書 | 床面積など住宅情報の証明 | 登記簿の情報と合致していること |
| 被保険者証の写し等 | 適用対象者であることを証明 | 要支援・要介護などの認定証も含む場合あり |
| 補助金・交付書類 | 補助金を受けていればその証明 | 補助金額を控除した金額が控除対象費用になる |
確定申告の直前になって焦らないためには、施工業者や税理士と事前に確認することが重要です。
参照:バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|国税庁
2.固定資産税の控除
バリアフリーリフォームを行った住宅については、改修完了翌年以降3年間にわたり、固定資産税額の3分の1が減額される制度があります。
減額を受けるためには、改修工事費用が50万円以上であることなどが条件となり、賃貸住宅は対象外となります。
介護保険の住宅改修や他の補助金制度と併用できる場合が多いため、総合的な負担軽減につながります。
バリアフリー改修促進税制の適用要件
こちらの要件を満たしている方は、申請することで減税の恩恵が受けられます。
1.減税を申請する本人が居住する住宅であること
2.申請者が65歳以上・要支援・障がい者のいずれかであること
3.新築から10年以上経過した住宅であること
4.賃貸住宅ではなく自宅であること
5.補助金を除いた工事費が50万円超(税込)であること
6.改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
7.店舗併用住宅は居住部分が全体の2分の1以上であること
申請は工事完了後3か月以内に、お住まいの市町村役場の税務課へ必要書類を提出する必要があります。
参照:バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置|国土交通省
バリアフリーリフォームで補助金・助成金・減税制度を申請するときの注意点

補助金や助成金、減税制度を確実に受け取るためには、申請のタイミングと必要書類の準備が極めて重要です。
制度ごとに対象条件や申請期限が異なるため、事前に詳細を確認しておく必要があります。
ここからは、補助金や助成金、減税制度の申請における注意点について解説します。
1.リフォーム補助金の申請は「工事前」が基本
多くの補助金制度では、工事着手後の申請は原則として認められておらず、この点を知らずに失敗する事例が非常に多く見られます。
申請には工事の見積書、設計図面、現況写真などが必要書類となることが一般的です。
とくに介護保険の住宅改修支援制度や自治体の助成金では、事前申請が必須条件となっており、工事開始後に気づいても対応できません。
そのため、リフォームを計画する段階で、まず市町村役場や地域包括支援センターなどの行政窓口に相談し、必要な手続きと書類を確認することがおすすめです。
施工業者との契約前に申請手続きを完了させておくことで、補助金を確実に受け取ることができます。
また、補助金を確実に受け取るためには、申請に対応できる信頼できる施工業者を選ぶことも重要です。
複数の業者を一括で比較できる「リショップナビ」を利用すれば、見積もりや工事内容を簡単に確認でき、申請条件に適した業者を効率的に見つけられます。
![]()
2.予定より早めに打ち切りになる助成金もある
補助金や助成金の多くは予算枠が設定されており、上限に達すると年度途中であっても受付が終了してしまいます。
とくに毎年度4月から6月にかけては申請が集中する傾向があり、人気の高い制度では半年程度で予算がなくなるケースも少なくありません。
また、自治体によっては先着順で受付を行っているため、制度の存在を知った時点ですでに締め切られていたという事例もあります。
こうした事態を避けるためには、年度初めから定期的に自治体のホームページをチェックし、募集開始と同時に申請できるよう事前準備を進めておくことが重要です。
3.減税制度の申請には確定申告が必要になる
所得税の控除や住宅ローン減税を受けるためには、翌年の確定申告で手続きを行う必要があります。
会社員の方で普段確定申告をしていない場合でも、減税制度を利用する年は必ず申告が必要となるため注意が必要です。
申告時には工事費用の領収書、施工業者が発行する工事証明書、住宅の登記事項証明書などの提出が求められます。
これらの書類に不備や提出漏れがあると控除が受けられないため、工事完了後は必ず書類を受け取り、大切に保管しておきましょう。
書類作成や申告手続きに不安がある場合は、税理士に相談するか、施工業者に書類作成のサポートを依頼することも可能です。
補助金・助成金・減税制度を活用してお得にリフォームを!

バリアフリーリフォームを実施する際には、補助金、助成金、減税制度を併用することで、大幅に経済的負担を軽減することができます。
ただし、これらの制度を確実に活用するためには、事前の情報収集と書類管理が重要となります。
たとえば、補助金申請の実績が豊富な専門業者と連携し、計画的にリフォームを進めることで、安心して準備することができます。
工事着手前の申請、予算枠の確認、確定申告の準備など、各段階で必要な手続きを漏れなく進めていきましょう。