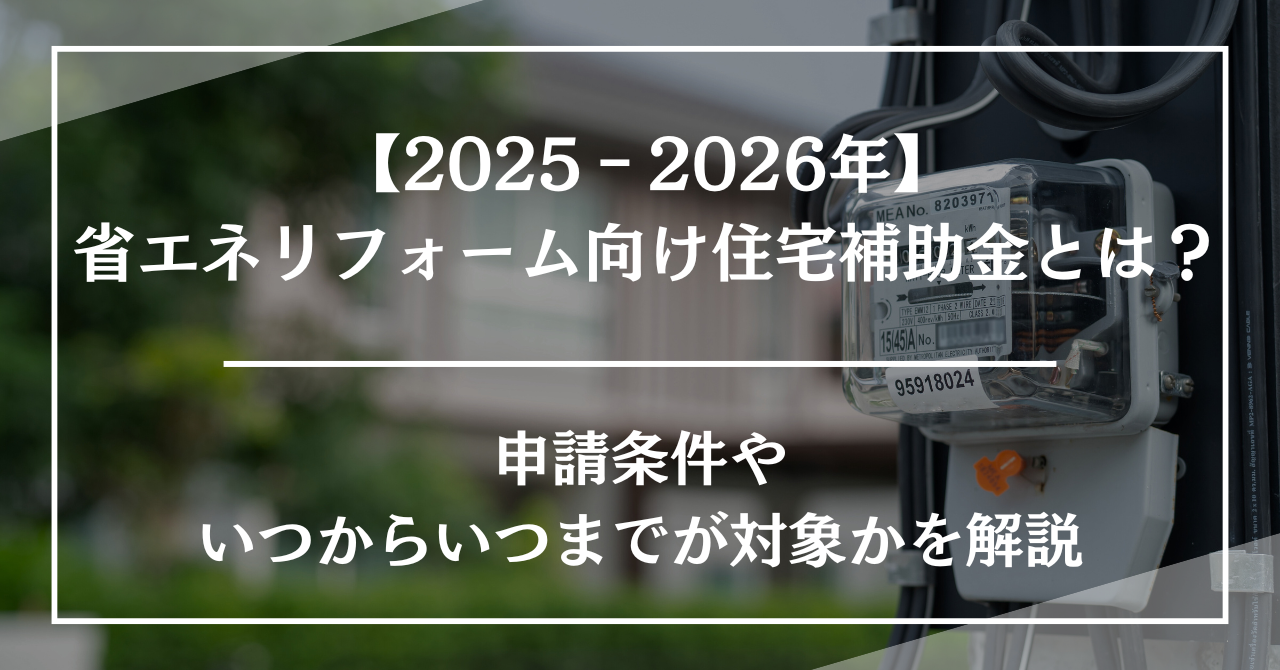※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「省エネリフォームの補助金ってどれを使えばいいの?」
「申請のタイミングを間違えると受け取れないって本当?」
「2026年も今の制度が続くの?」
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実は、2025年は「住宅省エネキャンペーン」など過去最大級の補助制度が用意されています。
そこで本記事では、2025年から2026年に申請できる省エネリフォーム向けの住宅補助金制度を解説します。
また、申請手順や注意点、よくある質問についても紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
省エネリフォーム工事の種類と費用相場

省エネリフォームを検討する際は、まず工事の種類と費用感を把握することが重要です。
代表的なリフォーム工事は以下の通りです。
| 工事種類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 断熱性能が高い窓へ交換工事 | 数十万円 |
| 外壁・屋根を含む大規模な断熱性能向上工事 | 100〜300万円 |
| エコキュートへの交換工事 | 40〜70万円 |
| ハイブリッド給湯器への交換工事 | 70〜90万円 |
| 太陽光パネル・蓄電池の設置工事 | 200〜600万円以上 |
とくに高額となる大規模工事を予定している場合は、国や自治体の補助金制度を活用して、経済的な負担を軽減することが有効です。
省エネリフォームは工事内容や費用が幅広いため、複数の業者から見積もりを取って比較するのが安心です。
▼費用や工事プランを確認しながら賢く計画を進めたい方は、希望するリフォーム内容に応じて全国の優良リフォーム会社を無料で一括比較・見積もりすることをおすすめします。
![]()
2025年に申請できる省エネリフォームの補助金制度

2025年には国や地方自治体が提供する複数の省エネリフォーム補助金制度が用意されています。
ここでは、主な制度として以下の5つを紹介します。
1.住宅省エネ2025キャンペーン
2.長期優良住宅化リフォーム推進事業
3.既存住宅における断熱リフォーム支援事業
4.次世代省エネ建材の実証支援事業
5.各自治体独自の補助金制度
それぞれの制度には対象となるリフォーム内容や申請条件、補助金額が異なるため、ご自身の計画に合った制度を選択することが大切です。
1.住宅省エネ2025キャンペーン
住宅省エネ2025キャンペーンは、2025年に国が総力を挙げて展開する大型の省エネ支援制度です。
国土交通省・経済産業省・環境省の3省が連携して実施しており、新築住宅とリフォームの両方が対象となっています。
最大の特徴は、複数の補助事業を併用することで最大260万円相当の補助を受けられる点です。
具体的には「子育てグリーン住宅支援事業」「先進的窓リノベ2025事業」「給湯省エネ2025事業」という3つの補助事業で構成されており、それぞれ申請要件や対象となる工事内容が異なります。
1-1.子育てグリーン住宅支援事業
子育てグリーン住宅支援事業は、窓断熱や外壁・屋根の断熱改修を含む幅広い省エネ改修工事を対象とした補助制度です。
リフォームの場合、実施する以下の必須工事の種類によって補助上限が異なります。
・開口部の断熱改修(窓・ドア)
・躯体の断熱改修(外壁・屋根・天井・床)
・エコ住宅設備の設置(高効率給湯器・換気設備など)
3つの必須工事カテゴリーのうち、2種類を実施した場合は上限40万円、3種類すべてを実施した場合は上限60万円が適用されます。
また、新築住宅を取得する場合には最大160万円という高額な補助枠が設定されています。
1-2.先進的窓リノベ2025事業
先進的窓リノベ2025事業は、高断熱窓やドアの改修工事に特化した補助制度で、最大200万円という高額な補助枠が設定されています。
窓は住宅の中で最も熱の出入りが大きい部分であり、断熱性能の高い窓に交換することで冷暖房効率が大幅に向上します。
また、補助金の申請が「窓リノベ事業者登録業者」を通じてのみ可能ということが最大の特徴です。
対象となる窓やドアの製品は事務局が登録した性能基準を満たすものに限定されており、どの製品でも補助対象になるわけではありません。
一般の方が直接申請することはできないため、必ず登録事業者に工事を依頼する必要があります。
1-3. 給湯省エネ2025事業
給湯省エネ2025事業は、エコキュートやハイブリッド給湯器などの高効率給湯器を設置する際に定額の補助を受けられる制度です。
対象となるのは既存の給湯器を高効率タイプに交換する工事で、設置工事費用を含めた契約が補助の対象です。
補助金額は給湯器の種類によって異なり、最大20万円の補助が設定されています。
また、給湯省エネ2025事業の補助金制度を活用したい場合、「給湯省エネ事業者登録業者」と契約することが必須条件となります。
登録業者でなければ補助金の申請ができないため、工事業者を選ぶ際には必ず登録の有無を確認しましょう。
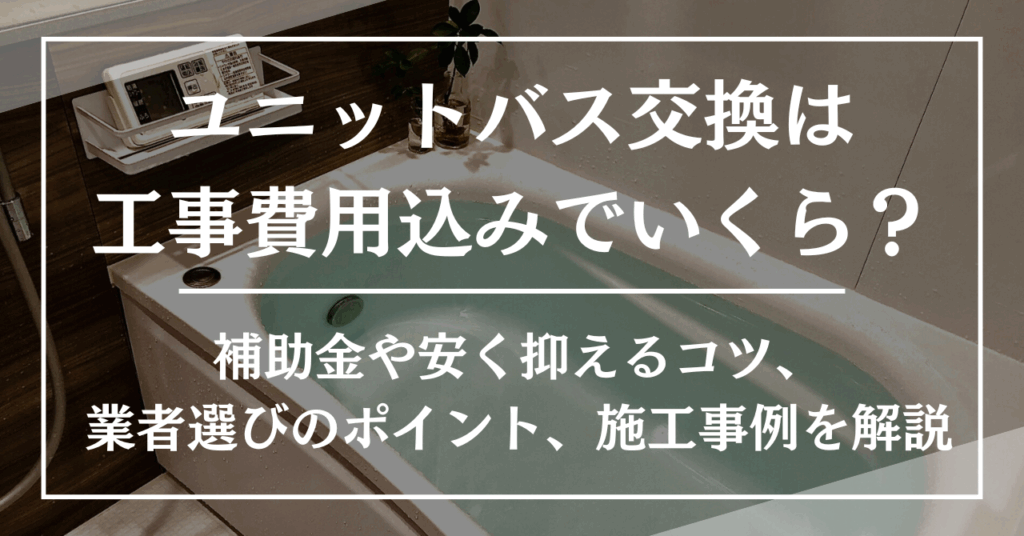
2.長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、住宅の性能を高めて長寿命化を図るリフォームを支援する制度です。
単なる省エネ改修だけでなく、住宅全体の質を向上させる総合的なリフォームが対象となることが特徴です。
補助率はリフォーム費用の3分の1で、補助上限は基本的に80万円から160万円となっていますが、条件によってはさらに上限が拡大される場合もあります。
申請にあたってはインスペクション(建物状況調査)の実施が必須で、加えて維持保全計画や履歴の作成も求められます。
一見ハードルが高く感じられますが、住宅の資産価値を維持し将来的な売却時にも有利になることを考慮するとメリットは大きいです。
3.既存住宅における断熱リフォーム支援事業
既存住宅における断熱リフォーム支援事業は、既存の住宅で断熱改修を行う際に活用できる支援制度です。
補助率は工事費用の3分の1、補助上限額は120万円が設定されています。主な対象工事は、断熱材の補強や外壁・屋根・基礎部分の断熱改修工事です。
とくに築年数が古い住宅では断熱性能が不十分なことが多いため、この制度を活用して断熱改修を行うことで居住快適性と省エネ性能の両方を向上させることができます。
ほかの省エネ関連補助制度と併用できるケースがあるため、総合的なリフォーム計画を立てる際には確認してみましょう。
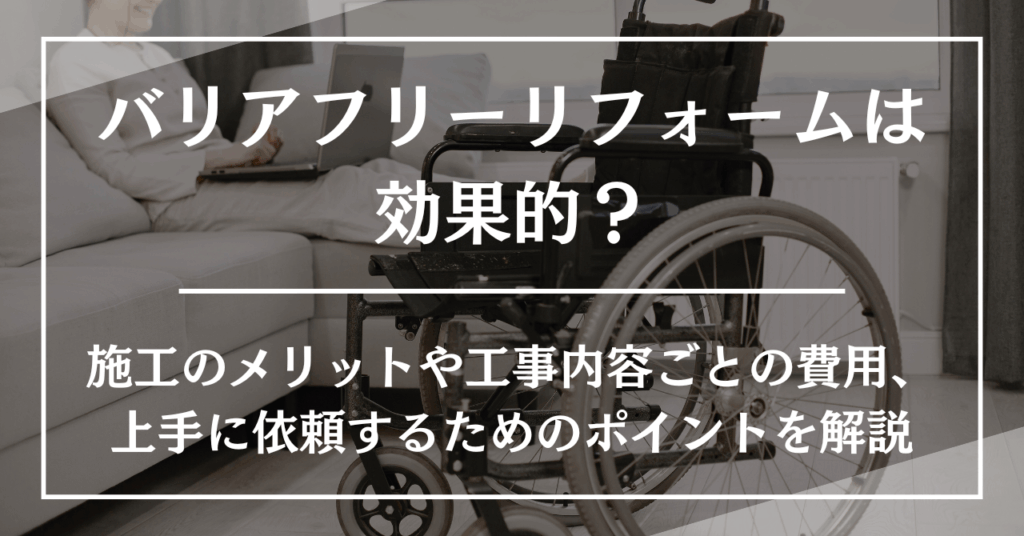
4.次世代省エネ建材の実証支援事業
次世代省エネ建材の実証支援事業は、新しい技術を用いた省エネ建材の導入を支援する制度です。
たとえば、従来よりも薄くて高性能な断熱材や、施工期間を大幅に短縮できる新工法を用いた改修工事が対象となります。
補助率や対象期間、具体的な要件は公募条件によって異なるため、申請を検討する際には最新の公募要領を確認する必要があります。
最先端の省エネ技術を導入したい方や、より高い断熱性能を実現したい方に適した制度といえるでしょう。
参照:令和6年度 次世代省エネ建材の実証支援事業|一般社団法人 環境共創イニシアチブ
5.お住いの地方自治体の補助金制度
国の制度に加えて、お住いの市区町村が独自に実施している補助金制度も見逃せません。
地方自治体の補助金は国の制度と併用できるケースが多く、うまく組み合わせることで補助金額を増やせます。
たとえば、断熱改修に特化した補助金、太陽光発電システムの設置支援、高効率エネルギー設備の導入補助など、自治体ごとに様々な制度が用意されています。
省エネリフォームを検討している方は、「〇〇市 リフォーム 補助金」といったように「(お住まいの市区町村名)+(関連キーワード)」で検索してみてください。
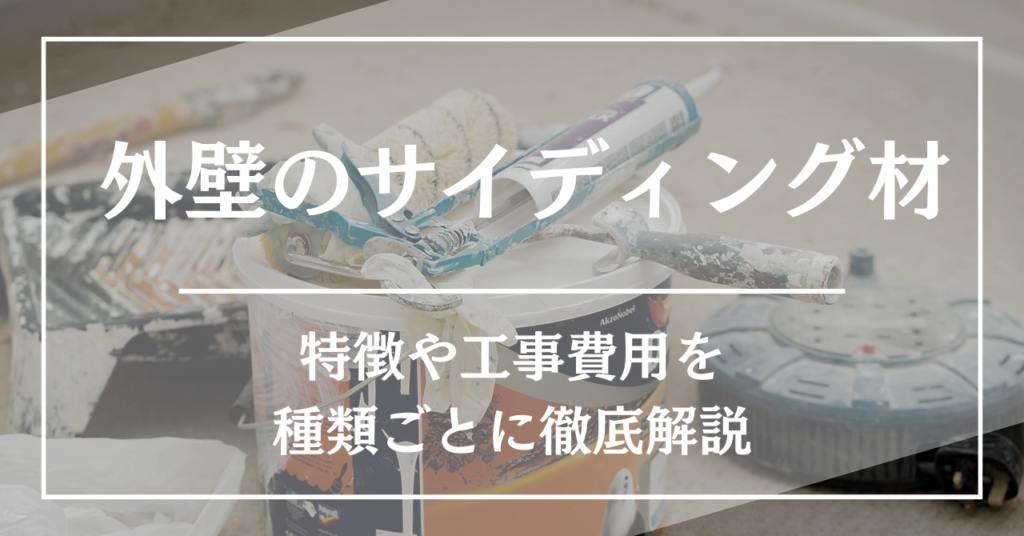
2026年に申請できる省エネリフォームの補助金制度

2026年の省エネリフォーム補助金制度については、2025年の制度が継続される見込みですが、現時点(2025年10月16日)では確定した情報は発表されていません。
政府は温室効果ガスの排出量を全体として実質ゼロにすることを目指す「カーボンニュートラル政策」を継続する意向であることから、何らかの形で省エネリフォーム支援は維持されると予想されます。
ただし、予算規模の縮小や申請要件の変更が行われる可能性は十分にあります。
過去の事例を見ても、年度ごとに補助金額の上限や対象となる工事内容、申請手続きの詳細などが見直されることは珍しくありません。
とくに予算配分については政治・経済状況の影響を受けやすく、前年度と同じ条件が維持されるとは限りません。
リフォームを検討している方は、2025年中に申請できる制度を優先的に活用しつつ、2026年の最新公募要領が発表され次第、速やかに情報収集することが重要です。
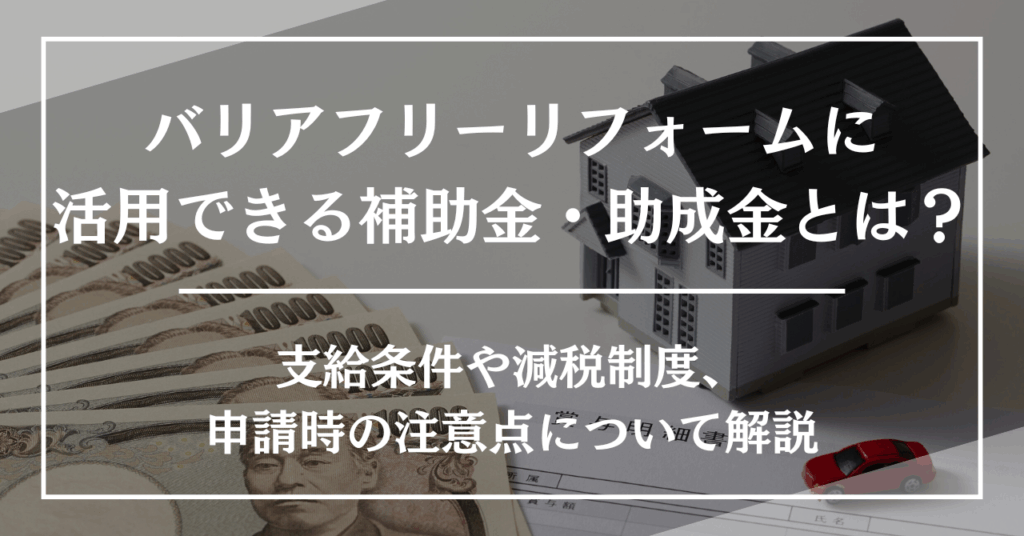
省エネリフォームの補助金制度を活用する手順

省エネリフォームで補助金を受け取るには、正しい手順で申請を進める必要があります。
ここからは、それぞれのステップごとに注意点を解説していきます。
1.どの補助金制度が活用できるか調べる
建物の築年数や現在のお住いの性能レベル、実施予定のリフォーム内容によって、活用できる補助金制度が変わってきます。
たとえば、窓の断熱改修だけを行うなら先進的窓リノベ2025事業が適していますし、給湯器交換なら給湯省エネ2025事業が該当します。
補助金制度を調べるときは、国が実施する制度と地方自治体の独自制度の両方を確認しましょう。
また、複数の制度を併用できるケースもあるため、併用の可否についても調べる必要があります。
補助金を活用したリフォーム実績が豊富な不動産会社や工務店に相談すれば、プロの視点から最適な制度の組み合わせを提案してもらえることもあります。
2.工事契約の前に交付申請をする
補助金制度の多くは、工事契約を結ぶ前に交付申請を行うことが求められます。
とくに長期優良住宅化リフォーム推進事業などでは、交付申請前に契約を締結してしまうと補助対象外となるケースがあるため注意が必要です。
また、制度によっては事業者登録や住宅登録の手続きを先に済ませる必要があります。
たとえば窓リノベ事業では登録事業者でなければ申請できませんし、給湯省エネ事業も同様です。
申請書類の作成には工事業者の協力が不可欠なため、補助金活用を前提とした工事であることを最初から業者に伝えておくことが大切です。
▼補助金を活用したリフォームを検討するなら、まずは複数の優良業者から見積もりを比較するのがおすすめです。
![]()
3.工事を開始して完了報告を受ける
交付申請が承認されたら、契約内容に沿って工事を開始します。
工事中は施工状況の写真や工程記録は、完了報告時に提出が求められるため残しておく必要があります。
工事が完了したら、補助事業者が実績報告書を作成し、事務局に完了報告を行います。
施工品質や仕様が当初の申請内容と一致しており、制度が定める性能基準を満たしているの証明が必要です。
もし工事内容に変更があった場合は、事前に変更申請が必要なケースもあります。
完了報告の内容に不備があると補助金の交付が遅れたり減額されたりする可能性があるため、業者と密に連携して正確な報告を行うことが大切です。
4.交付審査を受けて補助金の入金を確認する
完了報告を提出すると、事務局による交付審査が行われます。審査では提出書類の内容確認や、必要に応じて現地調査が実施される場合もあります。
審査を通過すれば補助金額が正式に確定し、事業者を経由して施主に補助金が入金されます。
審査過程では追加資料の提出を求められることも少なくありません。
また、書類の記載内容に不明点があったり、写真が不鮮明だったりすると、再提出が必要になり入金が遅れる原因となります。
一般的に申請から入金まで数ヶ月かかることも珍しくないため、資金計画には余裕を持っておくことをおすすめします。
さらに、補助金を受け取った後も、維持保全履歴などの書類を一定期間保存する義務がある場合があります。
工事完了後も数年間は、書類を大切に管理しましょう。
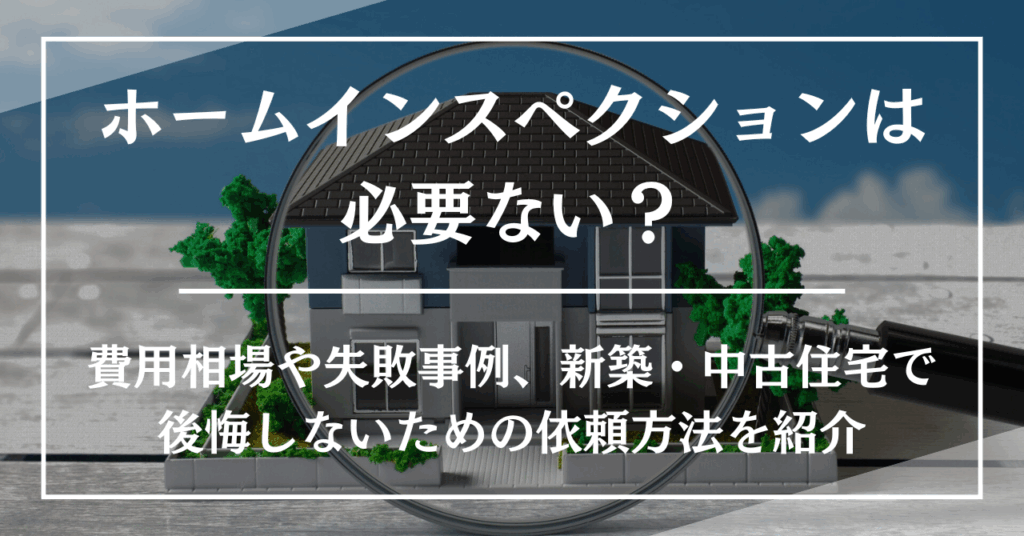
省エネリフォームの補助金制度に関するよくある質問

ここからは、省エネリフォームの補助金制度についてよくある質問を回答していきます。
1.省エネリフォーム関連の補助金制度は2026年以降どうなる?
2026年以降の補助金制度については、現時点で確定した情報はありません。
国の予算確保が難しくなれば、制度の縮小や統合が行われる可能性があります。
一方で、日本政府が掲げる2050年カーボンニュートラル目標の達成には、住宅の省エネ化が不可欠であるため、何らかの形で支援策は継続されると予想されます。
過去の傾向を見ると、省エネ政策の継続性は高く、制度名や枠組みが変わっても類似の補助制度が維持されてきました。
最新情報を定期的にチェックし、新制度の発表があり次第すぐに対応できる準備をしておくことが重要です。

2.年度をまたぐ工事の場合はどうやって申請する?
年度をまたぐ長期の工事では、補助金申請のタイミングを慎重に検討する必要があります。
申請年度内に契約・着工・完了のいずれかまたは全てを済ませることが要件となっているためです。
たとえば、2025年度の制度に申請する場合、2025年3月末までに工事完了報告を提出するケースが一般的です。
万が一、複数年度にまたがる大規模な工事を実施する場合、工事を段階的に分割して各年度で別々に申請する方法が考えられます。
しかし、翌年度以降も同様の補助金制度が維持されるかはわからないため、変更されるリスクも考慮して検討することが重要です。
3.「予算上限」で締め切られたらどうすべき?
多くの補助金制度は予算に限りがあり、申請額が予算上限に達した時点で受付が終了します。
一方で、年度が始まって早々にすべての年間予算を使い切ってしまうことは稀です。
たとえば、住宅省エネ2025キャンペーンなどでは、第一期や第二期といった形で期間を区切り、各期の予算が埋まり次第締め切られる仕組みとなっています。
万が一、希望していた制度の受付が終了してしまった場合は、代替となる他の国の制度や地方自治体が独自に実施している補助金制度の利用を検討しましょう。
また、次年度の制度開始を待つという選択肢もありますが、その間に要件が変更される可能性も考慮する必要があります。
いずれにしても、情報収集と早めの行動が重要と言えます。
補助金の予算上限に達してしまう前に、複数の業者から見積もりを取って早めに計画を進めるのがおすすめです。
▼一括見積もりサービスを利用すれば、条件に合った業者を効率よく比較・検討できます。
![]()
省エネリフォーム補助金を受け取りたいなら早めに申請を!

2025年には「住宅省エネ2025キャンペーン」をはじめとする複数の補助制度が用意されており、うまく活用すれば数十万円から最大260万円規模の補助を受けられます。
2026年以降の補助制度については不透明な部分もありますが、省エネ政策の継続性を考えると何らかの支援は続く見込みです。
「せっかくならお得に省エネリフォームしたい!」という方は、国の制度と地方自治体の独自制度を併用することがおすすめです。
各制度には予算上限があり先着順で締め切られることが多いため、リフォーム計画が決まったら速やかに申請準備を進めましょう。