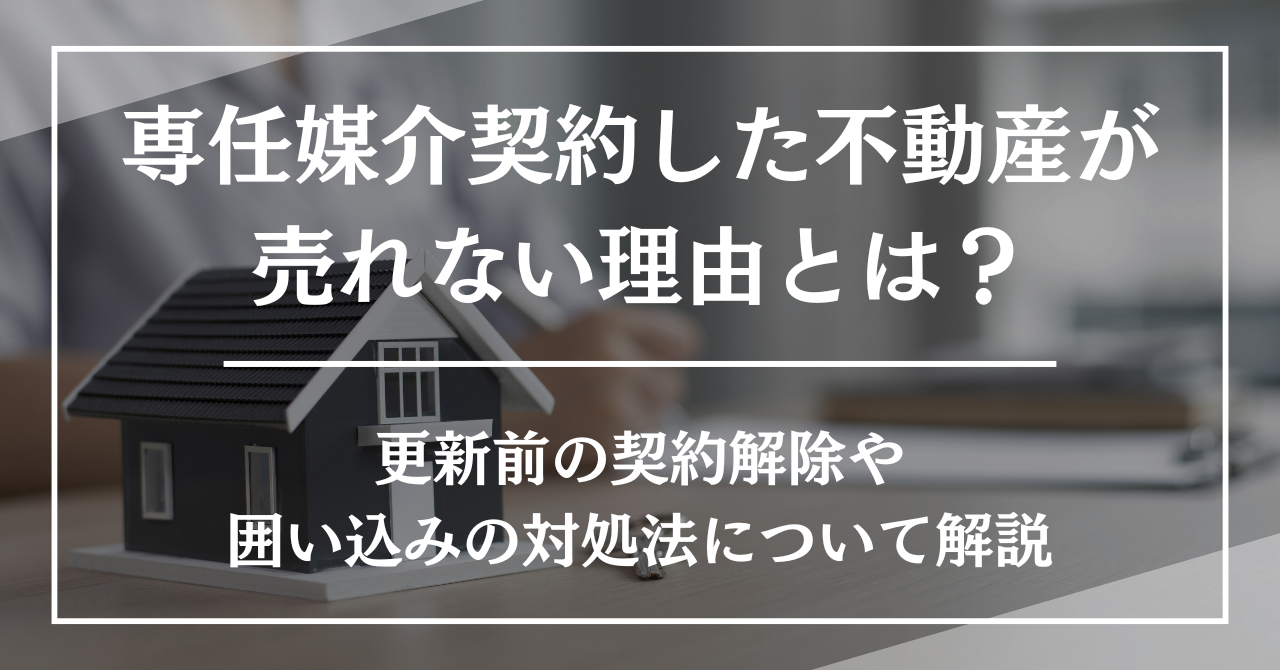※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「専任媒介で契約したのに全然売れない…?」
「担当営業が動いてくれない気がする…?」
「囲い込みって本当にあるの…?」
このような悩みを抱える売主様は少なくありません。
実は、専任媒介契約には「売れにくくなる落とし穴」が潜んでいることをご存じでしょうか。
契約更新や価格設定で迷う方も多いです。
そこで本記事では、専任媒介契約した不動産が売れない理由を宅建士の視点で徹底解説します。
また、契約解除や囲い込みへの対処法についても紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
専任媒介契約の特徴
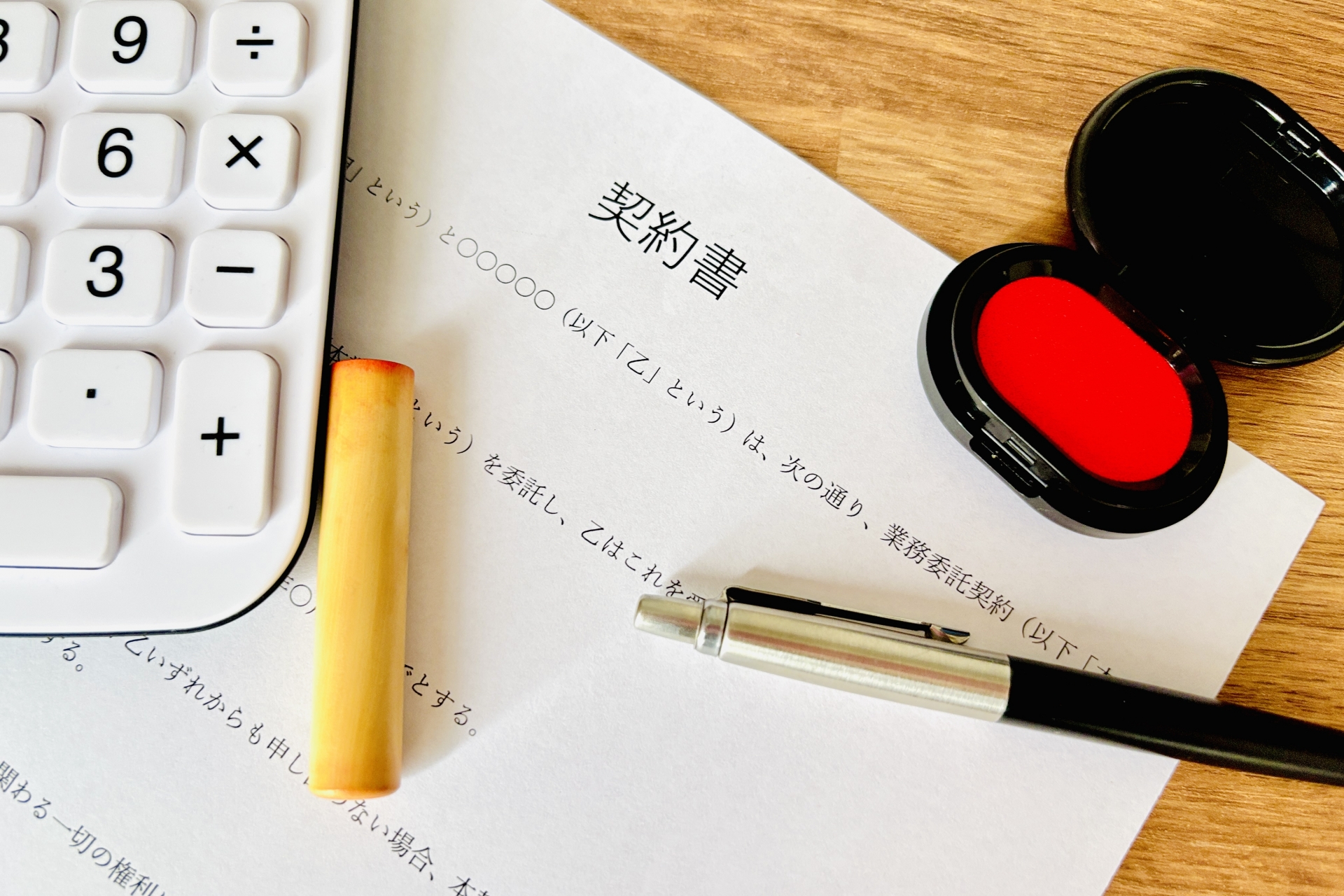
専任媒介契約とは、売却を1社の不動産会社に任せる契約形態のことです。
売主自身が見つけた買主とは直接取引できる自由が残されていますが、他社には重ねて依頼できません。
専任媒介契約を結ぶと、不動産会社は契約から7日以内に物件情報をレインズ(不動産流通標準情報システム)に登録しなければなりません。
また、14日に1回以上の頻度で売主に販売活動の進捗状況を報告する義務も課されています。
たとえば、「今週は○件の問い合わせがありました」といった報告書が届きます。
このように専任媒介契約は、販売窓口を一本化しながらも、売主の権利がしっかり守られる仕組みです。
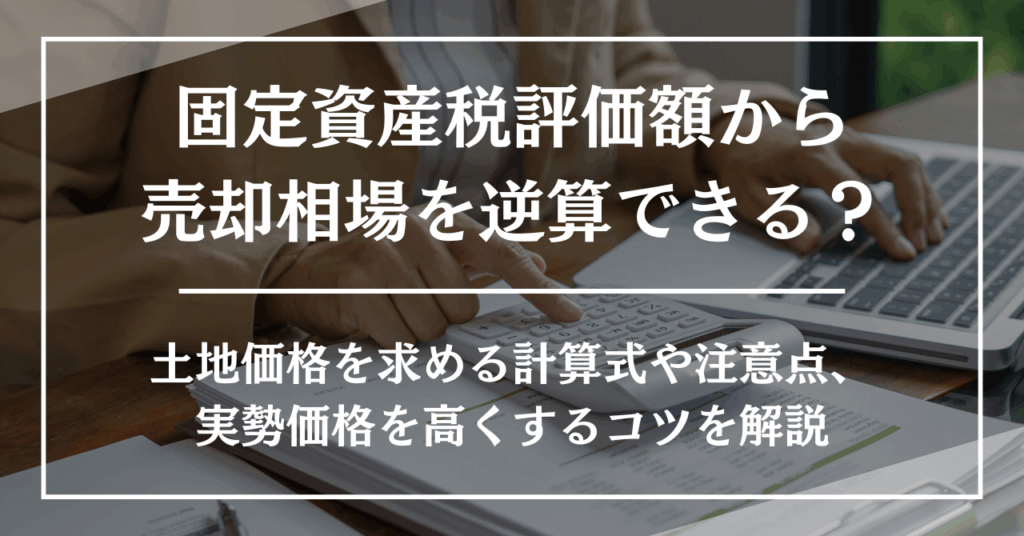
専任媒介契約した不動産が売れない理由

専任媒介契約を結んだのに物件が売れない背景には、いくつかの原因が考えられます。
不動産会社による囲い込み、相場から乖離した価格設定、広告・販売活動の不足、そして営業担当者の提案力不足などが主な要因です。
それぞれの問題点を理解することで、適切な対処法が見えてきます。
1.不動産会社が囲い込みをしている
囲い込みとは、売主と買主の両方から仲介手数料を得る「両手仲介」を狙って、他社に物件情報を提供しない行為です。
レインズには登録していても、他社からの問い合わせに「商談中です」と虚偽の回答をして紹介を断るケースがその代表例と言えます。
また、レインズの「取引状況」が契約後も「公開中」のまま変化しない、他社からの問い合わせが一切ない、担当者が「ネット広告は控えましょう」と提案してくるといった兆候があります。
囲い込みがあると、他社が優良な買主候補を抱えていても、その情報が売主に届かないため、本来なら早期に売れたはずの物件が何ヶ月も売れ残る事態を招くのです。
複数の不動産会社に確認すると、囲い込みの実態が明らかになることもあります。
▼まずは無料の訪問査定を利用して、現在の適正価格や販売戦略を確認してみてください。
![]()
2.売り出し価格が相場と乖離している
そもそも売り出し価格が周辺の類似物件と比べて高すぎると、買主の検討対象から外されてしまいます。
インターネットが普及して以降、買主は複数の物件を比較するため、明らかに割高な物件は内覧すらしません。
また、売主の希望を優先するあまり、市場相場を無視した査定を行う会社も存在します。
具体的には、契約を取りたいために最初は高値査定を提示し、後から「売れないので値下げしましょう」と提案する悪質なケースです。
とくに値下げの余地を残さない強気の価格設定は、市場で硬直化して長期間売れ残る原因になります。
3.担当者が広告・販売活動をおろそかにしている
専任媒介契約を結んでいるのに、担当者が積極的な広告活動を行っていないケースがあります。
たとえば、ポータルサイトでの掲載順位が常に下位、写真が暗くて枚数も少ない、間取り図が不鮮明、折込チラシを数ヶ月に1回程度しか出していないなどです。
また、販売力の弱い会社では、最低限のレインズ登録だけを行い、それ以外の宣伝活動をほとんど行わない傾向があります。
とくに専任媒介契約では他社に依頼できないため、担当者の積極性が売却成果に直結します。
売主から催促されて初めて広告を出すような受け身の姿勢では、本来売れるはずの不動産も売れません。
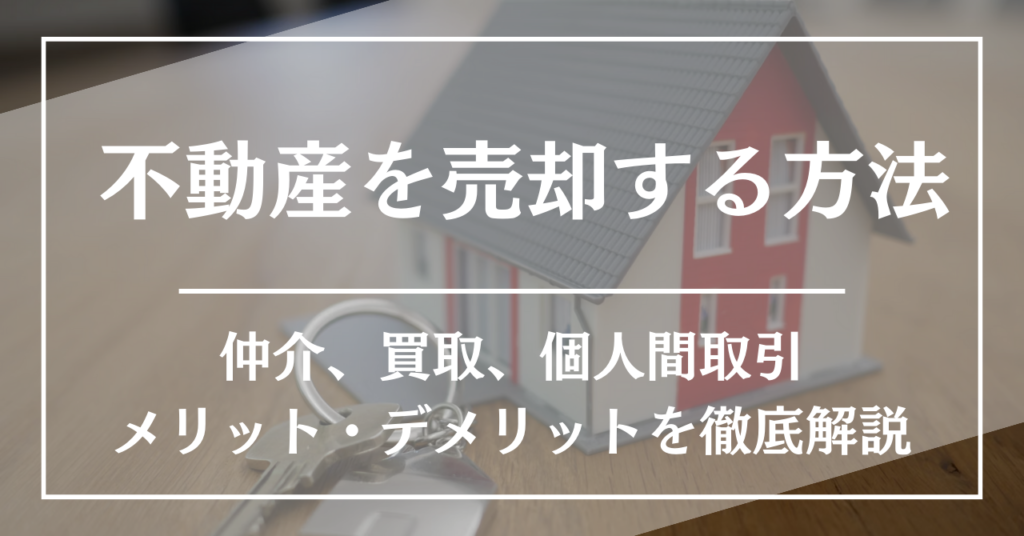
4.購入希望者に魅力を伝える営業活動ができていない
担当者が物件の魅力を効果的に伝えられず、間取りの活用提案やリフォーム後のイメージ提示もできていなければ、買主の購買意欲は高まりません。
不動産営業には、単に物件を案内するだけでなく、買主のライフスタイルに合わせた提案力が必要です。
しかし、専任媒介契約を結んでいても、担当者の営業スキルには大きな差があります。
たとえば、資金計画を示せない、周辺環境のメリットを説明できない、競合物件との差別化ポイントを打ち出せないといった問題があると、成約に結びつきません。
このように営業の質の低さが売却を長期化させている可能性があります。
▼信頼できる担当者に任せるためにも、まずは複数社の査定を比較して、提案内容や対応力を見極めるのがおすすめです。
![]()
専任媒介契約で不動産が売れないときの次の選択肢

物件が売れない状況が続く場合、売主にはいくつかの選択肢があります。
契約更新して販売期間を延ばす方法、他社に切り替える方法、一般媒介契約への変更、さらには契約期間中の途中解約など、状況に応じた対応を検討しましょう。
1.契約更新して販売期間を延ばす
専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月ですが、期間満了時に双方が合意すれば更新できます。
更新によってさらに売却活動を継続する期間を確保でき、新たな販売戦略を試すチャンスとして有効です。
たとえば、「広告の出し方を変える」「価格を見直す」「内覧の案内方法を改善する」といった新戦略を盛り込みます。
更新時には担当者と改めて話し合い、何が問題だったのかをしっかり分析しましょう。
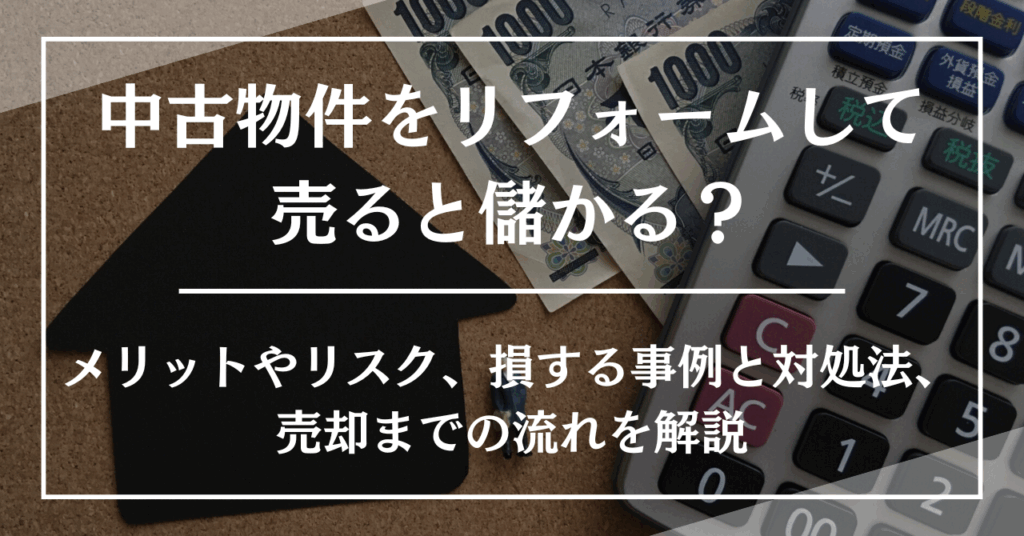
2.他社で新たに媒介契約を結ぶ
契約期間が満了すれば、売主は自由に別の不動産会社と新たに媒介契約を結べます。
不動産会社にはそれぞれ得意なエリアや物件タイプがあります。
最初に依頼した会社が必ずしも最適とは限らないため、複数社に査定を依頼して比較検討することが大切です。
とくに地域密着型の会社は、その地域特有の顧客ネットワークを持っているため、大手で売れなかった物件が地元業者で成約するケースも珍しくありません。
最初に契約した不動産会社に不信感がある、担当者が信用できないなどの問題があるときは、積極的に他社切り替えを検討しましょう。
3.一般媒介契約に切り替える
一般媒介契約とは、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約形態です。
専任媒介から切り替えることで、複数の業者が競争して販売活動を行うため、露出機会が増加します。
また、囲い込みのリスクを回避できる点も大きなメリットです。
一方で、レインズ登録義務や定期報告義務がないため、各社の活動状況を売主自身が管理する必要があります。
また、最終的に買主を見つけた会社が仲介手数料を得る仕組みなので、本腰を入れて販売活動をする不動産業者は決して多くはありません。
一般媒介契約への切り替えは、依頼している不動産会社に囲い込みの疑いがある場合の対処法として活用しましょう。
4.契約期間中に途中解約を申し出る
宅地建物取引業法では、不動産会社の不正行為や義務違反に対して、売主が契約を解除できる権利が認められています。
囲い込みが判明した場合、レインズ登録や定期報告を怠っている場合、虚偽の説明をした場合などは、解除の正当な理由となります。
また、過度な違約金請求は法律で制限されています。
途中解約を申し出る場合は、書面で契約解除を通知することが効果的です。
さらに販売活動が行われていない場合に催促した上で解除する、査定時の説明と実際の対応が大きく異なり虚偽があったと判断して即時解除するといった対応があります。
こうしたトラブルを避けるためにも、最初の段階で複数社の対応や誠実さを比較することが重要です。
▼まずは無料の一括査定サービスを利用して、信頼できる会社を見極めておくことを強くおすすめします。
![]()
専任媒介契約で物件が売れない不動産会社の見極め方

不動産会社選びを間違えると、売却は長期化してしまいます。
査定価格の根拠説明、担当者の誠実さ、具体的な販売戦略の有無、法令遵守の姿勢、そして地域での実績など、複数の観点から会社を見極めましょう。
1.査定価格の根拠を説明してくれているか
信頼できる不動産会社は、査定価格の根拠を明確に説明してくれます。
たとえば、直近6ヶ月以内の類似物件成約事例を3〜5件提示してくれる、平米単価や坪単価の根拠を周辺相場データとともに開示する、築年数・方角・階数などの条件による価格補正を具体的に説明するといった対応があれば信頼できます。
一方で、査定価格の根拠が不透明な会社は、契約を取るために高値を提示している可能性があります。
「このあたりは人気エリアなので高く売れます」といった曖昧な説明だけで済ませる業者は要注意です。
複数社に査定を依頼して価格の整合性を確認し、最も説得力のある説明をしてくれる会社を選びましょう。
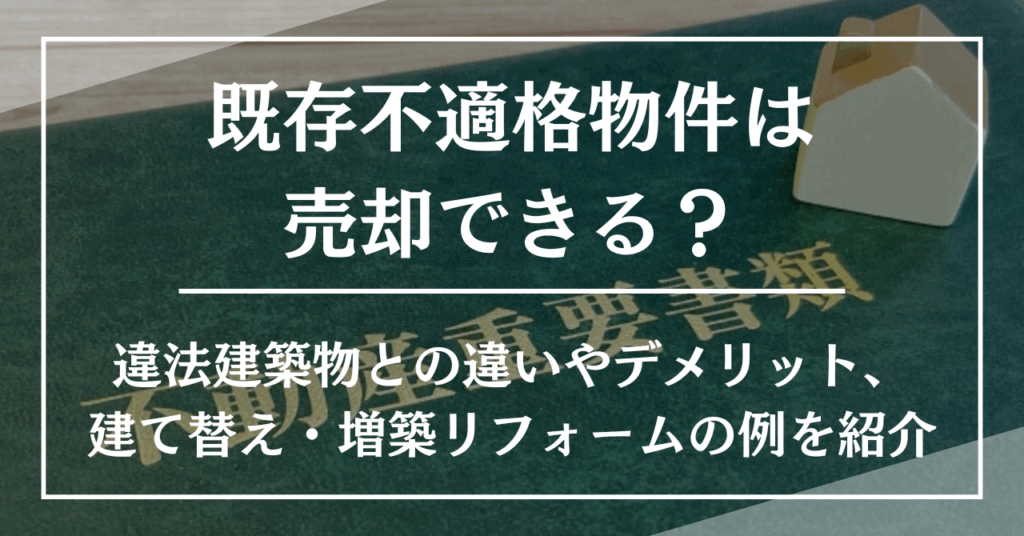
2.担当者が誠実で信頼できるか
不動産売却は数ヶ月にわたる取引になるため、担当者との信頼関係が非常に重要です。
連絡への返信が迅速か、質問に対して正直に回答してくれるか、売主に対して誠意ある対応をしているかといった点をチェックしましょう。
誠実性に欠ける担当者は、囲い込みや販売活動の手抜きを行うリスクが高まります。
都合の悪い質問をはぐらかす、約束した連絡を忘れる、売主の不安に寄り添わないといった態度が見られる場合は要注意です。
3.しっかりとした販売戦略があるか
優良な不動産会社は、契約前に具体的な販売戦略を提示してくれます。
どの媒体にどのように広告を出すか、ターゲットとする買主層はどこか、オンラインとオフラインをどう組み合わせるかといった計画が明確です。
一方で、販売戦略が曖昧な会社では、場当たり的な活動になりがちで効果が上がりません。
「とりあえずレインズに載せて様子を見ましょう」といった消極的な姿勢では、競合物件との差別化ができず埋もれてしまいます。
内覧希望者を増やすためのイベントを開催している、魅力的な写真・動画素材の準備といった具体的なアクションプランを持っている会社で媒介契約を結ぶことが効果的です。
4.会社が法律や法令を遵守しているか
媒介契約書に法律で定められた事項がきちんと記載されているか、売主に不利な特約を強制していないかを確認することが大切です。
悪質な不動産会社は、法律の抜け穴を利用して売主に不利な条件を押し付けることがあります。
たとえば、過大な違約金条項を設ける、レインズ登録や報告義務を曖昧にする、契約解除の条件を極端に厳しくするといった事例です。
こうした会社と契約すると、不動産のスムーズな売却が不可能なだけではなく、後々トラブルに発展するリスクが高まるため、法令を適正に守る会社で安心して取引を進めるようにしましょう。
5.そのエリアでの販売実績は豊富か
地域に精通している会社は、その地域特有の市場動向や買主のニーズを把握しているため、適切な価格設定や効果的な販売戦略を立てられます。
たとえば、過去の成約事例を地図上で示してくれる、同じマンションや近隣エリアでの売却成功事例を具体的に紹介してくれる、その地域の市場動向をまとめたマーケットレポートを持参してくれるといった対応があれば、信頼性が高いといえます。
一方で、地域事情を理解していない会社に依頼すると、的外れな価格設定や効果のない広告戦略になってしまいます。
買主候補のネットワークも弱く、売却に時間がかかる傾向があります。
地域の事情を理解した会社を選ぶには、複数社を比較して実績や提案力を見極めることが欠かせません。
▼まずは無料の一括査定サービスを活用して、あなたのエリアに強い不動産会社を効率よく選びましょう。
![]()
専任媒介契約を契約延長して「売れる物件」にする対処法

売却活動がうまく進まない場合でも、適切な対処法を取ることで状況を改善できます。
広告や販売活動の見直し、マッチングサイトの活用、内覧者からのフィードバック反映、そして価格の引き下げなど、複数のアプローチを組み合わせることを検討しましょう。
1.広告・販売活動を見直す
物件が売れない場合、宣伝活動の見直しによって、反響数が大きく改善する可能性があります。
掲載している媒体や物件の説明文を刷新し、写真や間取り図などのビジュアル要素を改善することで、買主の関心を引きやすくなります。
また、ポータルサイトの室内写真をプロカメラマンによる明るい写真に差し替える、360度パノラマ写真や動画・VR内覧システムを導入するといった対策は効果的です。
必要に応じてプロモーション予算を追加し、露出を増やすことも検討すべきです。
とくにオンラインでの物件検索が主流の現在、ポータルサイトでの露出強化は検索流入の増加に直結します。
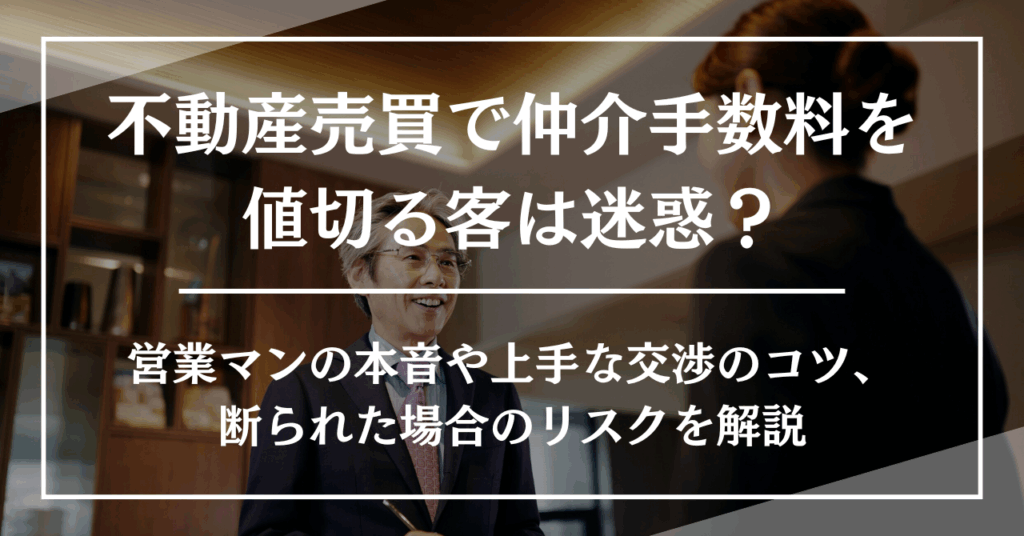
2.マッチングサイトを活用する
不動産会社が持つ独自の顧客データベースやマッチングシステムを活用することで、購入希望者との接点を増やせます。
たとえば、大手不動産会社では、過去の来店客や問い合わせ客の情報を蓄積しており、条件に合う買主候補に直接アプローチできます。また、SNSを活用した物件広告も認知拡大に有効です。
さらに、AIを活用したマッチングサービスの精度は年々向上しており、購入希望者の条件と物件の特性を自動的に照合してくれます。
こうしたシステムを導入している不動産会社に切り替えることも視野に入れて、販売活動を見直しましょう。
3.内覧時のフィードバックを活かす
内覧に来た購入希望者からのコメントや意見を集約・分析することが重要です。
買主視点での率直な感想には、物件の改善ポイントが隠れています。とくに競合物件が多いエリアでは、小さな改善の積み重ねが成約の決め手になることも少なくありません。
たとえば「壁紙が古い」「照明が暗い」といった指摘があれば、低コストで改善できる部分から手を付けることで、次の内覧者への印象が大きく変わります。
買主の意見を真摯に受け止め、改善サイクルを回していくことで、物件の評価が徐々に向上していきます。
4.売り出し価格を引き下げる
市場の反応を見て、売り出し価格の引き下げを検討することも有効な対策です。
買主は常に複数の物件を比較しているため、相場より高い物件は選択肢から外されてしまいます。
たとえば、4,980万円を4,500万円のようなキリの良い価格に設定して心理的なハードルを下げる、「期間限定プライスダウン」として一定期間の特別価格を設定するといった方法が効果的です。
数パーセントの価格調整だけでも、購入検討者の増加につながることがあります。
一方で、売れ残り期間が長くなると「何か問題がある物件では」という印象を持たれるため、早めの価格見直しが重要です。
また、価格調整を検討する際も、複数の不動産会社の査定を比較すると、適正価格の判断がしやすくなります。
▼まずは一括査定を活用して、信頼できる会社から妥当な価格提案を受けておきましょう。
![]()
不動産会社を見極めることがスムーズな売却への第一歩!

不動産の売却は、媒介契約を結ぶ会社選びで大きく左右されます。
信頼性、実績。販売戦略の3つを重視して慎重に選定することが重要です。
もし契約後に不透明な対応や販売活動の停滞が見られた場合は、契約更新を見送る、他社への変更を検討する、あるいは正当な理由があれば契約解除も選択肢に入れるべきです。
囲い込みや価格設定のミスは、不動産会社の能力差から生じる問題です。
売主自身が契約後も定期的に進捗状況をチェックして問題があれば早期に対処するといった姿勢が大切です。