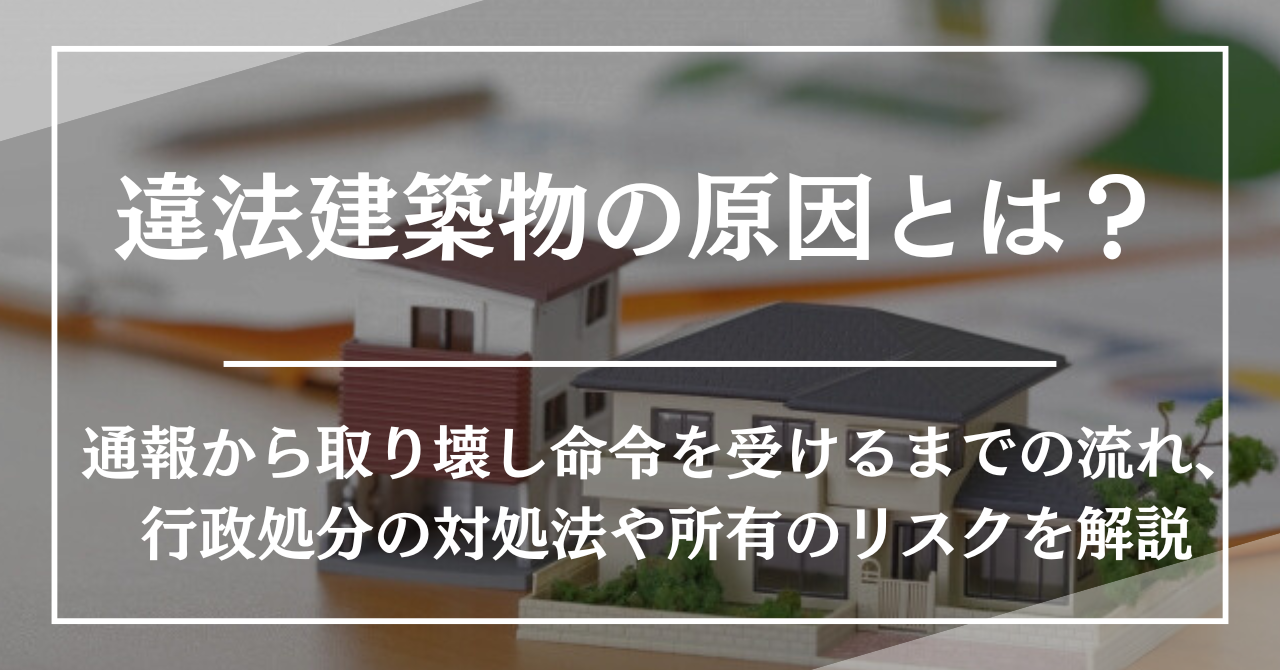※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「違法建築物に時効はある?」
「違法建築物は取り壊し命令を受ける?」
「違法建築物をそのまま所有しておくリスクは?」
建築基準法やその他の法令に違反して建てられた建物のことを違法建築物と呼びます。
たとえば、建ぺい率や容積率を超過していたり、無許可で増改築を行ったりなどが原因です。
違法建築物は、資産価値の大幅な低下だけではなく、罰金や是正命令の対象となる可能性があります。
そこで本記事では、違法建築物が生まれる原因や発覚理由について触れたのちに、行政から取り壊し命令を受けるまでの流れを解説します。
また、取り壊されないためにできる対処法やそのまま所有するリスクについても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
違法建築物が生まれる原因とは?

違法建築物が生まれる背景には、建築のルールが守られていないという共通点があります。
なぜそうした建物が存在してしまうのか。その主な原因は、大きく分けて以下の3つです。
1.悪質な施工業者が建築確認申請を行わなかった
2.施工業者が完了検査を受けていなかった
3.検査後に違法な増改築をした
それぞれの原因について、具体的に解説していきます。
1.悪質な施工業者が建築確認申請を行わなかった
建築確認申請がされていない建物は、最初から違法建築となります。
建築確認申請とは、「この場所に、このような建物を建てても法律的に問題ありません」と役所などに事前に確認してもらう手続きです。
これは、建築基準法という法律で義務付けられていますが、一部の悪質な施工業者は、コスト削減や工期短縮などの理由から、この建築確認を無視して工事を進めてしまいます。
たとえば、山間部で格安の戸建て住宅を販売していた業者が、実は建築確認を行っておらず、後から発覚して住民が立ち退きを迫られるというケースが報道されたこともあります。
確認を受けずに建ててしまうと、見た目は普通の家でも法律上は「違法建築」となり、後々重大なトラブルに発展します。
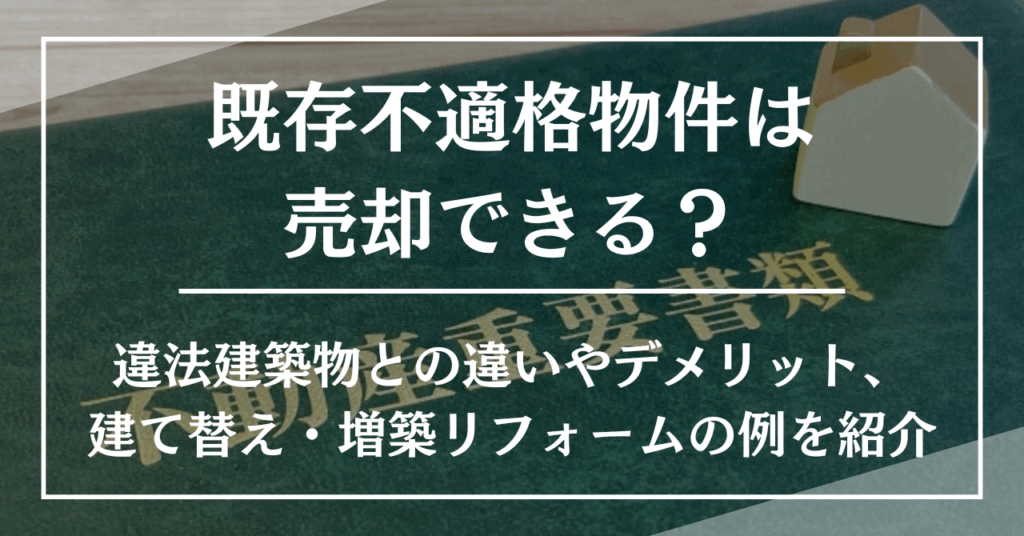
2.施工業者が完了検査を受けていなかった
建築確認申請をしても、最後に「完了検査」を受けなければ、建物は正式に認められません。
完了検査とは、「建築計画どおりに工事が終わったかどうか」をチェックするものです。
しかし中には、この完了検査を受けずに引き渡しまで済ませてしまうケースがあります。
実際に、中古住宅を購入した後、「検査済証が出ていない=完了検査を受けていない」ことが発覚し、住宅ローンの審査に通らなかったというトラブルもあります。
これは施工ミスや計画と違う造りを隠すためである場合が多く、悪質です。
3.検査後に違法な増改築をした
完了検査を通っていても、その後に違法な増改築を行えば、建物は違法建築物になります。
たとえば、「建てたあとに勝手に2階を増築した」「ベランダを部屋に変えた」といった変更を、役所に届け出ることなく実施した場合は違法です。
建築基準法では、建物の構造や使い方を大きく変えるときには、原則として「再び確認申請を行う」必要があります。
これを怠ると、最初は合法でも、増改築のせいで全体が違法建築になってしまうので注意しましょう。
このように完了検査を通過しても、その後の違法な増改築によって建物の法的ステータスが変わることがあります。
▼売却を検討するなら、複数の不動産会社に一括で訪問査定を依頼して、専門家に適正価格や売却戦略を確認するのがおすすめです。
![]()
違法建築物はどのように発覚する?

違法建築は、建てた本人が黙っていれば見つからないように思われがちですが、実は以下のようなきっかけで発覚することがあります。
1.近隣住民からの通報が一般的
2.災害時などの自治体の巡回調査
3.建築確認済証や検査済証を確認する
それぞれ解説します。
1.近隣住民からの通報が一般的
違法建築の発覚で最も多いのが、近隣住民からの通報です。
騒音や日照問題、防火面の不安など、周辺環境に影響が出ると住民が自治体へ通報します。
その際、建築確認や用途に違反がないか調査され、違法が見つかることがあります。
特に増築や改築を無許可で行うと、見た目の変化から気付かれやすくなります。
身近なトラブルがきっかけで、違法建築と判明することが少なくありません。
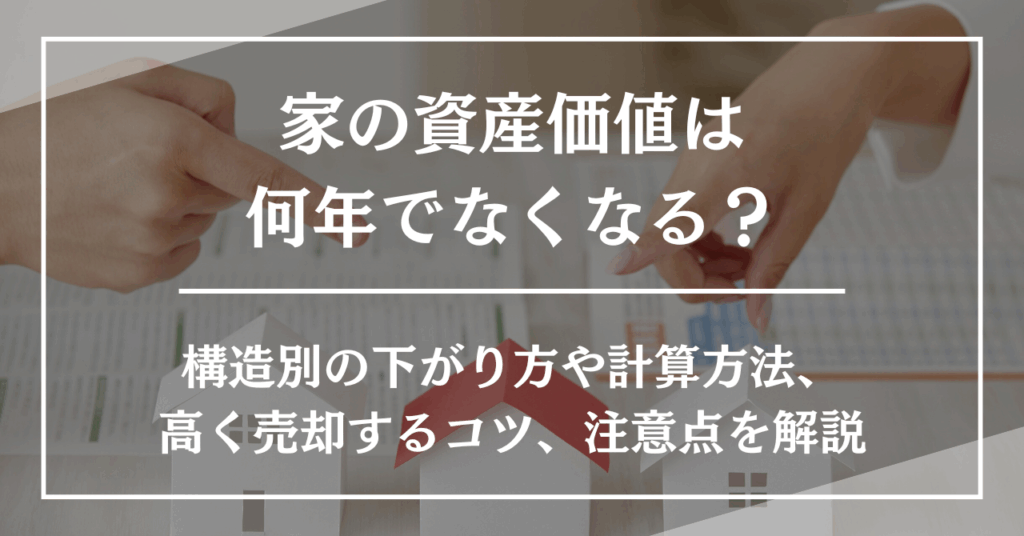
2.災害時などの自治体の巡回調査
地震や火災の後など、災害時に行われる自治体の巡回調査で違法建築が見つかるケースもあります。
自治体は建物の安全性を確認するために現場を調査します。
その際、建築基準法に違反する構造や増改築が明るみに出ることがあります。
特に老朽化が進んだ建物は調査対象になりやすく、違法建築のリスクが高いと判断されると指導や是正命令が出ることもあります。
3.建築確認済証や検査済証を確認する
相続や引っ越しが原因で不動産の売買やリフォームをするときに、建築確認済証や検査済証の有無を確認する中で違法が発覚することもあります。
これらの書類は、建築基準法に則って建てられたことを示す正式な証明です。
買主や金融機関、施工会社が確認した際に「書類がない」「内容が実際と違う」となると、違法建築の可能性が浮上します。
書類の不備が、不動産取引や工事の中断につながるケースもあるため、非常に重要です。
また、建築確認済証や検査済証の有無は、売却やリフォームの際に重要な判断材料となります。
不備や内容の相違があると、取引や工事がスムーズに進まないリスクもあるため、専門家による現地確認が安心です。
▼複数の不動産会社に一括で訪問査定を依頼できるサービスなら、物件の状態や適正価格を正確に把握でき、売却準備を効率よく進められます。
![]()
違法建築物が取り壊し命令を受けるまでの流れ

違法建築が発覚したからといって、すぐに取り壊し命令が下るわけではありません。
行政は段階的な対応を取るため、状況に応じた是正のチャンスがあります。
1.自治体が現地調査を実施する
2.違法建築が認定されると是正指導や勧告がある
3.勧告に従わないと行政命令が下る
4.取り壊し命令が下る
5.命令に従わないと行政代執行で強制撤去
ステップごとに詳しく解説します。
1.自治体が現地調査を実施する
通報や定期点検などで違反の疑いが生じると、自治体が現地に赴いて調査を行います。
職員が建物の構造や使用状況、建築確認書類との整合性を確認し、写真や図面と照合します。
場合によっては内部まで立ち入り調査が実施されることもあります。
この時点で嘘の説明やごまかしをすると、後の行政対応が厳しくなる可能性があるため、誠実な対応が求められます。
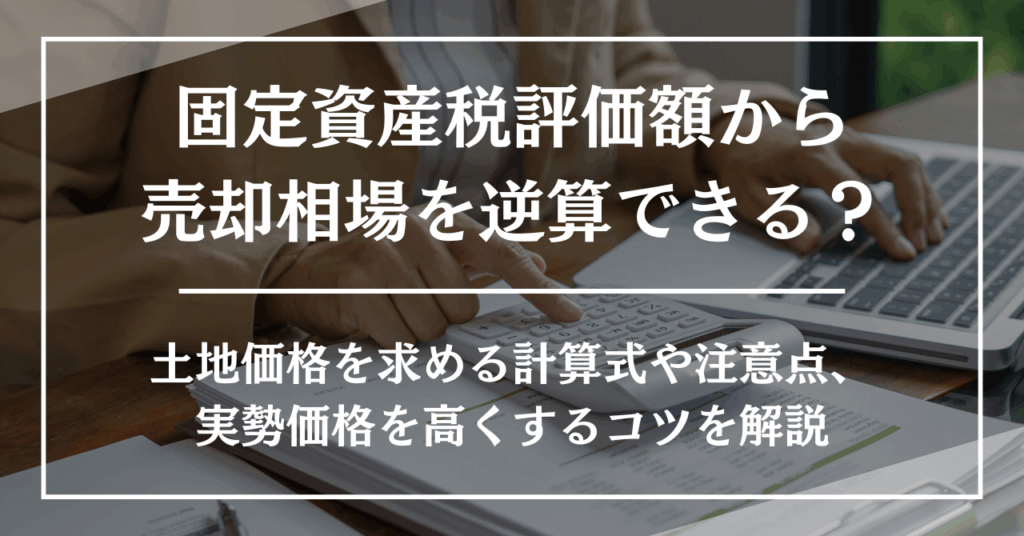
2.違法建築が認定されると是正指導や勧告がある
調査の結果、違反が明確になると、まずは是正指導や勧告という「警告段階」に入ります。
この段階では、違法部分の撤去や用途変更など、改善措置を取れば重大な処分を回避できる可能性があります。
たとえば、無許可のベランダを取り壊すだけで済むこともあります。
自治体も最初から厳罰を望んでいるわけではないため、早期の対応が重要です。
3.勧告に従わないと行政命令が下る
勧告を無視、もしくは改善の意思を示さない場合、次に「是正命令」などの行政命令が正式に出されます。
ここからは法律に基づく強制力を持つ段階に移行します。
「〇日までに違反部分を撤去すること」といった期限付きの命令書が送達され、従わないとさらに重い処分が科されます。
「様子見」は命取りです。命令が出る前に動くことが最も重要です。
4.取り壊し命令が下る
是正命令にも従わなければ、次はいよいよ「取り壊し命令」が下されます。
これは、違法建築物の全部または一部を自費で解体するよう求める強制措置です。
命令に従えば、自分で工事業者を選んで対応できますが、解体費用は高額になりがちです。
特に都市部では足場の設置や騒音対策も必要になり、数百万円単位の負担となることも珍しくありません。
取り壊し命令が下る前に、修繕や是正工事で解決できるケースも多いため、まずは専門業者に工事内容と費用を確認しておくことが重要です。
▼複数のリフォーム会社へ無料で一括見積もりを依頼できるサービスなら、必要な工事の内容や相場を早い段階で把握でき、無駄なコストを避けることにもつながります。
![]()
5.命令に従わないと行政代執行で強制撤去
取り壊し命令にも応じない場合、最終手段として「行政代執行」が行われます。
これは自治体が業者を手配し、強制的に建物を解体する措置で、費用は所有者に全額請求されます。
支払いを拒否すれば、財産の差し押さえや訴訟にも発展します。
加えて「行政処分歴」が残るため、将来的な不動産売却や融資にも悪影響が及ぶ可能性があります。
違法建築物を取り壊さないための対処法

違法建築物と判定されても、すぐに取り壊す必要があるとは限りません。
状況に応じて、合法的に建物を残すための対処法があります。
1.一級建築士に相談する
2.是正命令に対応するためにリフォームする
3.専門の不動産買取業者に売却する
ここからは、それぞれの対処法について解説します。
1.一級建築士に相談する
まず最初にすべきは、一級建築士などの建築専門家に相談することです。
一級建築士は、建築基準法や条例の構造・用途規定に精通しており、違法とされている部分を合法に戻すためのアドバイスをくれる可能性があります。
たとえば、「ほんの数センチの建ぺい率オーバーなら、緩和措置で合法化できる」ケースもあります。
自分だけで判断せず、専門的な視点から道筋をつけることが重要です。
2.是正命令に対応するためにリフォームする
違法な部分だけをリフォーム・修繕することで、取り壊しを免れるケースもあります。
たとえば、無許可で増築した部分を撤去し、元の構造に戻すことで、建物全体が合法扱いに戻ることがあります。
構造補強や用途変更なども、行政が求める内容に沿って計画を立てれば認められる場合があります。
費用はかかりますが、建物全体を失うよりは遥かに現実的な選択肢です。
是正命令への対応には、どの部分をどの程度修繕すべきかを専門家に見てもらうことが欠かせません。
▼複数のリフォーム会社に無料で一括見積もりを依頼できるサービスを利用すれば、必要な工事内容と費用感を早く把握できます。
![]()
3.専門の不動産買取業者に売却する
もし是正が困難であれば、違法建築物でも買取対象とする専門業者に売却する方法もあります。
一般の仲介業者では扱ってもらえない違法物件でも、再建築不可やワケあり物件に特化した買取業者であれば相談可能です。
売却額は安くなりますが、行政処分を受ける前に手放すことで、将来的なリスクや撤去費用を避けられます。
実家が知らず知らずのうちに違法建築となってしまった場合、「手放す」ことも冷静で前向きな判断と言えるでしょう。
違法建築の是正が難しく「売却」を選ぶ場合は、まず専門家による訪問査定で現在の価値を把握することが重要です。
▼通常では扱われにくい不動産でも、まずは無料査定で現状の価値を確認できます。
![]()
違法建築物を所有するリスク

違法建築物は単なる「建築ルール違反」にとどまらず、所有者に多くのリスクをもたらします。
1.違法建築に時効はない
2.住人・近隣住民の安全性に懸念がある
3.新たな増改築や用途変更が許可されない
4.次の買主が住宅ローン融資を受けられない
5.売却が難しく買い叩かれる可能性がある
それぞれのリスクについて詳しく解説します。
1.違法建築に時効はない
違法建築には「〇年経てば合法になる」といった時効は存在しません。
何十年経っていても、違法性が確認されれば是正命令や取り壊し命令が下されます。
特に、過去の法改正や登記ミスで見過ごされていた場合も、自治体の再調査で突然問題化することもあります。
「昔からあるから大丈夫」という油断が、最も大きな落とし穴になります。
2.住人・近隣住民の安全性に懸念がある
違法建築は耐震性・防火性など、安全面で基準を満たしていない可能性が高くなります。
たとえば、無許可の3階建てや木造の違法増築部分は、地震や火災時に崩壊や延焼の危険があります。
住人だけでなく、隣家にも被害が及ぶリスクがあるため、万が一の事故では所有者責任を問われることもあるでしょう。
見えないところで命に関わる問題を抱えているのが、違法建築の怖さです。
3.新たな増改築や用途変更が許可されない
一度違法と認定されると、役所からの建築許可が下りなくなることがあります。
たとえば、2階部分をリフォームしたくても、1階に違法な増築がある限り、申請そのものが却下される可能性があります。
また、住宅から事務所などへの用途変更も制限される場合があります。
「将来こうしたい」が叶わなくなるのも、見落としがちな大きなリスクです。
4.次の買主が住宅ローン融資を受けられない
違法建築物は金融機関からの評価が極端に低く、住宅ローン審査に通らない可能性が高いです。
購入希望者がローンを利用できないと、現金一括購入が前提となり、買い手の幅が大きく狭まります。
結果として売却期間が長期化し、資産価値が著しく下がる原因になります。
「売ろうと思っても売れない」現実が、違法建築の深刻な経済的リスクです。
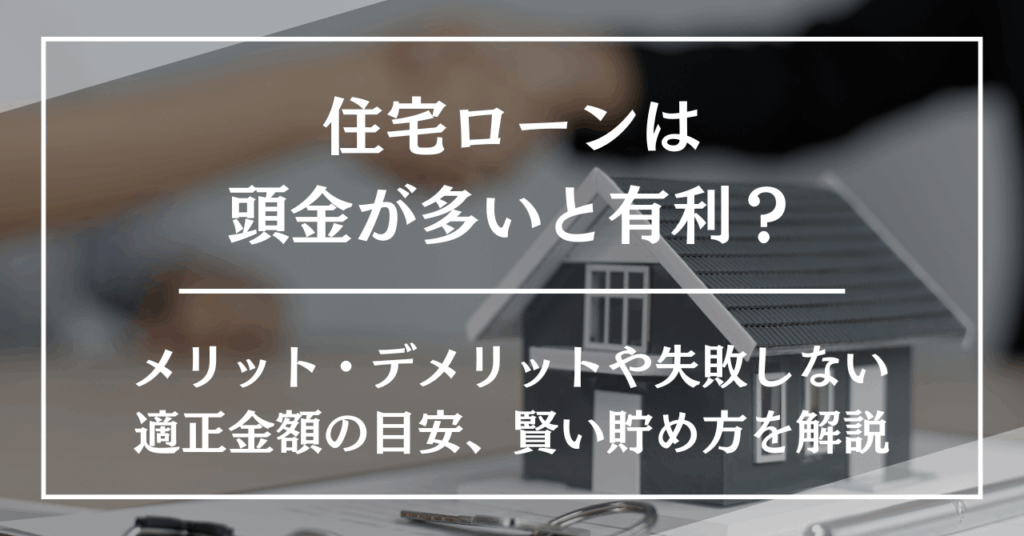
5.売却が難しく買い叩かれる可能性がある
仮に売却できたとしても、違法建築物はリスクを理由に大幅に買い叩かれることが一般的です。
通常の市場価格の半値以下でしか売れないこともあり、不動産としての資産価値は著しく低下します。
しかも、後から違法性が発覚した場合、買主から損害賠償を請求されるリスクもあります。
「売れたら終わり」では済まされないのが、違法物件の厄介なところです。
違法性が影響し「買い叩かれる」リスクを避けたい場合は、訳あり物件を専門に扱う買取サービスへ相談するのが近道です。
▼通常では扱われにくい不動産でも、まずは無料査定で現状の価値を確認できます。
![]()
実家が違法建築物だとわかったら専門家に相談を!

もし実家が違法建築かもしれないと感じたら、まずは一人で悩まず専門家に相談しましょう。
一級建築士や不動産に詳しい行政書士などに確認してもらうことで、合法化の可能性やリスク回避の道が見えてきます。
また、自治体の建築指導課も親身になって状況をヒアリングしてくれる可能性が高いです。
一方で、違法建築は放置すると、取り壊し命令や「なかなか売却できない」といった深刻な問題に発展しかねません。
迅速で真摯な対応を心がけましょう。