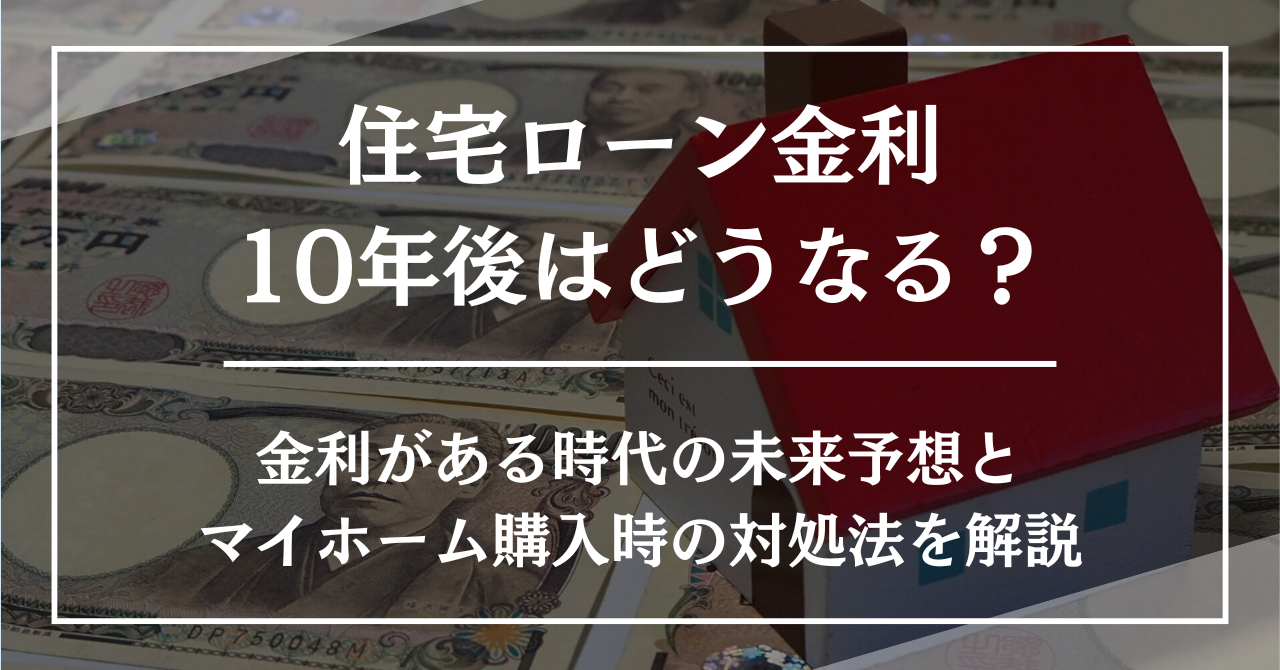※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net、楽天アフィリエイト含む)を掲載しています。
「住宅ローン金利は10年後にどうなる?」
「10年後の返済額はいくらに増える?」
「変動金利と固定金利の違いは?」
日本の住宅ローン金利は歴史的な低水準が続いていました。
2025年9月22日の債券市場では、10年物の国債の利回りがおよそ17年ぶりの高値水準1.665%まで上昇し、今後の金利動向が注目されています。
同じように将来の金利や返済計画に悩む方も多いでしょう。
そこで本記事では、住宅ローン金利10年後の未来予想を解説します。
また、金利上昇リスクへの備え方やローン選びのポイントも紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
参照:長期金利が一時1.665%、17年ぶり高水準 日銀利上げ観測で|日本経済新聞
住宅ローン金利の仕組み

住宅ローン金利の決定には、日本銀行の政策金利と市場金利が大きく影響します。
金利の仕組みを理解することで、今後の金利変動を予測し、適切な住宅ローン選択が可能です。
1.住宅ローン金利はどう決まる?
住宅ローン金利は政策金利と市場金利の組み合わせで決定されます。
日本銀行の金融政策と景気動向が金利水準に大きな影響を与えるため、これらの要素を理解することが重要です。
たとえば、政策金利が0.1%引き上げられると、住宅ローンの負担も増加する仕組みになっています。
現在の金利政策は物価安定を目指しており、今後の政策変更によって住宅ローン金利も連動して変化することが予想されます。
金利の変動に備えて、今の住宅ローンが最適かどうか見直してみませんか?
▼無料の一括比較サービス「モゲチェック」なら、わずか5分の入力で今より有利な条件の住宅ローンが見つかり、平均で約210万円もの削減に成功しています。
![]()
2.変動金利と固定金利の違いとは?
固定金利は返済期間中の金利が一定で返済額が安定する特徴があり、変動金利は市場金利の変動により低金利を享受できる可能性があります。
固定金利は長期金利に連動し、変動金利は短期の政策金利に連動する仕組みです。
2025年9月現在、変動金利は0.525~0.7%程度、固定金利は1.89~2.35%程度の水準で推移しています。
この金利差は約1.3%となっており、借入当初の負担軽減を重視するか、将来の金利上昇リスクを回避するかが選択のポイントです。
参照:9月の住宅ローン金利、大手4行が固定型引き上げ|日本経済新聞
3.日本の超低金利時代の歴史と背景とは?
バブル崩壊以降、日本の金利は継続的に低下し、マイナス金利政策の導入により史上最低水準の住宅金利が実現されました。
超低金利政策は経済の活性化と物価上昇を目指した金融政策の一つです。
2016年以降、フラット35の金利は1%前後で推移しており、多くの家庭にとって住宅購入の絶好の機会となりました。
しかし、この超低金利環境は永続的ではなく、経済情勢の変化に伴い金利水準も変動することを理解しておく必要があります。
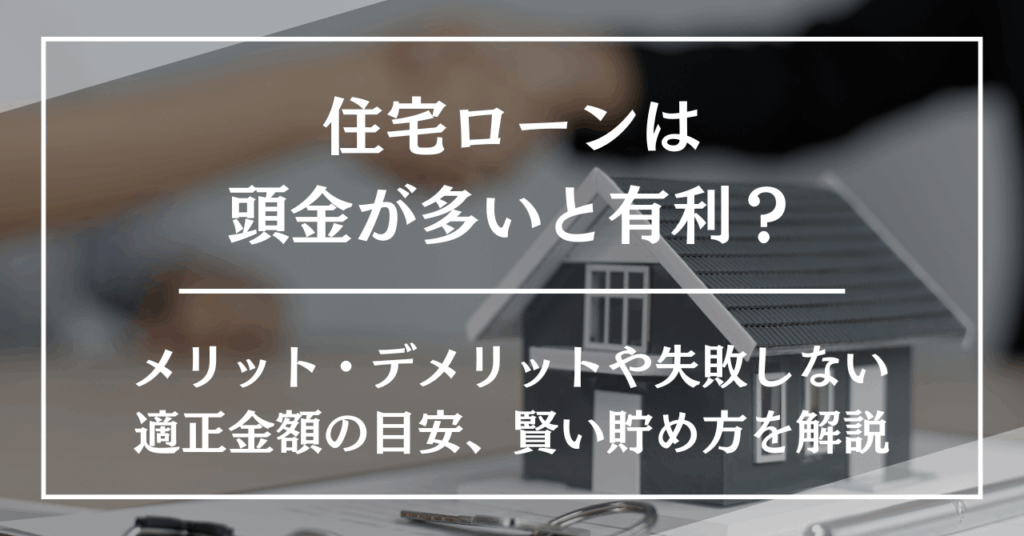
住宅ローン金利の過去10年間の推移

過去10年間の住宅ローン金利は、2013年以降の超低金利政策により安定して低水準を維持してきました。
とくに2016年のマイナス金利政策導入後は、変動金利・固定金利ともに歴史的な低水準で推移しています。
短期・長期プライムレート推移(2015〜2025)
| 年 | 短期プライム(%) | 長期プライム(%) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.05 | 1.30 |
| 2016 | 1.00 | 1.25 |
| 2017 | 0.95 | 1.20 |
| 2018 | 0.90 | 1.15 |
| 2019 | 0.85 | 1.10 |
| 2020 | 0.80 | 1.05 |
| 2021 | 0.85 | 1.10 |
| 2022 | 0.95 | 1.20 |
| 2023 | 1.10 | 1.35 |
| 2024 | 1.40 | 1.65 |
| 2025 | 1.90 | 2.10 |
注:上表は「説明用の具体例(画例)」です。公式の絶対値は日本銀行の該当ページから取得してください。
参照:長・短期プライムレート(主要行)の推移|日本銀行
2023年時点では変動金利が0.4%台、固定金利が1%前後で安定していましたが、直近では日本銀行のマイナス金利政策解除により、金利に上昇の兆しが見えています。
この10年間は住宅購入者にとって非常に有利な金利環境が続いており、多くの家庭が低負担で住宅ローンを組むことができました。
今の住宅ローン金利が相場通りの好条件なのか、金利上昇が予想される局面では見直しが有効です。
▼無料の一括比較サービス「モゲチェック」なら、わずか5分の入力で今より有利な条件の住宅ローンが見つかり、平均で約210万円もの削減に成功しています。
![]()
住宅ローン金利の10年後の未来予想

10年後の住宅ローン金利は、変動金利・固定金利ともに現在より上昇することが予想されますが、急激な上昇は考えにくく、比較的緩やかな推移が見込まれます。
ここからは向こう10年の住宅ローン金利について未来予想を紹介します。
1.変動金利は上昇するが低金利を維持する
変動金利は今後緩やかに上昇することが予想されますが、依然として歴史的には低金利水準を維持すると考えられます。
日本経済の回復が緩慢であることから、急激な利上げは実施しづらい環境にあります。
専門家の予測では、10年後でも変動金利は1.5~2.5%程度に収まると見られており、現在の0.5%程度から見ると上昇幅は1~2%程度にとどまる見通しです。
この程度の上昇であれば、適切な返済計画を立てることで十分対応可能な範囲といえるでしょう。
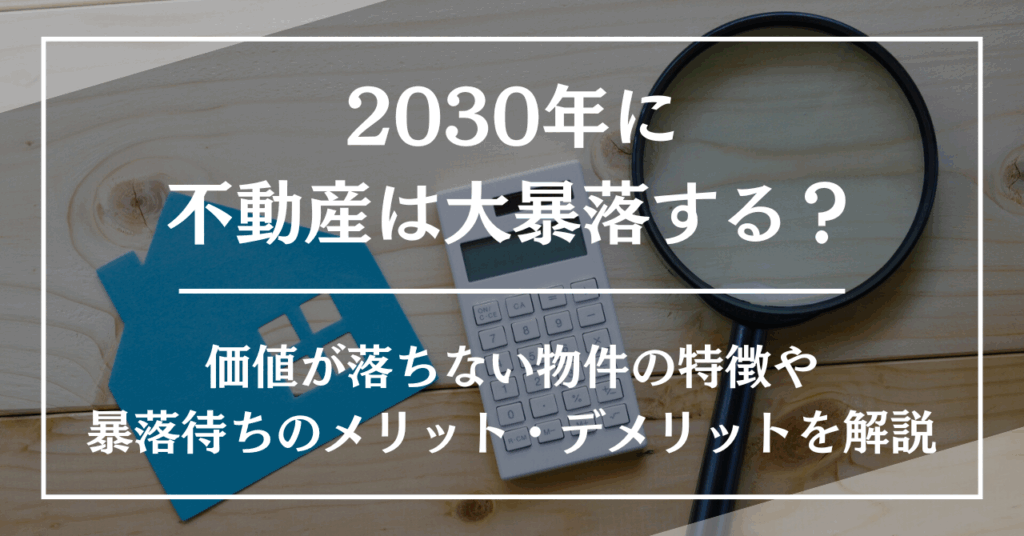
2.変動金利は日銀の政策金利に影響を受ける
変動金利の動向は日本銀行の政策金利に直結する仕組みとなっており、政策金利の引き上げが変動金利の上昇に直接影響します。
日銀は物価安定目標の達成に向けて金利をコントロールしているため、インフレ率の推移が重要な判断材料となります。
実際の例として、政策金利が0.25%引き上げられると、変動金利も約0.3%上昇する傾向があります。
今後は、日銀の金融政策会合での決定内容を注視することが重要です。
3.固定金利は上昇する可能性が高い
固定金利は長期金利の上昇に伴い、変動金利よりも大幅な上昇が予想されます。
国債の利回りと住宅ローンの固定金利には強い連動性があるためです。
現在の市場環境では、10年国債利回りが1%程度まで上昇した場合、固定金利は約2%前後になることが見込まれます。
この上昇は世界的な金利上昇局面や日本経済の正常化が背景にあり、今後数年間で段階的に進行する可能性が高いとされています。
固定金利での借入を検討している場合は、早期の実行が有利になる可能性があります。
4.固定金利は長期金利に影響を受ける
固定金利の水準は国債市場での長期金利が基準となっており、政策金利よりも市場参加者の将来金利に対する期待が強く反映されます。
とくに海外金利の動向にも敏感に反応する特徴があります。
たとえば、アメリカの金利上昇時には日本の長期金利も連動して上昇する傾向が見られます。
この仕組みにより、日銀の政策金利が据え置かれていても、市場の期待変化だけで固定金利が上昇することがあります。
住宅ローン検討者は、国内外の金利動向を総合的に判断して借入時期を決定することが重要です。
また、低金利水準が続くことが予想される今のうちに、住宅ローン金利を比較しておくことが重要です。
▼無料の一括比較サービス「モゲチェック」なら、わずか5分の入力で今より有利な条件の住宅ローンが見つかり、平均で約210万円もの削減に成功しています。
住宅ローンを組むときに抑えておきたいポイント
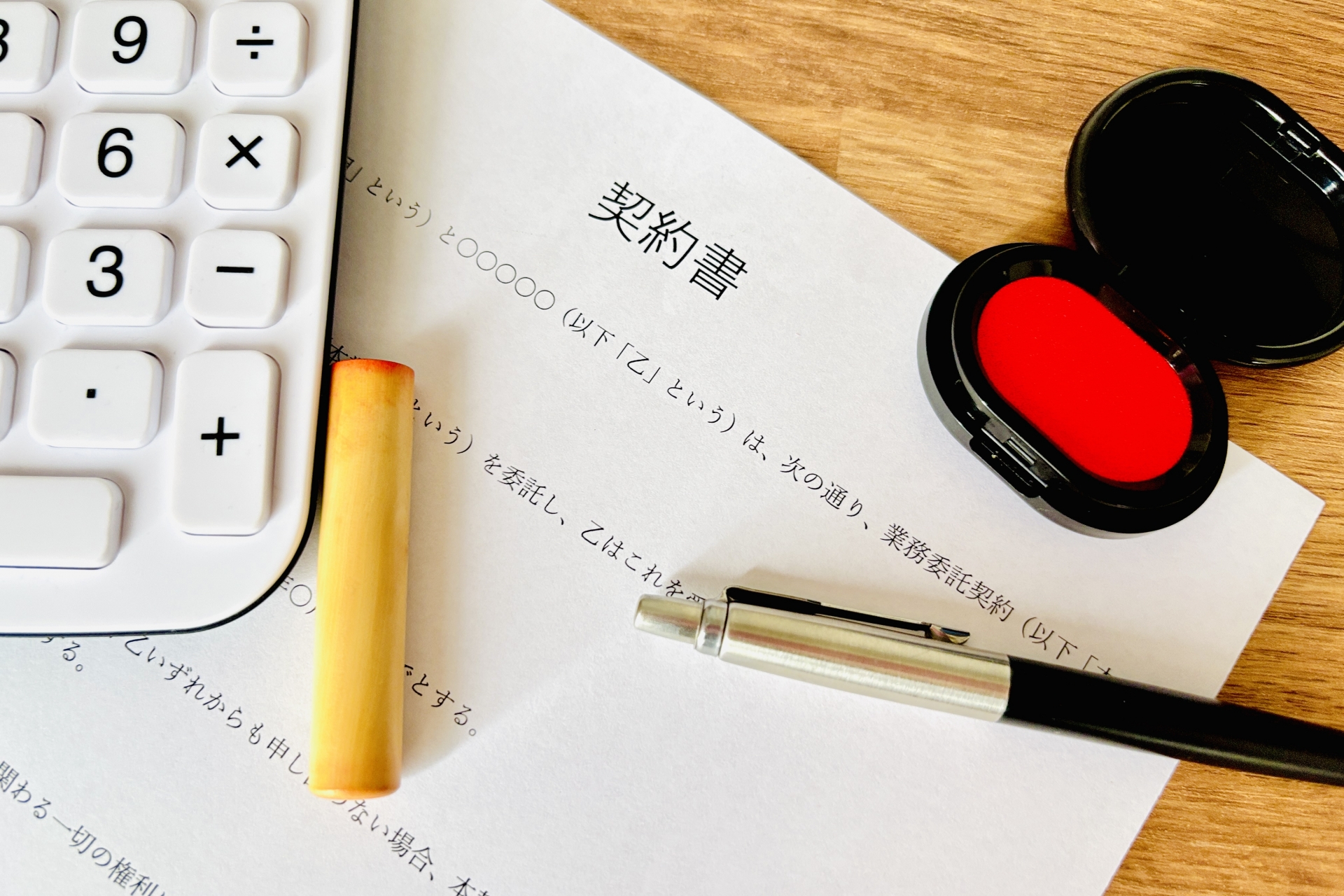
金利上昇局面において住宅ローンを組むときには、適切なリスク管理が必要です。
以下のマインドセットまたは対処法を講じることによって、金利変動の影響を最小限に抑えることが可能になります。
1.変動金利の上昇は想定する
変動金利での借入を選択する場合は、将来の金利上昇リスクを必ず考慮して返済計画を立てることが重要です。
金利が上昇した際の返済額増加に備えて、余裕資金を準備しておく必要があります。
具体的には、借入額3,000万円の場合、変動金利が1%上昇すると月々の返済額が約2万円増加します。
増加分を無理なく支払えるよう、家計に十分な余裕を持たせておきましょう。
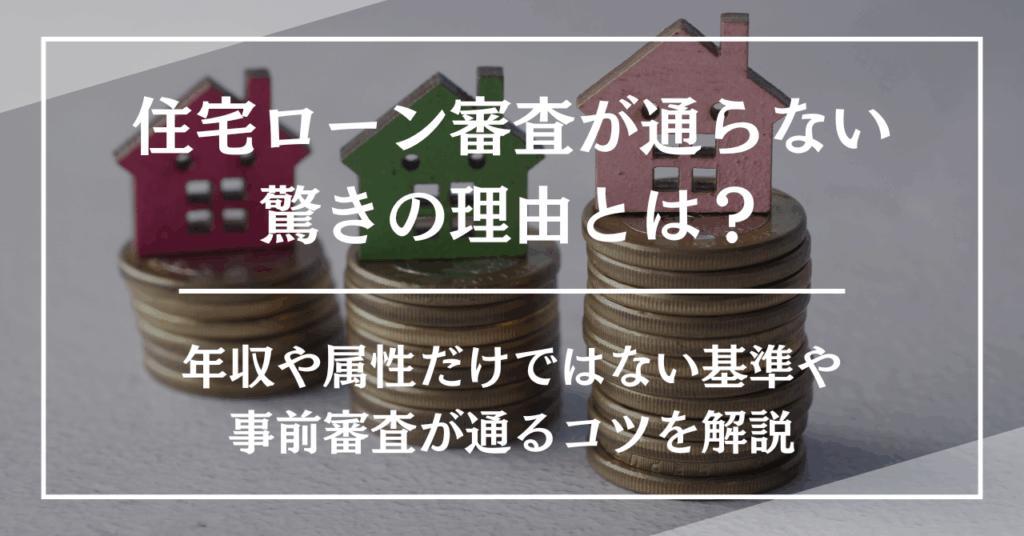
2.繰り上げ返済を効率的に活用する
金利上昇が本格化する前に元金を減らしておくことは、将来の利息負担軽減に非常に効果的な手段です。
とくに期間短縮型の繰り上げ返済により、総支払額を大幅に削減することができます。
たとえば、借入初期に300万円の繰り上げ返済を実行すると、総返済額を200万円以上軽減できる効果があります。
繰り上げ返済を行う際は、手数料や今後の資金需要も考慮して計画的に実施することが重要です。
また、住宅ローン控除との兼ね合いも検討し、税制メリットを最大化する時期を選ぶことも大切です。
3.変動金利と固定金利のミックスローン
変動金利と固定金利を組み合わせるミックスローンは、金利上昇リスクと低金利の恩恵のバランスを取ることができる商品です。
一般的には借入額の半分を固定金利、残り半分を変動金利とすることで、リスク分散効果を得ることができます。
たとえば、金利上昇局面では固定金利部分が安定性を担保し、低金利が続く場合は変動金利部分で利息負担を軽減できます。
また、将来のインフレや収入増加にも対応しやすくなります。
▼無料の一括比較サービス「モゲチェック」なら、わずか5分の入力で今より有利な条件の住宅ローンが見つかり、平均で約210万円もの削減に成功しています。
4.団体信用生命保険と火災保険として活用する
住宅ローン選択時は金利だけでなく、万一のリスクに備える保障内容も重要な比較要素です。
たとえば、団体信用生命保険は、借入人の死亡や事故によって住宅ローンを返済できなくなる場合のリスクを防ぐことができます。
そのため、わずかな金利差よりも保障の充実度を重視することが大切です。
近年、がん団信付きローンの加入率が年々上昇しており、疾病保障への関心が高まっています。
火災保険も含めて総合的な保障を検討し、家族の安心を確保することが重要です。
保障内容が充実している金融機関を選ぶことで、長期にわたる住宅ローン返済期間中の様々なリスクに対応できます。
住宅ローン金利の返済計画はしっかりと!

住宅ローンは人生最大の買い物となることが多く、金利上昇局面に備えた長期的な視点での返済計画立案が不可欠です。
たとえば、繰り上げ返済の計画的実施、金利上昇時の借り換え検討、ミックスローンの活用などを組み合わせることで、金利変動リスクを最小限に抑えることができます。
変動金利を選択する場合は金利上昇を想定した余裕のある返済計画を、固定金利を選択する場合は早期の実行を検討することをおすすめします。
住宅ローンは長期間にわたる重要な契約です。
専門家に相談しながら、自分の家計状況と将来の見通しに最適な商品選択を行い、安心してマイホームライフを送れるよう準備を整えましょう。