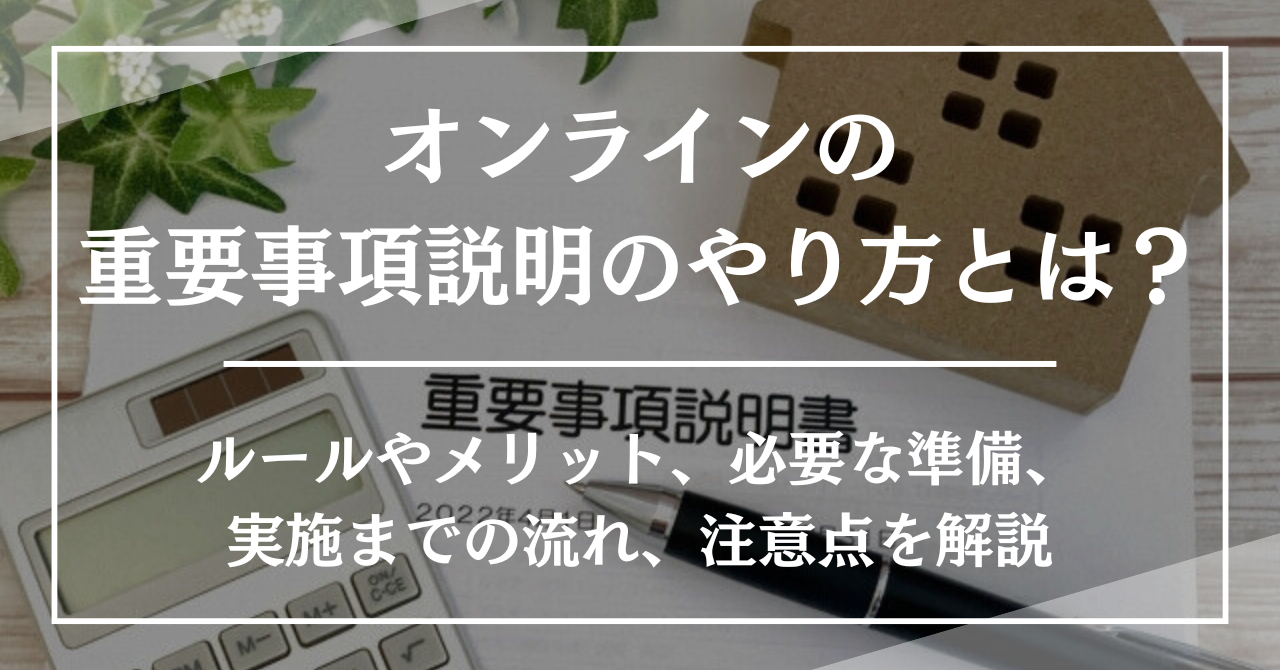「オンラインで重要事項説明は本当に認められる?」
「契約前に来店しないと手続きできないの?」
「通信環境が不安でも契約は進められるの?」
実は不動産取引でもオンライン重説が解禁され、全国で導入が進んでいます。移動や日程調整の負担を減らせる点に魅力を感じる方も多いでしょう。
そこで本記事では、オンラインの重要事項説明のやり方とルールを解説します。また、メリットや必要な準備、実施の流れや注意点についても紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
オンライン重説(IT重説)とは?

オンライン重説とは、従来対面で実施していた重要事項説明を、インターネット回線を利用して非対面で行う仕組みです。この制度は賃貸物件では2017年10月から開始され、売買物件でも2021年4月から本格運用がスタートしました。
不動産流通推進センターの調査によると、全国の不動産業者の導入率は22.1%に到達しており、急速に普及が進んでいます。これまで必ず対面で行う必要があった重要事項説明が、テクノロジーの発展により時代に合わせて変化した画期的な取り組みといえるでしょう。
参照:不動産流通業におけるIT技術の利用状況、効果と課題に関する調査の結果について|公益財団法人不動産流通推進センター
オンライン重説が推進される背景
オンライン重説が導入された背景には、遠方に住む顧客の負担軽減と、コロナ禍での非対面ニーズの高まりがあります。従来の対面説明では、顧客が物件所在地や不動産業者の店舗まで足を運ぶ必要があり、とくに転勤や進学で遠方から契約する場合は大きな負担となっていました。
また、時代とともにデジタル技術が発達し、映像と音声による双方向通信が安定して利用できるようになったことも、制度導入の後押しとなりました。国土交通省は宅地建物取引業法の解釈を見直し、一定の条件を満たせば対面と同等の効力を持つとして正式に認可したのです。
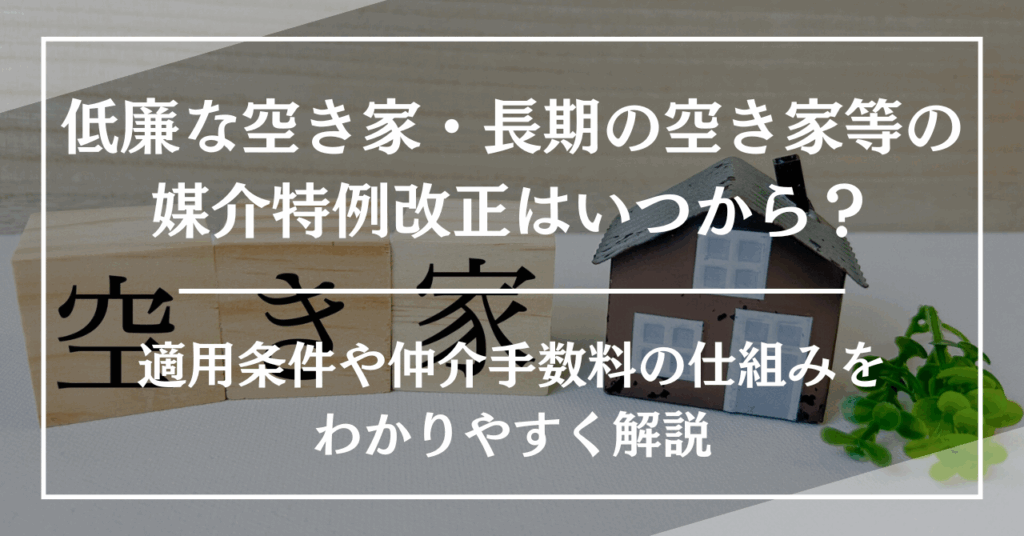
オンライン重説(IT重説)のルール

国土交通省の通知では、オンライン重説を実施する場合に、以下の4つの必須要件が定められています。
1.宅建士と顧客が図面等の書類と説明内容を十分理解できる程度に映像を視認でき、双方の音声を明確に聞き取れること
2.宅建士により記名押印された重要事項説明書と添付書類を顧客へ事前送付すること
3.顧客が重要事項説明書を確認しながら説明を受けられる状態で、映像・音声状況を説明開始前に確認すること
4.宅建士は宅建士証を画面に提示し、顧客が視認できたことを必ず確認すること
また、オンライン重説中に映像や音声に乱れがある場合は、直ちに中断する必要があります。説明を再開する場合は、すべての不具合が解消されてからでなければいけません。
オンライン重説(IT重説)を導入するメリット

オンライン重説のメリットは以下の4つです。
1.顧客が来店する負担を軽減できる
2.日程調整が柔軟に設定できる
3.重要事項説明を記録に残せる
4.印紙代や書類印刷代が節約できる
それぞれ解説します。
1.顧客が来店する負担を軽減できる
遠方に住む顧客にとって、オンライン重説はとても便利なサービスです。たとえば、東京の物件を大阪在住者が契約する場合、従来なら交通費往復で約3万円、移動時間は丸一日を要していました。一方、オンライン重説なら自宅からパソコン一台で参加でき、移動によるストレスや疲労も回避できます。
とくに育児中の方や介護が必要な家族がいる方、身体的な制約がある方にとっても大きなメリットとなります。このように、多様なライフスタイルに対応できる点がオンライン重説の大きな魅力といえるでしょう。
2.日程調整が柔軟に設定できる
オンライン重説は従来の対面説明と比較して、日程調整の自由度が大幅に向上します。仕事の都合で平日日中に時間を確保しにくい会社員の方でも、早朝や夜間の時間帯で柔軟にスケジュール設定が可能となります。
また、移動時間が不要なため、たとえば19時から開始しても20時には終了でき、翌日の仕事に支障をきたしません。不動産会社側にとっても、顧客の来店に合わせた会議室の準備や駐車場の確保、資料印刷などの事前準備が不要となり、業務効率が向上します。
3.重要事項説明を記録に残せる
オンライン重説では、重要事項説明の内容を録画・録音して正確に記録として残すことができます。後日顧客から説明内容について質問があった場合でも、実際の説明映像を確認することで正確な回答が可能です。「説明を受けていない」「聞いていない内容だった」といった紛争を未然に防ぐことができます。
また、新人宅建士の研修教材としても活用でき、説明技術の向上や標準化に役立ちます。社内でのコンプライアンス確認や品質管理の観点からも有効で、適切な重要事項説明が実施されているかを客観的に検証できる貴重な資料となります。
4.印紙代や書類印刷代が節約できる
書面での契約書類作成に必要な印紙代も、電子契約システムと組み合わせることで大幅に削減できます。
たとえば、売買契約では物件価格に応じて数千円から数万円の印紙代が必要ですが、電子契約なら印紙税は非課税となります。コピー代やファイリング費用、郵送費なども含めて考えると、年間で相当な経費削減効果が期待できるでしょう。
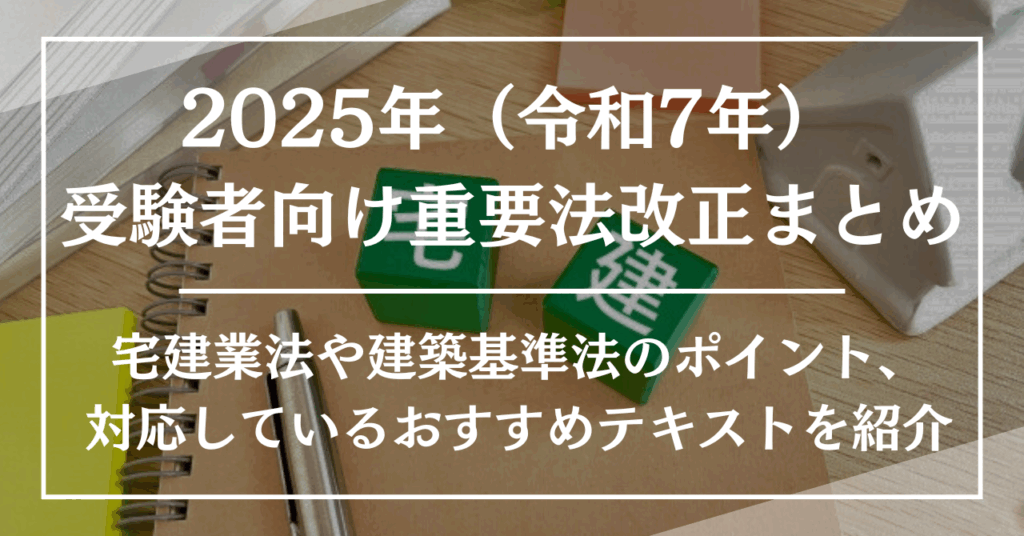
オンライン重説(IT重説)の導入に必要な準備

顧客にとっても不動産会社にとってもメリットが大きいオンライン重説ですが、導入には以下の準備が必要です。
1.デジタルデバイスの用意
2.インターネット環境の整備
3.オンライン会議ツールのインストール
それぞれ解説します。
1.デジタルデバイスの用意
オンライン重説を導入するためには、まずデジタルデバイスの準備が不可欠です。パソコンまたはタブレット端末に加え、高画質カメラとクリアな音声を収録できるマイクの用意が必要となります。
カメラの解像度は最低でもHD(720p)以上、できればフルHD(1080p)対応が理想的です。宅建士証や重要事項説明書の文字を鮮明に表示するため、画質の良さは妥協できません。マイクについては、周囲の雑音を抑制するノイズキャンセリング機能付きが望ましく、相手の声を聞くためのスピーカーも高音質なものを選ぶ必要があります。
デバイスの処理能力も重要で、映像処理に負荷がかかるため、メモリ8GB以上、CPUはCore i5クラス以上が推奨されます。また、長時間の使用に耐えるバッテリー容量と、安定した有線LAN接続ポートの確保も検討すべき要素です。
2.インターネット環境の整備
安定したオンライン重説の実施には、高品質なインターネット環境が不可欠です。推奨される通信速度は上り下りともに最低10Mbps以上、理想的には50Mbps以上の光ファイバー回線が望ましいでしょう。Wi-Fi環境よりも有線LAN接続の方が通信の安定性が高く、重要な契約手続きでは有線接続を強く推奨します。
また、同一のネットワーク上で他の機器が大量のデータ通信を行っていると、映像や音声が不安定になる可能性があります。そのため、オンライン重説の時間帯は他のインターネット利用を控えるよう事前に準備することが重要です。さらに、万が一の通信障害に備えて、スマートフォンのテザリング機能等の代替手段も用意しておくと安心です。
3.オンライン会議ツールのインストール
Zoom(ズーム)やMicrosoft Teams(チームス)等のオンライン会議ツールは、事前にインストールしておく必要があります。宅建士は顧客のデバイスに適したツールを選択し、事前に基本操作の説明を行いましょう。
高齢者や技術に不慣れな方には、アプリのダウンロード方法から画面の操作方法まで丁寧にサポートすることが求められます。また、音声のミュート・解除、カメラのオン・オフ、画面共有機能の使い方など、重説当日に必要となる操作を事前に練習してもらうことが重要です。
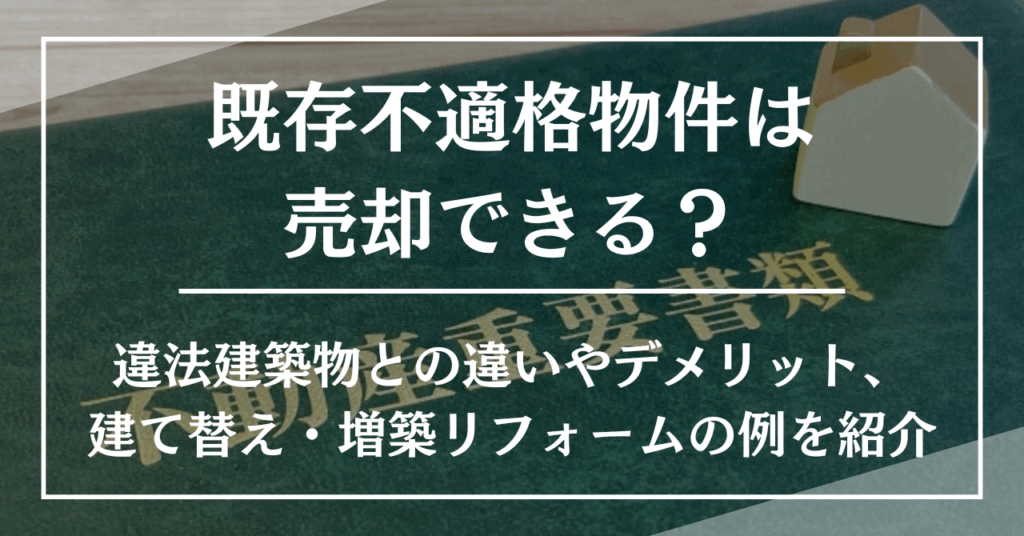
オンライン重説(IT重説)を実施するまでの流れ

オンライン重説を実施するまでの流れは以下の通りです。
1.オンライン重説の同意を取る
2.顧客のインターネット環境を確認する
3.接続テストを実施する
4.重要事項説明書などを送付する
5.オンライン重説を実施する
6.重要事項説明書などを返送してもらう
段階ごとにポイントを解説します。
1.オンライン重説の同意を取る
オンライン重説の実施前には、顧客との詳細な打ち合わせが欠かせません。まず、オンライン重説の仕組みやメリット・デメリットを説明し、顧客の理解と同意を得る必要があります。同意書には、技術的なトラブルが発生した場合の対処法や、録画・録音に関する取り決めも明記しておくべきです。
顧客が使用するデバイスの種類、インターネット回線の速度、オンライン会議ツールの操作経験なども事前に確認します。高齢者やオンライン会議ツールに不慣れな方の場合は、家族のサポートを受けられるか、代替手段があるかも検討する必要があります。
2.顧客のインターネット環境を確認する
オンライン重説を成功させるためには、顧客側のインターネット環境の事前確認が不可欠です。まず、使用予定のデバイス(パソコン・タブレット・スマートフォン)の種類と基本スペックを聞き取り、オンライン会議に適しているかを判断する必要があります。
通信速度については、上り下りともに最低10Mbps以上を確保できているか、実際の速度測定サイトを使って確認してもらうことが重要です。Wi-Fi環境の場合は電波強度も確認し、可能であれば有線LAN接続への変更を提案します。
3.接続テストを実施する
接続テストは本番の数日前に実施し、実際の重説環境を模擬して行います。映像の画質、音声の明瞭さ、画面共有機能の動作確認を行い、問題があれば事前に解決しておきます。
顧客には重要事項説明書と添付書類を郵送で送付し、手元に届いたことを確認してから本番日程を調整します。当日は開始前に再度映像・音声の確認を行い、宅建士証の画面提示による本人確認を実施します。
4.重要事項説明書などを送付する
重要事項説明書の送付は、オンライン重説における最も重要な準備工程の一つです。宅建士による記名押印済みの重要事項説明書と全ての添付書類を、説明実施日の3~5日前までに確実に顧客へ送付するようにしましょう。
送付方法は書留郵便や宅配便等の配達確認が可能な手段を選び、顧客による受領確認を必ず取ることが重要です。書類が手元に届いたら、不足や破損がないか確認してもらい、説明当日には手元で閲覧できる状態にしておいてもらいます。
5.オンライン重説を実施する
オンライン重説の当日は、開始前の確認作業から丁寧に進めることが重要です。まず映像・音声の品質確認を行い、宅建士証の画面提示による本人確認を実施します。重要事項説明は送付済みの書類を顧客が手元で確認しながら進め、各項目について理解度を確認しながら説明を行います。
契約書の説明も同時に実施する場合は、重要事項説明書との関連性を明確に示し、契約条件や支払い方法、引き渡し時期等の重要事項を強調して説明することが必要です。説明中は定期的に質問の機会を設け、専門用語を避けた平易な表現を心がけることで、顧客の理解を深めることができます。
6.重要事項説明書などを返送してもらう
オンライン重説完了後は、顧客による書類への記名押印と返送手続きが必要となります。重要事項説明書の顧客署名欄への記入と押印、契約書への署名押印を指定期日までに完了してもらい、返送用の封筒や宅配便伝票を事前に同封しておくことで手続きを円滑化できます。
返送方法は書留郵便や宅配便等の追跡可能な手段を指定し、到着確認を必ず行います。書類に不備があった場合の再送手続きについても事前に説明しておき、円滑な契約締結に向けた体制を整備することが重要です。
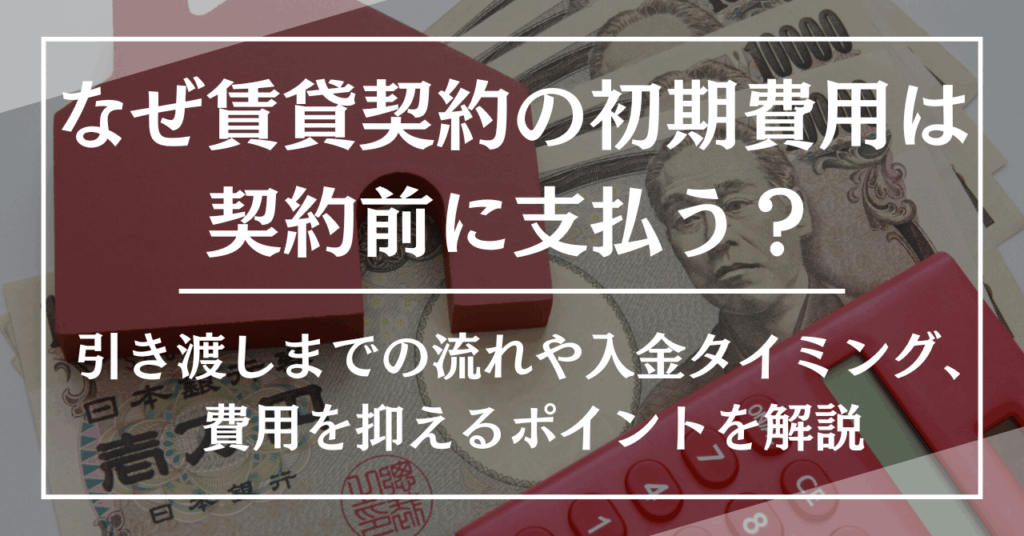
オンライン重説(IT重説)を導入するときの注意点

オンライン重説を導入するときの注意点は以下の3つです。
1.通信環境が悪いとやり直しする必要がある
2.重要事項説明を軽視してしまいかねない
3.対面よりも細かいニュアンスが伝わりずらい
それぞれ解説します。
1.通信環境が悪いとやり直しする必要がある
オンライン重説における最大のリスクは、通信環境の不具合による実施の中断です。映像が途切れたり音声が聞き取れなくなった場合、法令に基づき直ちに説明を中断し、技術的な問題が解決するまで再開することはできません。
復旧に時間がかかる場合は、別日程での再実施を検討する必要があり、顧客にとっても不動産会社にとっても大きな負担となります。このようなトラブルを防ぐため、事前の接続テストを入念に行い、通信環境の安定性を確認することが重要です。
2.重要事項説明を軽視してしまいかねない
オンライン重説の手軽さは大きなメリットである一方、重要事項説明の重要性を軽視してしまうリスクも抱えています。自宅でリラックスした環境で参加できるため、顧客が集中力を欠いたり、形式的な理解に留まってしまう可能性があります。
また、画面越しでの説明は臨場感に欠けるため、重要な契約内容の深刻さが伝わりにくい場合もあります。このような問題を防ぐため、宅建士は説明の重要性を改めて強調し、各項目について具体例を交えながら丁寧に説明することが必要です。
3.対面よりも細かいニュアンスが伝わりずらい
オンライン環境では、対面と比べて顧客の反応や理解度を読み取ることが困難になります。画面越しでは微細な表情の変化や身振り手振りが伝わりにくく、顧客が疑問を抱いていても気づかない場合があります。
そのため、通常よりも頻繁に理解度の確認を行い、「ここまでで何か質問はありませんか」「○○の部分は理解いただけましたでしょうか」といった具体的な問いかけを増やす必要があります。
また、専門用語の使用を極力避け、平易な言葉での説明を心がけることも重要です。重要なポイントでは画面共有機能を活用して視覚的な説明を加え、顧客の集中力が途切れないよう工夫することが求められます。
オンライン重説(IT重説)に関するよくある質問

ここからは、オンライン重説に関するよくある質問について回答していきます。
1.オンライン重説はカメラオフでもできますか?
オンライン重説においてカメラオフでの実施は法的に認められていません。国土交通省の通知では、宅建士が宅建士証を画面に提示し、顧客がこれを視認できることを確認することが必須要件とされています。
また、重要事項説明書や添付書類を顧客が確認しながら説明を受けられる状態であることも、映像による確認が前提となっています。音声のみでの実施は対面による重要事項説明と同等とは認められず、法的効力を持たない可能性があります。
そのため、必ずカメラをオンにした状態で実施する必要があります。技術的な理由でカメラが使用できない場合は、対面での重要事項説明に切り替えることが適切です。
2.オンライン重説は画面録画してもよいですか?
オンライン重説の画面録画は、顧客の同意を得た上であれば法的に可能です。録画により重要事項説明の内容を正確に記録できるため、後日のトラブル防止や品質向上に役立ちます。ただし、録画を行う場合は事前に顧客に対してその旨を説明し、書面による同意を取得することが必要です。
録画データの保存期間、利用目的、第三者への提供の有無についても明確に説明し、同意書に記載しておくべきです。また、個人情報保護法に基づく適切な管理体制を整備し、データの漏洩や悪用を防ぐ措置を講じることが重要です。顧客が録画を拒否した場合は、録画なしでの実施も可能ですが、説明内容の記録方法を別途検討する必要があります。
3.オンライン重説の所要時間は何分ですか?
オンライン重説の所要時間は、物件の種類や契約内容によって異なりますが、30分から60分程度となっています。賃貸物件の場合は比較的シンプルな内容が多いため30分程度、売買物件の場合は説明事項が多岐にわたるため45分から60分程度が一般的です。
対面での重要事項説明と比較して大きな時間差はありませんが、技術的な確認作業や接続テストの時間を含めると、やや長くなる傾向があります。また、顧客の理解度や質問の数によっても所要時間は変動します。初回のオンライン重説では操作説明に時間を要することもあるため、余裕を持ったスケジュール設定が推奨されています。
不動産業界でもオンライン化が進行中!

オンライン重説は、国土交通省が定めたルールに従って実施することで、従来の対面重説と同等の法的効力を持つことが可能です。顧客の利便性向上と業務効率化の両面でメリットがあり、とくにコロナ禍以降は非対面ニーズの高まりとともに導入が加速しています。
一方で、通信環境の安定性やコミュニケーション面での課題もあるため、事前準備の徹底と当日の丁寧な進行管理が重要です。宅建士としては、新しい技術を適切に活用しながらも、顧客への丁寧な説明と法令遵守を徹底することを意識しましょう。