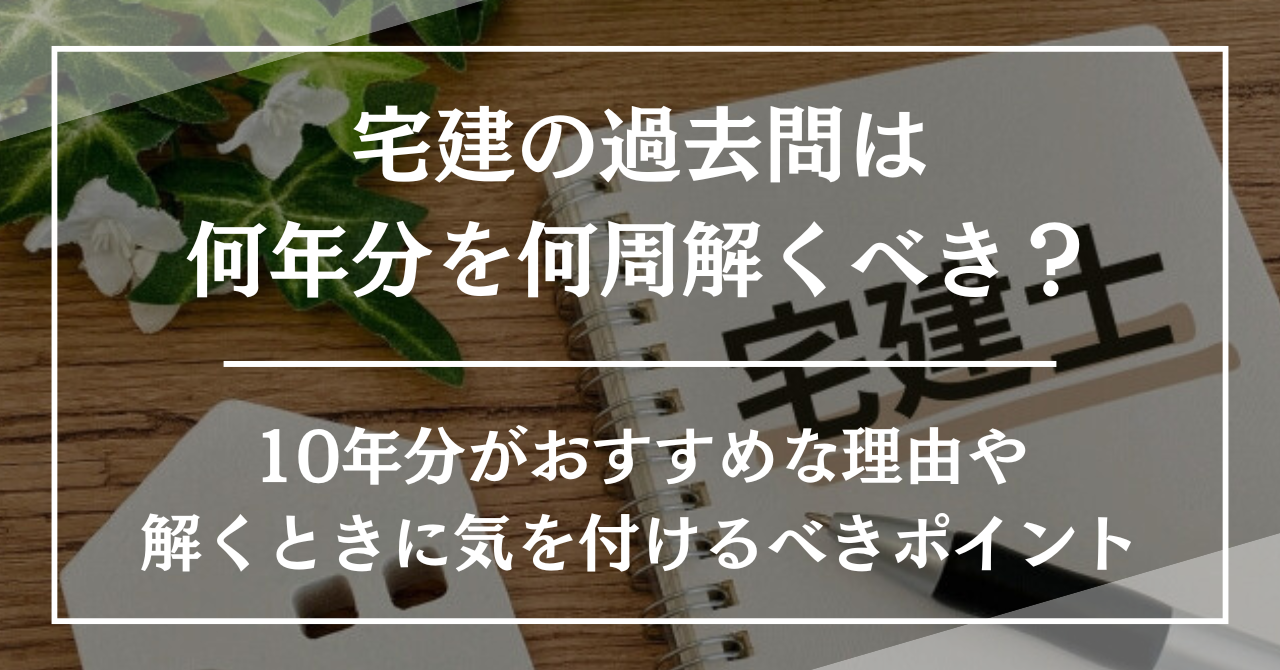※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net、楽天アフィリエイト含む)を掲載しています。
「宅建合格のために必要な過去問の勉強時間は?」
「宅建の過去問は最低何年分を解くべき?」
「宅建の過去問を解くときのポイントは?」
宅建試験において、過去問からの出題割合は一般的に7割から8割程度と言われます。
そのため、過去問を繰り返し学習することで、試験の傾向を把握し、出題形式や時間配分に慣れておくことは合格への最短ルートと言えます。
そこで本記事では、宅建の過去問は最低何年分、何周解くべきなのかについて、実体験からおすすめの勉強量、勉強時間について紹介します。
また、一般的に10年分解くことがおすすめされる理由や解いてるときに気を付けるべきポイントについても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
▼私も活用した本記事でおすすめしている過去問はこちらです。
目次
宅建試験は過去問だけで受かるのか?

宅建試験に合格するためには過去問演習が欠かせません。
合格者の大部分が最重要学習法として位置づけており、私自身も過去問なくして合格はありえませんでした。
しかし「過去問だけ」では知識が断片的になり、応用力が身につかないリスクがあります。
宅建業法で具体例を挙げると、過去問で「重要事項説明書で物件情報を記載するか否かの○×問題」を暗記しても、「重要事項説明書の記載事項」すべてを理解することはできません。
テキストでしっかりと制度の背景や目的を学んでから過去問で確認する、このインプットとアウトプットの組み合わせこそが実力定着の秘訣です。
特に独学者や初学者の方は、基礎固めを怠らず「理解してから演習」の流れを大切にしてください。
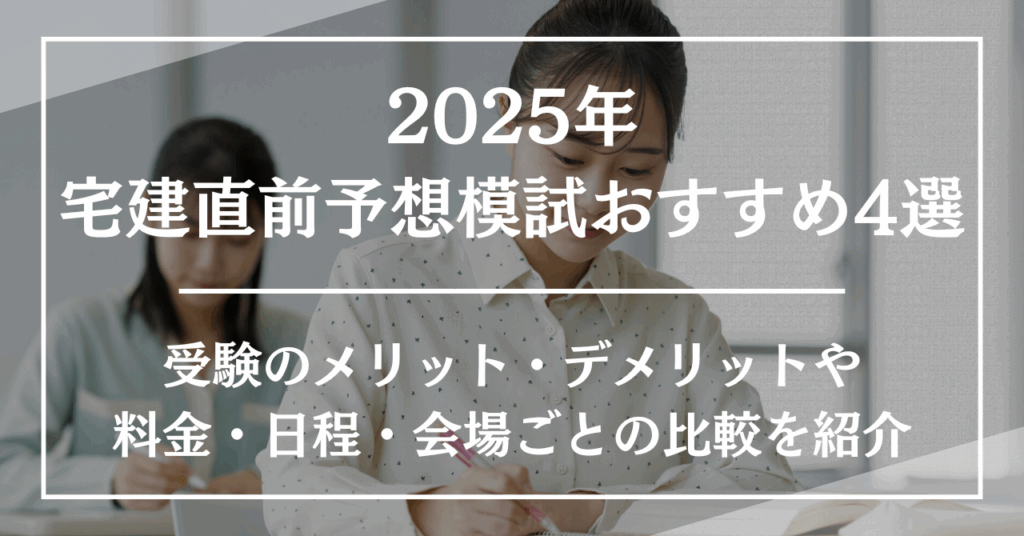
宅建の過去問は最低何年分を解くべきか?

宅建の過去問は最低でも5年分、できれば10年分を解くことをおすすめします。
宅建試験の出題傾向は数年単位では大きく変わらないため、直近の問題ほど本試験で類似問題が出る可能性が高いのです。
実際に私が受験した年も、前年度の問題とほぼ同じパターンの出題がありました。
ただし5年分では、民法の債権分野や都市計画法の細かい規定など、重要だが頻出度の低い論点をカバーしきれません。
10年分解けば主要論点はほぼ網羅でき、どの分野から出題されても対応できる実力が身につきます。
▼時間に余裕がある方は、さらに古い問題にも挑戦すると知識の幅が広がります。
宅建の過去問は最低何周するべきか?
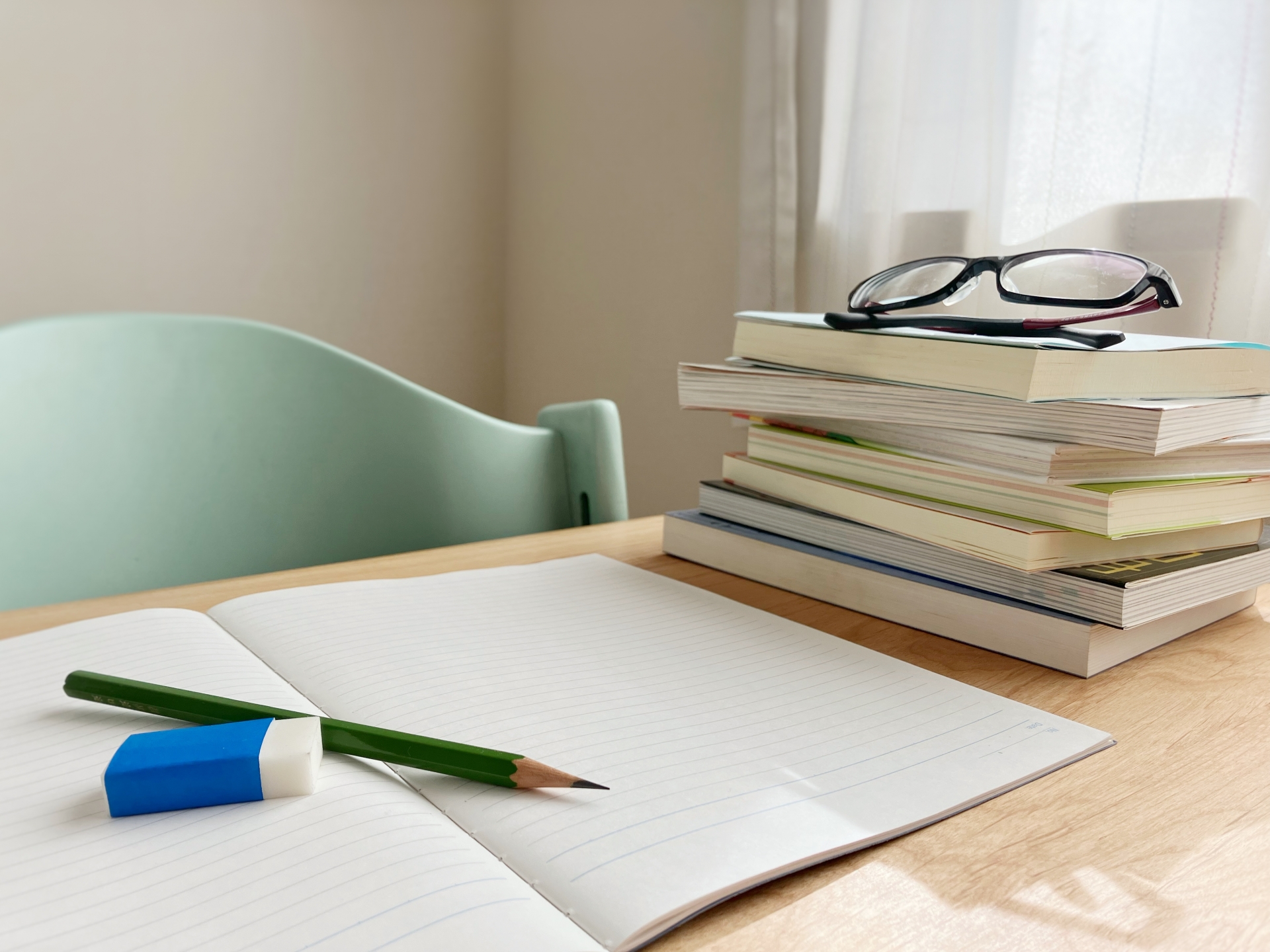
宅建の過去問は最低でも3周することをおすすめします。
1周目は正答率にこだわらず、出題形式や問題の傾向を把握することに集中しましょう。
私も1周目は3割程度しか正解できず不安でしたが、これは当然のことです。
2周目以降で理解の浅い分野を重点的に学習し、間違えた問題には印をつけて繰り返し解き直します。
宅建試験特有の「ひっかけ問題」や「紛らわしい選択肢」にも慣れていきます。
たとえば、宅建業法では「必ず」と「原則として」の使い分けが頻出ですが、繰り返し解くことでこうした出題の癖が身につきます。
合格者の中には5周以上している方も珍しくなく、反復こそが確実な合格への道です。
また、過去問の反復学習を効率的に進めたい場合は、体系的に整理された通信講座を併用すると理解がより定着します。
▼オンライン完結型の講座なら、繰り返し学習と重要ポイントの確認を同時に行い、最短で合格レベルまで実力を引き上げられます。
![]()
宅建の過去問を1回解くのに必要な時間は?

宅建の過去問を1セット解くには、本試験と同じ2時間(120分)を目安にしてください。
本試験は50問で2時間なので、1問あたり約2分24秒の計算になります。
ただし解説を読み、復習まで含めると1回で3〜4時間かかることも珍しくありません。
私の場合、間違えた問題はテキストに戻って関連知識を確認していたため、さらに時間を要しました。
初学者の方は理解不足でより時間がかかるのが普通です。
重要なのは時間配分の練習も兼ねて本試験形式で解くことです。
権利関係で時間をかけすぎて宅建業法で時間切れ、といった失敗を防ぐため、分野ごとの時間配分も意識して取り組みましょう。
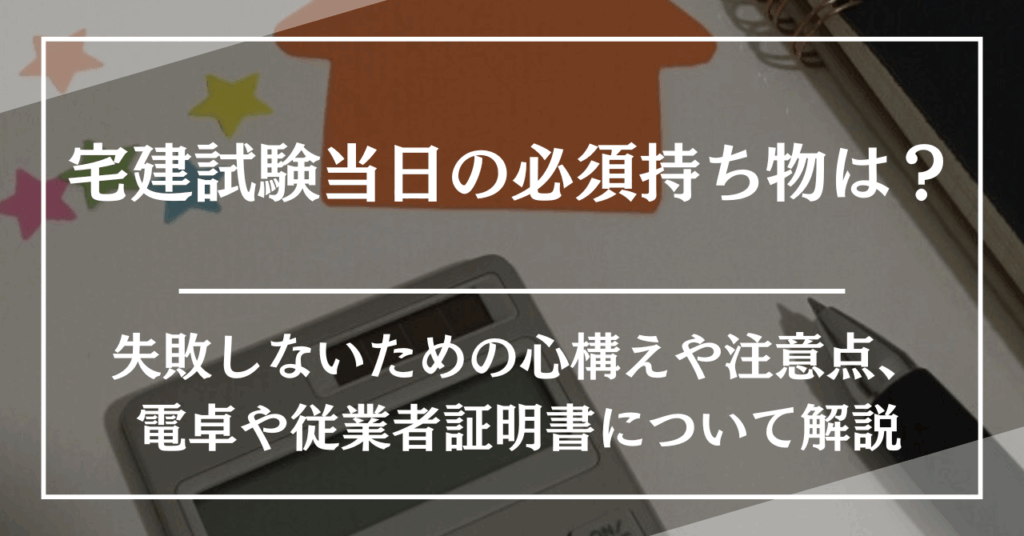
宅建の過去問を10年分解くことがおすすめされる理由

一般的に、宅建の過去問は10年分を解くことがおすすめされています。主な理由は3つです。
1.宅建試験の出題傾向がつかめる
2.網羅的に問題慣れすることができる
3.本試験で同様の問題が出る可能性がある
それぞれ解説します。
1.宅建試験の出題傾向がつかめる
過去10年分を解くことで、宅建試験の出題傾向が明確に見えてきます。
毎年繰り返し出題される「頻出論点」が判明し、どこに力を入れるべきかが分かります。
たとえば、宅建業法では「重要事項説明」「37条書面」「報酬」が毎年必ず出題され、民法では「売買契約」「賃貸借契約」「相続」が頻出パターンです。
法改正の影響を除けば出題傾向は安定しており、過去の傾向から本試験の予想も立てやすくなります。
私も過去問分析により「今年はこの分野が出そう」という感覚が身につき、実際に的中した経験があります。
この傾向把握により効率的な学習計画が立てられ、合格への最短ルートが見つかります。
また、過去問分析で効率よく学習ポイントを絞りたい場合は、体系的に整理されたオンライン講座を併用するとさらに効果的です。
▼解説と問題演習が連動した通信講座なら、頻出論点を重点的に反復し、傾向把握と得点力アップを同時に進められます。
![]()
2.網羅的に問題慣れすることができる
過去10年分であれば、宅建試験で出題される主要なパターンをほぼ網羅できます。
宅建業法の「免許」「業務」「監督処分」、民法の「物権」「債権」「相続」、法令上の制限の各種法律など、全分野にわたって様々な問題形式に触れられます。
また、苦手分野も繰り返し出題されるため、避けて通れず必然的に克服せざるを得ません。
私の場合、都市計画法が苦手でしたが、10年分解く過程で同じような問題が何度も出てきて、最終的には得点源にできました。
一つの論点について複数年の出題を比較することで、出題者の意図や重要ポイントも理解できるようになります。
▼網羅的な過去問演習により、本試験でどんな問題が出ても対応できる実力が身につきます。
3.本試験で同様の問題が出る可能性がある
宅建試験は過去問の焼き直しが頻繁にあり、類似問題が本試験で出題される可能性が高いです。
完全に同じ問題は出ませんが、数値や条件を少し変えただけの問題や、過去問の選択肢を組み合わせた問題がよく見られます。
たとえば、「建築基準法の建ぺい率・容積率」の計算問題は、毎年同じパターンで出題されています。
過去10年分を解いていれば、このような類似問題に確実に対応でき、貴重な得点源となります。
私の本試験でも、過去問で見たことのある宅建業法の分野の問題が多数出題され、それらはほぼ確実に正解できました。
「似た問題を見たことがある」という安心感は、試験本番での精神的な支えにもなります。
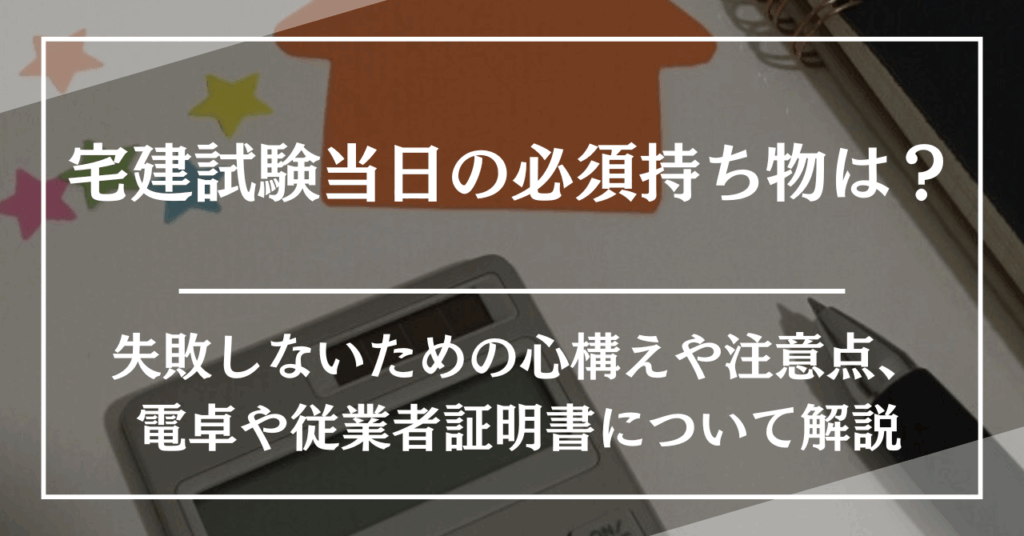
宅建の過去問を解くときに気を付けるべきポイント

宅建の過去問を解くときは、知識レベルやマインドセットの部分で準備が必要です。
とくに初学者が気を付けるべきポイントは以下の通りです。
1.テキストを最低1周してから過去問に挑戦する
2.本番と同じく時間を測って過去問を解く
3.過去問を解いた後は復習で周辺知識までインプット
4.過去問が難しくて解けなくても落ち込まない
それぞれ解説します。
1.テキストを最低1周してから過去問に挑戦する
過去問に取り組む前に、必ずテキストを最低1周は読んでから始めましょう。
知識ゼロの状態で過去問に挑むと、解説を読んでも理解できず挫折してしまいがちです。
私の周りでも、いきなり過去問から始めて撃沈した人を何人も見てきました。
宅建業法なら「免許制度とは何か」「なぜ重要事項説明が必要なのか」といった基本的な仕組みを理解してから演習に入ることで、個別の知識が有機的につながります。
テキスト学習で基礎を押さえてからアウトプットに移ることで、過去問の効果が最大限に発揮されます。
急がば回れの精神で、まずはしっかりとした土台作りを心がけてください。
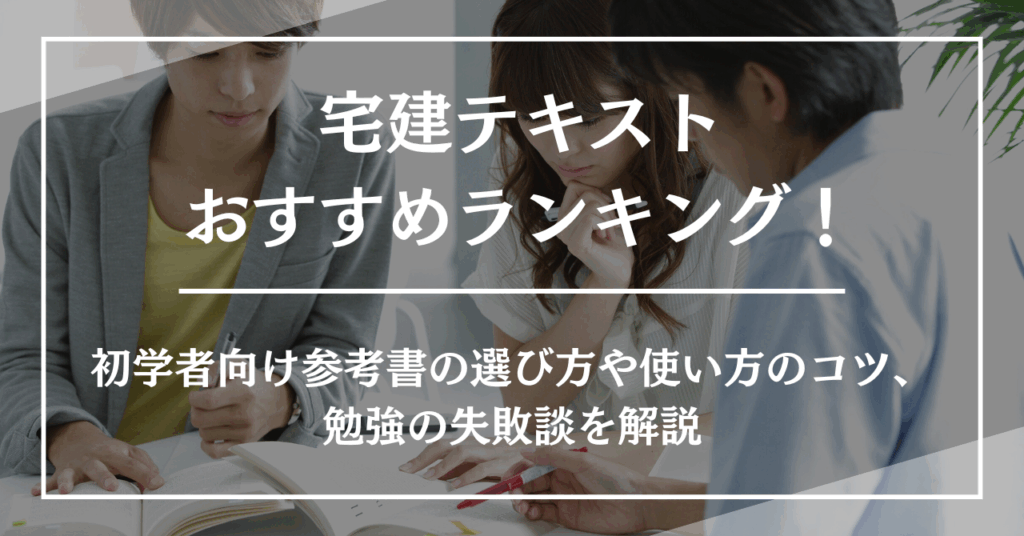
2.本番と同じく時間を測って過去問を解く
過去問演習では必ず時間を測り、実戦形式で取り組むことが重要です。
本試験では2時間という限られた時間の中で50問を解く必要があり、時間配分を間違えると実力があっても不合格になってしまいます。
私も最初は時間を気にせず解いていましたが、模擬試験で時間不足に陥り、慌てて時間管理を始めました。
権利関係14問で45分、宅建業法20問で60分、法令上の制限8問で20分、税・その他8問で15分という具合に、分野ごとの目安時間を設定しましょう。
緊張感を持って取り組むことで集中力も高まり、本番での実力発揮につながります。
時間配分の感覚は実践でしか身につかないため、普段から意識して取り組んでください。
3.過去問を解いた後は復習で周辺知識までインプット
過去問演習で最も重要なのは解いた後の復習です。
単に「正解か不正解か」だけで終わらせず、間違えた選択肢の理由や関連知識まで深く学びましょう。
たとえば、「建築基準法の用途地域」の問題で間違えたら、全ての用途地域の特徴を確認し、建ぺい率・容積率の規制も合わせて復習します。
また、正解した問題でも、他の選択肢がなぜ間違いなのかを説明できるレベルまで理解を深めることが大切です。
私は間違えた問題にはマーカーで印をつけ、翌日必ず解き直すルールを作っていました。
この徹底した復習により、同じミスを繰り返すことなく着実に実力が向上し、本試験での得点力アップにつながります。
さらに復習の精度をさらに高めたい場合は、解説と演習が連動したオンライン講座を活用すると効率的です。
▼体系的に整理された講座なら、間違えた問題の周辺知識まで漏れなく確認でき、短期間で得点力を伸ばせます。
![]()
4.過去問が難しくて解けなくても落ち込まない
過去問を解いて思うように点数が取れなくても、決して落ち込む必要はありません。
特に初学者の方は1周目で3〜4割程度の正答率になることも珍しくなく、これは全く普通のことです。
私自身も最初の過去問では散々な結果でしたが、それが学習のスタートラインでした。
重要なのは間違いを「失敗」ではなく「伸びしろ」と捉えることです。
間違えた問題こそが復習のチャンスであり、その問題を理解できれば確実に実力アップにつながります。
民法の「時効」で間違えたら時効全般を、宅建業法の「免許」で間違えたら免許制度全体を学び直す機会と考えましょう。
諦めずに継続することで、必ず点数は向上していきます。
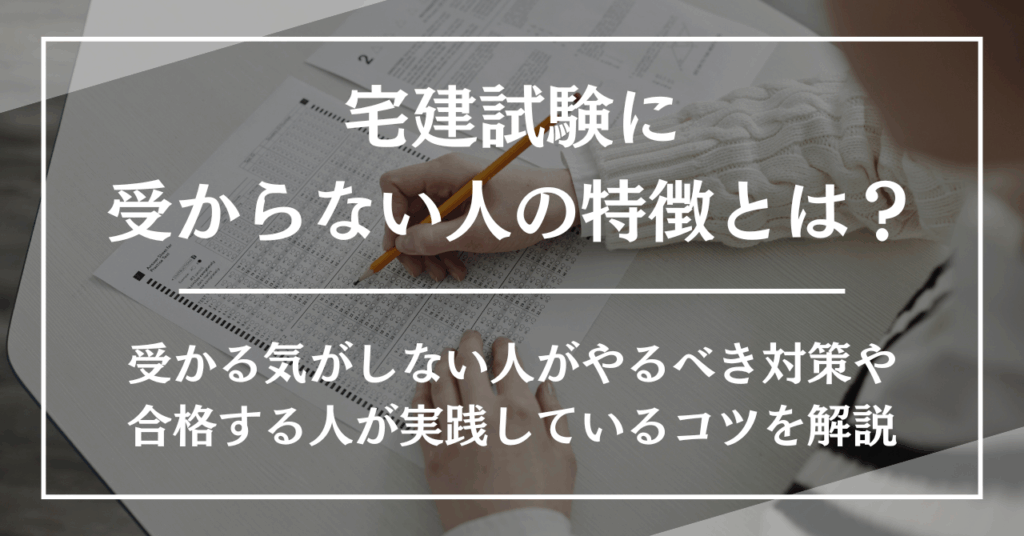
宅建の過去問は最低でも10年分を3周してみよう!
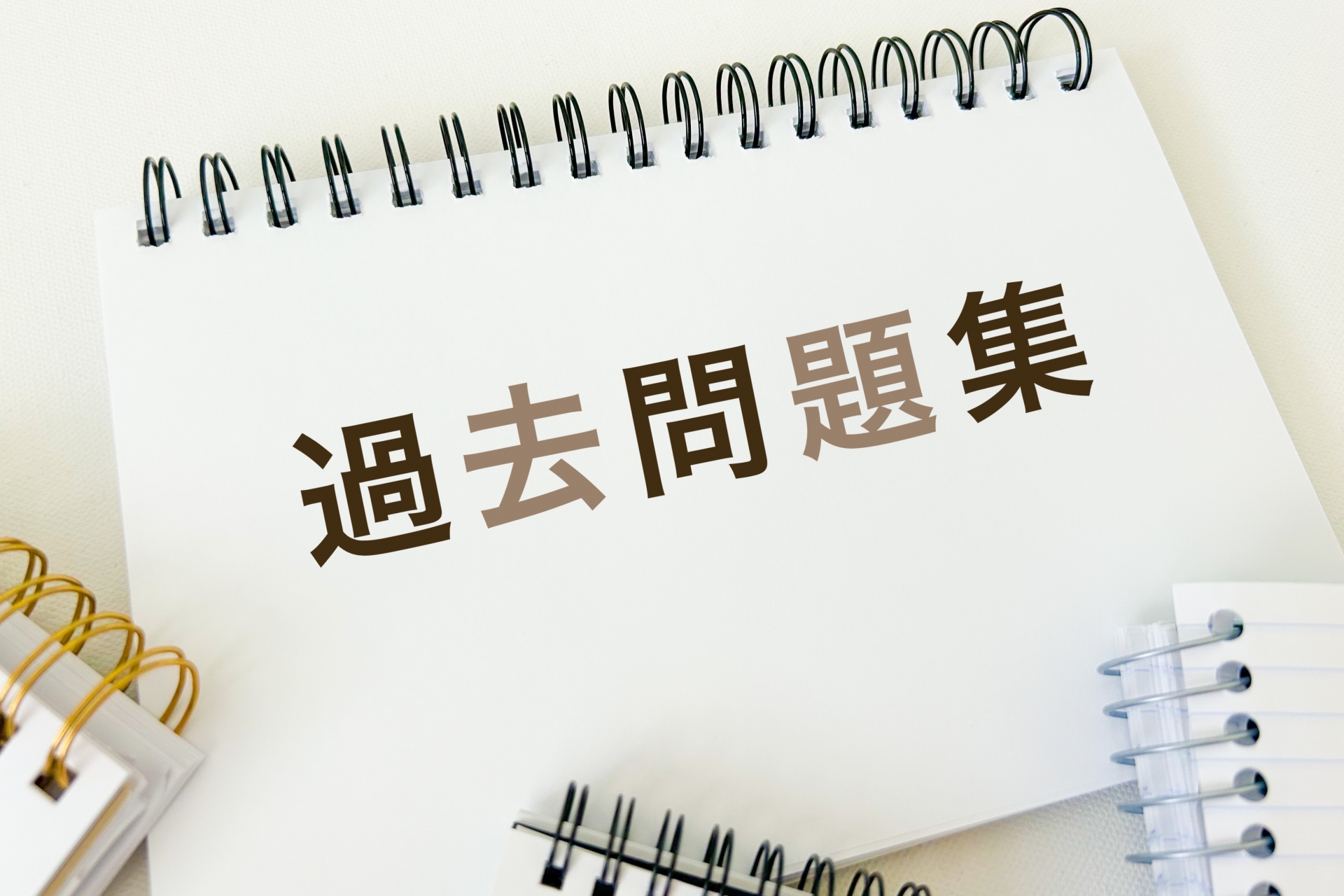
宅建試験合格において過去問は最重要教材であり、これなくして合格は困難と言えるでしょう。
最低でも10年分を3周することで、出題傾向の把握と安定した得点力が身につきます。
私の合格体験からも、過去問を徹底的にやり込むことの効果を実感しています。
ただし過去問だけでなく、テキストでの基礎理解、過去問での実践演習、そして丁寧な復習というサイクルを回すことが合格への王道です。
民法の複雑な条文も、宅建業法の細かい規定も、このサイクルを繰り返すことで必ず理解できるようになります。
「過去問を制する者は宅建を制する」という言葉を胸に、計画的に学習を進めていきましょう。
あなたの宅建合格を心から応援しています。