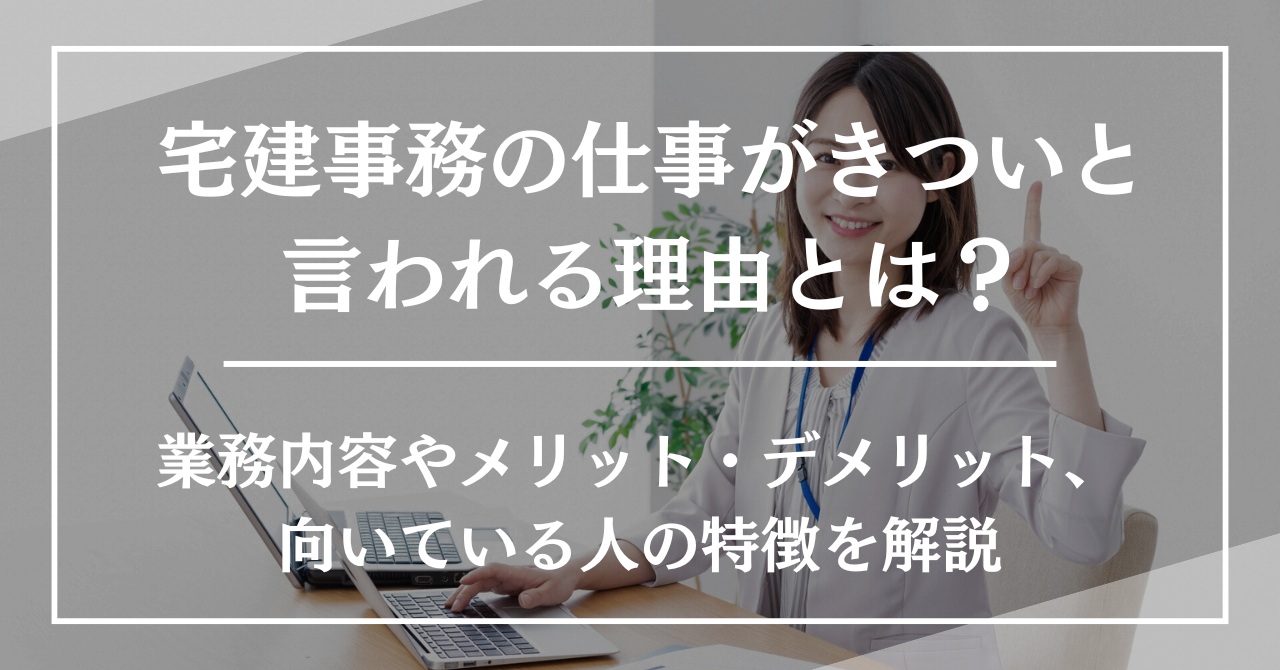※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「宅建事務の仕事はきつい?」
「女性でも宅建事務として働ける?」
「不動産業界のバックオフィス業務に興味がある!」
宅建資格を取得して就職や転職を考えている方の中には、このような疑問を抱えている方も多いでしょう。
そこで本記事では、宅建事務の仕事内容を紹介したうえで、「きつい」と言われる理由、宅建事務として働くメリット・デメリットを解説します。
また、宅建事務に向いている人・向いていない人の特徴も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
宅建事務の業務内容

宅建事務の業務内容はとても幅広いと言えます。
1.独占業務の重要事項説明や契約書の作成
2.データ入稿や写真撮影などの営業サポート
3.電話対応やお茶出しなどのお客様対応
それぞれ解説します。
1.独占業務の重要事項説明や契約書の作成
宅建事務の中核となる業務は、宅建士の資格が必要な重要事項説明書や契約書の作成です。
売買契約や賃貸契約では、金額や条件を正しく反映した書類作成が欠かせません。
ここで誤りがあれば、数千万円単位のトラブルに発展する可能性もあります。
物件価格や引渡し条件、ローン特約など複雑な条項を正確に記載するためには、一定の経験を積むことが必要です。
この業務は宅建士にしかできない独占業務であり、不動産取引の成否を左右する重要な役割を担っています。
▼「不動産業界に興味はあるけれど、まだ宅建を取っていない!」という方は、まず初めにオンライン通信講座を活用することがおすすめです。
![]()
2.データ入稿や写真撮影などの営業サポート
物件情報サイトへの入力・更新作業や、営業担当者の現地撮影サポートなど、契約業務以外でも営業活動の裏方を幅広く担当します。
私の担当エリアでも、新規物件の写真撮影に宅建事務の方が同行し、魅力的な物件写真の撮影をサポートしてもらっています。
また、スーモやアットホームなどの物件サイトへの情報登録も、正確性とスピードが求められる重要な業務です。
営業マンが外回りに集中できるのは、こうした事務サポートがあってこそです。
データ入力のミスは問い合わせ対応に直結するため、細かな作業も手を抜けない責任ある仕事となっています。
3.電話対応やお茶出しなどのお客様対応
来店されたお客様への一次対応、電話の取次ぎ、書類の受け渡しなど、営業マンの接客を円滑に進める基本業務も重要な役割です。
私がお客様との商談中に急な電話が入った際も、宅建事務の方が適切に対応し、商談を中断することなく進められました。
お客様の第一印象を左右する受付対応や、来客時のお茶出しなども、会社の信頼度に関わる大切な業務です。
単純に見える業務ですが、お客様の状況を瞬時に判断し、適切な営業マンへ繋ぐ判断力も必要です。
営業成果の土台を支える、なくてはならない存在として日々感謝しています。
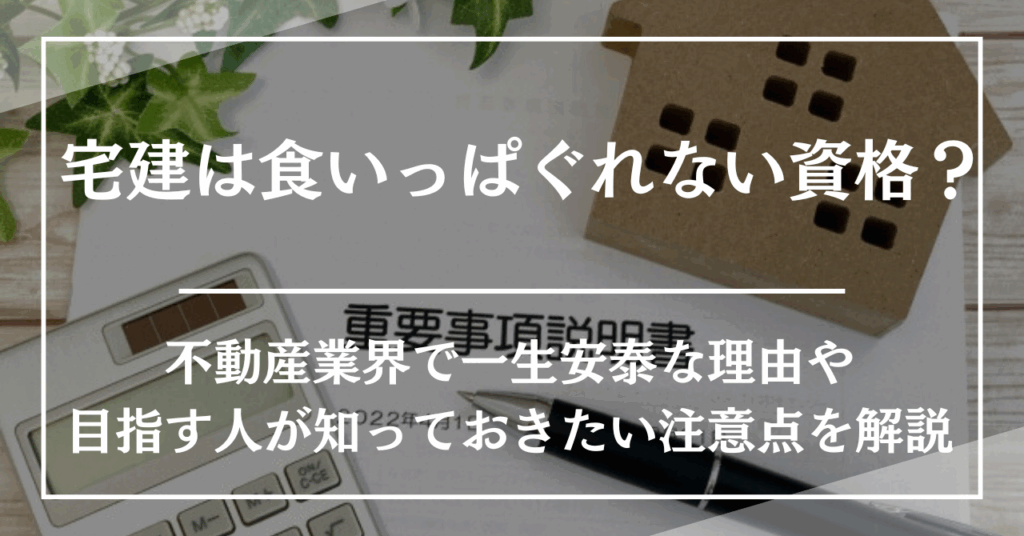
宅建事務の仕事がきついと言われる理由

宅建事務がきついと言われる理由がこちらです。
1.高額取引のため責任が大きい
2.細かいミスも許されない
3.お客様のクレーム対応がある
それぞれ解説します。
1.高額取引のため責任が大きい
不動産取引は1件あたり数千万円から億単位の契約に関わるため、些細な誤字・記載ミスでも重大な損害賠償につながるリスクがあります。
私が知っている事例の中には、契約書の金額記載ミスで数百万円の損失が発生しそうになったケースがあります。
宅建事務は一般的な事務職と違い、ミスの影響が甚大なため、常に高いプレッシャーを感じながら業務を行う必要があります。
この責任の重さが、宅建事務の仕事がきついと言われる最大の理由です。
責任感の強い人ほど、このプレッシャーを強く感じる傾向にあります。
一方で、「裁量権がある仕事にやりがいを感じる!」という方も多いでしょう。
▼そのような方は、求人数No. 1の「宅建Jobエージェント」を活用して、不動産業界への転職を実現しましょう。
![]()
2.細かいミスも許されない
金額・住所・契約条件など、契約書の一字一句が法的に重要な意味を持つため、細かなミスも許されない環境で働く必要があります。
宅建事務をしている私の知人は、「1つの契約書を最低3回は見直すルールを自分に課している」とおっしゃっていました。
住所の番地違いや契約日の記載ミスなど、小さなミスでも契約が無効になる可能性があるため、書類チェックには相当な神経を使います。
完璧を求められる業務環境が、精神的・身体的な負担となる可能性はあります。
3.お客様のクレーム対応がある
契約書の不備や説明不足によるお客様からの問い合わせ・クレームを受けるケースもあり、精神的なストレスを感じる場面があります。
私も営業として同席することがありますが、宅建事務の方が最初に電話対応することが多く、お客様の不満を直接受けることになります。
「重要事項説明で聞いていない条件がある」「契約書の内容が話と違う」といったクレームに対し、冷静に対応する必要があります。
中には「お客様の怒りをぶつけられると、自分のミスではなくても落ち込んでしまう」という方も多いでしょう。
営業とは違う形でのお客様対応スキルが求められるのも事実です。
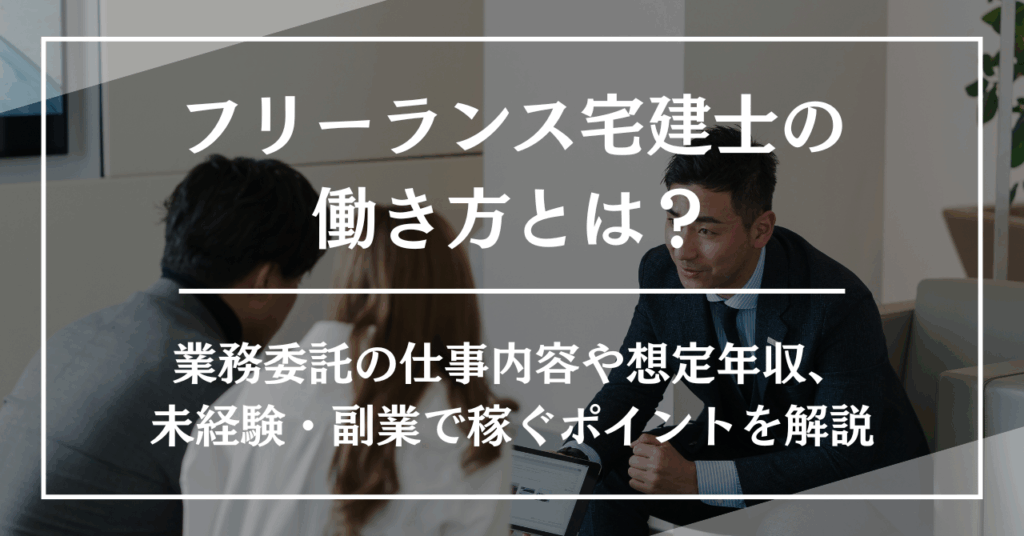
宅建事務として働くメリット

宅建事務として働くメリットは、こちらの3つです。
1.未経験からでも始められる
2.営業数字のプレッシャーがない
3.土日休みの勤務も可能な場合がある
それぞれ解説します。
1.未経験からでも始められる
宅建資格さえあれば実務未経験でも採用されやすく、不動産業界への入り口として選びやすい選択肢であると言えます。
私の職場でも、前職が全く違う業界だった宅建事務の方が複数名活躍していました。
元専業主婦の方は「育児の合間に宅建を勉強していたおかげで、思ったより早く業務に慣れた」と話していました。
営業職と違って契約数などの実績を求められることもなく、資格の知識を活かしながら徐々にスキルアップできる環境があります。
転職エージェントでも「宅建事務は未経験歓迎の求人が多い」と教えてもらいました。
新しい業界へのチャレンジとして、リスクを抑えて始められる魅力的な選択肢です。
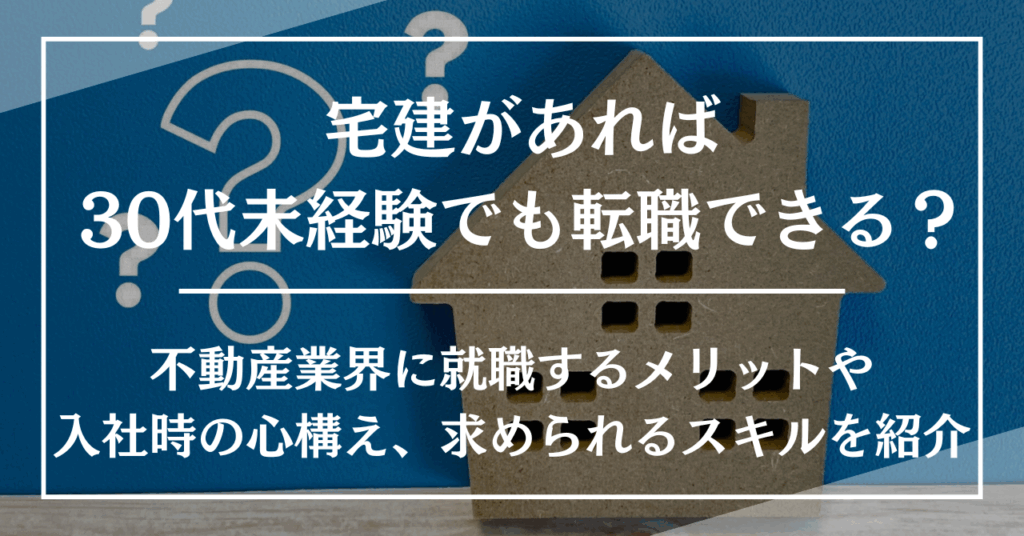
2.営業数字のプレッシャーがない
売上ノルマに追われることがなく、事務作業が中心なので安定志向の人に適した職種です。
私たち営業マンが毎月の契約目標に追われる中、宅建事務の方々は着実に業務をこなすことに集中できる環境にあります。
成果主義のプレッシャーから解放され、専門性を活かして確実に業務を進められる点は大きなメリットです。
精神的な安定を重視する方にとって、働きやすい環境と言えるでしょう。営業の激しい競争環境が苦手な方には最適な職種です。
3.土日休みの勤務も可能な場合がある
営業職は土日出勤が一般的な不動産業界でも、宅建事務には平日勤務の求人も存在し、家庭との両立がしやすい環境を見つけられます。
私の会社でも、平日専門の宅建事務として働く方がいて、「子供の学校行事に参加できるのが嬉しい」と話していました。
土日は営業マンが接客対応を行い、平日に事務処理を集中して行う体制の会社も増えています。
ワークライフバランスを重視したい方、とくに子育て世代には大きなメリットとなります。
全ての会社がこの勤務体系ではありませんが、求人選択時に土日休みの条件で探すことで、理想的な働き方を実現できる可能性があります。
▼たとえば、宅建Jobエージェントでは「土日休み限定」を希望すれば、担当者が条件に合った求人情報を紹介してくれます。![]()
![]()
宅建事務として働くデメリット

一方で、宅建事務として働くためには難しい点やデメリットもあります。
1.宅建資格を持っていないと始められない
2.取引に必要な専門知識の幅が広い
3.年収は営業に比べて決して高くはない
それぞれ解説します。
1.宅建資格を持っていないと始められない
宅建事務として独占業務の経験をしたい方は、まず宅建資格を持っていることが条件となります。
一般的な事務職と違って国家資格が必要という点で、高いハードルがあります。
企業によっては「資格保持者以外の応募は受け付けていない」と明言している求人もあります。
資格取得には半年から1年程度の学習期間が必要で、時間とコストがかかります。
また、合格率15%前後の難関試験をクリアしなければスタートラインに立てません。
ただし、一度取得すれば生涯にわたって活用できる価値ある資格でもあります。
▼これから宅建に挑戦しようとする社会人の方におすすめなのが、スケジュールが柔軟に組めて初学者でもわかりやすいプロ講師の解説が聞ける通信講座です。
![]()
2.取引に必要な専門知識の幅が広い
宅建事務として働いていると、契約書の作成時に民法・借地借家法・税金など、幅広い専門知識が求められる場面があります。
そのため、資格取得後も継続的な学習が必要です。
とくに税制改正や法律の変更に対応するため、5年に一回の頻度で法定講習を必須で受講します。
単純な事務作業ではなく、高度な専門知識を要求される点で、一般的な事務職よりも学習負担が重いのが実情です。
▼重要な法改正については、こちらの最新宅建テキストから学ぶことができます。
3.年収は営業に比べて決して高くはない
歩合給のない固定給メインの給与体系のため、営業職のような大幅な収入アップは期待できません。
営業マンが好成績を出すと年収600万円を超える中、宅建事務の平均的な年収は400万円前後に留まることが多いです。
安定性はありますが、高収入を目指したい方には物足りない水準かもしれません。
お金よりも働きやすさを優先する方には適していますが、収入最優先の方には営業職の方が魅力的でしょう。
キャリアアップによる管理職昇格も営業職ほど多くないのが実情です。
▼不動産業界の職種ごとの年収条件について詳しく知りたい方も、まずは求人数No. 1の「宅建Jobエージェント」への無料登録がおすすめです。
![]()
宅建事務に向いている人の特徴

宅建事務に向いている人の特徴はこちらです。
1.人とのコミュニケーションが好き
2.事務作業に抵抗がない
3.誰かのサポートにやりがいを感じる
それぞれ解説します。
1.人とのコミュニケーションが好き
電話対応や来客対応が日常業務の中心となるため、人との会話や接客が苦にならない性格の方に適しています。
活躍されている宅建事務の方々は、お客様との電話でも明るく丁寧な対応を心がけており、その姿勢がお客様の満足度向上に大きく貢献しています。
「お客様から『ありがとう』と言われると、一日の疲れが吹き飛ぶ」タイプの方には天職と言えるでしょう。
コミュニケーション能力は業務を円滑に進める上で欠かせないスキルであり、この分野が得意な方は大きなアドバンテージを持てます。
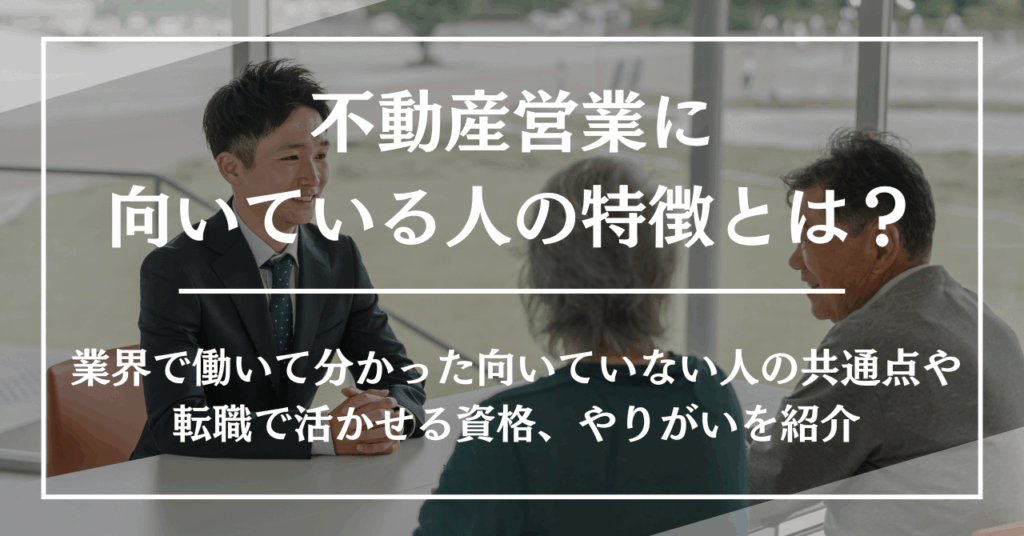
2.事務作業に抵抗がない
契約書作成やデータ入力など、コツコツとしたデスクワークを継続できる集中力と忍耐力が必要です。
私の同僚の宅建事務の方は「細かい作業が好きで、完璧な入稿作業ができたときの達成感が何よりも嬉しい」と話しています。
一日の大半をパソコンに向かって過ごすため、デスクワークに抵抗がない方でないと長続きしません。
正確性を重視し、じっくりと取り組める性格の方には向いている職種です。
逆に、じっとしていることが苦手で常に動き回りたいタイプの方には、ストレスの多い環境になってしまう可能性があります。
3.誰かのサポートにやりがいを感じる
営業マンの成果を裏から支える役割に喜びを感じられる、サポート精神旺盛な方に最適な職種です。
私自身、宅建事務の方々のサポートがあってこそ営業活動に集中でき、契約を獲得できていると実感しています。
私の知人に「営業さんが契約を取れたときは、自分のことのように嬉しい」と話す宅建事務の方がいますが、他人の成功を自分の喜びとして感じられる方には非常に向いています。
チームワークを重視し、縁の下の力持ちとしての役割を楽しめる方には理想的な職場環境です。
▼不動産業界に少しでも興味がある方は、まずは求人数No. 1の「宅建Jobエージェント」に無料登録してみてください。
![]()
宅建事務に向いていない人の特徴

一方で、宅建事務に向いていない人の特徴はこちらです。
1.責任感を感じるのが苦手
2.コツコツ作業するのに抵抗がある
3.自分自身が最前線に出て活躍したい
それぞれ解説します。
1.責任感を感じるのが苦手
不動産業界は高額な商材を扱うため、常にプレッシャーを感じる環境が「辛い」と感じやすい方には適していません。
私が見てきた中でも、責任の重さに耐えられずに短期間で転職していった宅建事務の方が何名かいました。
ミスが許されない環境で、常に緊張感を持って業務に取り組む必要があるため、プレッシャーに弱い方には向いていない職種です。
責任を負うことに対して前向きに取り組める性格でないと、長期的に働き続けるのは困難でしょう。
2.コツコツ作業するのに抵抗がある
データ入力や書類作成がメイン業務となるため、単調な作業を長時間続けることに集中力を保てない方には不向きです。
私の職場でも、「同じような作業の繰り返しで飽きてしまう」と言って営業職に転向した元宅建事務の方がいました。
変化に富んだ業務を求める方や、クリエイティブな仕事を好む方には物足りない環境かもしれません。
また、細かい作業に対する集中力を長時間維持する必要があるため、注意力散漫になりやすい方には適していません。
ルーティンワークを苦痛に感じる性格の方は、他の職種を検討した方が良いでしょう。
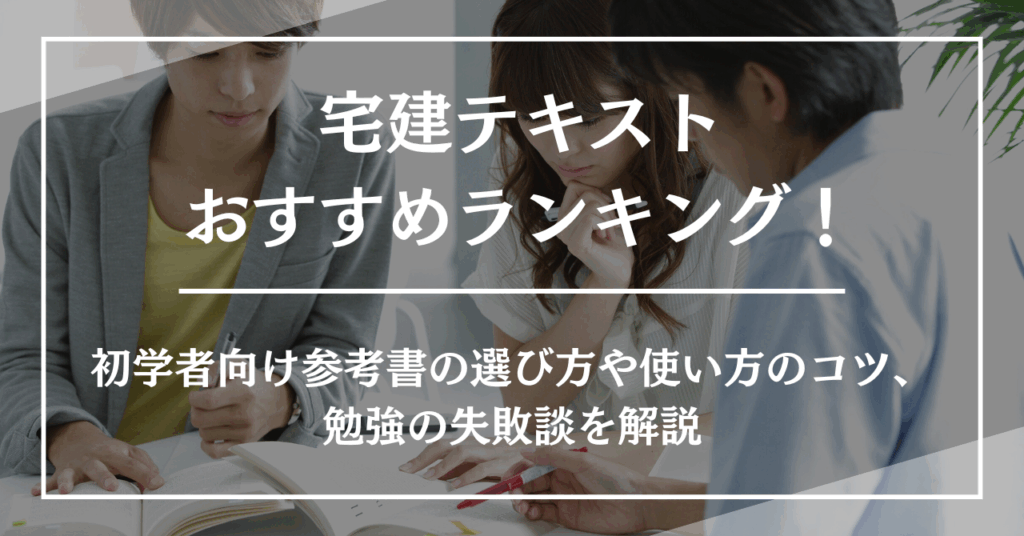
3.自分自身が最前線に出て活躍したい
契約を取って直接評価されたいタイプや、お客様との交渉を楽しみたい方には営業職の方が向いています。
宅建事務は重要な役割を担っていますが、お客様から直接感謝される機会は営業職ほど多くありません。
成果を数字で実感したい方や、自分の営業力で勝負したい方には物足りない環境です。
キャリアアップの選択肢も営業職ほど豊富ではないため、野心的にキャリアを築きたい方には制約を感じる可能性があります。
宅建事務へ転職するまでの流れ

業界未経験の方がこれから宅建事務へ転職する場合、こちらのステップを踏む必要があります。
1.宅建資格を取る
2.転職エージェントに登録する
3.気になる求人に応募してみる
それぞれ解説します。
1.宅建資格を取る
宅建事務への転職には、まず宅建資格の取得が最低限の必要条件となります。
合格率15%前後の難関試験ですが、計画的に学習すれば確実に合格を目指せます。
私の職場の宅建事務の方々に聞くと、「独学で6ヶ月から1年程度の準備期間が必要」との回答が多いです。
法律知識がゼロからでも、毎日2時間程度の学習を継続すれば合格可能な試験です。
通信講座やオンライン学習サービスも充実しており、働きながらでも効率的に学習できる環境が整っています。
資格取得後は生涯にわたって活用できる価値ある資格なので、まずはここからスタートしましょう。
▼独学で一発合格を目指している方は、学習スケジュールが柔軟に組めるオンライン通信講座がおすすめです。
![]()
2.転職エージェントに登録する
不動産業界専門の転職エージェントを活用することで、効率的な転職活動が可能になります。
私の会社でも、優秀な宅建事務の方は転職エージェント経由での採用が多いです。
たとえば、宅建Jobエージェントなどの業界専門のエージェントなら、求人票だけでは分からない会社の雰囲気や詳細な業務内容も教えてもらえます。![]()
履歴書の書き方指導や面接対策も受けられるため、転職成功率が格段に向上します。
▼まずは不動産業界に強いエージェントに登録して、幅広い求人情報を収集することをおすすめします。
![]()
3.気になる求人に応募してみる
大手不動産会社と中小の地域密着型企業では業務内容や待遇に大きな差があるため、複数の会社を比較検討することが重要です。
私の経験上、大手は研修制度やマニュアルが充実している一方、中小企業は幅広い業務経験を積めるメリットがあります。
年収だけでなく、勤務時間や職場環境、将来性なども総合的に判断して、自分に最適な会社を見つけましょう。
実際に面接を受けてみることで、会社の雰囲気や求められるスキルレベルも把握できます。
宅建事務に応募する前に確認すべきこと

宅建事務に応募する前に確認すべきポイントはこちらの3つです。
1.家庭を持っている人は時短勤務もおすすめ
2.大手と地域密着型の不動産会社がある
3.不動産業界に特化した転職エージェントを選ぶ
それぞれ解説します。
1.家庭を持っている人は時短勤務もおすすめ
宅建事務はパート勤務や時短勤務の求人も豊富にあり、ワークライフバランスを重視した働き方を実現できます。
私の職場でも、子育て中の時短勤務で働く宅建事務の方がたくさん活躍しており、「子供の迎えに間に合う時間で働けるのがありがたい」と話しています。
時給も一般的な事務職より高く設定されることが多く、資格の価値を実感できます。
家庭の事情に合わせて柔軟に働ける環境を求める方には、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
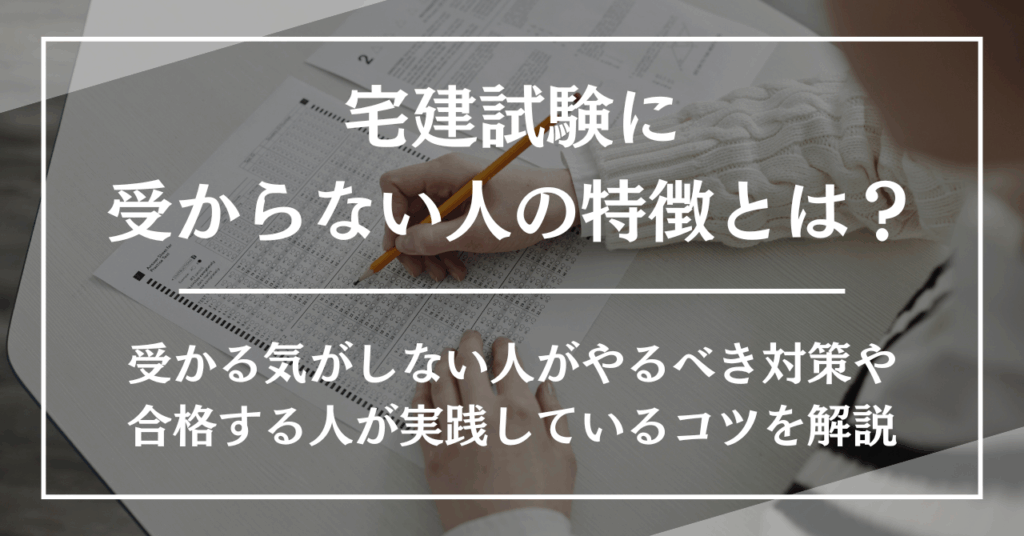
2.大手と地域密着型の不動産会社がある
大手不動産会社はマニュアルや研修制度が整備されている一方、地域密着型の会社では幅広い業務経験を積むことができます。
私が見てきた範囲では、大手は分業制で専門性を高められ、地域密着型は営業サポートから管理業務まで多岐にわたる経験が可能です。
たとえば、三井のリハウスや住友不動産ステップなどの大手では、システム化が進んでおり効率的に業務を行えます。
一方、地元の不動産会社では、お客様との距離が近く、アットホームな環境で働けるメリットがあります。
自分のキャリアプランに合わせて、会社規模を選択することが重要です。
3.不動産業界に特化した転職エージェントを選ぶ
業界特有の求人情報や働き方に関する詳細な情報を得るため、不動産業界専門の転職エージェントの活用をおすすめします。
私の会社で働く宅建事務の方は「宅建Jobエージェントを活用した」とおっしゃっていました。
一般的な転職サイトでは分からない、業界の裏事情や会社の評判なども教えてもらえます。
また、宅建事務特有の悩みや不安にも的確にアドバイスしてくれます。
▼転職成功率を高めるためにも、専門性の高いサポートを受けることが重要です。
![]()
宅建事務がきついと感じるかどうかは人による

宅建事務は、不動産業界特有の責任の重さできつい面もありますが、営業ノルマがなく安定して働けるメリットも大きい職種です。
私が日々接している宅建事務の方々を見ていると、営業職に比べてプレッシャーは確実に少なく、家庭やライフスタイルを優先した働き方を実現している方が多いです。
向き不向きは個人の性格や価値観によって大きく左右されるため、自分の将来設計や働き方の理想と照らし合わせて判断することが重要です。
責任感を持って専門的な業務に取り組みたい方、人をサポートすることにやりがいを感じる方には天職となる可能性があります。
まずは宅建資格取得から始めて、不動産業界での新しいキャリアを検討してみてはいかがでしょうか。