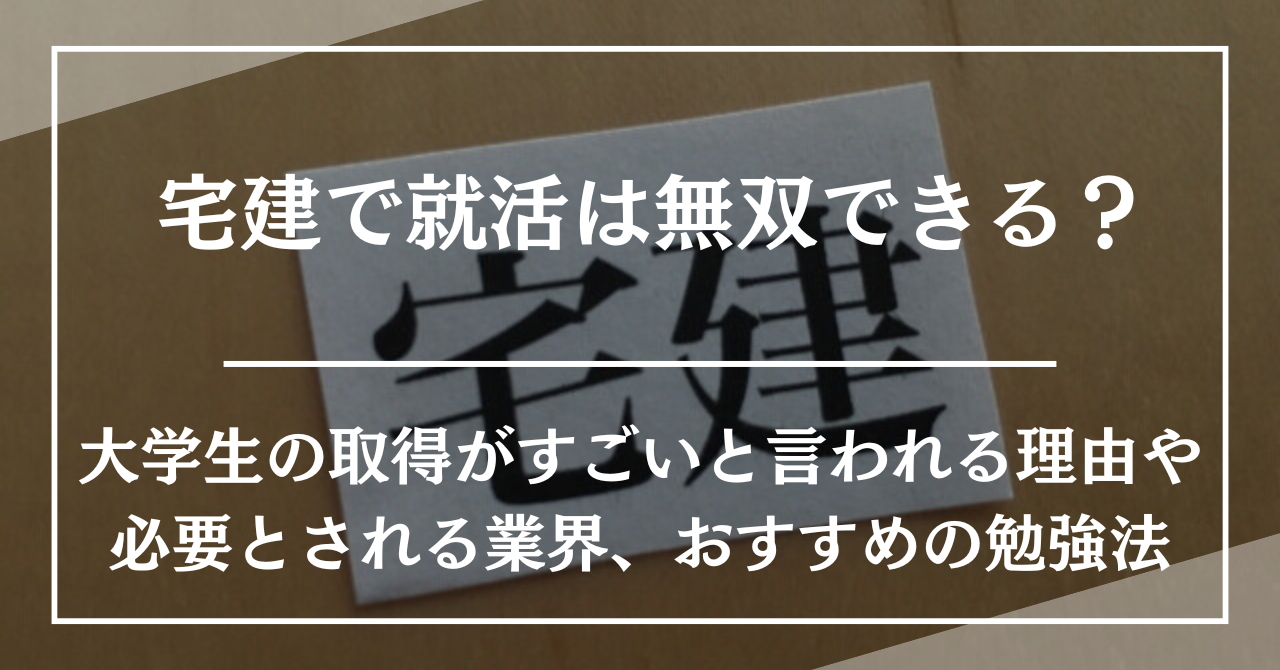※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net、楽天アフィリエイト含む)を掲載しています。
「大学生の宅建取得率はどれくらい?」
「大学生が宅建を取得するメリットは?」
「宅建保有の大学生が就活で無双する業界とは?」
宅地建物の契約前に内容を説明したり、重要事項説明書や契約書に記名押印したりなど、宅建士には不動産業界で重要な独占業務を担当する権利があります。
また、税金制度や法律についての学びを深められることも魅力です。
一方で、「大学生のうちに宅建を取得するのは難しい」と感じる方も多いでしょう。
そこで本記事では、宅建を取得すると就活で無双できる業界や大学生が宅建を取得するメリット、合格のための効果的な勉強法について解説します。
目次
大学生の宅建取得はすごい?

大学生で宅建を取得することは間違いなく「すごい」ことです。
宅建は国家資格の中でも合格率15〜17%前後の難関資格であり、学業と両立しながら合格するには相当な努力と計画性が必要です。
私は大学休学期間中に取得しましたが、就職活動では面接官から「どうやって勉強時間を確保したの?」と必ず質問され、努力・計画性・専門性を具体的にアピールできました。
同世代の就活生で宅建を持っている人は非常に少なく、圧倒的な差別化要素となります。
とくに法学部以外の学生が宅建に合格していると、学習意欲の高さと実行力をより強く印象づけることができます。
この希少性と実用性の高さが、大学生の宅建取得を「すごい」と評価される理由です。
▼ちなみに、大学生の初学者でも図解とイラストで法律関係の知識がしっかり理解できたおすすめのテキストはこちらです。
宅建を取得すると就活で無双できる業界

大学生で宅建を取得すると就活で「無双できる」と言われている業界はこちらの3つです。
1.不動産業界
2.建設業界
3.金融業界
それぞれ理由を解説します。
1.不動産業界
不動産業界では宅建士が法的に必須であり、有資格者は採用段階から即戦力として高く評価されます。
宅地建物取引業法により、事務所ごとに5人に1人は宅建士を置く必要があるため、採用時点で宅建を持っていると圧倒的に有利です。
私も大手不動産会社の面接で「宅建があるなら即戦力だね」と言われ、内定に直結しました。
賃貸仲介から売買仲介、管理会社まで幅広い業務で活用でき、重要事項説明や契約書への記名押印は宅建士にしかできない独占業務です。
新卒から月1〜3万円の資格手当がつく企業も多く、年収ベースで見ると同期より12〜36万円も多くスタートできます。
不動産業界を志望するなら、宅建は必須の武器と言えるでしょう。
また、宅建資格を持っていることで有利になるのは確かですが、自分に合った企業や職種を見極めることも同じくらい重要です。
▼不動産業界専門の転職支援サービスなら、賃貸仲介・売買仲介・管理会社など多様な選択肢の中から、あなたの適性や希望条件にぴったりの企業を紹介してもらえ、資格手当や待遇面も含めた最適なキャリアを築けます。
![]()
2.建設業界
建設業界でも宅建の価値は非常に高く、土地取引や不動産開発に関わる際の専門知識として重宝されます。
大手ゼネコンや住宅メーカーでは、営業職や開発職で「不動産知識がある人材」として差別化できます。
私の友人も建設会社に就職し、宅建の知識を活かして用地取得の交渉で活躍しています。
建設業界は技術系のイメージが強いですが、実際には土地の権利関係や法規制の理解が欠かせません。
宅建で学ぶ都市計画法や建築基準法の知識は、建設プロジェクトの企画段階から直接活用できます。
また、顧客との契約や説明業務でも宅建の知識が信頼獲得につながります。
建設業界での差別化を図りたい学生には、宅建は強力な武器となります。
3.金融業界
金融業界では不動産担保融資や不動産投資商品の提案において、宅建の知識が大きな武器となります。
銀行、信託銀行、保険会社では不動産関連業務が多く、宅建士がいることで専門性の高いサービスを提供できます。
私の先輩も銀行に就職し、住宅ローンの審査や不動産担保評価で宅建の知識を活かしています。
とくにFPや証券外務員と組み合わせると、資産運用の総合的なアドバイザーとして差別化できます。
不動産と金融は密接に関連しており、両方の知識を持つ人材は希少価値が高いと言えます。
金融機関でも資格手当の対象となることが多く、キャリア形成の面でも大きなアドバンテージです。
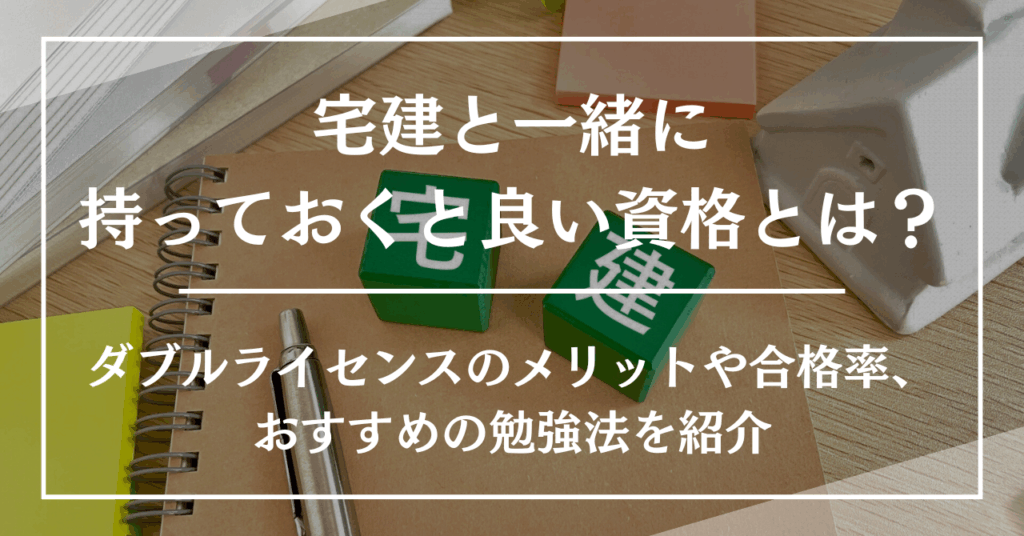
宅建を取得した大学生は就活で無双できる理由

大学生が宅建を取得すると就活で無双できる理由はこちらの3つです。
1.宅建士には独占業務がある
2.不動産業者は宅建士設置の義務がある
3.難関国家資格に合格したという格が付く
それぞれ解説します。
1.宅建士には独占業務がある
宅建士の最大の強みは、法律で定められた独占業務があることです。
重要事項説明や契約書への記名押印は宅建士にしかできない業務で、これが「代替できない資格」としての価値を生み出しています。
他の多くの資格とは違い、宅建士がいなければ不動産取引自体が成立しないため、企業にとって必要不可欠な存在なのです。
この独占性により、景気に左右されにくい安定した需要があります。
AI化が進む現代でも、法的責任を伴う重要事項説明は人間が行う必要があり、将来性も高い資格と言えます。
就活では「なくてはならない資格を持っている」という強いアピールができます。
なお、宅建士の独占業務という強みを最大限に活かすには、その価値を正当に評価してくれる企業を選ぶことが重要です。
▼不動産業界専門の転職支援サービスなら、資格保有者を優遇する企業や、将来性のあるキャリアパスを提供する企業を厳選して紹介してもらえ、あなたの市場価値を最大化できます。
![]()
2.不動産業者は宅建士設置の義務がある
法律により不動産業者は事務所ごとに従業員5人に1人以上の宅建士を置く必要があり、有資格者は採用時点で即戦力として評価されます。
私が内定をもらった会社でも「宅建があるなら新人研修の一部を省けるね」と言われ、スタートダッシュで大きなアドバンテージを実感しました。
また、不動産業者には宅建士の設置義務があるため、常に一定の需要があり、転職市場でも有利に働きます。
新卒採用では同じ能力なら宅建士を優先する企業が多く、内定率向上に直結します。
3.難関国家資格に合格したという格が付く
宅建は合格率15〜17%の難関国家資格であり、合格すること自体が高い能力の証明となります。
とくに独学で合格した場合、自己管理能力と継続力の証明として面接官に強い印象を与えます。
私も面接で「どうやって勉強したんですか?」と必ず質問され、計画的な学習方法を説明することで評価を得られました。
他の就活生と比較しても宅建保有者は圧倒的に少なく、希少性による差別化効果は絶大です。
また、法律系の国家資格は「真面目で責任感がある」というイメージも醸成します。
企業は新卒に対して基礎能力や学習意欲を重視するため、難関資格の取得は最高のアピール材料となります。
なお、難関資格の学習方法をより効率化したい場合は、体系化されたオンライン講座を活用することで、独学では補えない理解の深まりを得られます。
▼中でも、法律系に強い通信講座を提供するサービスなら、自宅で学習を完結させつつ最短距離で実力を引き上げられます。
![]()
大学生が宅建を取得するメリット

大学生が宅建を取得することのメリットは「就活に強い」だけではありません。
こちらのメリットも併せて押さえておきましょう。
1.就職先で資格手当の対象となる
2.実践的な法律知識を身につけられる
3.就職後は勉強時間をなかなか確保できない
それぞれ紹介します。
1.就職先で資格手当の対象となる
宅建を取得すると多くの企業で月1〜3万円の資格手当がつき、新卒から給与に大きな差が生まれます。
私の過去の就職先では月2万円の資格手当があり、年間24万円、30年間で720万円の差となる計算です。
この金額の大きさを考えると、大学生のうちに取得する価値は十分にあります。
とくに不動産業界では資格手当の金額が高く設定されている企業が多く、初任給25万円+資格手当3万円で月28万円からスタートできる場合もあります。
入社後に宅建を勉強する同期と比較して、初月から経済的なアドバンテージが明確に現れます。
また、昇進や昇格の際にも宅建保有者が優遇されることが多く、長期的なキャリア形成においてもメリットは計り知れません。
一方で、資格手当の金額や昇進制度は企業によって大きく異なるため、待遇面を含めて総合的に企業を比較することが重要です。
▼不動産業界専門の転職支援サービスなら、資格手当の金額や昇給制度、キャリアパスまで詳しく教えてもらえ、長期的に見て最も有利な条件の企業を見つけることができます。
![]()
2.実践的な法律知識を身につけられる
宅建で学ぶ民法、借地借家法、不動産登記法などの知識は、社会人になってからも様々な場面で活用できます。
私もマイホームの購入をしたときに、契約書の内容理解や取得に必要な税金知識が大いに役立ちました。
また、とくに民法は日常生活の様々な契約に関わる基本法であり、賃貸契約、売買契約、相続など身近な問題で知識が活かされます。
一度宅建を学習しておけば、就職後の業務理解も早く、新人研修で他の同期より一歩先を行くことができます。
さらに、転職や独立を考える際にも武器となり、キャリアの選択肢を広げてくれます。
実用性の高い法律知識を身につけられることは、宅建取得の大きなメリットです。
3.就職後は勉強時間をなかなか確保できない
社会人になると残業、研修、飲み会などで自由な時間が極端に少なくなり、資格勉強は非常に困難になります。
私の同期も「宅建を取りたいけど時間がない」と嘆いていました。
大学生のうちは比較的自由に時間をコントロールでき、集中的に勉強に取り組める貴重な期間です。
とくに4年生の後期は就活も終わり、卒論以外は時間に余裕があることが多いため、この時期の活用が重要です。
社会人になってから宅建に挑戦する人の合格率は学生より低く、働きながらの勉強がいかに大変かを物語っています。
在学中に取得しておけば、入社後は実務に集中でき、同期より早くスキルアップできます。
限られた学生期間を最大限に活かしたい方は、効率よく理解を深められる法律系通信講座を活用すると、独学より短期間で確実に実力を固められます。
▼中でも体系化されたオンライン学習サービスなら、スマホ一つで計画的に学習でき、社会人になる前に資格取得を現実的な目標にできます。
![]()
大学生が宅建取得のために効果的な勉強法

一方で、大学生は部活に勉強にバイトにとなにかと言って忙しいものです。
大学生活と資格取得の両立を望む方におすすめしたい、合格のための勉強法はこちらです。
1.内定先が決まったらすぐに勉強を開始する
2.内定先の企業が開催する勉強会に参加する
3.YouTubeでスキマ時間を有効活用する
それぞれ解説します。
1.内定先が決まったらすぐに勉強を開始する
内定が決まったタイミングで宅建の勉強を開始することで、入社前に有利なスタートを切れます。
私の友人も内定後すぐに勉強を始め、入社前に合格できたおかげで研修期間を短縮してもらっていました。
一般的に、宅建合格までに必要な勉強時間は300時間から400時間と言われています。
就活が終わってホッとする気持ちはわかりますが、少しでも合格率を上げるために、内定をもらったその日から宅建合格への第一歩を踏み出しましょう。
10月の試験に向けて逆算スケジュールを立て、3〜6ヶ月の準備期間を確保することが重要です。
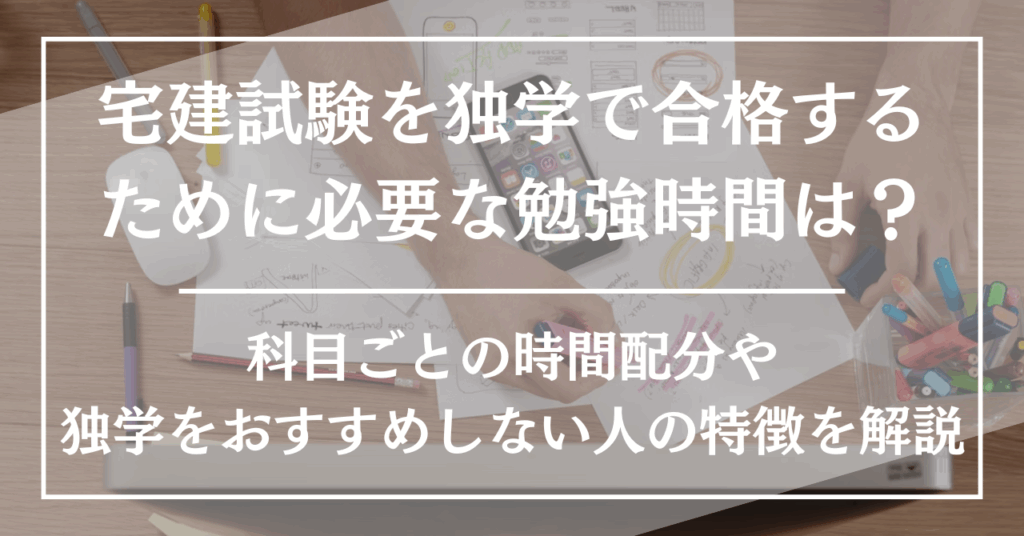
2.内定先の企業が開催する勉強会に参加する
不動産業界や金融業界の企業では、内定者向けの宅建勉強会を開催することが多く、積極的に参加すべきです。
社内外の宅建士が講師となるため、実務に直結した知識を学べるのが大きなメリットです。
勉強会は、過去問の傾向分析や効率的な勉強法など、プロの指導を無料で受けられる貴重な機会です。
また、同期との絆も深まり、お互い切磋琢磨しながら学習を進められます。
同期とのグループ学習により継続しやすく、一人では挫折しがちな長期学習も乗り切れます。
企業によっては合格祝い金や特別手当もあり、モチベーション維持にも効果的です。
▼勉強会に参加する場合でも教材は自前のことが一般的です。私も活用したおすすめテキストはこちらです。
3.YouTubeでスキマ時間を有効活用する
大学生の限られた時間を最大限活用するため、YouTubeでの学習は非常に効果的です。
通学時間、移動時間、空きコマなどのスキマ時間に無料で質の高い解説を聞けるのは大きなメリットです。
私も電車内でイヤホンをして宅建動画を聞き、効率的にインプットを進めました。
とくに民法の複雑な概念や宅建業法の数値暗記などは、繰り返し聞くことで自然と頭に入ります。
コストを抑えたい大学生にとって、無料で学べるYouTubeは強い味方です。
ただし、YouTubeだけでは不十分なので、テキストや過去問との併用が必須です。
スキマ時間を有効活用し、まとまった時間で問題演習を行うという使い分けで、効率的に合格力を身につけましょう。
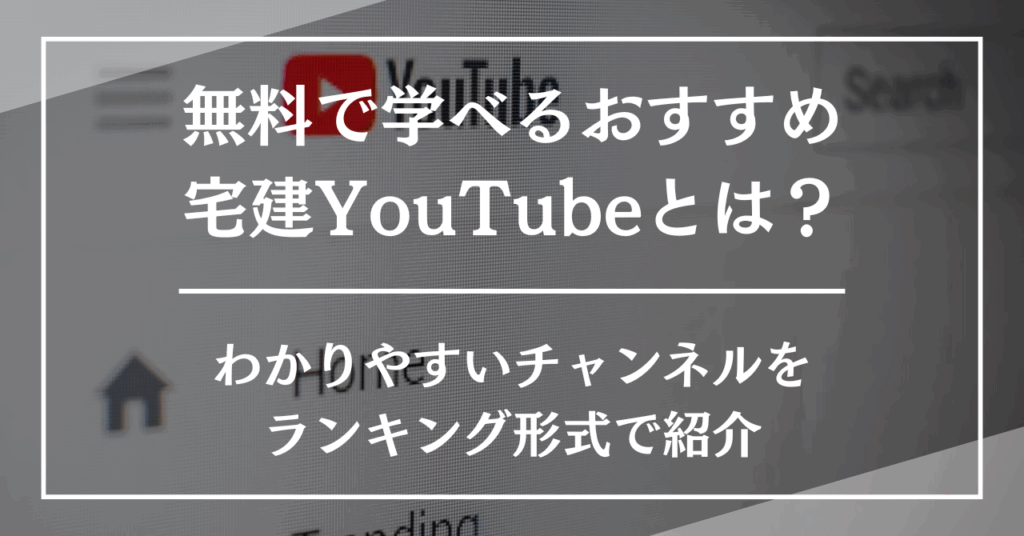
大学生の宅建取得に関するよくある質問

ここでは大学生の宅建取得に関するよくある質問に対して回答していきます。
大学生の宅建取得率はどれくらい?
現在、大学生に限った宅建の合格率、取得率の公表はありません。
ただし、毎年の宅建合格者のうち大学生が占める割合は約10%前後と少数派であることは事実です。
これは挑戦者数が少ないことが主な理由です。
難易度自体は社会人と同じで、むしろ時間に余裕がある大学生の方が有利な面もあります。
私の大学時代の友人で宅建に挑戦したのは私を含めて3人だけでしたが、全員合格できました。
少数派だからこそ希少価値が高く、就活での差別化効果は絶大です。
効率よく合格を狙いたい方は、要点が体系化されたオンライン講座を使うことで、独学よりも短期間で合格レベルまで到達できます。
▼中でも学習設計がしやすい通信型サービスなら、大学生活と両立しながら確実に実力を積み上げられます。
![]()
不動産業界に就職するといくら稼げる?
大手不動産会社では初任給25万円+宅建手当2〜3万円で月27〜28万円からスタートするのが一般的です。
歩合制の営業職なら成果次第で年収500〜1000万円も狙えます。
年収を大幅に上げるためには1件ずつの案件をコンスタントに成約させ続けることがポイントです。
私の先輩も入社3年目で年収600万円を超え、同世代の平均を大きく上回っています。
宅建があることで高収入を得られる可能性が格段に高まります。
また、高収入を実現するには、歩合制度が充実していて成長できる環境がある企業を選ぶことが重要です。
▼不動産業界専門の転職支援サービスなら、年収モデルや歩合制度、実際の社員の収入事例まで詳しく教えてもらえ、あなたの収入目標を実現できる企業とのマッチングをサポートしてくれます。
![]()
宅建は一生有効な資格なの?
宅建試験に合格した事実は一生有効ですが、宅建士として業務を行うには5年ごとの法定講習受講が必要です。
ただし、この講習は形式的なもので負担は軽微であると言えます。
私も更新講習を受けましたが、最新の法改正情報を学べて有益でした。
一度取得すれば基本的には一生活用できる資格と考えて問題ありません。
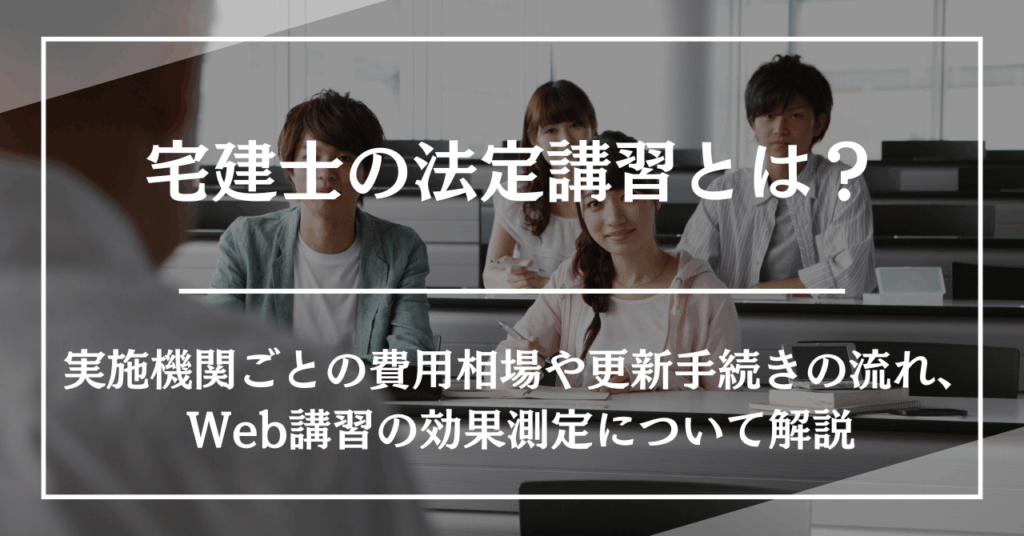
大学生で宅建を取得して有利に就職しよう!

宅建は大学生が挑戦する国家資格の中でも「就活直結度」が最も高い資格の一つです。
不動産業界はもちろん、建設業界や金融業界でも高く評価され、内定率向上と初任給アップの両方を実現できます。
また、宅建士には独占業務と設置義務により安定した需要があり、資格手当による経済的メリットも大きいのが特徴です。
社会人になると勉強時間の確保が困難になるため、時間に比較的余裕のある在学中の取得が断然有利です。
内定後の勉強会参加やYouTube活用など、大学生ならではの効率的な学習法を駆使すれば、合格は十分に可能です。
宅建を武器に就職活動でも入社後のキャリアでも「無双」できる人材を目指し、ぜひ挑戦してください。