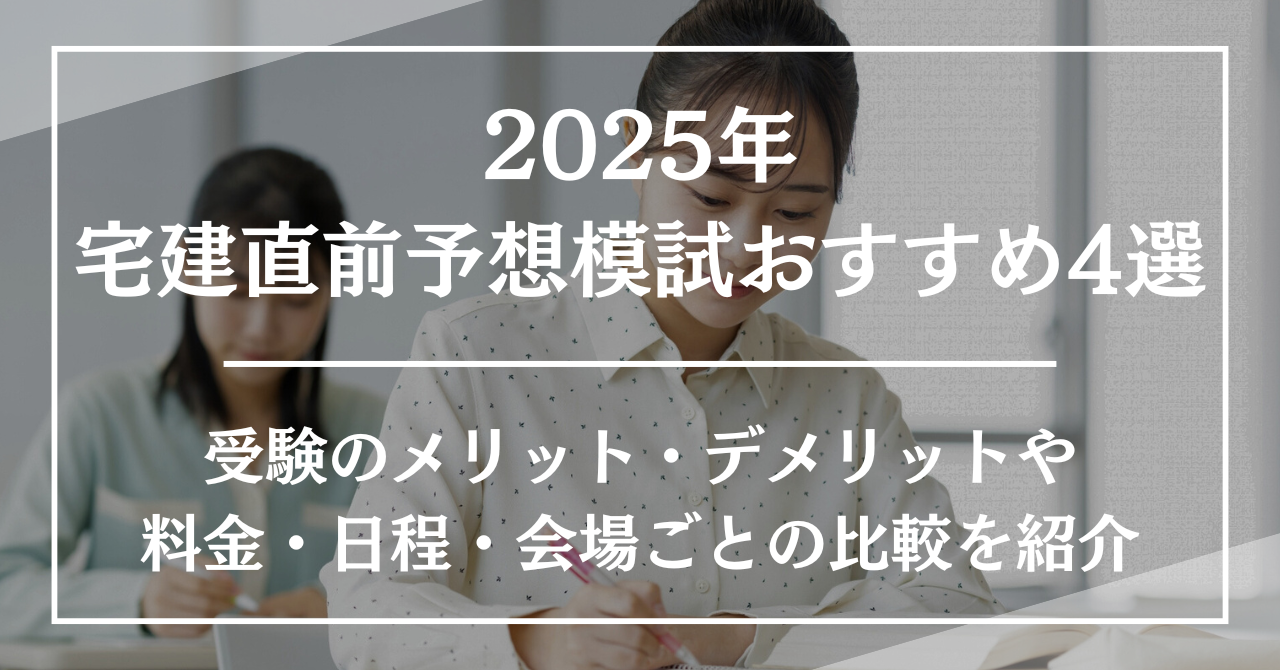※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
「宅建直前予想模試はいくつ受けるべき?」
「自宅受験と会場受験のどちらがおすすめ?」
「宅建直前予想模試は何回受ければ合格できる?」
2025年に宅建試験を受験する方は、宅建直前予想模試で実践力を身につけることがおすすめです。
試験中の時間配分や初めての問題に出くわした場合の対処法をシミュレーションできるためです。
一方で、どの会社の模試を受ければよいか悩んでいる方も多いでしょう。
そこで本記事では、宅建予想模試の種類や受験のメリット・デメリット、おすすめの教材について解説します。
料金や日程、会場ごとに分けて紹介しますので、ぜひあなたのスタイルに合った予想模試を探してみてください。
目次
宅建直前予想模試を受験するメリット

宅建試験の受験予定者が、直前予想模試を受験するメリットは以下の3つです。
1.本試験の形式に触れて緊張感に慣れられる
2.苦手分野を発見して勉強計画が立てやすくなる
3.最新の出題傾向を把握できる
それぞれ解説します。
1.本試験の形式に慣れて緊張が緩和される
宅建の本試験は、制限時間内に多くの問題を解く必要があるため、焦りや緊張で実力を発揮できない人も少なくありません。
直前予想模試では、本番と同じ形式・時間で問題に取り組むため、試験の流れや雰囲気に慣れることができます。
たとえば「問題を解くペース」や「時間配分の感覚」がつかめるようになるため、当日も落ち着いて対応しやすくなります。
本番で実力を出すためには、場慣れしておくことがとても重要です。
なお、本試験形式に慣れるには、模試だけでなく質の高い問題演習と解説講義がセットになった通信講座を活用することも効果的です。
▼オンライン講座なら、本試験レベルの問題を繰り返し解きながら、間違えた箇所を講師の解説動画で即座に復習でき、本番で確実に得点できる実力を養成できます。
![]()
2.苦手分野を発見して勉強計画が立てやすくなる
模試を受けると、自分の得意・不得意な分野が点数や解答時間から明確になります。
たとえば「民法は点が取れるけど、宅建業法は時間が足りない」といった課題に気づくことができます。
これにより、残りの勉強時間をどこに使うべきかがはっきりし、効率的な学習が可能です。
宅建試験は出題範囲が広いため、すべてを満遍なく勉強するのは非効率です。模試を活用して、戦略的な学習を進めましょう。
3.最新の出題傾向を把握できる
宅建試験では、毎年少しずつ出題の傾向が変わることがあります。
直前予想模試は、その年の法改正や出題傾向を反映して作られていることが多いため、本番に近い問題を解くことができます。
たとえば「最近よく出ているテーマ」や「出題のされ方の特徴」を模試で体感できれば、本試験に向けた準備も的を絞って進められます。
最新情報を取り入れた勉強が、合格への近道になります。
2025年の最新法改正については以下のページを参考にしてください。
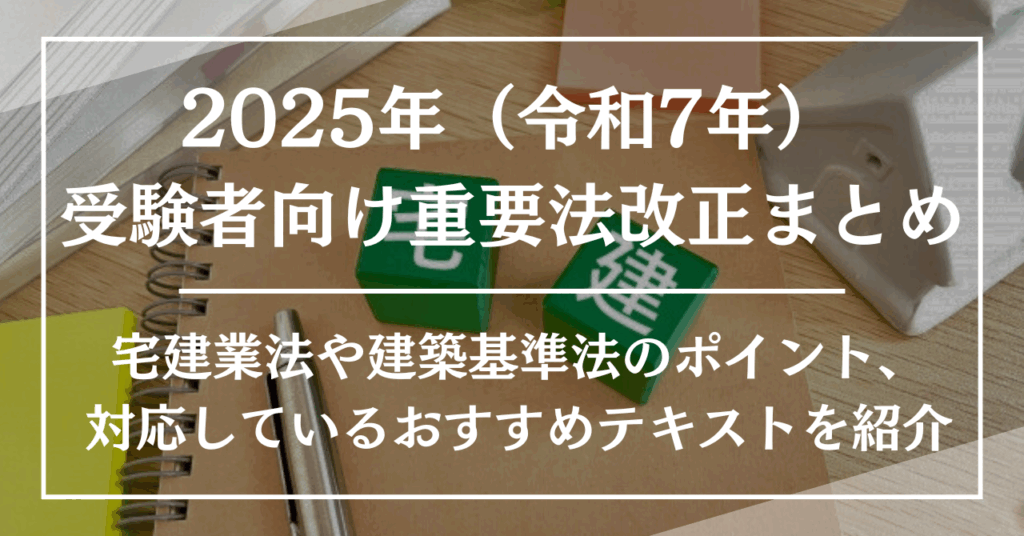
宅建直前予想模試を受験するデメリット
 宅建試験対策として直前予想模試を受験するメリットは多いと言えます。
宅建試験対策として直前予想模試を受験するメリットは多いと言えます。
一方で、デメリットについても把握しておくことが重要です。
1.費用や移動時間などのコストがかかる
2.結果に一喜一憂するとメンタルがブレる
3.宅建試験対策をしていないと問題が難しすぎる
それぞれ解説します。
1.費用や移動時間などのコストがかかる
直前予想模試は、1回当たり3,000円から5,000円ほどの費用がかかることが一般的です。
また、会場受験の場合は交通費や移動時間も発生します。
たとえば地方在住の場合、模試会場まで数時間かかるケースもあり、時間的な負担も考慮しなければなりません。
模試を受ける価値は十分にありますが、予算やスケジュールに余裕があるかを事前に確認しておくことが大切です。
また、費用や移動時間などを最小限にしたい方は、会場受験ではなく市販の予想問題集を活用する方法がおすすめです。
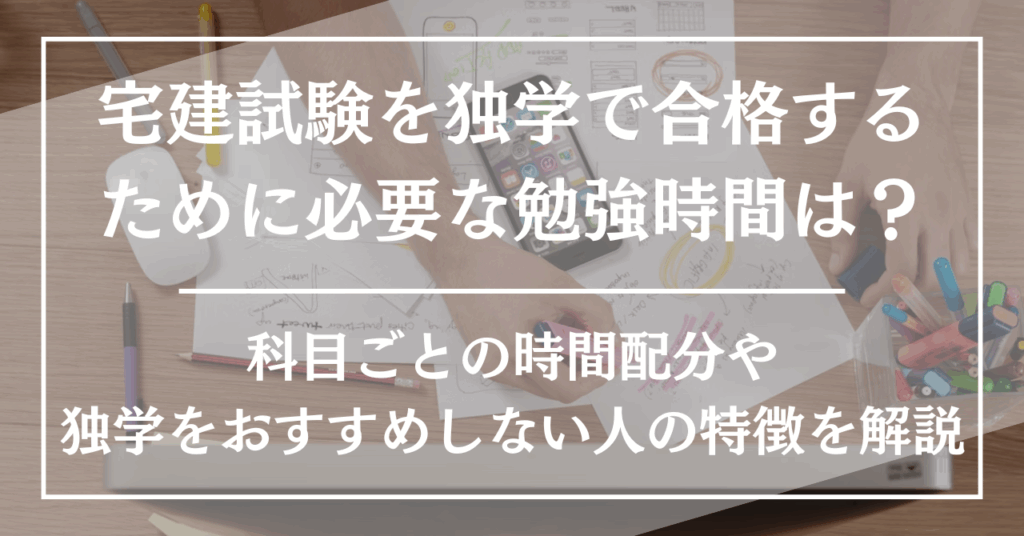
2.結果に一喜一憂するとメンタルがブレる
模試の点数に一喜一憂してしまうと、気持ちが不安定になり、逆に勉強のモチベーションを下げてしまうことがあります。
とくに初めての模試で思うように点数が取れないと、「自分には向いていないのでは」と感じてしまう人もいます。
模試はあくまで現状を知るための材料であり、合格・不合格を決めるものではありません。
結果に一喜一憂せず、冷静に分析する姿勢が大切です。
また、模試の結果に左右されず着実に実力をつけるには、体系的なカリキュラムと充実したフォロー体制がある通信講座で学習することが有効です。
▼オンライン講座なら、定期カウンセリングや質問対応を通じて学習の進捗を客観的に把握でき、メンタル面でもサポートを受けながら合格まで安定したペースで学習を続けられます。
![]()
3.宅建試験対策をしていないと問題が難しすぎる
模試は本試験と同じレベル、あるいはやや難しめに作られている場合が多いため、基礎が固まっていない状態で受けると「まったく解けない」と感じることがあります。
たとえば法律用語が分からず、問題文の意味すら理解できないといったケースです。
模試を最大限活かすには、ある程度の勉強を終えてから受けることが重要です。焦らず準備をしてから臨みましょう。
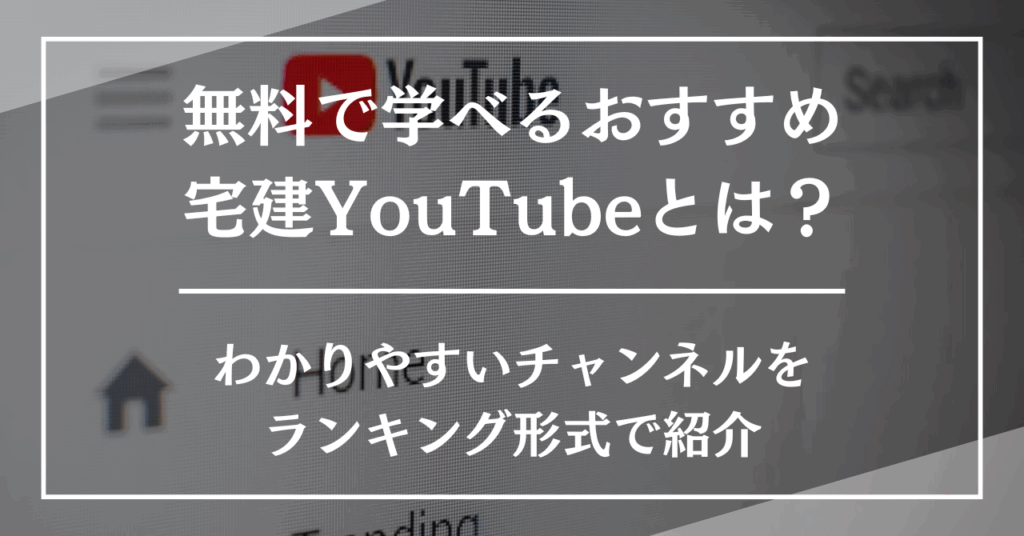
2025年におすすめの宅建直前予想模試4選

2025年受験者におすすめの会場受験、自宅受験可能な宅建直前予想模試はこちらの4つです。
それぞれの試験会場や料金・内容、申し込みについては、各リンクからご確認ください。
2025年におすすめの宅建直前予想問題集3選

2025年受験者におすすめの宅建直前予想問題集を3つ紹介します。
1.2025年版出る順宅建士当たる!直前予想模試(LEC出版)
2.本試験をあてるTAC直前予想模試宅建士2025年度版(TAC出版)
3.みんなが欲しかった!宅建士の直前予想模試2025年度版(TAC出版)
実際の体験談や口コミを踏まえて、それぞれの教材の魅力や詳細を解説します。
1.2025年版出る順宅建士当たる!直前予想模試(LEC出版)
▲画像をタップすると商品詳細ページに移行します。
LECの定番シリーズ「出る順宅建士」の直前予想模試は、過去問を徹底分析したうえで本試験の出題傾向を的確に反映しているのが大きな特徴です。
難易度も本試験レベルに調整されているため、本番同様の緊張感を持って取り組めます。
実際の受験生からも「問題の質が高く、解説が理解しやすい」「試験直前の実力チェックに最適」との口コミが多数寄せられています。
解説には重要ポイントが簡潔にまとめられており、知識の抜け漏れを確認しながら効率よく学習可能です。
▼直前期の総仕上げとして、本試験さながらの模試を体験したい人に特におすすめの一冊です。
2.本試験をあてるTAC直前予想模試宅建士2025年度版(TAC出版)
▲画像をタップすると商品詳細ページに移行します。
「本試験をあてる」の名の通り、的中率の高さで毎年人気のTAC直前予想模試です。
最新の法改正や出題傾向を踏まえた予想問題が収録されており、受験生からも「過去に実際の試験で出た!」という声が多く寄せられています。
問題量が多く、複数回分の模試を解くことで本番の時間配分や解答スピードを磨けるのも魅力と言えます。
さらに詳細な解説が付いているため、解いた後に知識を整理し直すのに最適です。
「一度はTAC模試を解いておくべき」と言われるほど定評があり、直前期に本試験対応力を強化したい方には欠かせない定番の予想模試となっています。
▼すでに別の直前模試を受験している方でも、後悔が残らないように試験までに一度挑戦しておくことがおすすめです。
3.みんなが欲しかった!宅建士の直前予想模試2025年度版(TAC出版)
▲画像をタップすると商品詳細ページに移行します。
初学者から経験者まで幅広い受験生に支持されているのが、TAC出版の「みんなが欲しかった!」シリーズの直前予想模試です。
特徴は何といっても丁寧でわかりやすい解説と言えます。
重要論点をかみ砕いて説明してくれるため、苦手分野の理解を深めやすく、知識の整理に役立ちます。
受験生の口コミでも「解説が親切で復習がしやすい」「弱点補強に最適」と高評価を得ています。
模試の難易度も程よく設定されており、基礎を確認しながら実戦形式で取り組める点も安心です。
▼直前期に「最後の総復習をしっかり行いたい」「自信を持って本番に臨みたい」という方におすすめできる一冊です。
宅建直前予想模試に関するよくある質問
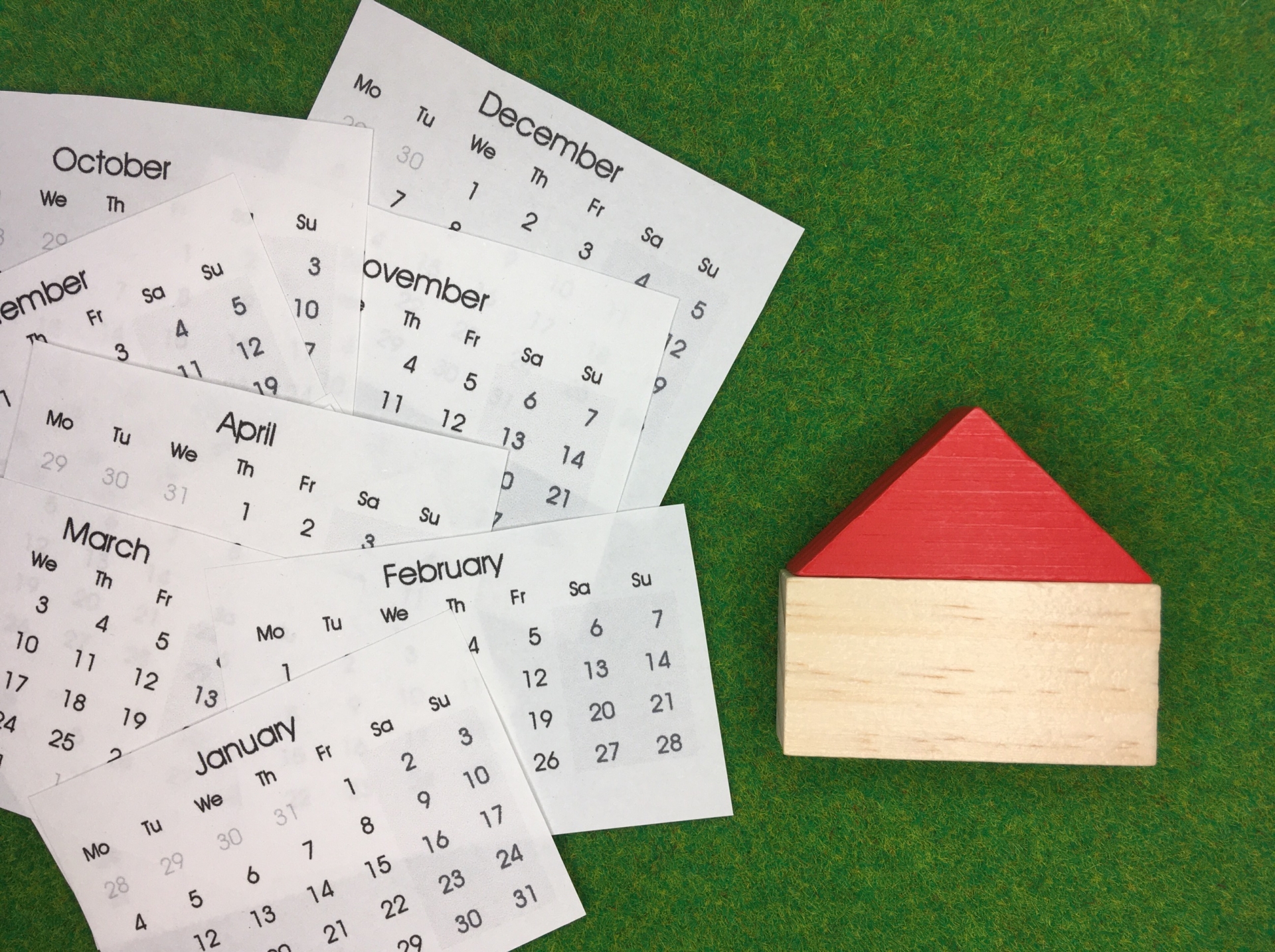
ここからは、宅建直前予想模試に関するよくある質問について回答していきます。
宅建直前予想模試はの会場受験はいつ開催されていますか?
宅建直前予想模試の会場受験は、例年9月中旬〜10月上旬にかけて実施されることが多いです。
大手予備校(LEC、TAC、日建学院など)が複数日程を用意しているため、都合のよい日を選びやすいのが特徴です。
ただし、申込は定員制で早めに締切ることもあるため、公式サイトでスケジュールを早めに確認することが重要です。
「宅建 模試 会場 2025」などで最新情報を検索しましょう。
宅建直前予想模試は何回受けるべきですか?
宅建直前予想模試は、少なくとも1回、多くて2〜3回受けるのがおすすめです。
1回目は現状把握、2回目以降で改善点を試す目的があります。
予想模試は内容がやや難しめに作られていることもあるため、繰り返し受けることで実践力や時間配分の感覚が磨かれます。
また、複数の模試を比較することで最新の出題傾向にも対応しやすくなります。
宅建直前予想模試を選ぶときの注意点はありますか?
模試が出版された時期によっては法改正に対応していない古い問題が含まれているケースもあります。
必ず表紙に「2025年度対応」と明記されたものを選びましょう。
また、宅建模試を選ぶ際は、「本試験に近い形式・難易度かどうか」を重視しましょう。
予備校ごとに問題のクセや難易度が異なるため、過去の受験者の口コミやレビューを確認するのも有効です。
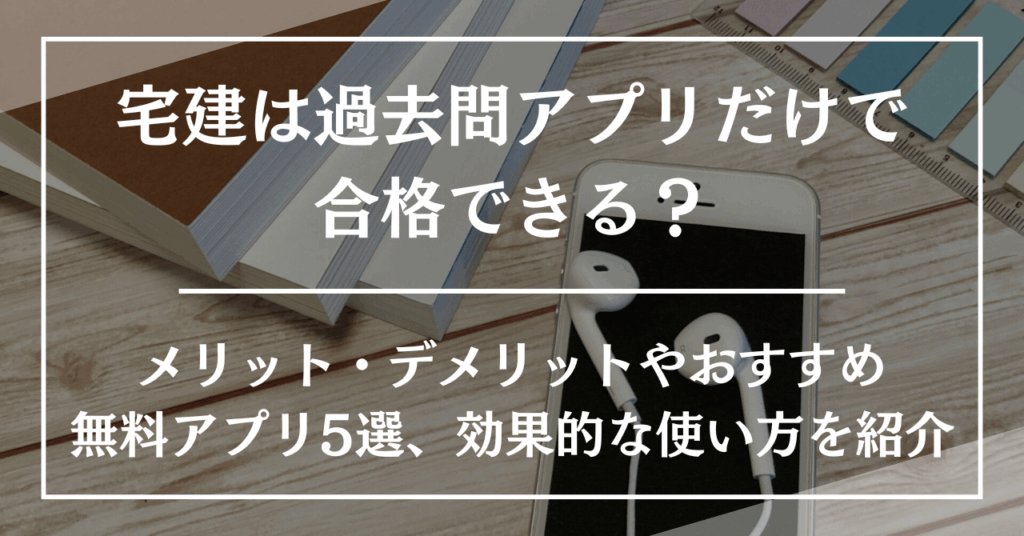
宅建直前予想模試の後にやるべき勉強法
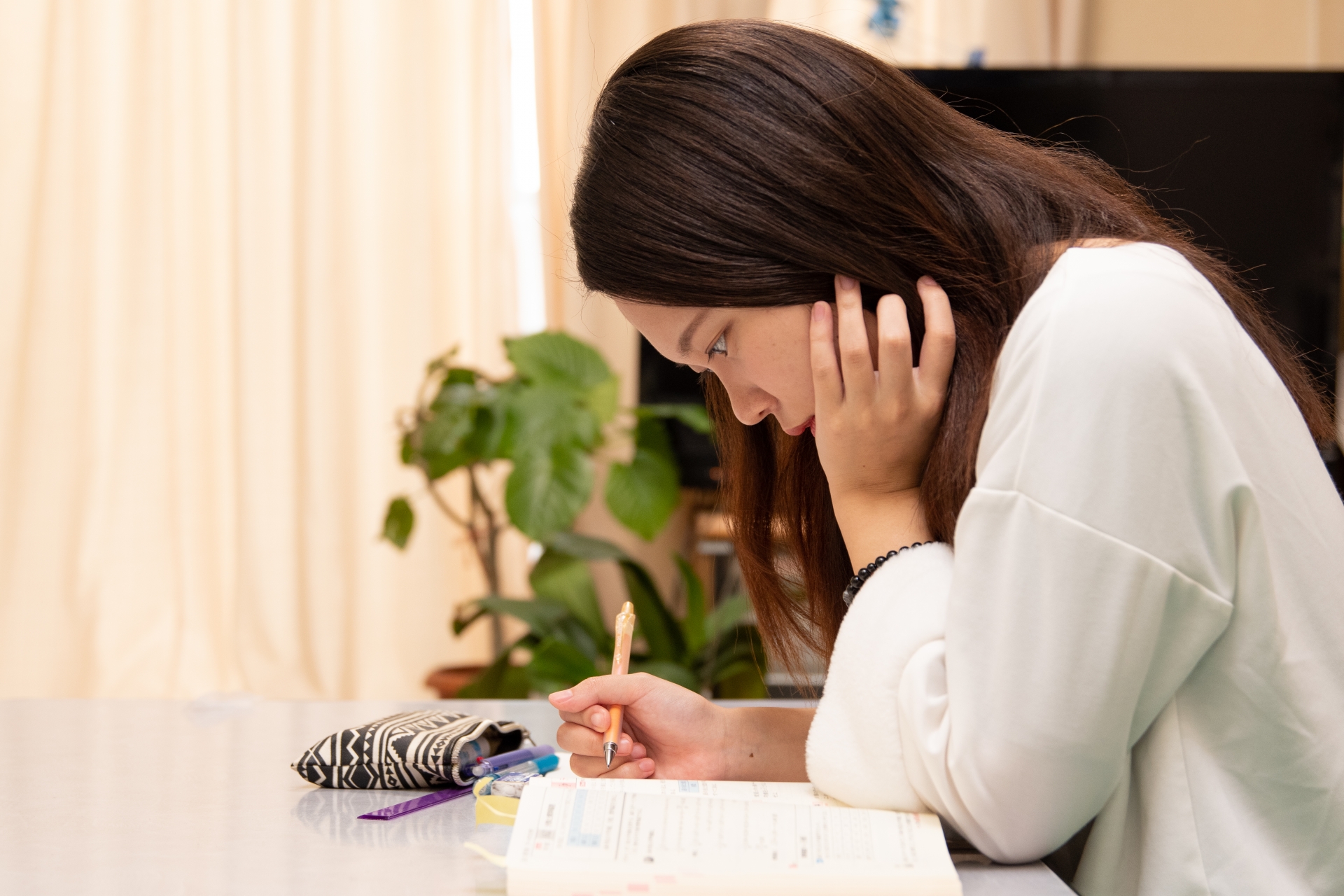
宅建直前予想模試を受験して、その結果で一喜一憂する方は多いですが、それは危険信号です。
模試を活用して本試験対策にどれくらい落とし込めるかが重要になってきます。
こちらは3つのおすすめの勉強法です。
1. なんとなくで解いた問題を復習する
2.間違えた分野から苦手をつぶしていく
3.分野ごとの時間の使い方を見直す
それぞれ解説します。
1. なんとなくで解いた問題を復習する
模試を受けた後、「たまたま正解した問題」や「なんとなく答えた問題」を放置してしまうのは危険です。
本試験では確実な理解が求められるため、曖昧な知識は今のうちに固めておく必要があります。
根拠があいまいな問題は試験中にチェックを入れて、試験後に必ず見直しできるようにしておきましょう。
また、模試で正解だったとしても、「なぜ正解だったのか」「他の選択肢はなぜ違うのか」を確認しましょう。
曖昧な知識を確実な理解に変えるには、問題の解説だけでなく、背景知識まで丁寧に説明してくれる教材を活用することが重要です。
▼オンライン講座なら、一問一問に対する詳しい解説動画や、講師への質問機能を通じて、「なぜその答えになるのか」を深く理解でき、本試験で応用が利く確かな実力を身につけられます。
![]()
2.間違えた分野から苦手をつぶしていく
模試の結果から、自分が間違えた問題の分野を分析することで、効率よく苦手を克服できます。
たとえば「法令上の制限」や「権利関係」で点数が伸びていない場合は、その分野に絞って集中的に復習するのが効果的です。
「宅建試験の直前になって焦って全範囲をやり直す」のはとても非効率な勉強法です。
一方で、点数が取りにくい箇所を優先的に補強することで、限られた時間で合格ラインに届く可能性が高まります。
「大きなマイナスを作らない」ことが合格への近道と言えます。
3.分野ごとの時間の使い方を見直す
宅建試験は50問を2時間で解くため、時間配分の工夫が合否を分けることもあります。
模試で時間切れになったり、焦ってミスをした場合は、解く順番や各分野にかける時間を見直しましょう。
たとえば「宅建業法はスピード重視」「権利関係は後回し」など、自分に合った順番を模索することが重要です。
本番で焦らないためにも、模試を通じて自分のペースを確立し、安定して得点できるスタイルを作っておきましょう。
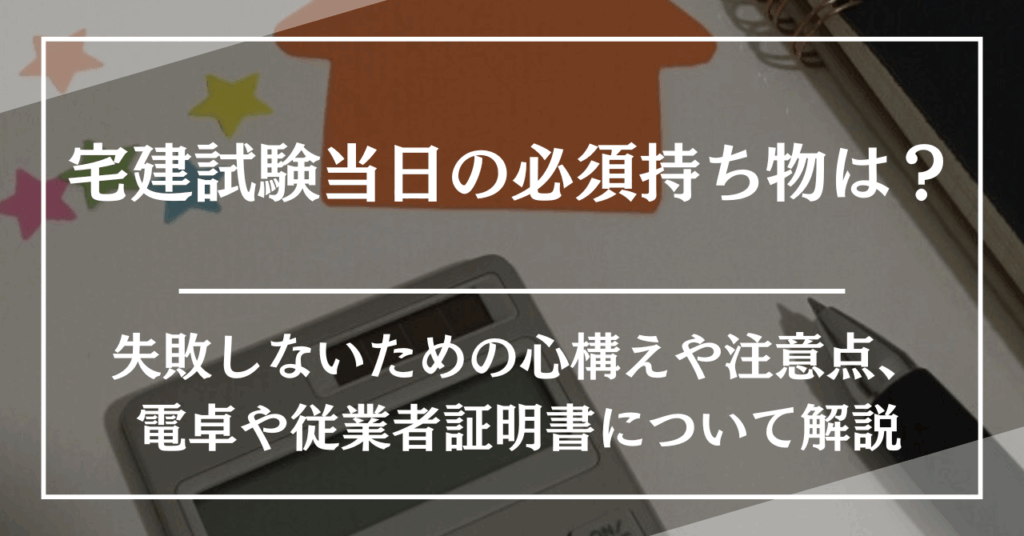
宅建直前予想模試で実践力を磨こう!

宅建試験の合否を左右するのは、知識量だけでなく「本番で発揮できる実践力」です。
直前予想模試は、本試験と同じ形式・時間配分で取り組めるため、試験本番に近い環境で実力を試す絶好の機会です。
しかし、模試は受けただけでは意味がありません。
復習で曖昧な知識を補強し、苦手分野を把握して重点的に学習することが重要です。
さらに、時間配分や解く順番も模試を通じて見直しましょう。
模試を活かして実践力を磨くことで、宅建試験本番でも落ち着いて問題に取り組めるようになります。
残りの時間を有効活用し、合格を確かなものにしましょう。