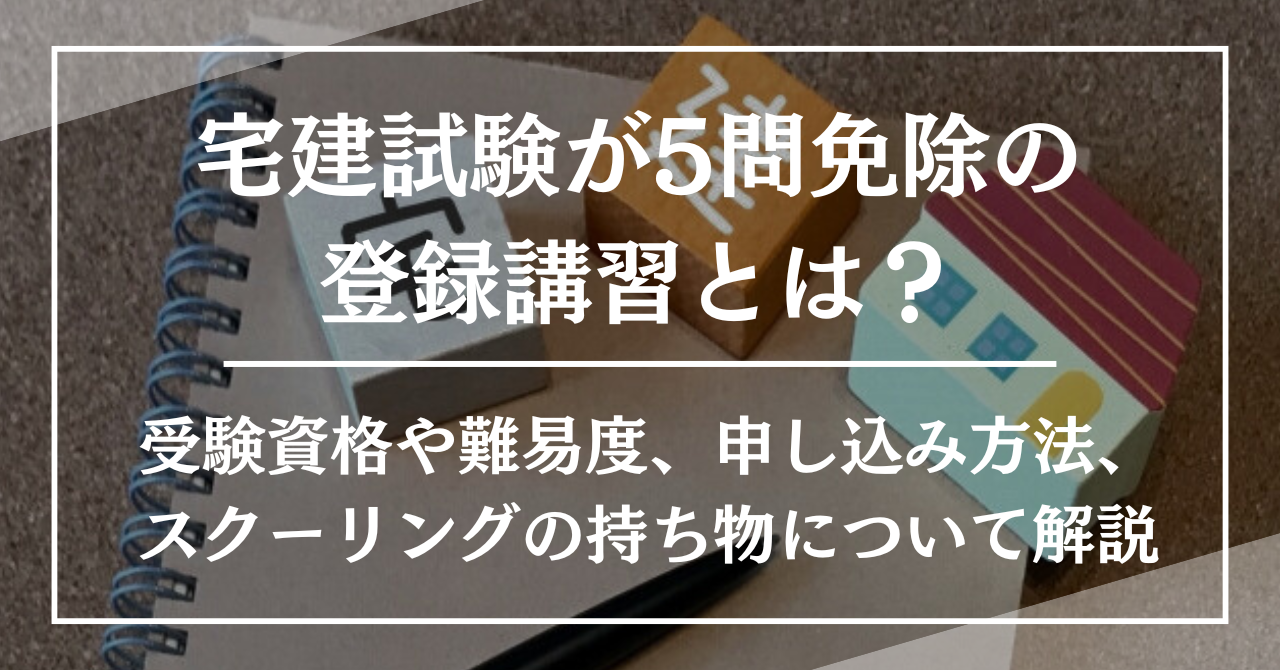※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net、楽天アフィリエイト含む)を掲載しています。
「宅建試験が5問免除になるずるい講習があるってホント?」
「受験料が高いのに登録講習を受講するメリットはある?」
「スクーリングに必要な持ち物や学習のポイントは?」
宅建試験は合格率16~18%で推移する難関試験の一つです。
合格への近道として50問中5問を免除扱いする登録講習に魅力を感じる受験者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、登録講習の受験資格やメリット、難易度について解説します。
また、登録講習を実施している機関やスクーリングの持ち物などについても紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
宅建5問免除の登録講習とは?

宅建試験で出題される50問のうち、登録講習を修了することで5問が免除されます。
特に独学では対策が難しい分野が含まれるため、受験者にとって大きなメリットです。
ただし、講習は誰でも受けられるわけではなく、受講資格が定められています。
これからその条件や内容を詳しく解説します。
登録講習の受験資格
登録講習は、以下のような「宅建業に従事している方」が対象です。学生や未経験者は受講できません。
1.宅建業者に所属している(正社員・契約社員など)
2.受講時点で宅建業に従事している
3.登録講習機関が求める証明書類を提出できる
たとえば、不動産会社に勤めている営業職の方であれば、基本的に受講可能です。
申込時には「従業者証明書」などの提出が求められることが多いため、事前に勤務先へ確認しておきましょう。
登録講習の学習内容やカリキュラム
登録講習は、宅地建物取引業法第16条第3項に基づいた講習です。
宅建試験の出題範囲のうち、免除対象となる5問分の内容を重点的に学習します。
具体的な学習内容については以下の通りです。
1.宅建業法・都市計画法・建築基準法などの関連法令
2.民法・借地借家法を基にした取引トラブルの防止知識
3.土地・建物の種類、構造、地積などの基礎知識
4.不動産の需給に関する統計や市場動向
5.宅地・建物の調査対象や調査手法に関する知識
6.不動産取引に関わる税金(登録免許税・不動産取得税など)
法律や税に関する知識が中心で、独学では難しい分野が多く含まれます。
また、学習教材やカリキュラムのタイトルなどは実施機関ごとに異なります。
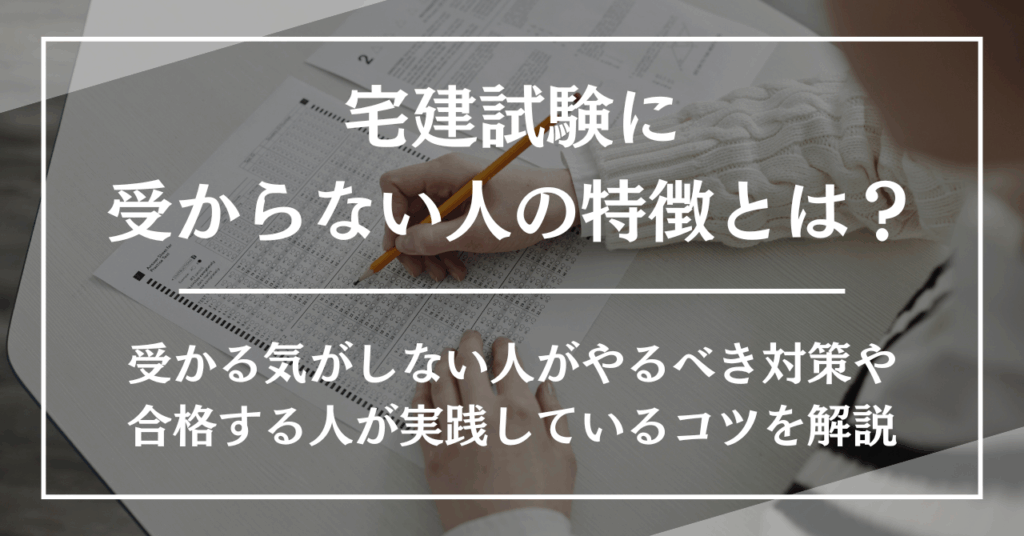
登録講習のスケジュール
登録講習は、「通信学習」と「スクーリング(対面学習)」の2部構成で進められます。
全過程を修了し、最終試験に合格すると修了証が交付され、その後3年間の宅建試験では5問免除が適用されます。
| カリキュラム | 学習内容 | 時間目安 |
|---|---|---|
| 1.通信学習 | 教材による自宅学習 | 2ヵ月程度 |
| 2.スクーリング | 講師による対面授業 | 1日~2日 |
| 3.修了試験 | 4択式の学科試験(20問) | 60分程度 |
スクーリングは1日~2日での完結型が多く、土日開催も豊富です。
社会人でもスケジュールを調整しやすく、働きながらの受講できます。
また、宅建合格のためには残り45問で確実に得点するための基礎学習も並行して進めることが重要です。
▼オンライン通信講座なら、通勤時間やスキマ時間を活用して効率的に学習でき、登録講習と組み合わせることで合格率を大幅に高めることができます。
![]()
登録講習を受講するメリット

登録講習を受講するメリットは以下の3つです。
1.宅建試験の「その他関連知識」が5問免除
2.修了試験の難易度が高くない
3.宅建試験対策になる
それぞれ解説します。
1.宅建試験の「その他関連知識」が5問免除
登録講習を修了すると、宅建試験のうち「その他関連知識」と呼ばれる5問分が3年間免除されます。
これは、主に税金や建築関連法など、出題範囲の中でも難解で苦手とする人が多い分野です。
実際に、宅建試験に合格した人の中には「この5問があったら落ちていたかも」と話す方もいます。
たった5問と思うかもしれませんが、合格ラインが例年7割前後(35点前後)であることを考えると、5問免除は合否を分ける重要なアドバンテージになります。
勉強時間や精神的負担を軽減できるのも大きな魅力です。
▼「その他関連知識」の全体像や難易度がわからない方は、ぜひ一度過去問を解いてみてください。
2.修了試験の難易度が高くない
登録講習の最後には修了試験がありますが、その難易度はそれほど高くありません。
基本的には講習で学んだ内容から出題され、選択式の形式(4択問題)で行われます。
出題数は20問程度で、合格基準も7割以上とされています。
受講者のほとんどが初回で合格しており、万が一不合格になっても再試験を実施してくれる機関が多いです。
独学で挑む宅建本試験に比べるとプレッシャーは低く、しっかり受講していれば問題なくクリアできる内容です。
安心して受講に臨めるのも、登録講習のメリットのひとつです。
3.宅建試験対策になる
登録講習の内容は、宅建試験と重なる部分が非常に多く、実はカリキュラム全体の約80%が本試験の出題範囲に含まれます。
たとえば、宅建業法や民法、不動産に関わる法律などが中心で、講師の解説を通じて基礎から学べるため、独学での理解が難しい人にも向いています。
通信学習だけでなく、対面やオンラインによるスクーリングもあり、短期間でも効率的に理解を深められる設計です。
つまり登録講習は、5問免除のためだけでなく、本試験の基礎固めとしても非常に効果的であると言えるため、試験前の準備として活用する価値は十分にあります。
また、登録講習で基礎を固めた後は、残りの出題範囲を体系的にカバーし、過去問演習まで充実した通信講座で総仕上げをすることが重要です。
▼オンライン講座なら、登録講習では扱わない分野も含めて全範囲を効率的に学習でき、倍速再生やスキマ時間学習などの機能を活用して、働きながらでも無理なく合格力を養成できます。
![]()
登録講習の実施機関と受験料

令和7年2月20日時点で国土交通大臣の認定を受けた登録講習機関は25社あります。
各社の講習会場、受験料、特長や口コミはそれぞれ異なり、自身の勤務場所や日程に合った機関を選ぶことが重要です。
以下に代表的な機関の情報を整理しました。
| 会社名 | 会場(主な開催地) | 受験料(税込) | 特徴・口コミ | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 東京リーガルマインド(LEC) | 全国24拠点(札幌~那覇) | 18,000円 | ・全国展開で通いやすい ・平日・土日開催豊富 |
公式サイト |
| TAC株式会社 | 都心主要都市(東京・大阪・名古屋等) | 19,000円 | ・駅近教室多数 ・広範な日程と早割あり |
公式サイト |
| 総合資格学院 | 東北~九州に多数会場 | 16,000円 | ・コスパ重視の方に◎ ・再受講制度あり |
公式サイト |
| 日建学院 | 全国47都道府県で開催 | 15,000円 | ・地域密着型 ・受験料が比較的安価 |
公式サイト |
| 日本宅建学院 | 東京、大宮、横浜、名古屋、大阪 | – | ・宅建専門スクール ・初心者に優しい授業設計 |
公式サイト |
(※受験料についての詳細や最新のスクーリング日程は各機関サイトで確認をお願いします。)
上記のように、受験料や会場へのアクセスの良さ、日程などを比較することで、自分のライフスタイルに最適な機関を選びやすくなります。
その他の実施機関の情報については、国土交通省の一覧ページおよび各公式サイトをご確認のうえ、ご検討ください。
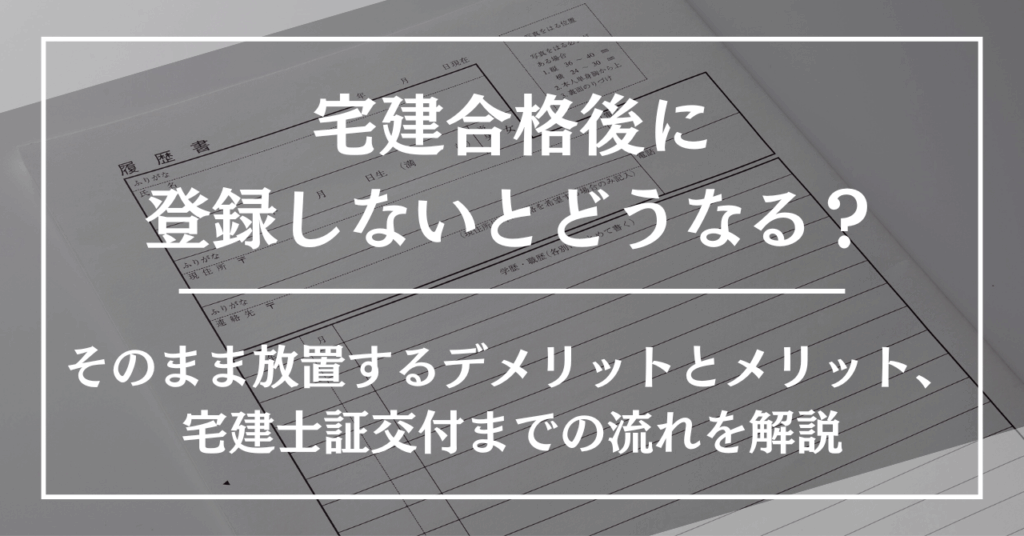
登録講習の申し込みから宅建試験5問免除までの流れ

登録講習の申し込みから宅建試験受験までの流れは以下の通りです。
1.必要書類を揃えて登録講習を申し込む
2.教材を受け取り通信講座を受講する
3.スクーリング後に修了試験を受験する
4.登録講習修了者証明書を受け取る
5.宅建試験の5問免除を申請する
それぞれ解説します。
1.必要書類を揃えて登録講習を申し込む
登録講習を受けるには、まず必要書類を揃えて申し込みを行います。
一般的に必要なのは「顔写真入りの従業者証明書のコピー」です。
申し込みはWeb・郵送のどちらかで受け付けている機関が多く、定員に達し次第締切となるため早めに行動しましょう。
特に人気の都市部の会場は満席になりやすいため、講習日程と自分のスケジュールを照らし合わておくことが大切です。
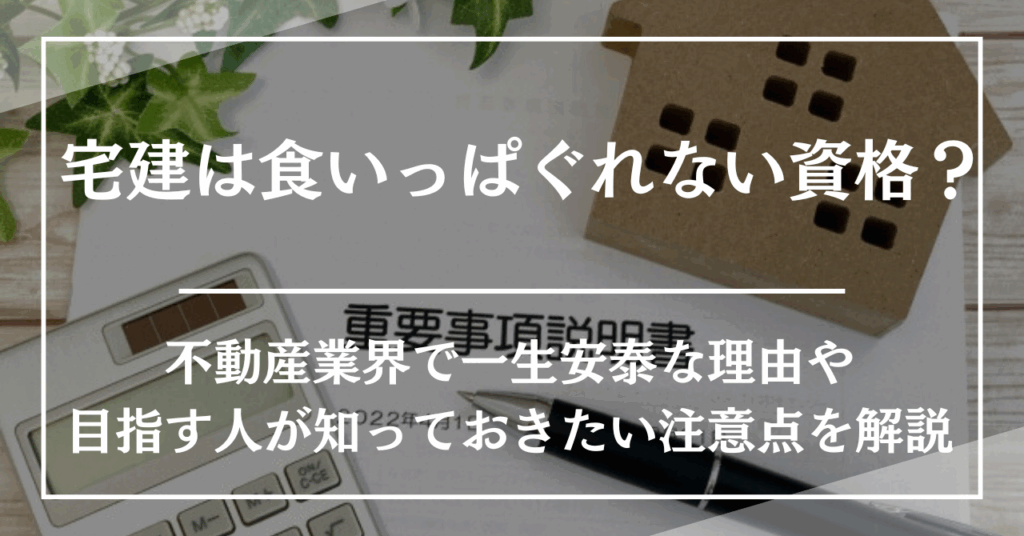
2.教材を受け取り通信講座を受講する
申し込み後は、登録講習機関から教材が送られてきます。受講生はその教材を使って通信学習を進めます。
内容は宅建業法や民法など、宅建試験に直結する範囲が中心で、動画講義やeラーニングにより自宅で効率的に学習することが一般的です。
ここでの学習が修了試験に直結するため、内容をしっかり理解しておくことが重要です。
通勤・通学時間やスキマ時間を活用して、繰り返し復習することで定着を図りましょう。
3.スクーリング後に修了試験を受験する
通信学習を終えると、スクーリング(対面講義)に参加し、その後に修了試験を受けます。
スクーリングは1日~2日で完了することが多く、講義の要点を再確認できる貴重な機会です。
修了試験は、基本的に通信学習とスクーリングで扱った内容から出題されるため、しっかり学習していれば合格可能です。
試験はマークシート方式で、7割程度の正答率で合格するケースが一般的です。
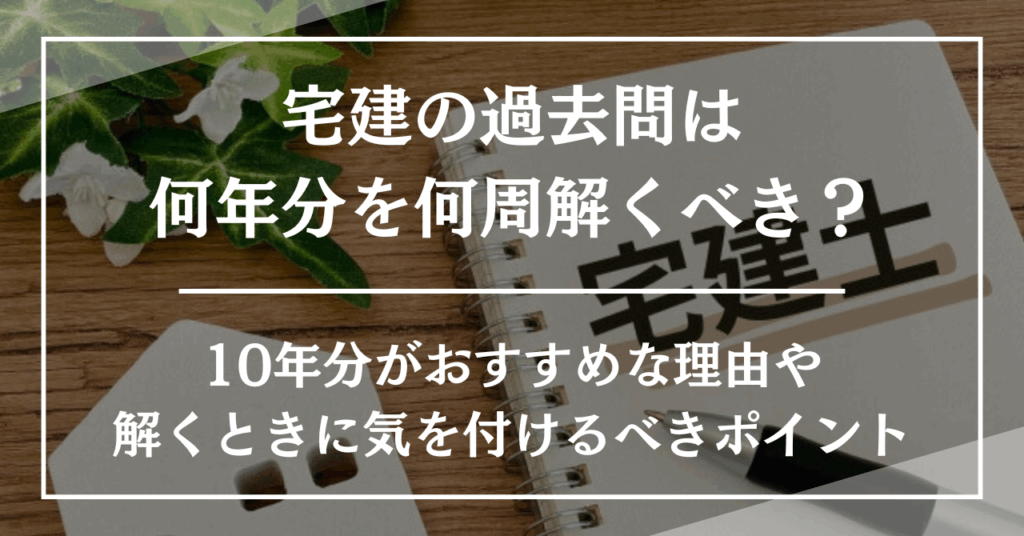
4.登録講習修了者証明書を受け取る
試験に合格すれば、晴れて「登録講習修了者証明書」が交付されます。
これは宅建試験で5問免除を受けるために必要な公式書類です。
万が一、紛失してしまった場合には再発行ができますが、手数料を支払う必要があるため注意が必要です。
証明書は郵送で届くことが多く、届くまでに数日〜1週間ほどかかります。
受け取ったら内容に間違いがないかを確認し、大切に保管しましょう。
この証明書があることで、宅建試験本番での精神的な余裕にもつながります。
5.宅建試験の5問免除を申請する
最後に、宅建試験の受験を申し込む際に、登録講習修了者証明書の原本を同封して5問免除の申請を行います。
申請しなければ免除が適用されないため、提出書類の確認は必須です。
5問免除されるのは「その他関連知識」という分野で、法律初学者にとって得点源になりにくい難所と言えます。
時間配分が重要な宅建試験では、5問分の余裕が大きなアドバンテージになります。
また、5問免除で得られた時間的余裕を最大限に活かすには、残りの出題範囲を確実に得点源にする実力を身につけることが不可欠です。
▼オンライン通信講座なら、宅建業法や権利関係など配点の高い分野を重点的に学習でき、講師作成のオリジナルテキストと充実した問題演習で、5問免除のアドバンテージを合格につなげる確かな実力を養成できます。
![]()
登録講習のスクーリングの持ち物

登録講習の後半で実施される「スクーリング」は、1日~2日の対面授業と修了試験がセットになっており、忘れ物があると試験が受けられない場合もあります。
受講のために必要な持ち物は以下の通りです。
・宅建業従業者証明書の原本
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・受講票・修了試験の受験票
・筆記用具(HB以上の鉛筆、消しゴム)
・時計(スマホは不可)
・配布教材
特に受講票と身分証は本人確認に必須です。当日は余裕を持って準備しましょう。
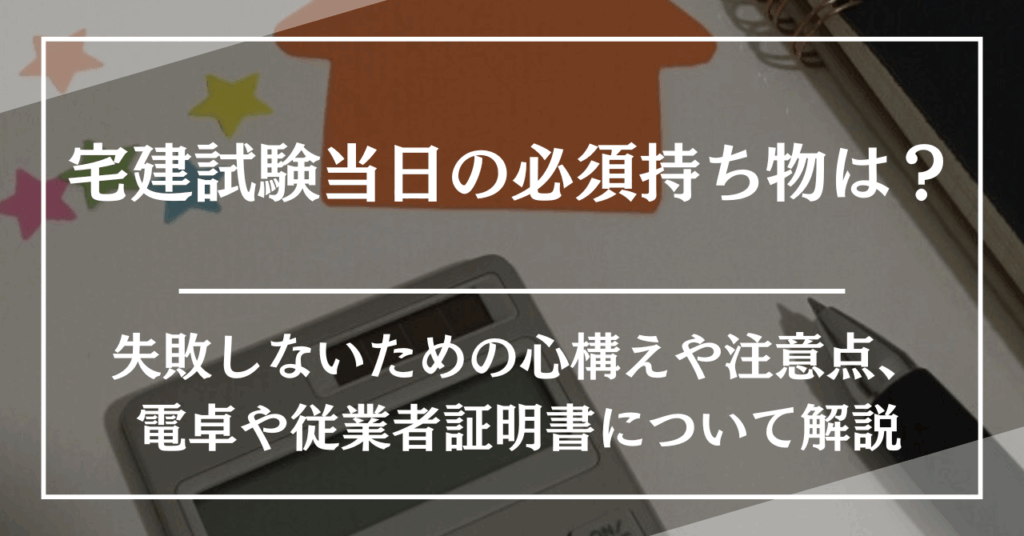
登録講習に関するよくある質問

ここからは、登録講習に関するよくある質問に回答します。
宅建登録実務講習との違いは?
宅建登録講習は「宅建試験前」に5問免除を受けるための講習です。
一方、宅建登録実務講習は「宅建試験合格後」、実務経験が2年未満の方が宅建士として登録するために受ける講習です。
対象不動産の調査業務や媒介契約書の作成業務などの実務について学習します。
混同しがちですが、登録講習は試験のためであるのに対して、実務講習は登録のための講習と覚えておきましょう。
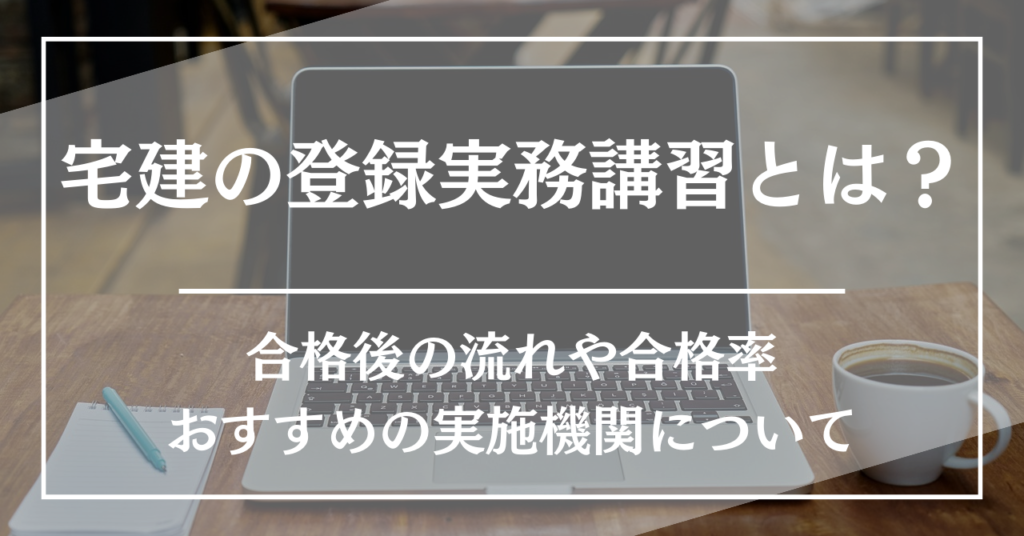
宅建法定講習との違いは?
宅建法定講習とは、宅建士証の更新を行う際に義務づけられている講習です。
対象は、宅建士として登録済みで「宅建士証の有効期限が近い方」や「登録後1年以内に宅建士証を交付されなかった方」などが挙げられます。
講習は基本的に1日で、最新の法改正や実務知識、重要事項説明の注意点などが中心です。
オンライン講習を実施する団体も増え、働きながらでも受けやすくなっています。
形式だけでなく内容も実務向けに洗練されており、現場で役立つ情報が得られる実践的な機会となっています。
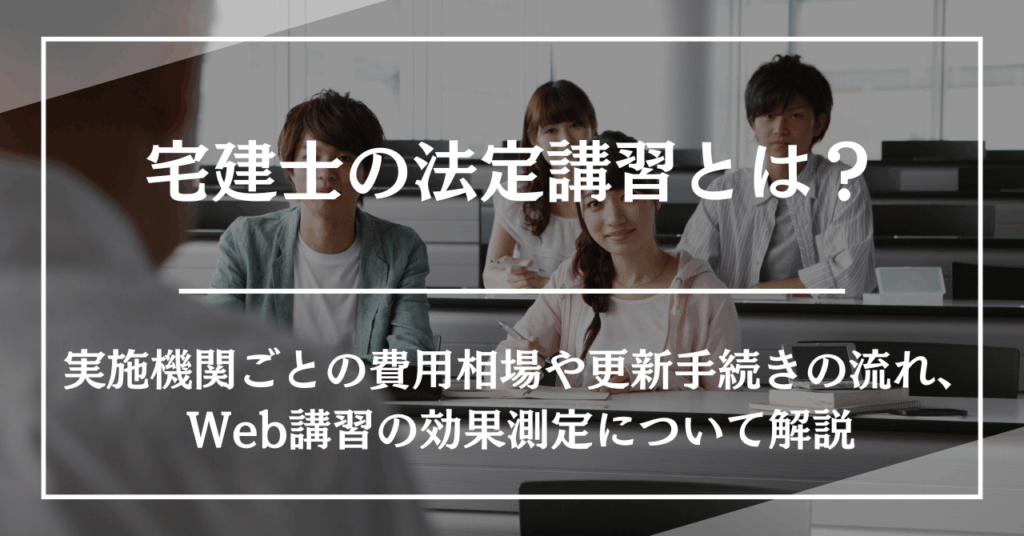
登録講習の修了試験に落ちたらどうなる?
登録講習の修了試験は合格しないと「5問免除」が受けられませんが、多くの実施機関では再試験制度があります。
再試験は受講期間内であれば追加費用なしで受けられることも多いので、あきらめずに再チャレンジしましょう。
しっかり復習すれば合格できる難易度です。
登録講習の修了証に有効期限はある?
登録講習の修了証(修了者証明書)には有効期限があり、修了日から「3年以内」に宅建試験を受験しなければ免除は適用されません。
つまり、講習だけ受けても試験を放置すると無効になります。
受講後はできるだけ早く本試験の受験を計画しましょう。
修了証の有効期限内に確実に合格するには、計画的かつ効率的な学習スケジュールを立てることが重要です。
▼オンライン通信講座なら、定期カウンセリングで学習進捗を管理してもらえ、限られた期間内でも無駄なく合格レベルまで到達できるカリキュラムとサポート体制が整っています。
![]()
宅建試験合格のために登録講習を活用しよう!

宅建試験の合格率を少しでも上げたい方には、登録講習の活用がおすすめです。
5問免除によって実質45問中の合格を目指せるほか、講習の内容自体が本試験の出題範囲と重なるため、学習の土台づくりにもなります。
さらに、修了試験の難易度は本試験よりも低めに設定されており、受講によるリスクも少ないのが魅力です。
受験資格に該当する方は、自己学習だけに頼らず、登録講習という制度をうまく取り入れることで、合格への近道を確保しましょう。