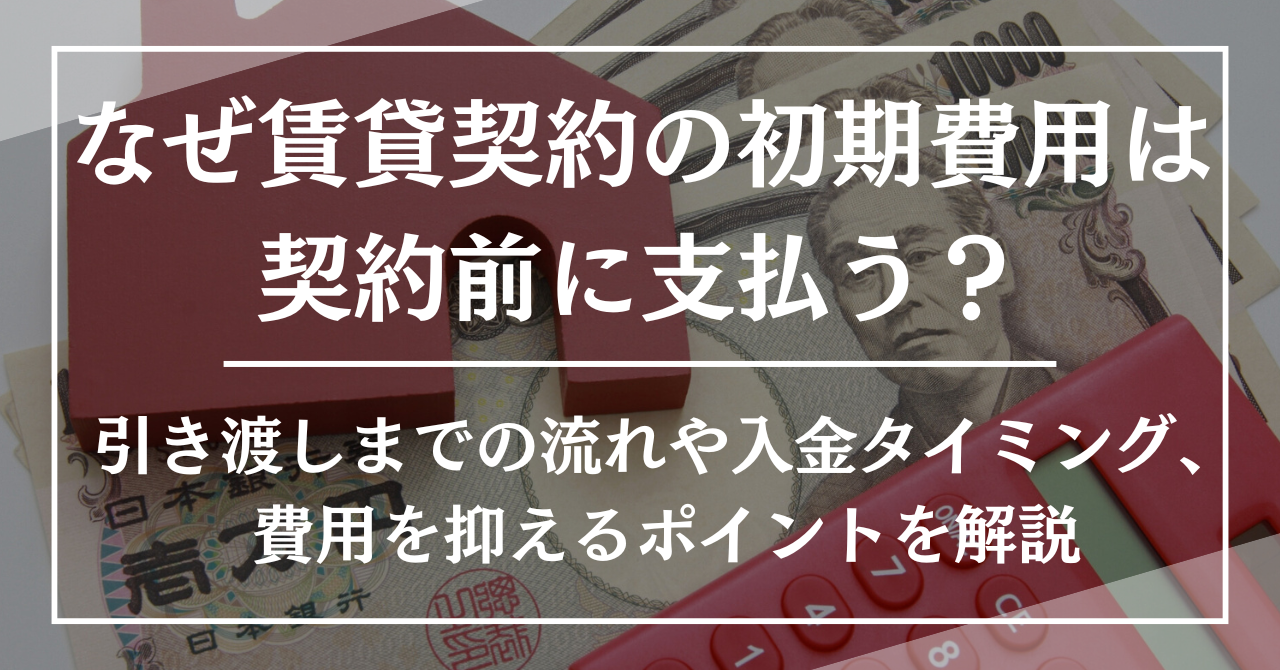※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。
「賃貸契約の初期費用はいくら必要?」
「賃貸契約前に入金を求められるのは違法?」
「賃貸物件探しから引き渡しまでの流れは?」
進学や就職、転勤などで新しい拠点に引っ越すときに、賃貸物件を探す方も多いでしょう。
そのときに、貸主の押印がない契約書に対して、高額な初期費用を支払うことに疑問を持つ方も多いはずです。
そこで本記事では、なぜ賃貸契約の初期費用を支払うタイミングは契約前が多いのかについて解説します。
また、初期費用の相場や引き渡しまでの一般的な流れ、費用を抑えるポイントについて紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
賃貸物件選びから引き渡しまでの流れ

賃貸物件選びから引き渡しまでの一般的な流れは以下の通りです。
1.気になる物件を見つけて内覧する
2.入居申し込みを出して審査を受ける
3.重要事項説明を受けて契約内容を確認する
4.入金方法に従って初期費用を支払う
5.契約締結・鍵の引き渡し
それぞれ解説します。
1.気になる物件を見つけて内覧する
賃貸契約の第一歩は、希望条件に合う物件を見つけて内覧することです。
間取りや設備、周辺環境などは写真だけではわからない点も多く、現地確認が重要です。
たとえば、「日当たりが良いと思ったら隣にビルがあった」「駅からの距離が想像より遠い」といったギャップもよくあります。
内覧では、不動産会社の担当者と一緒に気になる点を確認しましょう。
納得したうえで申し込むことで、後悔のない契約につながります。
2.入居申し込みを出して審査を受ける
気に入った物件が見つかったら、入居申込書を提出し、入居審査を受けます。
これは貸主(大家さん)や管理会社が「安心して貸せるかどうか」を確認するために必要なステップです。
審査では、収入や勤務先、連帯保証人の有無などがチェックされます。
たとえば、世帯月収が家賃の3倍以上あれば通過しやすいとされています。
審査に通らないと契約はできないため、必要書類を揃え、正確に記入することが重要です。
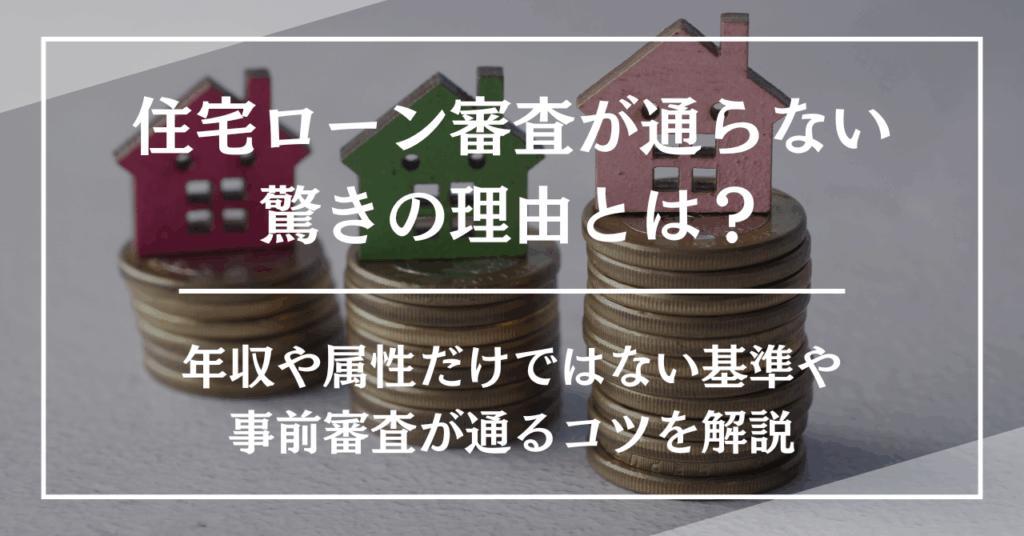
3.重要事項説明を受けて契約内容を確認する
入居審査に通過したら、契約の前に「重要事項説明」を受けます。
これは宅地建物取引士(宅建士)が、契約に関する法律的な注意点を説明する義務のある手続きです。
たとえば、「更新料があるか」「途中解約時の違約金はどうなるか」など、後からトラブルになりやすい項目が詳しく説明されます。
この段階で内容をよく確認し、不明点は遠慮せず質問しましょう。
4.入金方法に従って初期費用を支払う
契約内容を確認し納得できたら、提示された初期費用を指定口座へ入金します。
初期費用には敷金・礼金・仲介手数料・前家賃などが含まれ、物件によっては家賃4~6か月分かかる場合もあります。
たとえば、家賃8万円の物件なら総額30万円以上になることも珍しくありません。
入金が確認されて初めてスムーズに契約が成立するため、期日を守ることが重要です。
支払い後のキャンセルには注意が必要なので、慎重に進めましょう。
また、このときに毎月の家賃や初期費用の支払いを、より便利かつ安心に管理したい場合は、クレジットカードで家賃を自動決済できるサービスの活用がおすすめです。
▼一度手続きを行えば、全国の賃貸物件や駐車場、共益費なども対象となるため、毎月の支払いをスムーズに自動化できます。
![]()
5.契約締結・鍵の引き渡し
初期費用の支払いが完了すると、正式に賃貸契約が成立し、鍵が引き渡されます。このタイミングで初めて物件に自由に入れるようになります。
また、鍵の受け取りは契約開始日の当日が一般的です。
たとえば、4月1日契約であれば、その日に鍵を受け取るケースが多いです。
引っ越しやライフラインの手続きもこの段階から可能になるため、スケジュールを事前に組んでおくとスムーズに入居できます。
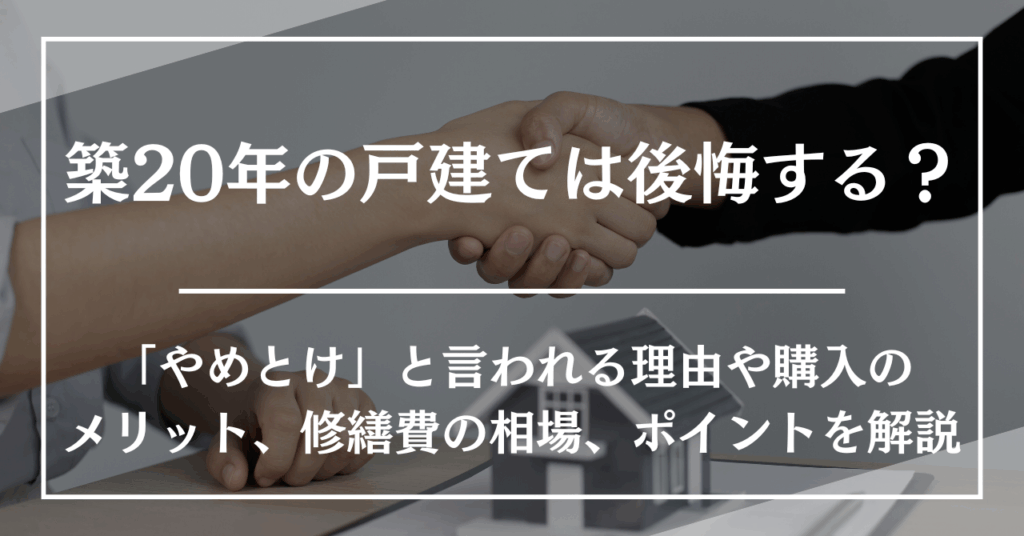
賃貸契約の初期費用はいつ払う?

賃貸契約の初期費用は、基本的に契約書への署名・押印を済ませた「契約直前から契約締結前」に支払うのが一般的です。
具体的には、重要事項説明を受けた後、不動産会社から初期費用の見積書が提示され、数日以内に指定口座へ振り込む形が多く見られます。
借主としては、実際の契約前に大きな費用を支払うことに不安を感じる方もいるでしょう。
一方で、これは貸主や管理会社が「この借主は本当に契約する意思があるか」を確認するために必要な手順でもあります。
金額が大きいため、不安がある場合は宅建士による重要事項説明で質問しておくと安心です。
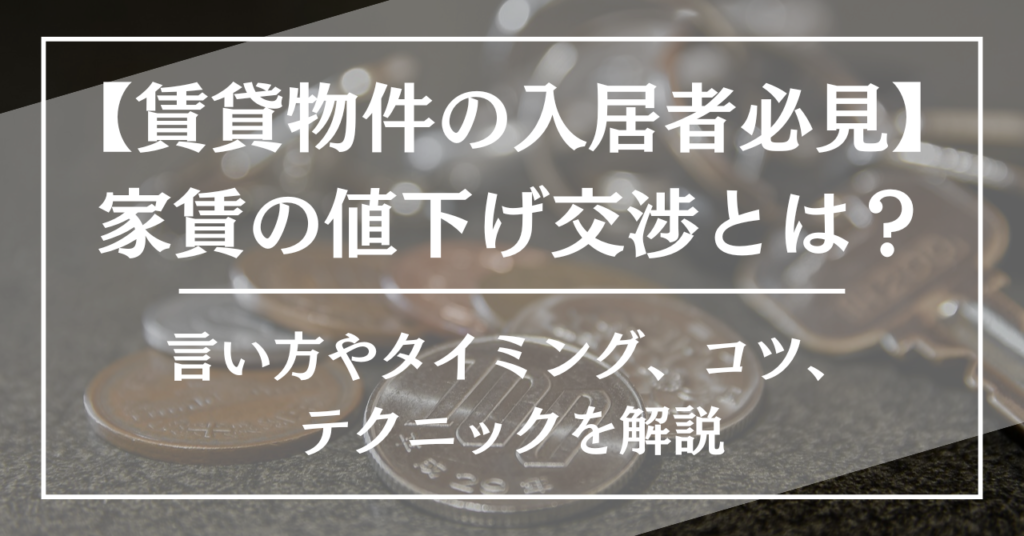
賃貸契約の初期費用を契約前に支払う理由

契約前に高額な初期費用を入金することに抵抗がある方も多いかもしれませんが、実際の賃貸仲介の現場では「入金→契約」の流れが一般的です。その理由は以下の通りです。
1.契約当日は貸主が立ち会わないため
2.初期費用を現金で持参するのは大変であるため
3.必要書類の準備に時間がかかるため
それぞれ解説します。
1.契約当日は貸主が立ち会わないため
賃貸契約では、契約当日に貸主が直接立ち会うケースはほとんどありません。
多くの場合、契約業務は管理会社や仲介会社の宅建士が代理で行います。
そのため、貸主の署名や押印を事前に済ませる必要があり、初期費用の入金もあらかじめ行うのが一般的です。
実際の現場では、契約書類を貸主へ回すタイミングで「支払い済み」であることが前提となるケースが多いため、入金が契約の一部として扱われているのです。
2.初期費用を現金で持参するのは大変であるため
初期費用は家賃の4〜6ヶ月分にのぼることが多く、現金で持参するのはセキュリティ面や物理的にも現実的ではありません。
そのため、ほとんどの不動産会社では銀行振込による事前入金をお願いしています。
たとえば、家賃8万円の物件なら初期費用が30万円を超えることもあり、現金で持参するリスクは非常に高くなります。
振込であれば記録も残り、双方にとって安心です。
また、初期費用や毎月の家賃の支払いを、より安全かつ手軽に管理したい場合は、クレジットカードで家賃を自動決済できるサービスの利用がおすすめです。
▼現金や振込の手間を省けるうえ、入金忘れの心配もなく、ポイントやマイルも貯まるため、賢く支払い管理ができます。
![]()
3.必要書類の準備に時間がかかるため
賃貸契約には、住民票や本人確認書類、連帯保証人の承諾書など、提出すべき書類が複数あります。
これらの準備には時間がかかるため、契約日までに手続きを段階的に進める必要があります。
その一環として、初期費用の入金も事前に完了しておくことで、契約当日には書類確認と説明に集中できるようにしています。
特に繁忙期は手続きが混み合うため、前倒しの入金がスムーズな契約につながります。
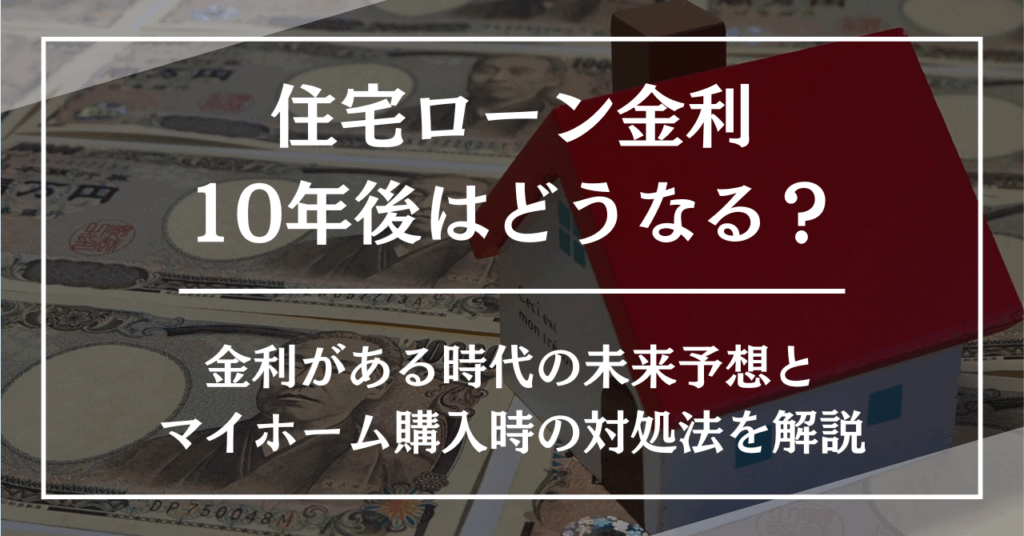
賃貸契約の初期費用の相場と内訳

賃貸契約の初期費用は、トータル家賃5か月分が相場です。
ここからは、必要な費用の内訳について詳しく解説していきます。
1.敷金・礼金
敷金と礼金は、初期費用の中でも大きな割合を占める費用です。
敷金は退去時の修繕費などに充てられる預り金で、家賃1〜2ヶ月分が相場です。
礼金は貸主への謝礼として支払うもので、最近では「礼金ゼロ物件」も増えています。
ただし、ゼロだからといって必ずしもお得とは限らず、他の費用に上乗せされている場合もあるため、内訳の確認が重要です。
地域や物件によって差があるため、事前に不動産会社に相談しましょう。
また、敷金や礼金などの初期費用をよりスマートに管理したい場合は、クレジットカードで家賃を自動決済できるサービスの活用がおすすめです。
▼銀行振込や現金でまとめて支払う手間を省けるだけでなく、ポイントやマイルも貯まるため、毎月の支払いをよりお得に、かつ安全に行えます。
![]()
2.前家賃・日割り家賃
賃貸では、契約月の「日割り家賃」と翌月の「前家賃」を一括で支払うケースが一般的です。
たとえば、7月20日から入居する場合、7月20日〜31日までの日割り家賃に加え、8月分の家賃も支払います。
この前払い方式は、入居当日から家賃滞納を防ぐための対処法です。
家賃発生日は契約日とは異なることもあるため、初期費用の総額を見積もる際は、日割り分が含まれているか必ず確認しましょう。
3.仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社が物件を紹介・契約までサポートするための報酬です。
法律で上限が定められており、「家賃の1ヶ月分+消費税」が基本です。
ただし、キャンペーンなどで「仲介手数料半額」や「無料」としている会社もあります。
注意点として、広告には「0円」と表示されていても、実際は別途事務手数料がかかるケースもあるため、内訳の明細をしっかりチェックすることが大切です。
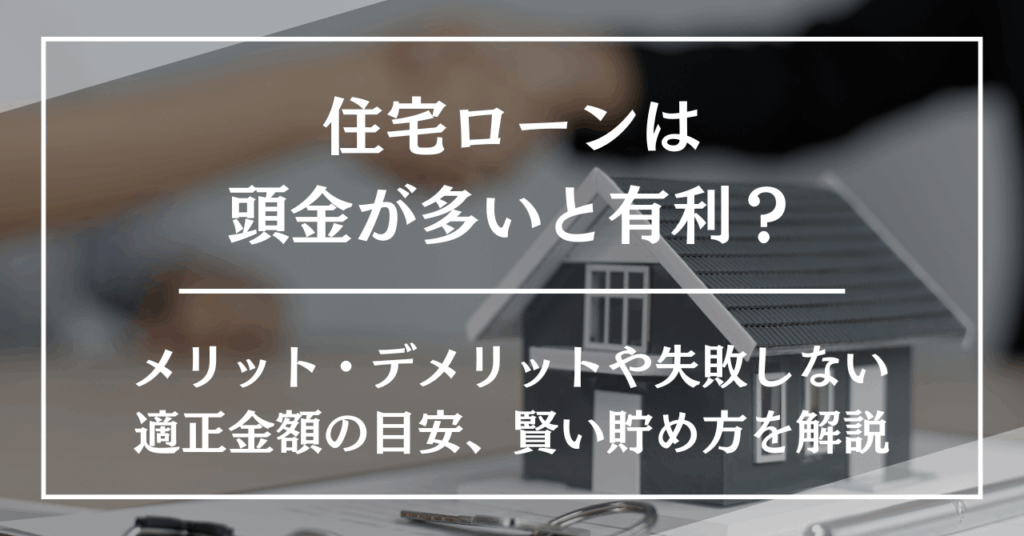
4.鍵交換費用
鍵交換費用は、新しい入居者の安全を守るために必要な費用で、5,000〜25,000円程度が相場です。
たとえば、前の入居者がスペアキーを持っている場合、防犯性の観点から入居者にはリスクがあります。
また、オートロックやディンプルキーなど特殊な鍵を採用している物件では、費用が高くなることもあります。
一部の物件では鍵交換が任意になっているため、契約時に確認して選択できるケースもあります。
5.火災保険料
賃貸契約では火災保険の加入が義務付けられており、費用は1〜2年分で15,000〜20,000円程度が一般的です。
不動産会社が指定する保険に加入するのが一般的ですが、希望があれば自分で選べるケースもあります。
その場合は補償内容を確認し、自分に合った保険を選ぶことが重要です。
保険は火災や水漏れによる損害を補償するだけでなく、他人の家財や部屋に損害を与えた場合の賠償責任にも対応します。
6.管理費・共益費
管理費・共益費は、建物の共用部分の維持管理や清掃、設備点検などに使われる費用で、家賃とは別に毎月支払います。
初期費用としては、前家賃と一緒に1ヶ月分前払いするのが一般的です。
物件によっては、家賃に含まれていることもあり、タワーマンションやオートロック付きの物件では高めに設定されている場合があります。
月額だけでなく、設備内容とコストのバランスも確認しましょう。
7.保証会社費用
保証会社費用は、連帯保証人の代わりとして家賃滞納などに備えるための費用です。
初回保証料は、賃料総額の50〜100%程度が相場で、年間更新料が別途かかる場合もあります。
たとえば、家賃10万円の場合、保証料は初回で3〜5万円ほどになるケースが多いです。
現在ではほとんどの賃貸契約で保証会社の利用が必須となっており、利用条件や更新料の有無をしっかり確認しておきましょう。
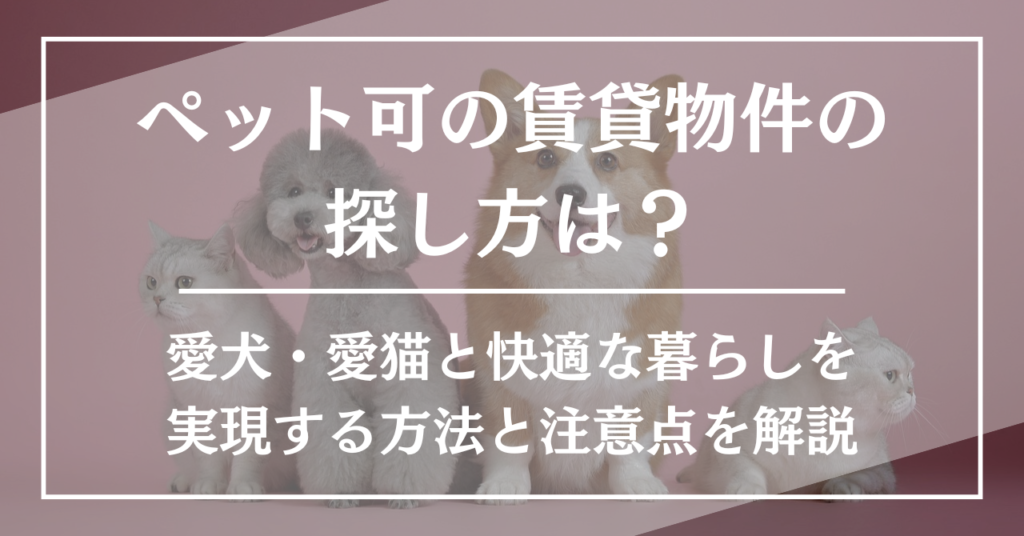
賃貸契約の初期費用を抑えるためのポイント

賃貸物件の初期費用をできるだけ抑えたい方は、以下のポイントを抑えることが効果的です。
1.敷金・礼金なし物件を選ぶ
2.フリーレント付き物件を選ぶ
3.仲介手数料が無料・半額の不動産業者を探す
4.引っ越しのタイミングを閑散期にずらす
5.家具・家電付きの物件を選ぶ
物件選びの工夫と費用の見直しで、初期費用を数万円〜数十万円抑えることも可能です。それぞれ解説します。
1.敷金・礼金なし物件を選ぶ
初期費用を抑えるうえで、敷金・礼金ゼロの物件は最もインパクトがあります。
一般的に、家賃1〜2か月分ずつ必要なため、ゼロなら数万円〜十数万円の節約になります。
ただし、退去時に原状回復費用が高額になるリスクもあるため、契約時に内容を細かく確認しましょう。
礼金ゼロ物件は増加傾向にあり、特に築年数が経過した物件や駅から遠い物件に多く見られます。
また、敷金や礼金を抑えて初期費用を節約したい方には、家具家電付きで仲介手数料も無料の「レオパレス21」がおすすめです。
▼全国約57万戸の物件から選べ、入居当日からWi-Fiや生活必需品が揃っているため、引っ越し後すぐに快適な生活を始められます。
![]()
2.フリーレント付き物件を選ぶ
フリーレント物件とは、「一定期間家賃無料」の特典がついた物件です。
1〜2か月分の家賃が無料になるため、前家賃や初月の日割り家賃が不要になる場合もあります。
貸主が空室を早く埋めたいときに使われる手法で、特に閑散期や築古物件に多く見られます。
契約期間の縛りがあることも多いので、途中解約時の違約金条項も事前にチェックしましょう。
3.仲介手数料が無料・半額の不動産業者を探す
仲介手数料を抑えることで、初期費用を1か月分カットできます。
最近では「仲介手数料無料」や「半額」を売りにした不動産会社も増えており、特にネット上で探しやすくなっています。
ただし、仲介手数料が安くても、別名の事務手数料やサポート費が加算されている場合もあるため、総額で確認することが大切です。
明細を必ずチェックしましょう。

4.引っ越しのタイミングを閑散期にずらす
賃貸市場には繁忙期(1〜3月)と閑散期(5〜8月)があり、閑散期は交渉がしやすく、条件が緩和される傾向にあります。
貸主が早く入居者を見つけたい時期なので、敷金・礼金の減額交渉やフリーレントの提案も通りやすくなります。
また、引っ越し業者の料金も下がるため、トータルコストを抑えるチャンスです。
時間に余裕があるなら閑散期の引っ越しがおすすめです。
5.家具・家電付きの物件を選ぶ
家具・家電付き物件を選ぶことで、引っ越し時の購入費用や運搬費用を削減できます。
冷蔵庫・洗濯機・ベッドなどの基本設備が整っていれば、初期費用を数万円単位で節約可能です。
とくに単身赴任や学生の一人暮らしには最適で、すぐに生活を始められることも大きなメリットです。
ただし、設備の状態や退去時の取り扱い(クリーニング費負担など)は契約前に確認しておきましょう。
また、敷金や礼金を抑えて初期費用を節約したい方には、家具家電付きで仲介手数料も無料の「レオパレス21」がおすすめです。
▼全国約57万戸の物件から選べ、入居当日からWi-Fiや生活必需品が揃っているため、引っ越し後すぐに快適な生活を始められます。
![]()
賃貸契約の初期費用が払えないときの対処法

気に入った賃貸物件の家賃が高額になればなるほど、賃貸契約の初期費用も大きくなる傾向があります。
支払いが困難なときは、以下の対処法を実践することがおすすめです。
1.クレジットカード払いを選択する
2.不動産業者に分割払いを依頼する
3.家族や友人から借りる
それぞれ解説します。
1.クレジットカード払いを選択する
初期費用の支払いが厳しい場合は、クレジットカード決済が可能な不動産会社を選ぶのが効果的です。
カードで支払えば、一括引き落としのほかにリボ払いや分割払いができ、資金繰りの柔軟性が広がります。
たとえば「仲介手数料+初月家賃+保険料」などのまとまった費用でも、カード会社の支払いサイクルに応じてタイミングを調整できます。
対応可否は業者により異なるため、事前確認が必須です。
さらに、初期費用や毎月の家賃をカードで支払いたい場合は、クレジット決済に対応している賃貸サービスを活用すると便利です。
▼カード払いにすることでポイントやマイルも貯まり、支払い管理を効率化しながらお得に活用できます。
![]()
2.不動産業者に分割払いを依頼する
現金での一括支払いが難しい場合、不動産会社に「初期費用の分割払い」を相談するのも現実的な手段です。
とくに地元密着型の不動産業者は柔軟に対応してくれるケースがあります。
たとえば「契約金の半額を契約時、残りを翌月末までに」といった交渉が成立することもあります。
不動産会社との信頼関係と契約条件がカギとなるため、早めに相談することが重要です。
3.家族や友人から借りる
一時的な資金不足であれば、家族や信頼できる友人から借りることも選択肢の一つです。
金融機関に比べて利息が発生せず、返済条件も柔軟に相談しやすいメリットがあります。
とくに就職や進学など将来的に安定した収入が見込める場合、理解を得やすい傾向にあります。
ただし、トラブルを防ぐためにも、金額・返済期日を明確に決めておくことが大切です。
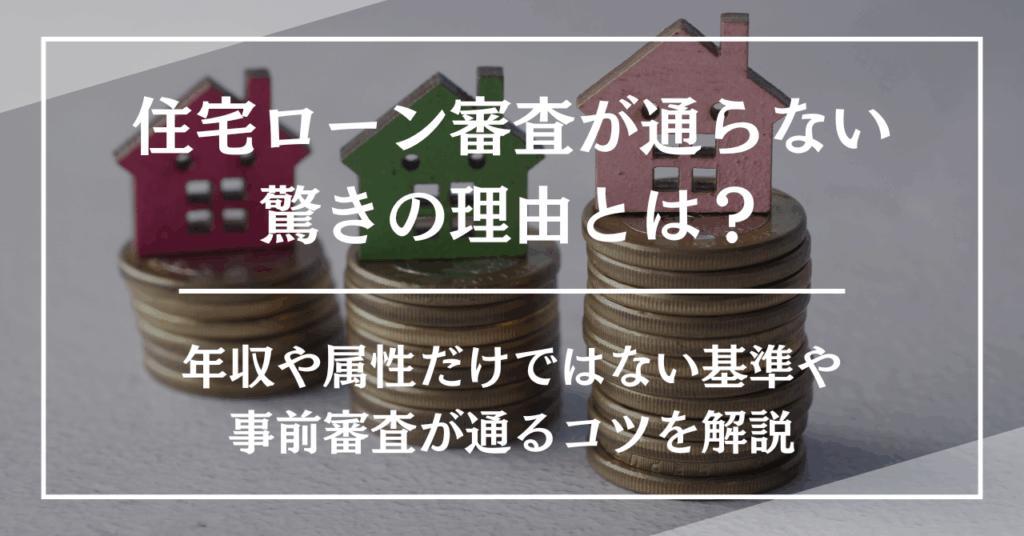
賃貸契約の初期費用に関するよくある質問

ここからは、賃貸物件の初期費用に関するよくある質問について回答します。
賃貸契約前に入金を求められるのは違法?
結論から言えば、契約前に初期費用の入金を求めること自体は違法ではありません。
実務上では「入金をもって契約成立」とみなすケースが多く、貸主側のリスク回避のためにも一般的な流れです。
たとえば、入居審査が通過した後に初期費用の振込案内が届き、支払い後に契約書が作成されるのが一般的です。
ただし、領収書の発行や契約条件の書面提示がないままの請求は不適切ですので、慎重に対応しましょう。
初期費用の支払いは振込以外の方法を選べる?
初期費用の支払い方法は、不動産会社や管理会社によって異なります。
業者によっては振込以外にもクレジットカード払いや電子マネー決済、現金持参が可能な場合もあります。
とくに近年では、利便性向上のためにカード決済に対応する不動産会社が増えています。
たとえば「一部をカード払い、残額は銀行振込」といった組み合わせも可能です。
事前に支払い方法の選択肢を確認しておくことが大切です。
また、初期費用の支払い方法に悩んでいる場合は、クレジット決済に対応している賃貸サービスを利用すると便利です。
▼振込忘れや現金の持参によるトラブルも防げるうえ、ポイントやマイルも貯まるため、毎月の家賃支払いを効率的かつお得に管理できます。
![]()
初期費用の支払いはどのくらい待ってもらえる?
支払い期限は「契約当日まで」が原則ですが、慣習として「審査通過後1週間から10日以内」に設定されていることが一般的です。
事情がある場合は不動産会社に相談することで猶予を得られることもあります。
たとえば「給料日まで待ってほしい」といった希望も、内容次第で柔軟に対応してもらえるケースがあります。
ただし、長く待ってもらうのは信用問題に発展するため難しく、他の申込者に優先されるリスクもあるため、相談は早めに行うのが鉄則です。
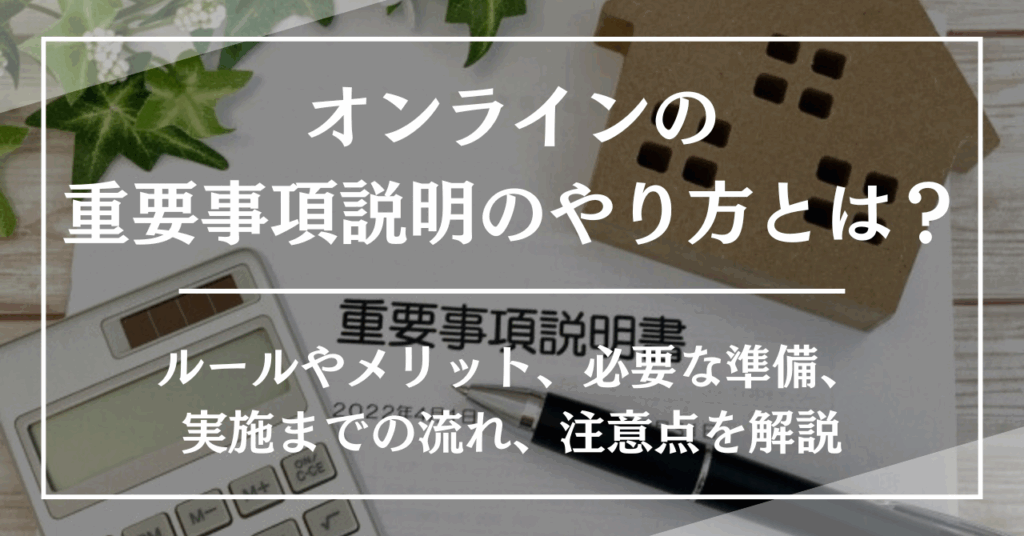
引っ越しに向けて家賃5か月分を用意しよう!

引っ越しにかかる賃貸契約の初期費用は、敷金・礼金・仲介手数料・前家賃などを含め、家賃の約5か月分が目安です。
加えて、引っ越し代や家具・家電の購入費もかかるため、余裕をもって資金を準備しておくことが大切です。
費用が高額になる場合は、敷礼ゼロ物件や分割払い、カード決済などを活用すれば負担を軽減できます。
初期費用の仕組みを理解し、無理のない引っ越し計画を立てましょう。