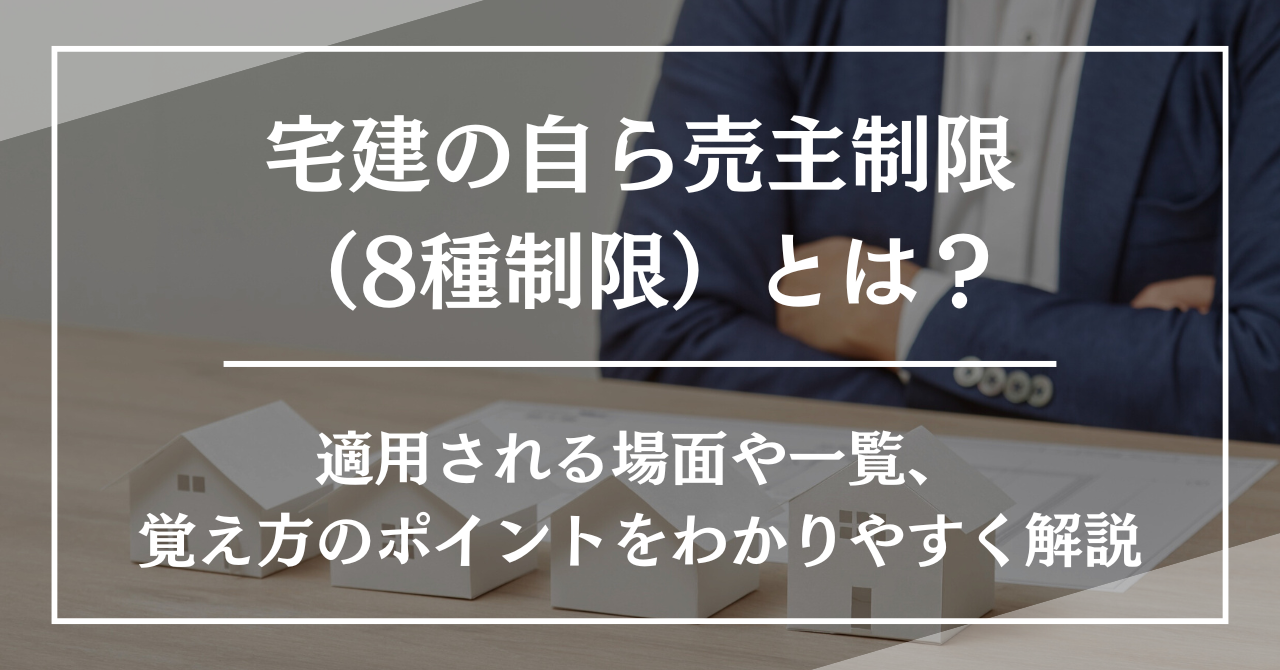※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net、楽天アフィリエイト含む)を掲載しています。
「8種制限って何をどう覚えればいいの?」
「自ら売主制限ってどんな取引に適用されるの?」
「宅建試験ではどこまで理解すれば得点できるの?」
そんな疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
自ら売主制限(8種制限)は、宅建業法の中でも消費者保護を目的とした最重要テーマの一つです。
宅建試験でも毎年出題され、実務でも売主側の行動を大きく制限します。
そこで本記事では、宅建の8種制限とは何か、その内容や適用場面をわかりやすく解説します。
また、8種制限の一覧や効率的な覚え方のポイントについても紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
宅建の自ら売主制限(8種制限)とは?

宅建の自ら売主制限とは、不動産会社が売主として物件を販売するときに守るべきルールのことです。
合計8つあることから「8種制限」とも呼ばれています。
不動産の専門知識を持たない一般のお客様を守ることを目的としており、制限の内容は宅地建物取引業法(宅建業法)という法律で決められています。
もし制限がなければ、専門知識や交渉力で圧倒的に有利な立場にある悪質な不動産会社は、高額な手付金を要求したり、不当に重い違約金を設定したりする可能性があります。
そのため、8種制限は買主の利益を最優先に考えた消費者保護の仕組みであり、安心して不動産取引ができる土台となっています。
なお、法律系の難関資格に対応したオンライン講座では、映像授業や多機能学習システムを活用して効率的に学習できます。
▼宅建を含む多数の資格に対応しているため、自分に合ったカリキュラムで学びを進めたい方におすすめです。
![]()
宅建の自ら売主制限(8種制限)が適用される場面

自ら売主制限(8種制限)が適用されるかどうかは、売主と買主がそれぞれ「不動産会社かどうか」によって決まります。
それぞれケースごとに、自ら売主制限が適用されるかどうか見ていきましょう。
1.売主が宅建業者で買主が宅建業者以外のとき
売主が不動産会社で買主が一般のお客様である場合、自ら売主制限(8種制限)がすべて適用されます。
たとえば、建売住宅を販売する不動産会社が、個人のお客様に新築一戸建てを売る場合がこれに該当します。
また、中古物件を買い取り、リフォームをして再販売する業者が、個人のお客様に販売する場合も同様です。
この場合では、買主が最も弱い立場にあるため、8種制限による保護が最大限に機能する場面といえます。
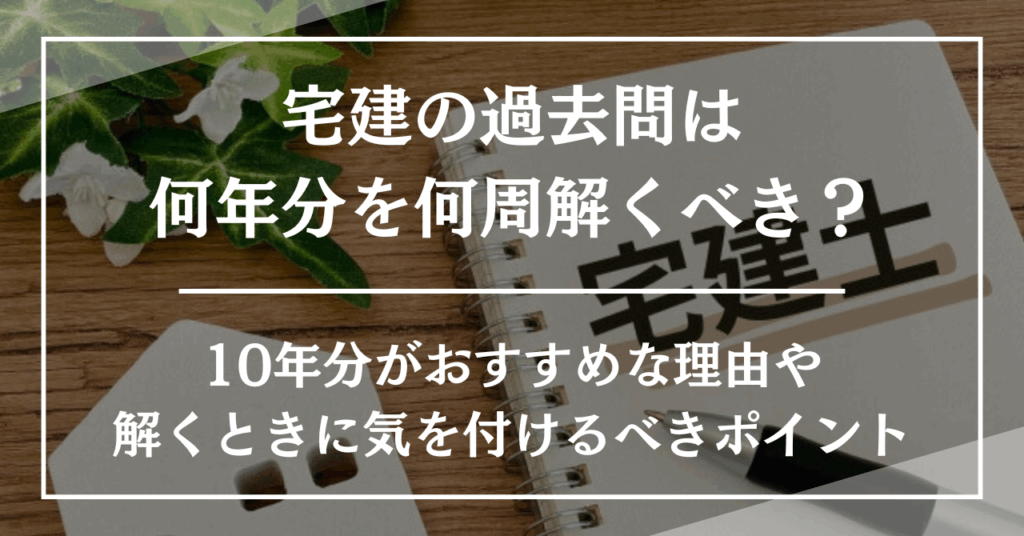
2.売主が宅建業者以外で買主が宅建業者のとき
売主が一般の個人で買主が不動産会社の場合、自ら売主制限(8種制限)は一切適用されません。
宅建業法が保護するのは「買主」であり、専門知識を持つ不動産会社は保護の対象外とされているためです。
たとえば、個人が所有する中古住宅を不動産会社に買い取ってもらうケースが該当します。
買主が専門業者である以上、自己責任で取引を進められると考えられているため、制限は適用されない仕組みです。
ただし民法上の一般的なルールは適用されます。
3.売主が宅建業者以外で買主が宅建業者以外のとき
売主と買主がともに一般の個人である場合、自ら売主制限(8種制限)は適用されません。
宅建業法は不動産会社の業務を規制する法律であり、個人間の取引には原則として関与しないためです。
たとえば、個人が所有する中古マンションを別の個人に売却する場合がこれに当たります。
この場合は、手付金の金額も損害賠償の取り決めも、当事者間の合意で自由に設定できます。
ただし完全に自由というわけではなく、民法の契約ルールや消費者保護に関する一般的な法律は適用されるため、極端に不公平な契約は無効になる可能性があります。
4.売主が宅建業者で買主が宅建業者のとき
売主と買主がともに不動産会社の場合、自ら売主制限(8種制限)は原則として適用されません。双方が専門業者であり対等な立場で取引できると判断されるためです。
たとえば、建売業者が仕入れた土地を別の不動産会社に転売するケースが該当します。
不動産会社同士の取引では、双方が契約内容を十分に理解し、リスクを判断する能力を持っています。
そのため、法律による保護は不要とされ、商慣習に基づいて自己責任で取引を進めることが認められています。
また、専門的な知識を踏まえた取引が求められる場面でも、体系的な学習によって理解を深めておくことは大きな武器になります。
▼法律系資格に対応したオンライン講座なら、宅建を含む幅広い分野を効率的に学べます。
![]()
宅建の自ら売主制限(8種制限)の一覧

自ら売主制限(8種制限)は、手付金の上限設定から所有権の移転まで、取引の各段階で買主を守るための具体的なルールを定めています。
それぞれの制限は宅建業法第39条から第47条の3に根拠があり、違反すると業者には罰則が科されます。
ここからは、各制限の内容と目的について詳しく見ていきます。
1.自己の所有に属しない物件の売買契約締結制限
不動産会社が自分の所有していない物件を売る契約を結ぶことは、原則として禁止されています。
宅建業法第33条の2で規定され、悪質な業者による架空販売や二重契約を防ぐために機能しています。
たとえば、不動産会社がまだ取得していない土地について、先に一般のお客様と売買契約を結ぶケースです。
自己所有でない物件を先に販売してしまうと、後から所有権を取得できなかった場合に買主に引き渡せず、大きな損害を与えるリスクがあります。
ただし例外として、売主から物件を取得する契約をすでに結んでいて確実に取得できる見込みがある場合には、契約が認められます。
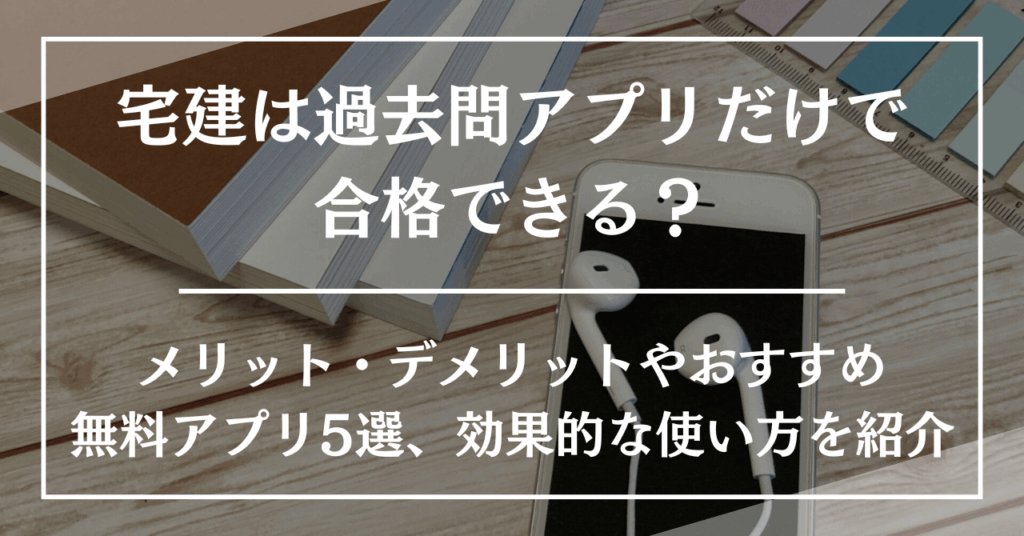
2.クーリング・オフ
クーリング・オフとは、不動産会社が自ら売主となる場合に、買主が一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
宅建業法第37条の2で定められており、申込みや契約から8日以内であれば、理由を問わず解除が可能です。
たとえば、展示会場や仮設テント、路上など業者の事務所以外の場所で雰囲気に流されて契約してしまったケースです。
この場合、業者は無条件で契約を解除し、受け取った手付金等を全額返還しなければなりません。
クーリング・オフは買主に「考え直す権利」を保障する重要な消費者保護制度です。
3.手付金額の制限等
不動産会社が自ら売主となる場合、受け取れる手付金の額は売買代金の20%以内に制限されています。
高額な手付金を要求されると、買主は多額の資金を一度に用意しなければならず、経済的負担が大きくなるためです。
また、万が一契約が解除された場合、手付金が返還されないリスクも高まるため、過大な手付金の設定は無効とされます。
たとえば、売買代金が3,000万円の新築住宅の場合、業者が受け取れる手付金の上限は600万円(3,000万円×20%)です。
手付金額の制限があることで、買主は合理的な範囲内の初期費用で安心して契約を進めることができます。
宅建試験でも頻出ポイントであり、「20%以内」という数字だけでなく、なぜこの制限があるのか、どのような場合に適用されるのかといった背景まで理解するが大切です。
▼これから試験対策を始める方は、8種制限全体を体系的に整理し、図表や具体例を使ってわかりやすく解説しているテキストを選びましょう。
4.損害賠償額の予定等の制限
不動産会社が自ら売主となる場合、契約違反があった際の損害賠償額や違約金の合計は、売買代金の20%以内に制限されています。
この制限がなければ、業者が一方的に高額な違約金を設定し、買主が契約を解除したくてもできない状況に追い込まれる恐れがあるためです。
たとえば、5,000万円の物件で損害賠償の予定額を1,500万円(30%)に設定する契約は違法です。
上限は1,000万円(5,000万円×20%)となり、それを超える部分は無効となります。
また、損害賠償と違約金の両方が設定されている場合は、合計額で20%以内である必要があります。
5.手付金等の保全措置
手付金等の保全措置とは、不動産会社が倒産した場合でも買主が支払った手付金等を確実に返還してもらえるよう、業者に保全義務を課す制度です。
保全措置が義務付けられている金額は物件が「完成」しているか、「未完成」かで変わります。
| 物件の状態 | 手付金などの基準額 |
|---|---|
| 完成前の物件 | 代金の 5%超 または 1,000万円超 |
| 完成物件 | 代金の 10%超 または 1,000万円超 |
たとえば、4,000万円の新築マンション(未完成)を購入し、手付金として300万円を支払う場合、業者は保全措置を講じる必要があります。
もし業者が倒産しても、買主は保証機関から手付金の返還を受けられるため、資金が保護されます。
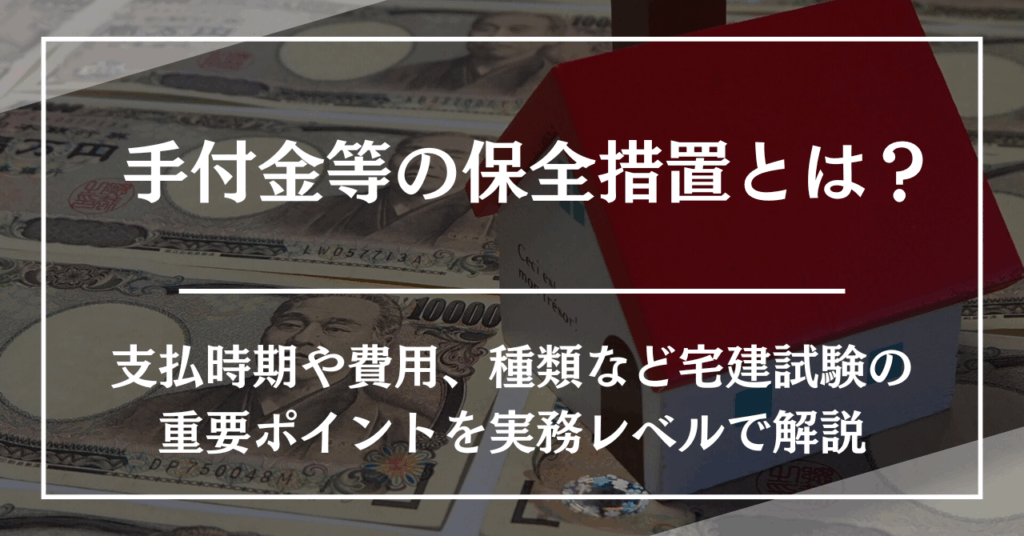
6.担保責任の特約の制限
不動産会社が自ら売主となる場合、物件に欠陥(契約不適合)があっても、責任を免除したり軽くしたりする特約は原則として無効です。
たとえば「責任期間を引渡し後1年以内とする」「雨漏りなどの欠陥が見つかっても売主は責任を負わない」といった内容は、買主に不利となるため宅建業法で禁止されています。
宅建業者が売主の場合、買主に対して引渡し日から2年間は、修補や損害賠償などの責任を負う必要があります。
一方、民法では原則として「引渡しから1年間」が責任期間とされていますが、宅建業法により、業者が売主の場合はこれより短くする特約は無効です。
つまり、買主は引渡しから少なくとも2年間は、発見した欠陥について売主である業者に修補や損害賠償を請求できる権利が保障されています。
7.割賦販売契約の解除等の制限
不動産を分割払いで購入する「割賦販売契約」では、買主が支払いを遅らせても、宅建業者(売主)はすぐに契約を解除したり、残金の一括請求をしたりすることはできません。
買主が代金の3割(10分の3)以上を支払っている場合は、業者が契約を解除するために次の2つの要件を満たす必要があります。
1.30日以上の猶予期間を設けること
2.書面で支払いを催告すること
たとえば3,000万円の物件で、900万円(30%)以上を支払済みの買主が1回分を滞納しても、業者は直ちに契約を解除できません。
買主には、支払いを続けるための一定の猶予が法律で保障されています。
こうした法律上の保護を正しく理解するためにも、体系的な学習で知識を整理しておくことが役立ちます。
▼法律系資格に対応したオンライン講座なら、宅建分野も含め効率的に学習を進められます。
![]()
8.所有権留保等の禁止
所有権留保とは、売買代金を分割で支払う(割賦販売)場合に、買主が代金を全額支払い終えるまで、物件の所有権を売主のもとに留めておく(移転登記をしない)という特約のことです。
民法上は認められる手法ですが、宅建業法は買主の地位が不安定になることを防ぐため、原則としてこれを禁止しています。
不動産取引では、所有権が移転しないと買主は物件を自由に利用できず、登記もできないため、第三者に対抗することもできません。
また、万が一業者が倒産した場合、支払った代金を失うリスクも高まります。
そのため、買主が代金の全部または一部を支払った時点で、所有権を買主に移転し登記を行う必要があります。
宅建の自ら売主制限(8種制限)の覚え方のポイント

自ら売主制限(8種制限)は、宅建試験に毎年1〜2問は出題されるの頻出テーマです。
ここからは、宅建試験対策として8種制限の覚え方のポイントを解説します。
1.制限の目的を意識する
自ら売主制限(8種制限)を学習する際は、各制限が「なぜ設けられたのか」という目的を意識することが最も重要です。
目的を理解すれば、細かい条文の内容も自然に頭に入り、応用問題にも対応できるようになります。
すべての制限に共通するのは「買主保護」と「業者の不当行為の抑制」という2つの視点です。
不動産会社と一般の買主では知識や交渉力に大きな差があるため、法律が介入して公平性を保つ必要があります。この大前提を押さえておけば、個別の制限内容も理解しやすくなります。
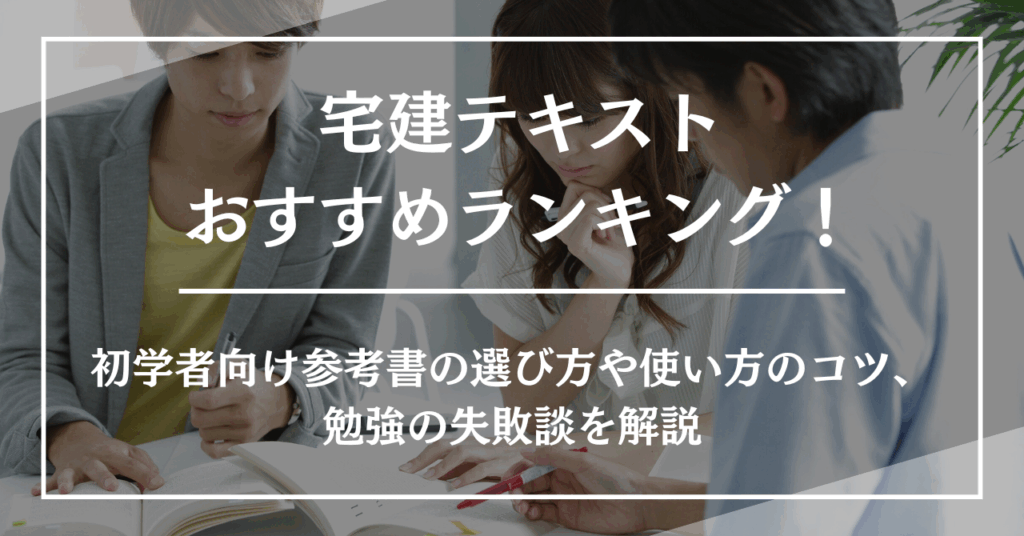
2.テキストの表から数字を覚える
自ら売主制限(8種制限)では、割合や日数といった数値を正確に覚えることが重要となります。
宅建試験では具体的な数値を問う出題が多い傾向があり、覚え間違いがそのまま失点につながることも考えられます。
表を何度も見返し、数値を声に出して読み上げるなど、複数の感覚を使って記憶に定着させましょう。
▼視覚的に8種制限で出てくる数値を暗記するには、TAC出版の「みんなが欲しかった!宅建士の教科書」がおすすめです。
3.過去問演習で知識を定着させる
自ら売主制限(8種制限)の知識を定着させるには、過去問演習が欠かせません。
過去問を解く際は、単に正解を選ぶだけでなく、なぜその選択肢が正しいのか、他の選択肢はどこが間違っているのかを丁寧に確認することが大切です。
また解説を読んで条文と実際の事例を結びつけることで、理解が深まります。
おすすめは解説文がわかりやすいLEC出版の「出る順宅建士当たる!直前予想模試」です。
過去問で繰り返し出題されるパターンを把握すれば、本番でも自信を持って解答できます。
実践的な知識を積み重ねて、確実な得点力アップにつなげましょう。
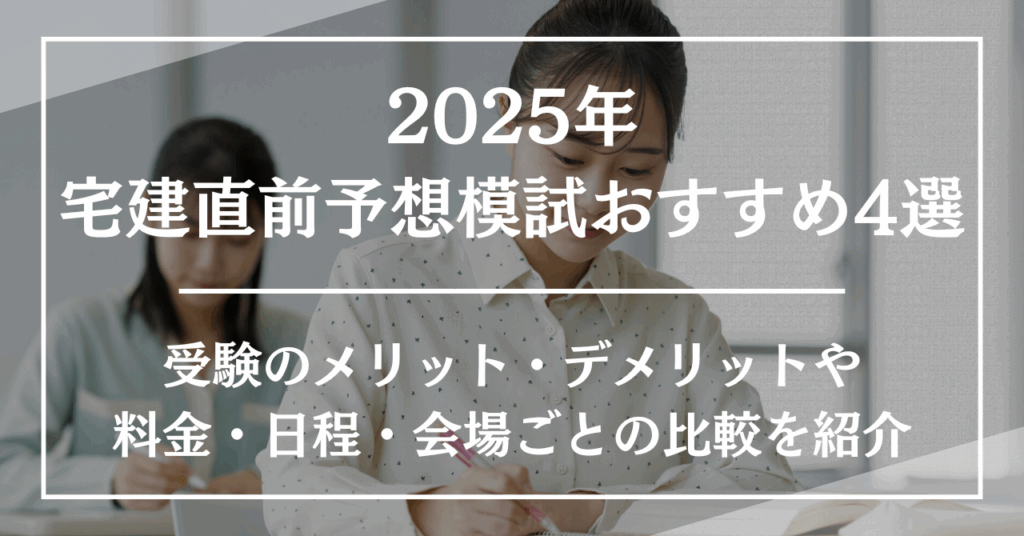
宅建試験では自ら売主制限(8種制限)を得点源にしよう!

自ら売主制限(8種制限)は宅建試験において確実に得点すべき重要分野です。
学習のポイントは、条文をただ暗記するのではなく、「誰を守るための制限なのか」という目的を常に意識することです。
割合や日数などの数値を表にまとめて正確に覚え、過去問演習を繰り返すことで知識を定着させましょう。
また、実務においても8種制限は不動産会社が遵守すべき基本ルールであり、買主との信頼関係を築くうえで欠かせない知識です。
一覧表と過去問を活用して8種制限をしっかり理解し、試験本番で確実に得点できるよう準備を進めていきましょう。